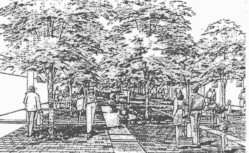震災後二年を経た「支援ネットワーク」
暮らしと住まいの復興へ まちづくり専門家への期待
(株)計画技術研究所・所長 林 泰義
はじめに
阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク(略称・支援ネット)の活動は、 「まちづくり専門家」の歴史の新しいバージョンを開くものでした。とりわけ「市民まちづくり」の視点からは、 貴重な実績を残してきたように思います。
「きんもくせい」はこの間の「支援ネットワーク活動」を次々に発信する貴重なメディアとして重要な役割を担ってきました。 この事にこの紙上をお借りして感謝したいと思っています。
「まちづくりの専門家」が、 何人も各被災地に迅速に飛び込んでいけたのは、 やはり震災前から様々な地域との関わりがあったのに加えて、 被災者の力にならねばと言う強い気持ちから止むに止められなかったのでしょう。
この専門家達が、 バラバラなままでなくネットワークを作り、 お互いに支え合い、 自治体とのパートナーシップのもとで活動したことが、 今日の復興に大きな力となったことは、 既に広く知られています。
「まちづくりの専門家」の社会貢献として、 全く新しい方式を開拓し、 従来にない大きな成果を上げてきたと思います。
今回は、 これらの専門家に加えて「住民とともに復興まちづくり」を考える「まちづくりの専門家」が重要な役割を担いました。 その専門的特質は「制度手法の眼鏡」を通して見るのではなく、 「住民の暮らしと住まいの再建そしてコミュニティの再生」と言う、 「生活の視点」からどうしたらニーズに応えられるかを考える所にあると思います。 「まちづくりの専門家」は、 住民と一緒に考えることを専門とするという意味で新しい専門家です。
行政の縦割りの施策を住民の努力で横につなぎ、 多様なニーズに対応する「まちづくり」の意義が社会的に認められてきました。 松本地区で考えている高齢者の住まいと福祉サービスの拠点が一体になったプロジェクトは、 その一例です。 言うまでもなく、 真野地区や野田北部地区の住民活動は、 まさに「総合的まちづくり」です。
住民サイドの復興まちづくり組織は、 より多様に発達し、 それとともに「まちづくり専門家」の役割も重要になっていくことと予想されます。
近く成立が期待されている「市民活動促進法」は、 こうした動きを支える一つの力になると期待しています。
ハノーバー市(ドイツ)では、 既に20年あまり前に、 市役所の提案した既成市街地の幹線街路計画への地区住民の反対に対して、 その住民組織に調査費を与えています。 住民はコンサルタントを決めてカウンタープランを立案しました。 市は、 その両案を見開きの頁毎に対比した色刷りの冊子を作り、 住民参加の討議をし、 幹線道路を地下に入れる案で合意に達しています。
西須磨や北淡町などは、 行政側に「市民のカウンタープラン方式による参加」の発想が在れば、 復興が軌道に乗る可能性があると思われます。
●カウンタープランが認められる世界では、 支援ネットワークの専門家の活躍の場は広がり、 成果も一層上がると期待できるのではないでしょうか。 (4月29日 記)
p1
この新メニューの応募状況が一部の住宅を除いて不調だったが、 私は不思議なことではないと受け取っているが、 行政は秋の第四次一元募集に向けて仕切り直しが必要である。 不調に終わった原因について、 私の考えを記してみます。
コレクテイブハウジングはそれぞれの住宅は台所、 浴室、 便所が備わった独立した住戸で、 それに協同スペース(協同台所、 食堂、 談話室、 多目的室等)があり、 日常生活の中で自然な形で住人同士がふれあえる集合住宅である。 協同室の使い方や維持管理の仕方は居住者が決めて、 協同室を核に協同生活が展開され、 下町の長屋的なふれあいと助け合いの生活が期待でる。 このような住まい方を自分のライフスタイルとして選択するには少し考える時間がいるだろう。 住まい方の意識はとても保守的なもので、 募集の直前に新しい住まい方等の情報を知っても、 それを自分の住まい方の選択肢として取り込めるものではない。 日ごろからこういう生活がしたい、 こういう生き方もあるらしいと、 自分の問題としてとらえていなければ、 新しい住宅が開発されたとしても関心はもてないだろう。 情報を自分のものにしていく醸造期間が必要である。
グループ入居制度は、 多くの高齢者が新しく移り住む地域の、 新しい出会いに大きな負担を感じており、 仮設住宅で仲よくなった人たちが一緒に移り住めるようにという暖かい配慮が感じられる制度である。
グループでの応募は、 自分の中の醸造だけでなく、 他者との共有の醸造も要る。 将来の生活を他者と共有するためには、 例えば、 一緒に草花の手入れをしながら、 或いはお茶を飲みながら、 話し合える時間が必要だろう。
「こんど公営住宅に移っても、 一緒にこんなんできたらええのにねぇ」
「グループ入居制度というのがあるんやて。 今度の募集の時、 グループで応募してみえへん?」
「ふーん、 そんなら○さんも誘うてみよか。 」
「△さんはどうやろ?」
というように、 グループはできるもんだと思う。 このようにしてできたのがほんまもんのグループ入居で、 誰かがコーディネイトしてグループ化を図るものではないと思うが、 グループをつくって応募するのは、 かなりのエネルギーが要るので、 場合によってはグループ化のきっかけづくりの適切なコーディネイトが必要だろう。 なお高齢者がグループで移ろうという仲良しは2〜3人で、 4人、 5人という大きさではないようだ。 それでは数世帯規模のグループはできないのかというと、 皆無ではなく、 そのグループの中に夫婦世帯か、 比較的元気な(やや若い)リーダー格がいれば可能性はありそうだ。 今回グループ入居制度の応募は21件あり(真野コレクティブを除く)、 17件が2世帯のグループだった。 グループ応募が少なかった一因は、 グループ入居が可能な住宅が限られていて、 その立地や住戸型に人気がなかったということにもありそうだ。
真野ふれあい住宅(21戸の高齢者向けと8戸の一般世帯向け)は2.3倍の応募があり、 グループ応募は5件である。 うち一般世帯向け住宅だけをみると2DK(6戸)は2.7倍、 3DK(2戸)は6.0倍で、 単身世帯と母子世帯の応募が多く、 比較的若い世代が多い(応募世帯の全家族人数の年齢構成では30歳以下が32%、 30歳台と40歳台で29%)。 4月末には入居者が確定し、 その後入居までの半年間に協同居住の学習や体験の機会をもち、 協同室の維持管理の方法や協同生活のルールづくりが予定されている。
コレクティブハウジングは高齢者に限らず、 単親世帯、 男女協働世帯、 単身世帯や幼児のいる世帯等にとっても、 共に住まうことの安全性、 安心感、 そしてふれあう楽しさをもつ暮らし方で、 1事例からだけの分析であるがその需要は潜在的にあると確信した。
(付記)高齢者は元の地域に戻りたいという強い願望があり、 住宅入居申込案内書を手にして見るのは地域別の頁で、 自分の元いた地域の住宅一覧。 新メニューまで目が届かない。 新メニューが目につくような工夫がほしい。
(4月18日記)
p2
・背山臨水の長田は、 条里制町割が今日に残る「風水に適う地」であり、 また「風水思想」が生活に根ざしている東アジアの人々が多く住む街でもある。 長田のまちづくりにおいて風水思想に注目することは、 まちづくりを通じて東アジアとの文化交流といった意味でも意義がある。
そこでJR新長田駅を中心におおむね新湊川と妙法寺川の間の新長田地域について「風水」による都市環境の骨組みの構築を試みる。
・「風水」とは、 地形、 風や水の流れ、 方位などから、 環境と人間の相関関係を正確に知ることによって、 自然の動きに調和した人間の相関関係を組み立てる中国古代に起こった地理学であり、 日本を含む、 東アジアの都市、 建築、 庭園、 墓の造営に少なからず影響を与えた快適居住環境形成の空間デザインの手法ともいえるものである。
・「風水」とは、 「目に見えざる<気>の動きを可視的な地上の現象(風や水など)によって判断し、 人間生活に<気>のもたらす吉福が及ぶよう、 生活(造形)空間を整えること」と表現されている。
今日の都市計画では、 自然環境との調和、 景観形成、 造園などの環境形成において、 主として物的に人間とその対象物とが対峙し、 一定の距離をもって見る「美」という概念を用いるのに対して、 「風水」においては、 人間と対象物が一体となって感情が交流した「気持ちいい」「心地よい」という住む側の主観的な「美」の概念としてとらえられている。
・「風水の風景」とは、 文部唱歌の「故郷」「夕焼小焼」「赤とんぼ」など詩で表されるような自然と生活が一体になった「ふるさとの風景」「なつかしい、 気持ちいい風景」として例えられる。
気候は、 風に左右されるものであり、 風の動きは山の形状、 位置、 高さなどに左右されるので、 風の判断としては山のあり方が重要視され、 また水は、 人とその地に天恵と「生気」の流れをつくるものとして重要視されている。
・風水都市の日本における事例としては、 平城京、 京都(平安京)、 鎌倉などを代表に数多くの歴史都市にその影響を見ることができる。
・風水による理想都市計画の基本的な態は、 おおむね以下のように整理される。
震災後のネットワーク活動が開いた意味
今でもはっきり覚えているのは、 小林郁雄さんからのFAXです。 震災後10日も経たない内に、 早くもコンサルタントや建築家の「復興市民まちづくり支援ネットワーク」が立ち上がりだしていたのでした。 新しい専門家の登場
従来の災害復興では区画整理、 再開発そして土木や建築設計と言う専門領域が重要な役割を担いました。 「ハード」から「ソフト」まで一体のまちづくり
この場合、 「まちづくり」は、 役所の縦割りで切り分けられた「ハード」領域のみの「街づくり」ではなく、 高齢者問題や、 失業者の再就職などを含む「ソフト」と一体になった「総合的なまちづくり」を意味しています。 アメリカで言えばCommunity Developmentとほぼ一致すると思います。 カウンタープランの発想のない日本
ドイツやアメリカなどでは、 まちづくり計画や開発計画を巡って、 行政と市民が対立した場合、 行政によるプランに対して、 市民がカウンタープランを創ることにより、 両者が対等の立場で話し合う土俵を創るという方法が社会的に定着しています。
新しい住まい方の受け入れには醸造期間がいる!
〜災害復興住宅第三次一元募集のための出前説明会を巡って〜
今回の復興公営住宅第三次一元募集には新メニューが3つあった。 協同居住型集合住宅(コレクティブハウジング )、 グループ入居制度、 ペットと一緒に住める住宅で、 いづれも公営住宅としては全国初の試みである。 コレクティブハウジング事業推進応援団は、 分かりやすい応募の手引書を作成して(上田耕蔵さん作成)、 仮設住宅を巡って出前説明会を行った。
(被災地にコレクティブハウジングを!/その10)
石東・都市環境研究室 石東 直子新メニューの受け入れには醸造期間がいる!
まず、 情報が行き届かなかった。 新製品開発の情報を、 欲している人に届ける知恵が十分に出されなかった。 次に、 情報をキャッチして、 それを自分の選択肢に入れるには時間が必要である。 真野ふれあい住宅の応募状況
コレクティブハウジングは、 協同居住をしたいというライフスタイルの選択なので、 居住者参加型の住まいづくりが望まれる。 しかし、 今回のような復興公営住宅では居住者参加型を採るのはなかなか難しい。 神戸市営コレクティブハウジング(真野ふれあい住宅)は地域の関心をもつ人たちがワークショップをやって計画づくりに参画したが、 真野地域だからできたということも言えそうだ。 居住者参加型住まいづくりに代わるやり方はいくつか考えられるが、 県営コレクティブハウジング(片山ふれあい住宅)はその努力をしないで募集をした。 片山ふれあい住宅に応募者がなかったのは、 入居後の住まい方のイメージが十分に知らされなかったことと、 グループ入居の条件(一人暮らし高齢者の6人グループだけの応募)が現実離れしていたことにもよると思う。
新長田駅北地区土地区画整理事業・まちづくり報告(4)
(株)久保都市計画事務所 久保 光弘
3.新条里都市・ながた
気持ちいい地域の空間(自然)をつくるためのグランドデザイン
・新長田駅周辺地域は、 「西の副都心」に位置づけられ、 重点復興地域として土地区画整理事業、 再開発事業等、 約230haにおよぶそれぞれの地区でまちづくりが進められている。 これらの地区が一体となって長期的に住工商が相乗効果を生み出せる街として新生していくためには、 その基盤としての都市の環境イメージを鮮明化させ、 それをまちづくりに参加する人々が共有していくことが大切である。 3-1 風水思想ー快適空間をつくる東アジアの思想
・今日の都市計画は、 明治以来の西欧的思想、 科学的知識が基本となっているが、 明治以前の日本の都市づくりにおいて影響を与えてきたのは東アジアの思想であり、 その中核が「風水思想」である。 3-2 風水による理想都市計画モデル
1)風水の3要素
・風水思想による快適空間(吉地判断、 吉地造形)の基本要素は、 (1)風(山)、 (2)水、 (3)方位の3要素となっている。 2)風水による理想都市計画モデル
・風水による理想都市計画モデルとしては、 図-8のように示される。
3-3 新長田地域の風水都市としての空間構造
・上記の風水モデルに照らして新長田地域をみると、 以下のような風水都市としての構造をもっている。 1)北に六甲山系・高取山
・北に六甲山系が連なり、 とりわけその中の独立峰「高取山」は、 平地に近い秀麗な神体山(神撫山、 神奈備山)で摂津富士とも呼ばれている。 高取山は「龍脳」にあたる。 2)南に長田港(海)-ながたなぎさ
・今日、 長田市街地は海とのつながりが希薄なものとなっているが、 JR新長田駅前ジョイプラザの最上階のレストランからみると今さらのように海が近いのに驚く。 長田は、 古くから瀬戸内海有数の大漁村という歴史をもつ駒ケ林から発展した「海のまち」でもある。 長田港周辺をウォーターフロントとして再生させ、 市街地と海とのつながりを復活させることは、 当地域にとって特に重要な課題である。 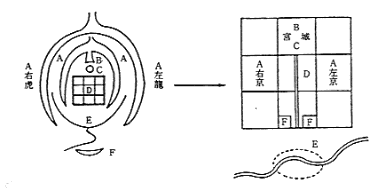
図8 風水モデル