<特集>“白地区域”の復興まちづくり
阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク 中井 豊(中井都市研究室)
はじめに-“白地区域”の現状
被災地の約8割を占める“白地区域”は、 区画整理や再開発などの震災復興都市計画事業地区(被災地域の約3%)に比べ行政からの支援が格段に乏しく、 震災後2年以上を経て様々な問題点が浮かび上がってきています。もちろん、 都市計画事業にかかればそれですべてがうまくいくわけではなく、 行政と住民、 また住民同士の軋轢が多くの地区で生じ、 未だに解決されないままの状況も見られます。 しかしながら、 多くの“白地区域”でのこの2年間は、 そういった問題すら起こっていません。 また、 自主的に活動を進めている地域では、 復興まちづくりの困難さ、 都市計画事業地区との格差をひしひしと感じながら、 悪戦苦闘を強いられてきています。
まちづくり協議会の結成についていえば、 都市計画事業地区では行政の支援も受けながらすべてのエリアで結成されてますが、 “白地区域”では住民の自主的なものに任されており、 震災後結成された100以上のまちづくり協議会のうち、 “白地区域”は数カ所にとどまっています。
また、 震災から2年以上がたち多くの“白地区域”では住宅再建のピークを越えた感がありますが、 多くの解体空地が虫食い状にそのまま残されており、 今後のまちづくりを考えていく上での大きなテーマとなっています。
震災以後定点調査を行ってきている大学の6つのグループの報告(神戸市長田地区・味泥地区・灘区南東地区・住吉地区、 芦屋地区、 西宮市安井地区)、 被災地の現場に関わっているまちづくりコンサルタント等からの復興まちづくりの実践報告(神戸市東部地域、 野田北部地区、 西宮市安井地区、 宝塚市川面地区)、 東京のコンサルタントの方からの被災市街地まちづくり手法の提言(水口俊典さん)、 行政の方からの制度活用動向の報告(兵庫県都市住宅部計画課、 神戸市アーバンデザイン室)といった、 非常に盛りだくさんの報告を集中的に行い、 “白地区域”の復興まちづくりの問題点・課題を多角的に検討しました。
報告のあと行われたフロアー討議では、 もともとのコミュニティが弱いところでの復興まちづくりの困難さ、 専門家の地元支援のあり方・地域との関わり方、 白地区域への行政支援策充実の必要性、 などを中心に熱っぽい意見交換が行われました。
なお今回の紙面で、 報告者の中から兵庫県の清水喜代志さん、 並びにプランナーの野崎隆一さんより、 シンポジウム以降の経過等も加えた報告をいただきました。
被災地で現在展開されているまちづくりは、 被災地以外でのこれからのまちづくりのモデルケースともなり得ると考えます。 こういった、 住民並びに支援する専門家の自主的な取り組みに、 あとしばらくの間、 ご支援のほどよろしくお願いします。
p1
頓挫の原因として最も多いのが合意形成の失敗であるが、 比較的初期段階でプランと事業試算を出しただけで、 キーポイントの権利者の賛同を得られずつぶれたというケースもあれば、 何とか大まかな合意を得て進めていながら、 内部の紛争によってつぶれたケースもある。
ある1例では、 3軒の協調化で、 真ん中の1軒が土地評価を大きく超える債権があったため、 断念せざるを得なかったものもある。 借地権問題は、 借地借家臨時処理法に対して過剰に地主側が反応した結果、 地主が法の有効な間には一切話に乗らないという態度をとったことが挙げられる。 法が、 ある意味では、 逆効果を生んだとも言える。 底地の売り渡し、 共同事業への参加、 これらをかたくなに拒み続けるケースが多かった。 多くの借地人が転居先の家賃と地代の二重支出に耐えられず、 借地権を手放している。
唯一、 市場再建のケースでは、 地主が借地権割合での土地の分割に同意してくれたが、 それにしてもほぼ1年あまり地主とのやりとりに費やしてきて、 やっとという状態であった。 その後も借地権という実体のない権利をどう数値に置き換えるかということで数カ月かかり、 事業の目途のたったのが震災後2年経過してからであった。 任意事業であるため、 様々なハードルをクリアして全地権者の同意が得られないと事業化できないということが、 膨大なエネルギーを注ぎながらも成果の少ない大きな理由であると言える。
しかし一方で、 昨年の秋頃から、 地元実力者の中にもまちづくり協議会をつくりたいと考える人間も現れ、 現在少しずつではあるがまちづくり協議会へ向けた動きが進みつつある。 その背景には、 市場の再建等、 我々の活動に対する彼らの再評価があるのではないかと考えている。
一方、 南の酒蔵エリアでは、 数名の建築家達が酒蔵のある町並みの復興に向け、 行政や都市計画家達とはまた違うスタンスで、 粘り強くイベントを通じての活動を続けていることも加えておきたい。
以上、 3つの視点から、 甲南・魚崎地区の現状を総括してみたが、 全体として、 困難な課題はより困難になっていると同時に、 急速な復興によって生じてきた新たな問題も多く出現してきたと言える。 それらの課題は、 縦割りの行政、 異なる分野の専門家達のバラバラな活動によって取り組まれるのではなく、 それらが複合的に密接に関係し合っている現地の住民の場から取り組まれなければならない。 今ようやく地元の高齢者支援活動をしているグループや、 商業者団体との交流も生まれ、 幅広い地域に密着した活動ができる体制が生まれつつある。 それに伴い、 まちづくり主体としての「まちづくり協議会」の発足が、 以前にもまして待たれているのではないだろうか。
震災復興はその意味で新たな段階に入ったと言える。 震災復興の過程で住民主体のまちづくり協議会がどれくらい生まれるか、 真の復興はそれにかかっている。
そこで、 都市計画事業で復興が進められている以外の地域での、 共同化等による再建に対する支援方針について兵庫県からお話しさせていただきます。
地区内のかなりの割合で被災し、 住民の方が共同化再建に一致して進んでいるもの、 震災前からまちづくりに取り組む機運があったものなどを中心に、 早期に立ち上がれるものはかなり進展してきていると思われます。
また市街地の復興には、 まちづくりコンサルタントの方が住民と連帯して、 共同化再建等を進めていただいている地区が数多くあります。 この中には、 (2)で述べる復興基金によるまちづくり支援事業を活用された例もあります。
これまでに、 平成9年2月現在まで(1)アドバイザー派遣94地区(共同化等26地区、 セミナー43地区など)、 (2)コンサルタント派遣114地区(共同化等64地区など)、 (3)まちづくり活動助成43地区に支援を行っています。
これらの状況を踏まえ、 接道等の課題から単独では再建できないが、 再建の意欲があり共同化や協調化によって再建に進める可能性のある土地の方には、 できるだけ行政側から支援していきたいと考えています。
喫茶スペースを持ったギャラリーのようなもので、 地域住民の方々が使われるもよし、 まちづくりにかかわる人々の集会や勉強会、 研究の場とするもよし、 ひろくまちづくり活動の場となりますようにとの願いをこめています。
震災直後から定期的に発行をつづけてきた「阪神大震災復興市民まちづくり支援ニュース/きんもくせい」は第50号をもって、 いったん終刊いたしますが、 今後も刊行物(ギンモクセイという説も?)や研究会など、 いろいろな形で市民まちづくり支援を続けていくつもりです。 “きんもくせい”という店はその一つのかたちを変えたまちづくり活動と考えています。
茶店きんもくせいは、 喫茶とスペースだけでなく、 パン屋さん(パンはご存じ、 あのフロインドリーブのパンです)とともに、 いろいろなものの展示販売もいたします。 たとえば『復興市民まちづくり』(Vol.1〜8)やその他多くのまちづくりを担ってきた資料や図書など、 和田誠さんにお願いして描いていただいたマーク(お店のマークでもありますが)のグッズたち、 “がれきに花を”で芽生えた花の種苗や樹木と移動生垣や土、 そして地区住民の方々の手による手芸品や菓子といったご自慢の自作品の販売などもいたします。
開店はゴールデンウイークのころになりそうですが、 庭の若葉を眺めながらコーヒー、 紅茶を楽しみ、 100年先の神戸を夢みてまちづくりに励みたいと願っています。
店主敬白/天川佳美
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
“白地区域”の復興課題を総括的に検討した
「きんもくせい」40,41号で概略が報告されていますが、 昨年の12月14日に神戸東部市街地白地地域復興支援チームと震災復興・実態調査ネットワークの共催による“白地区域”をテーマとしたシンポジウムを開催しました。
「12・14白地区域被災実態・復興方策シンポジウム」ネットワークで新たに取り組み始めていること
このシンポジウムを契機として、 “白地区域”の復興まちづくりに関するネットワーク独自の取り組みを始めています。 1つ目は共同化適地調査で、 今後共同再建を進める必要のあるエリアを抽出し、 専門家が連携して地元の共同再建を啓発・支援しようとするものです。 2つ目は空地の実態調査で、 今後の復興まちづくりの大きなテーマである空地問題を考えていく上で、 まず実態把握を行おうとするものです。 この他、 震災後一貫して取り組んできている地元まちづくり組織の立ち上げ支援も継続していく予定です。 
震災復興促進区域・重点復興地域
・震災復興都市計画事業地区指定図<神戸市>
東灘区甲南・魚崎地区より白地地域の現状を見る
遊空間工房 代表 野崎 隆一
震災直後、 関西建築家ボランティアのメンバーとしてこの地区との関わりを続けて3年目を迎えるが、 地区の現状と将来の展望を語るに際し、 3つの視点から地区の現況を見ておきたい。 1.復興状況
震災直後、 ボランティア団体が調べたデータによると、 地区内の60%強の建物が全壊あるいは半壊と判定されていた。 その後、 平成7年8月の調査では解体整地された敷地のうち、 再建に着手したものは10.8%であった。 それが12月の調査では35%を超え、 平成8年3月の調査ではほぼ50%に達していた。 しかし、 急速な復興はこの頃までで、 夏頃から変化が見えなくなり、 今年の1月末の調査では約64%であった。 つまり被災宅地のうち30%近くが更地として固定化しそうだと考えられる。 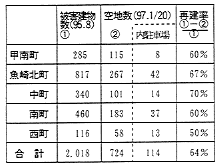
魚崎・甲南地区/2年目の状況2.復興プロジェクト
小学校の避難所の相談コーナーより始まったものを中心とし、 我々が何らかの形で関わった復興プロジェクトは11ヵ所をかぞえる。 うち頓挫したのは、 合意形成に失敗したものが4ヵ所、 借地権問題によるものが2ヵ所で、 現時点で見通しのたっていないものが2ヵ所、 また事業化の決まったもの、 すでに着工しているものは3ヵ所という状態である。 3.まちづくり
震災の年に避難所を中心に地区の活動メンバーと、 復興後の地区のあり方について討議をしながら「魚崎地区まちづくりシンポジウム」を4回開催し、 その後も活動メンバーを中心に、 建築家や大学関係者も加わり10数回にわたる勉強会を重ねた。 しかし、 東灘のこの地区は、 旧五箇町村からの地縁性が強く、 財産区等に象徴される地元実力者がもとの地位を取り戻すにつれ、 まちづくりメンバー達の行動が様々な形で制約を受けはじめた。 我々外部からの専門家が実力者達に会いに行き調整を試みたが、 難航した。 
震災2年目の魚崎・甲南地区
狭隘道路にしか接道しない空地も多く点在している
今後のまち復興の支援について
兵庫県都市住宅部計画課長 清水 喜代志
震災から3年目に入り、 量的には市街地の復興がかなり進んできた中で、 これからはよりきめ細かく再建を支援していかねばならない時期に入ってきました。 (1)共同化等による再建
共同化再建のうち、 国庫の助成による再建は、 これまで申請があったもので優良建築物等整備事業(優建)31件、 住宅市街地総合整備事業(住市総)20件、 密集住宅市街地整備事業(密住)3件、 その他に組合再開発、 組合区画整理などとなっています。 このほか助成を受けずに自力で共同化したものもあります。 (2)まちづくり支援事業
まず相談会・セミナー等の開催にあたって(1)「アドバイザー派遣」の制度があります。 そこで再建の方針ができると次の段階である計画づくりへの助成には(2)「コンサルタント派遣」の制度があります。 実際の再建事業には先程述べた住市総、 優建、 組合再開発、 組合区画整理などの補助制度が使われます。 まちづくり協議会の活動には(3)「活動助成」を受けることが可能です。 (3)市街地の再建の課題
被災地の多くは既成市街地で、 特に木造住宅が密集していた市街地が多く、 そこでは接道していないとか、 敷地が狭いなど、 そのままでは建築が困難な敷地も多数ありました。 復興の初期に更地がたくさんある間は、 住民の方がまとまって共同化や区画整理等を行うことによりそれらの条件は克服され再建されてきました。 しかし、 被災地で約8万戸の建築が着工され、 これに加えて約8万戸の公的住宅建設が進められているなど住宅復興が進んでくると、 再建できていない敷地については、 再建のための事情は深刻化しているのではないかと考えられます。
などが懸念されます。 (4)支援施策
(1)行政発意のアドバイザー派遣
残された更地は小規模に散在しているため、 課題を抱えて再建できない被災者がいてもなかなか支援事業の申請に至らない場合があると思われますので、 再建が遅れていて接道等の条件が悪いなどの地区には、 行政側からアドバイザーを派遣するなどの支援を行おうと考えています。 (2)専門家による現地相談
「阪神・淡路まちづくり支援機構」とも連携して、 弁護士、 建築士、 土地家屋調査士などの専門家の方による現地相談なども行っていきます。 (3)阪神淡路復興基金事業による「小規模共 同建替等支援事業」
共同再建への国庫による助成制度は、 共同化の規模が小さくなると活用しにくくなってきますので、 復興基金事業として「小規模共同建替等支援事業」を設け、 今後も小規模化すると思われる共同再建を支援することとしました。 対象、 助成内容などの詳細については検討中ですが、 より小規模な共同化についても支援が受けられるよう検討しています。 (5)今後の課題
今後まちづくり協議会活動への支援の強化や、 更地の活用を検討していくことなども、 よりよいまちづくりのために取り組んでいきたいと思います。 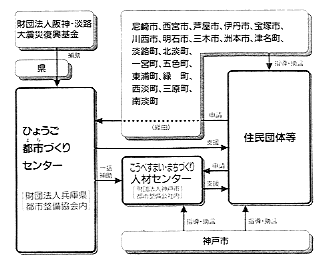
復興まちづくり支援事業のしくみ
INFORMATION
まちづくり(有)きんもくせい ご挨拶
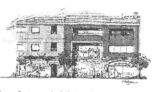

きんもくせいロゴ
茶店「きんもくせい」正面
茶店「きんもくせい」内部。 2〜30名の会合ができます。 神戸復興塾・第2回公開講座開催される
3月27〜29日の3日間、 神戸復興塾の第2回公開講座が京都府立大学住居学科3回生8名の参加により開催されました。 長田のコレクティブ住宅や、 神戸西部市街地(真野地区・鷹取東地区など)、 神戸東部のマンション再建地、 区画整理・再開発が進む六甲道駅周辺地区、 白地区域の魚崎地区などを見学するとともに、 復興まちづくりに直接関わる講師陣によるレクチャーが行われました。 
魚崎地区でのレクチャー神戸復興塾・勉強会シリーズ
<第1回 しごとから考える>―市民は何で食べていくか-
ネットワーク事務局より
第18回神戸西部市街地連絡会
……神戸西部のこれからの復興まちづくりを、 ケミカルシューズ等の地場産業の復興をテーマとして検討します。 (なお、 報告者は追ってお知らせします。 )
P.4
Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
 きんもくせい46号へ
きんもくせい46号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ