終刊にあたって
(株)学芸出版社
2年前の1月17日未明、 阪神・淡路地区を襲った大地震は、 日本を揺り動かしました。多くの人々がそれぞれの立場から、 被災地に対し何か支援できないものかと考えました。
私たちもその一人です。
建築、 まちづくりの出版を手掛けていることから、 その面で協力できることはないか考えていましたが、 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局の方々との以前からのお付き合いもあって、 このような形で「地元密着型のまちづくり通信」を合本し、 生の声を全国に伝えてゆくことに致しました。
継続購読をしてくださった読者の皆様をはじめ、 多くの方々に支えられ、 3ヵ月に1号ずつ、 計8号を発行して参りましたが、 2年を経た今、 当初の使命を果たしたものと判断し、 本号で終刊とさせていただくことになりました。
今まで支えてくださいました読者の皆様、 店頭で常に好意的に展示くださった書店の皆様、 また無理なスケジュール、 コストでの発行を手助けしていただいた製作関係の皆様に改めて厚く御礼申し上げます。
私共は、 今後とも復興市民まちづくりへ関心を持ち続け、 まちづくりに取り組む方々の情報交流のためのお手伝いをさせて頂きたいと考えております。
『復興市民まちづくり』はこのような形でお届けいたしましたが、 これからは、 5年,10年続く復興まちづくりのなかで、 適切な時期を捉えた出版等で復興市民まちづくりの現場と、 全国の方々を繋ぐ一助となりたいと思います。
当面は下記の当社のホームページで、 様々な情報提供を行ってゆきたいと考えております。
皆様の一層のご支援、 ご協力をお願い致します。
まちづくりニュース発行者・編集者・支援者からのメッセージ<抜粋>
(VOL.8にはこの全文並びに他5名のメッセージも掲載しています)
清水 光久(「真野っこガンバレ!」編集長)
今世紀はじめての、 都市直下型地震ということで、 その貴重な体験を後世のために残す必要があるにもかかわらず、 全国のマスメディアはそれをしませんでした。
被災地では、 いろいろなグループが震災の記録を残す努力をしています。
その中にあっても、 被災地全域にわたって、 個々の動きを「市民まちづくり」としてまとめ得ることができたことは、 たかく評価されるものだと確信します。
後藤 祐介(復興まちづくり戦士/ジーユー計画研究所)
今回、 これまで約2年間に8号まで続いてきた復興まちづくりニュースの合本発行が打ち止めになることとなりました。これまでの合本は、 阪神・淡路大震災における復興まちづくり活動のバロメーターとして、 そのマンパワーを全国に伝えるものでしたが、 ここで打ち止めになることは残念であり、 寂しい限りです (中略) 今後とも、 阪神・淡路大震災の情報伝達に何かとご尽力賜りますようお願い致します。
小林郁雄(阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク)
『復興市民まちづくり』全8冊は、 被災地における被災民によるリアルタイムの呼びかけであり、 全国・全世界への阪神・淡路大震災復興まちづくり原典資料になるものと考えます。震災復興まちづくりを真剣に研究するならば、 多くの評論・調査(ほとんどが通り一遍のアンケートで住民真意を代表していると思っている、 あまりにワンパターンな)などを百編通読するよりも、 ここに綴られている市民の各地区での悪戦苦闘の生のニュースを百回精読することを、 お勧めします。

「復興市民まちづくり」創刊号表紙
長田区日吉町6丁目/復興区画整理区域内共同化一番乗りをめざして
『復興再建共同化住宅 サンコート鷹取』の事例
まちづくり(株)コー・プラン 吉原 誠
1.地域の概要
長田区日吉町6丁目は、 震災復興区画整理区域内の中で先頭を走ってきた鷹取東第一地区のほぼ中央北側に位置する。この地域は、 121世帯、 308人が生活していたが、 25.1%と高齢化が進んでいた。
そして、 阪神・淡路大震災によりほとんどの建物が倒壊・焼失し、 多くの犠牲者を出した。
鷹取東第一地区では、 1996年8月に仮換地指定が始まり、 日吉町6丁目は、 1997年の1月20日に仮換地の指定を受けた。
その途中11月にまちなみ誘導型地区計画が都市計画決定され、 建ぺい率が角地並みに10%割り増しされることになった。
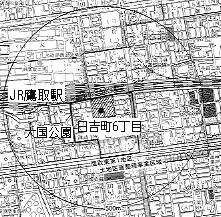
位置図
2.事業の経過
1996年4月21日、 東尻池町7丁目立江地区共同建替での公団との基本協定の締結を見学した後、 長田区日吉町6丁目の人達と初めて会った。これまで、 あまり住民集会に参加したことがなかった私は、 その雰囲気に圧倒されたのを記憶している。
その後、 月2回のペースで勉強会を行い、 昨年の11月に地区計画が決定された頃、 建設組合を設立、 今年に入って1月20日に地権者14名が集約換地を受け、 2月16日に住宅・都市整備公団への企画提案を提出、 2月下旬に住市総の補助申請を提出、 3月2日に2回目の近隣説明会を開催するに至り、 公団との基本協定締結の一歩手前までこぎ着けた。
その間いろいろな出来事があった。
一日も早く地元に戻りたいと願う住民の「具体的なプランを早く提示してくれ」という声の中、 意向調査アンケートから始まり、 等価交換の仕組み、 資金計画、 共同建替の補助制度、 そして仮換地と減歩率の説明を行ってきた。
当初この事業に参加の意向を表明した地権者は26名いた。
しかし、 勉強会を開く度に、 いろいろな原因で組合設立までには14名に減ってしまった。
事業を進めていく上では妥当な人数かもしれないが、 抜けていった人たちが、 仮換地の決まった狭小敷地で今後どのように住まいを再建していくかを考えると心配である。
人数がここまで減ってしまった原因には、 仮換地がなかなか決まらなかったことと、 等価交換の仕組みを理解できずにそんなおいしい話はないと思われてしまったことが大きかったのではないだろうか。
地区計画において容積率が300%になるインナーボーナス制度の見送りなども影響している。
敷地がどこになるかわからないので参加人数が確定できない。
参加人数が確定できないので敷地規模が決まらない。
このような悪循環がしばらく続くことになった。
当初、 候補地としては、 日吉町6丁目の北部でJR沿いがあげられたが、 従前の権利者の理解が得られず公園の南側の敷地661.57m2に仮換地を受けることになった。
けれども、 公園の南側に敷地が決まったことにより、 総合設計制度によって設置される公開空地と公園とのつながりができるという点では、 今後のまちづくりの面からは緑や広場の拠点となることが期待できる。
この方式を採用したのは、 地権者のほとんどが面積30〜40m2の狭小敷地を所有し、 多くが高齢者であるために一戸建ての再建が困難であるという背景があった。
従前敷地の約1.2倍の床面積の等価交換を確保し、 権利者の負担を減らすためには、 なるべく多くの保留床を確保しなければならない。
けれども、 インナー型総合設計制度を活用しても、 容積率200%に50%の上積み(保留床10戸分)するのがやっとで、 工事費を極力抑えなければならないという問題があった。
その中で住市総の補助は、 総工費の2割弱とはいえ大きな意味を持っている。
しかし、 この綱渡りのような条件下で「サンコート鷹取」の建築計画が具体化できたのは、 14名全員が地権者であり、 他の共同化でみられるような複雑な権利関係がなかったことと、 短冊状の集約換地(下図参照)を受けた住民の「再び日吉町6丁目で暮らすためには、 共同化しかあらへん」という強い思いが大きかった。
また、 建ぺい率70%のうち20%を公開空地および緑道として確保し、 建物、 敷地内外ともに光と風を多く取り入れ、 インナー型総合設計制度を導入している。
総戸数は26戸で、 地権者用の権利床が14戸、 賃貸が2戸、 保留床を10戸確保している。
その中でできるだけ早期に着工し、 竣工一番乗りをめざしている。
すでに地盤調査に取りかかってはいるが、 着工までにすべきことは、 公団との手続が主であり、
今後、 狭小宅地、 資金力といった問題を抱える区画整理地区で等価交換による共同化の話は、 増えるだろう。
「一日も早く日吉町6丁目に戻りたい」この声を聞いてから、 間もなく一年が経とうとしている。
この一年間が平常時の事業に比べて長かったかどうかは、 初めてこういう事業に携わった私にはわからない。
仮換地の指定が進んでいる鷹取東第一地区でさえ、 この共同住宅の場合、 竣工までまだ一年近くかかるが、 再び、 日吉町6丁目で暮らせる日が来るのも絵に描いた餅ではなくなっている。
共同化への長い道のりももうすぐ折り返し点に来ているのだろうか...
これらは、 インターネット上で各まちづくり団体の活動状況などをホームページで公開し、 情報交換を図ろうとするためのものです。
すでにいくつかの団体のホームページが公開中で、 順次、 神戸市内全域のまちづくり団体のホームページを公開していく予定です。
ホームページのURLは、
是非ご覧ください。
また県外避難者支援全国ボラネットでは県外各地に避難されている方々を集めて説明会を開きました。
この詳しい報告は後の号で掲載致します。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
3.事業の特徴
この事業は、 14名の地権者が、 集約換地を受けた土地を一度、 ディベロッパーである住宅・都市整備公団に売り渡し、 公団が建設した共同住宅の床(従前敷地の約1.2倍)を譲り受けるというグループ分譲制度を活用した「等価交換」方式を採用している。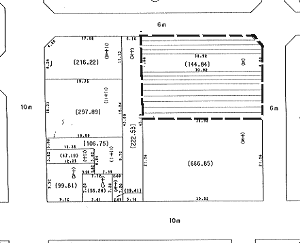
仮換地指定図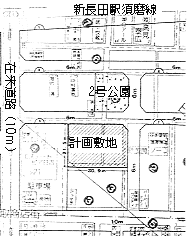
計画敷地周辺図4.建築計画概要
この建物は、 なるべく低層とし、 周辺環境への日影などの影響を抑えている。
5.今後の展開
現在、 この「サンコート鷹取」以外にもこの鷹取東地区には、 いくつかの共同化の計画が進行中である。
1)土地の評価額の算定
などが挙げられる。
2)公団との基本協定の締結
3)建物竣工後の管理形態の確立
4)換地処分の際の清算金の問題
5)保留床の処分方法の確定
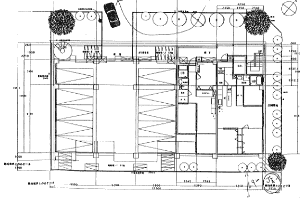
配置図・1階平面図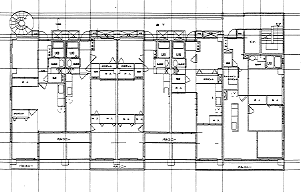
基準階平面図
「復興再建共同化住宅サンコート鷹取」完成イメージ模型
長田区日吉6丁目共同建替え参加者の方々
建替敷地での記念撮影
INFORMATION
神戸まちづくり協議会連絡会 ホームページ開設
3月20日(木)に阪神・淡路コミュニティ基金から連絡会のまちづくり団体にパソコン21台が贈呈されることになりました。
http://www.marin.or.jp/machiren/
です。災害復興公営住宅第3次募集始まる
コレクティブ・ハウジング事業推進応援団は手分けをして姫路や加古川方面、 西神NNT、 長田区や灘区など仮設住宅の住民の方々に、 全国で初めての試みの公営コレクティブ・ハウジング、 一般の公営住宅におけるグループ募集及びペットと共に住む住宅などの新しい制度について独自の『出前説明会』を行いました。
仮設住宅での『出前説明会』の様子定期借地権の活用による住宅再建に関する研究会
<第2部>4名によるシンポジウム
<第3部>パネルディスカッション
“いどばたフォーラム”
「地震死傷者問題に関する学際シンポジウム」
1.基調講演
「世界の地震と人的被害」塩野計司(長岡高専)
「集団災害と救急医療」鵜飼卓(大阪市総合医療センター)
2.テーマ別報告・討論(各部門5名による報告と討議)
<1部>何が起きたのか(被害の実態)
<2部>何が生死を分けたのか(被害の原因)
<3部>どうすれば死傷を軽減できるか(予防と事後対応)
3.総括と今後の展望
TEL.078-803-1017 FAX.881-3921 E-mail:kaz@arch.kobe-u.ac.jp
震災復興・実態調査ネットワーク
<フィールド調査について>長田地区、 灘地区、 東灘地区、 芦屋地区
ネットワーク事務局より
第17回・神戸西部市街地連絡会
〈報告〉
グ)
※以後の予定
第18回:4月22日(火) 「まちづくりと産業・景観」
第19回:5月27日(火) 「再開発と住宅づくり」
P.4
Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
 きんもくせい45号へ
きんもくせい45号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ