
JRの自然の土手(西宮市安井地区)
震災で壊れた住宅の再建が進み、 プレハブ系のハウスメーカーの住宅が建てられていく。
震災前の住宅地のイメージに合わせてと、 屋根は黒、 外壁はベージュやチャコールグレー系で色彩は押さえている。
形はさまざま。
そばを歩くと住宅展示場の中に迷い込んだような気がするが、 JRの高い車窓から見ると、 その屋根は黒々とし、 テカテカと輝いている。
一種異様な住宅群が武庫川までの阪神間に点在している。
嘆かわしい風景の出現と思うが、 被災者の気持ちを思うと、 速く建ち上がり、 隣とは違うプランや外観をもつメニューがあり、 大工さん不足の今、 個人的判断に負かされていてはこれで善しとせざるをえなかったということも理解できる。
しかし、 しかしである。
夙川を渡って西ノ宮駅に至る2キロ程の区間に進められているJRの土手の修復工事を見た時、 これはもう黙ってはおれないという気になった。
土手の地盤を固めて、 全面をビニールの人工芝とやらで覆い、 その上を数センチ幅の金属棒で碁盤の目状に押さえている。
土手一面がテカテカのグリーンと白っぽい金属片の格子模様で埋め尽くされていく。
なんということを……・。
タンポポもススキも、 背高あわだち草も一切の雑草は生えず、 一匹の秋の虫も生息できないようにと、 ビニールシートで覆っていけば、 短くない歳月は維持管理のためのJRの経費は不要となるという発想だろうか。
もう、 バカらしくて多くを語る気はしないが、 言わなければならない。
夏になると、 人工芝はグングン温度が上がって、 その照り返しで沿道の民家に熱風を送り届けるだろう。
雨が少なく風が吹く秋から冬、 春先は人工芝に溜まった砂塵が舞い上がり、 沿道の民家に吹き込み、 そばを通る人はマスクや頬かぶりが必要となるだろう。
春になっても、 草木の芽ぶく気配は一切感じられない。
沿道の民家では一年中、 窓を開けて風を誘い込むことすらできない。
そして、 幾度めかの夏を迎えるころ、 テカテカ輝やいていた人工の緑は変色し、 点々と引っ掛かったゴミくず、 空き缶、 ボロ布等々によって、 ボロ雑巾の垂れ幕がぶら下げられたような景観をさらけだすことになるだろう。
夙川を越えたJRの沿道に西宮市立安井小学校がある。
自然の大切さ、 環境共生、 町に緑をと学習したけど、 どこにそんなんあるのん、 校庭の前の土手を見て、 子供たちの頭は混乱する。
安井地区をはじめ公園のない住宅地では、 JRの自然の土手が唯一まとまった面積の自然に接する場所でもある。
今まだ工事が進んでいない区間は写真1)に見るようにホットするような自然の土手がある。
ここの土手は鉄軌道から法面で下がり、 その裾には1〜2米幅の平地があって、 JR敷地と道路境界にフェンスがある。
このフェンスを50センチでも30センチでもJR敷地内に移してもらって、 ここを沿道の人たちが使用できる花壇や菜園に提供してほしい。
花壇等に使う住民は責任を持って美化、 清掃に努める。
阪神グリーンネットもJRの沿道の住民も人工芝の撤去と合わせてJRに提案しましょう。
安井地区から西にバックし、 東灘区の住宅地を走るJRの土手は震災後の応急処置としてコンクリートパネルで覆われ、 高いコンクリート塀が続いている区間が少なくない。
これはあくまで応急処置と聞く。
復旧事業が一段落したら、 ぜひJRも沿道地区のまちづくりの環境形成に目を向けてほしい。
安らぎのあるまちを形成し、 植物や虫の生存権も認めるような視点がほしい。
(2月5日記)




・平成8年秋、 味泥地区にある西求女塚公園内の西求女塚古墳についての解説板が大幅に書き換えられた。
震災前、 味泥下町活性化委員会は地区の歴史の掘り起こしをし、 その中で著しく姿をゆがめ変えられている西求女塚古墳を地区再生のシンボルとしようとその復元整備を市に提案し、 それを受け入れた市教育委員会は発掘調査を行っていた。
その結果、 古墳時代中期の前方後円墳と考えられていたこの古墳は、 3世紀末から4世紀始めの古墳時代初期のもので、 日本でも「最古級の前方後方墳」とわかった。
更に驚くべきことに、 中国製銅鏡が12面出土し、 そのうち7面は邪馬台国の女王「卑弥呼」が魏帝から贈られたとの説がある「三角縁神獣鏡」であり、 1ヶ所からのこの出土数は全国でも3番目に多いものであった。
・この発掘調査においてさらに重要なことを我々は知ることになった。
この古墳はひどく荒らされており、 宅地になっていた時期もあることから、 出土品はほとんど期待されていなかったにもかかわらず上記のような出土があったのは、 この古墳の基盤である砂層の中央部が過去の大地震による液状化現象、 噴砂現象、 激しい振動により著しく陥没した結果によるものであった。
石室がこれだけ崩壊したのは全国でもめずらしく過去の神戸大激震を物語っているといわれていた。
これによってほとんどの人々が大地震がないと思っていた神戸にも、 震度6程度以上の「大地震が古墳時代前期以降では、 少なくとも5世紀末と16世紀にあった」ことを知らされた。
これは、 今回の阪神淡路大震災の2年前のことであった。
神戸は、 あまりにも明治より前の歴史に関心が薄い都市のようである。
歴史は文化的側面だけでなく、 忘れた頃にやってくる地震など自然災害に対する重要な情報源でもあることをこの機会に思い返すことが必要ではないだろうか。
・今回の大震災によって、 西求女塚古墳の復元調査は中断された。
しかし、 地域特性を生かしたまちの再生は文化の再生でもある。
西求女塚古墳の復元をこの震災を期にあらためて、 その復元の意義を問い直し、 あらためて位置づけを行って、 しかるべき時期に復元調査の再開が行われることが望まれる。
(1)西求女塚古墳は今回の大震災だけでなく、 神戸の過去の大震災の記憶をもつ「神戸大震災の記憶装置」といえる。
後世の人々に大震災を伝える記憶装置、 阪神淡路震災メモリアルパークの一つとして、 西求女塚古墳の復元整備を位置づけてはどうだろうか。
(2)西求女塚古墳のあったこの地は、 古代から敏馬の浦といわれ、 新羅使節の神酒饗応を行う公的な国際性のある港であり、 港湾管理者として「津守」がおり、 外交使節の畿内での最初の接待を行い、 検疫所の役割を併せもっていた。
元神戸市港湾局長鳥居幸雄さんは著書「神戸港1500年」の中で、 ここ敏馬の浦を「港都神戸誕生の地」と述べられている。
ウォーターフロント型古墳である「西求女塚古墳は、 港都神戸誕生のシンボル」といえるものである。
(3)震災前、 歴史が見えなくなった当地区において住民達が歴史を掘り起こし、 インナーシティのイメージチェンジを図るためのシンボル、 起爆剤として、 西求女塚古墳の復元にまちづくりとして取り組んできた。
多分文化財復元をまちづくりとして取り組んできた例はほとんどないであろうし、 「古墳のある下町」は、 大都市市街地に例のない神戸の新しい地域文化をつくるであろう。
今や、 西求女塚古墳復元は、 新生下町をめざす味泥の地区アイデンティティ形成上、 不可欠なものとなっている。
この段階では前方後円墳で描いている。
住宅再建について規制がなく、 かつまちづくり支援が行われた味泥地区の場合で、 時間とまちづくりの関係について特徴的なポイントを整理しておく。
・震災後10日位の時点では、 「これまでやってきたまちづくりもおしまい」という声を聞いた。
しかし、 3週間後位になると「住民が茫然自失な状況から一日でも早く抜け出して希望が持てることが必要である」という意識が生まれた。
1ケ月に満たない2月14日に最初の味泥復興委員会が行われ、 復旧の混乱と交通がままならぬ状況の中にも関わらず、 疎開地から多くの役員の方が集まられた。
・大震災であっても、 地域を支えるまちづくり組織があれば、 以外に早い時期に人々の気持ちは復興に向かうことになる。
これは、 住宅再建、 まちの復興が早期に取り組めなかった都市計画事業区域などの区域等にみられた初期の精神的ストレスの高まりと比較すると、 住民の精神面からみてもまちづくり組織があることはたいへん重要であることがわかる。
平成7年4月、 5月頃をピークに多くの住民が相談に集まったが、 9月頃の相談会では新たな相談者は皆無の状況となった。
このような状況から「再建できる人」が住宅再建の意志を固める時期は、 概ね震災後半年以内であろうと推測される。
・これはまちづくりの観点からみれば、 まちの再生として取り組める最も重要な時期は、 「人々のおもいやりの求心力」が高く、 「再建できる人」の意志が定まっていない震災後半年以内であり、 「再建できる人」の意志が一旦決まった段階以降では、 共同再建を含め、 住民間の協調によるまちづくりの大幅な進展は、 たいへん難しくなる。
すなわち、 「一般地区における震災復興まちづくりの大枠は、 震災後の半年以内」に決まるといっても過言でないように思う。
しかし、 不在地主などの協力等もあったが、 住宅再建条件など個人個人の生活条件が一致することはたいへん難しく、 数ケ所の共同建替検討があったものの、 現在共同建替事業の実現に至っているものは2街区となっている。
・そのうちの一つは神戸復興住宅メッセが支援した3階建ての「3軒共同建替」(従前は1戸を除き未接道の4戸連棟住宅)で各世帯が1階〜3階を垂直所有する従前の居住感覚を生かした共同住宅であり、 既に完成している。
もう一つは以下に紹介する「中庭をもつ中層共同住宅」である。
・従前、 当街区は街区面積約1,700m2、 戦前長屋等5棟(40戸)あり、 地主1名、 借地家主1名、 借地人18名、 持地人4名、 借家人9名という大規模かつ複雑な権利関係を有している街区である。
現在、 市住宅局、 専門家(コーディネータ:間野博(広島女子大学)、 建築:森崎建築設計事務所)の支援のもとに、 住宅都市整備公団がデペロッパーとなり、 今年春に着工が予定されている。
震災直後住民がまとまって相談会に出席していた。
当街区の借地家主、 借地人代表等と、 コンサルタントが森南土地区画整理事業区域に在住の地主と面談した。
この折、 地主は味泥まちづくりの方向に共感がもたれ、 以後共同建替だけでなく、 味泥復興委員会の特別委員として役員会に参加されている。
36世帯中、 個人的事情で3世帯が転出。
中庭のあるコート型配棟。
新町屋のイメージ。
このため、 震災前でのまちづくり委員会は、 まず地区のイメージチェンジを図ることが必要ということで歴史や自然の再生に注目したシンボル事業やイベントを中心にまちづくり活動が行われてきた。
・しかし、 震災後は、 復興のための戸建住宅の再建だけでなく、 大規模な更地での建設動向がでてきた。
これまでまちづくりの対象としていなかった国道43号以南の準工業地域で震災直後にラブホテルが建設され、 このまま放置しておくと、 国道43号以南にラブホテル街が出現するのではないかと危惧されている。
駅前にはスノーボード場の計画がでてきた。
これについては、 復興委員会で事例を見学し、 建設企業と話し合い、 結果として建設される方向となったが、 周辺地区に風紀上悪い施設ができないか等が心配されている。
また、 大規模な更地での高層マンションの建設が進む可能性がある。
・復興委員会は、 7年4月に「味泥復興マスタープラン」、 7年8月に「味泥いえなみコード(いえなみ憲章)」を作成したが、 そのようなソフトなものでは、 現在の建築動向をみたとき、 実効力において不十分であり、 環境を守るための建築のコントロールが必要な状況となってきた。
・このため、 現在味泥復興委員会は味泥地区のまちづくりの基本理念を「古墳のある新生下町づくり」として「まちづくり協定」を定めるための検討を行っている。
東京在住で味泥出身の若い慈さんは、 震災直後、 味泥のまちづくりニュースをインターネットでみて、 電話をいただき、 会合にも顔をみせておられたが、 今は「ふるさと味泥」にUターンし、 味泥復興委員会の「事務局」の中心となって活躍されている。
今回は95年9月から12月までの記録で、 地区計画をまちづくり協議会で決める経過を中心に、 震災後増加している違法建築の問題、 鷹取救援基地の神田神父と子供たちとの対話、 などが描かれています。
2月18日には、 こうべまちづくり会館ホールにおいて上映会とシンポジウム“そだて!市民のまちづくり”が行われ(主催:港まち神戸を愛する会)、 第5部の映像を巡って、 まちづくり協議会や地域コミュニティのあり方、 3年目を迎えた復興まちづくりの展望などについて語られました。
内容、 販売店は以下のとおり。
これは昨年の1年目につづき開かれたもので、 震災2年目の復旧復興状況や、 模型による住宅復興の提案などがわかりやすく展示されました。
震災後AAネットワーク等の活動に関わり、 昨年惜しくも亡くなられた高橋裕嗣(港まち神戸を愛する会副会長)さんが撮られた写真も展示しております。
1.大震災を知っていた古墳
震災メモリアルパークとしての位置づけを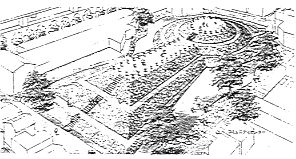
図1 発掘調査の契機となった味泥下町活性化委員会による古墳復元プラン
(平成3年味泥下町活性化委員会作成。2.一般的地区では、 震災後半年以内が重要
・味泥地区は震災によって大半が全半壊した復興都市計画事業の対象でない一般的地区であるが、 震災前にまちづくり協議会があり、 初期から復興まちづくりに取り組むことができたいわゆる「灰色地地区」である。1)住宅再建意識は、 震災3週間後には芽生える。
2)まちの再生は、 震災後半年で大枠が決まる
・復興委員会は、 被害建物の診断相談会の実施後、 建築基準法に適合しない敷地に対する住宅再建は、 共同建替、 戸建住宅建替のための専用通路の確保など隣地との協力が不可欠であることから、 地区毎に「住宅再建懇談会(相談会)」を重ねて、 隣地権利者間の調整が行われた。3)取り残された未接道宅地
・「再生できる人」の意外と早い住宅再建の動きは、 一方では建築できない未接道宅地を取り残し、 長期的な課題を生む結果となっている。3.味泥の共同建替の特徴
・「住宅再建懇談会」(相談会)においては、 共同建替の専門家支援として、 小規模な共同建替は神戸復興住宅メッセ準備室(当時メッセは開設準備段階であった)、 まとまった規模の共同建替は、 建築コンサルタント(4社)に支援をお願いした。住宅種別による群建築
都通4丁目街区再建事業(ア)実現の要因
(イ)特徴
4.「まちづくり協定」づくりへ
・震災前、 味泥地区は、 典型的なインナーシティの一般的市街地として、 沈滞化し、 古い賃貸住宅等老朽木造住宅の更新は、 遅々として進まなかった。5.味泥復興委員会の近況
・復興委員会には、 松阪会長のもと震災前にも増して、 多くの役員の方々が集まられている。
(平成9年2月3日記)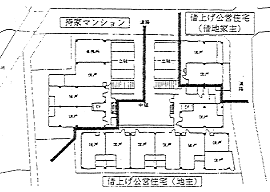
図2 都通4丁目街区再建事業完成予想図
図3 住宅種別による棟分けコート型中層共同建替
INFORMATION
「野田北部・鷹取の人々」第5部完成
震災後、 神戸市長田区野田北部・鷹取地区で継続的にまちづくりの記録を撮り続けている青池監督の「人間のまち、 野田北部・鷹取の人々」の第5部が完成しました。
シンポジウム風景('97.2/18、 こうべまちづくり会館)神戸・ポストカードブック
記憶から記録へ
神戸在住の写真家である米田定蔵さんの撮られた震災前と震災後の神戸の風景を収めたポストカードが出来ました。
X.078-641-0289)ポストカードの一例
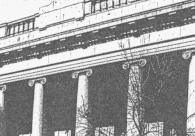
第一勧業銀行神戸支店(神戸市栄町通、 1916竣工)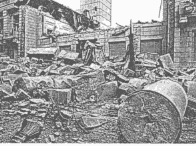
震災で崩壊した第一勧業銀行(1995.1/17撮影)住吉地区復興パネル展開催
1月16日から20日の5日間、 “白地区域”である神戸市東灘区住吉地区で震災復興の支援・調査活動を継続的に行ってきている住吉復興支援チームによるパネル展が開かれました。
パネル展風景('97.1.20コープこうべシーア)第2次・コレクティブハウジング事業推進応援団
―第6回ミーティング―
「写真で語りつぐ私たちのまち」写真展
※プロの写真家たちによる震災前の風景や震災後の状況を記録した写真展。
ネットワーク事務局より
第20回・東部市街地連絡会
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
(神戸市中央区三宮町 三宮駅南250m)
P.4
Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
 きんもくせい44号へ
きんもくせい44号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ