「きんもくせい通り協調住宅」の特徴
当該敷地は、 住宅市街地総合整備事業(住市総)区域である重点復興地域(六甲地区)の北東角に位置する。住市総の用件は敷地規模が200m2以上であり、 右表に示すように基準をなんとかクリアーできた(ちなみに優建事業はおおむね300m2以上)。
この建物は、 建築基準法上は1棟扱いであるが、 各々の敷地に建物を“0ロット協調化”(隣戸間の壁の隙間をあけない)により建てており、 敷地の共有化はしていない(すなわち、 マンションのような区分所有建物ではない)。
このような建物のメリットとしては、 建築工事の効率化、 敷地の有効利用、 柔軟な増改築への対応性などがあげられる。
街並みの形成を意識したデザインもこの建物の大きな特徴である。
建物全体を前面道路から2mセットバックさせ、 そこを緑地とし(住市総の適用条件にも対応している)、 道路空間にゆとりを持たせるとともに、 その上部をパーゴラとすることによって潤いのある景観形成を目指した。
協調化した建物の外壁は、 イエローとブラウンに塗り分けられ、 それぞれの“個”を意識しつつも、 パーゴラにより一体感のある景観を生み出すことが出来た。
また、 1階壁面には安藤忠雄氏の提唱による“復興タイル”(INAX製)を用いていることもこの建物の特徴である。
これは、 かつてヴォーリスらが阪神間の建物によく用いたのと同様のスクラッチタイルで、 阪神間らしい街並み復興への願いを込めている。
しかしながら、 途中でこの計画から撤退を余儀なくされたYさんは、 その原因が木造からRC造へ建替えるに当たっての膨大な借地権の更新料がネックとなったことを考えると、 補助率のアップなどもっと共同建替えに魅力のある施策を講じても良いのかと思う。
われわれはこの状況を“プレハブ村”と呼んでいるが、 そんな中にあって「きんもくせい通り協調住宅」は、 周辺住民の注目度も高く、 まだ内容が決まっていない1階店舗について、 「喫茶店がいい。
絶対はやるわ。
」などと提言してくれる。
この建物を起爆剤として、 周辺や他地域に魅力的な建物が一つでも多く再建できることを願っている。
左側の3階建てが当該建物。
その後、 区画整理の事業計画決定と第2段階都市計画決定が平成7年12月27日および28日になされ築地復興まちづくりの第1段階を経過している。
その後約1年間、 助走を経ていよいよ本格的な整備事業が始まろうとしている段階であるが、 この過程で築地地区復興委員会を中心におこなってきた検討や顕在化してきた課題等をいくつか紹介しておきたい。
第1は改良住宅(公営受皿住宅)の整備計画と入居条件に関連した課題である。
まず、 全体整備計画戸数約500戸のうち第1期建設約100戸については、 43号沿道騒音の問題等でその適否について議論があったが、 結局他に選択肢がなく地区に隣接した旧国鉄尼崎港駅跡地に建設が決まった。
2期以降の地区内建設については、 当初、 日影の条件等から有利な北側庄下川沿いの街区への集中配置案が示されたが、 景観面からの反対や、 人口のバランス、 これからの町の発展という観点からの意見・提案もあり、 南北の分散配置に落ち着いた。
この間、 復興委員会やブロック会議で何度か議論を重ね、 最終的に築地地区福祉会館で300分の1模型を展示して、 多くの人に見てもらった。
まちの表通りである本町通り(旧中国街道)に沿った部分には1階を店舗等とした低層型の建物がならぶことになる。
このような中で、 あたらしい住宅に対する期待が高まると同時に、 入居条件等に関して具体的な要望や意見が出てきた。
たとえば、 世帯人員等と入居住戸規模の対応が機械的すぎないか。
普段はいいが、 息子家族など親戚が来たときに対応できない。
また、 長年いっしょに暮らしてきたペットの飼育を認めてほしいなどなど。
人情と非人情が交錯する微妙な問題提起が多かったが借家人分科会はこれらを集約し、 市の回答を得ながら基本的な理解を拡げていった。
つぎに事業用地の先行買収開始を契機として出てきた課題がある。
買収補償額が一定額に満たない零細権利者世帯の改良住宅入居を認めることになったこともあり、 とくに小規模宅地所有者から土地・建物の補償額を早く知りたいという声が強まった。
家主と借家人の意向対立も顕在化してきた。
家主が用地買収に応じない限り借家人は改良住宅に入居できないためである。
家主といっても規模など千差万別である。
小規模な賃貸住宅の経営によって暮らしをつないできたという老婦人は、 借家人の気持ちは分かるが手放せないという。
大きな地主の心配も潜在している。
はたしてこの築地で賃貸住宅の再建経営がやっていけるのか。
将来展望が見えてこない。
今まで650世帯が民間賃貸住宅に住んでいたまちが、 505戸の公営住宅を抱えることになるのだ。
賃貸住宅市場は窮屈になるだろう。
特目入居(地区限定)型の改良住宅建設は、 短期的には人口の流出を防ぎまちの安定に貢献するが、 長期的なまちづくりの観点からはどうか。
活力あるまちとしての一定の開放性・流動性を確保するための取り組み、 仕掛けが必要となっている。
ある日、 阪神尼崎駅前の喫茶店で近くの客同士の話しが耳に飛び込んできた。
「築地は今ある建物みんな壊して、 マンションみたいな住宅建てるらしいけど、 あんなとこ誰もいかへんで」「そやね、 ゴーストタウンになるんちゃう」…と。
「なにいうてんねん」と突き上げてくる言葉をにがいコーヒーと一緒にぐっと飲み込んだ。
阪神大震災ではその産業的文化遺産である木造酒蔵が壊滅的な打撃を受けました。
以後は主に一部の中小メーカーが、 その地酒復興の熱意(灘の酒はもはや全国ブランドとして画一的な味というイメージが広がっていたため)もあって、 破壊された木造酒蔵のたたずまいを再現して見学コースや資料館を設けるなど(計画中)で、 産業の発展と街の再興がおし進められています。
しかし、 震災後約2年たった今こそ、 この街が以前のように潤いのある豊かな街並みに戻るのか、 あるいは単なる工場地帯になってしまうのか、 再びその具体的方策が問われる時期になったのかもしれません。
ここに街並みの活性化という視点から、 わたしたちがとり組んだ試みのいくつかを報告させていただきたいと思います。
写真展の会場は魚崎郷の中心にあって、 酒ラリーではゴール地点でもある西浜公園と浜福鶴という酒造メーカーの前庭に大桶(酒造メーカーではもう使われていないのですが、 酒粕業を営む「小林晴吉商店」が時代を生き抜いてきた大桶を守っておられたのでそれをお借りしました)それも黒光りした分厚い杉板で作られた直径2mはある大桶を計14個並べその中に、 古い木造酒蔵の写真を展示しました。
さらに唯一震災を免れた「辻井酒造」の100m以上の長さで続く板塀にも写真パネルを貼ってふたつの空間を結びました。
大桶はやはり迫力があり、 木造酒蔵の持っていた空気やにおいを呼び戻してくれたと考えています。
街並みとしてはたった2日間の点と線ではありましたが、 貴重なイメージを過去から未来へとつなげ、 場のイメージを再認識してもらうための良いイベントであったと思います。
中でも清酒メーカーの灘泉や福寿は特に情熱的に力を注ぎ木造酒蔵のたたずまいを再現されました。
「木は呼吸しているから温度、 湿度の調整を自然にやってくれる。
工場みたいな鉄筋蔵より気合いが入ります」とは灘泉の岩手県から来た南部杜氏の言葉です(神戸新聞1996年4月)。
酒造りに賭ける意気込みが伝わってきます。
灘泉が酒蔵の再建イベントを催された時に、 わたしたちは木造酒蔵の写真展示という形で参加させていだたきました。
これを何とか早く復活できないかとのことで、 「酒蔵の道」沿いの各酒造メーカーの敷地の一部を利用させていただき、 “フォリー”(シンボル的なあずまやの意)を設けることで灘三郷をつなげる提案をしました。
この“フォリー”にどんな機能を持たせることも可で、 たとえばそれを看板、 休憩所、 直販店、 酒蔵の門、 壁、 子供の遊び場、 櫓、 緑と水のオアシス、 ミニギャラリー等として仮設的にも(恒久的にも)設置することができます。
こうした利点から、 一日でも早い「酒ラリー」の復活を願いました(「きんもくせい」18号'95.10/18参照)。
これもひとつひとつは点ではありますが、 それが線、 あるいは面となり発展しながら酒蔵が街並みの生きた風景として再現されれば…………という提案(願い)です。
それらは決して灘五郷だけの課題ではありません。
たとえば蔵人や杜氏の高齢化です。
若い人が育たない、 あとを引き継ぐ人がいない、 ただそれだけの理由で(酒の低迷もあるが)廃業や蔵取り壊しに追い込まれるのは、 もはや全国的な傾向でした。
なぜ若い蔵人が育たないのでしょうか?
そこが若い人の集まれる場、 あるいは興味をそそる魅力的な場でなかったのではないかという反省から、 日本一の酒所である灘五郷、 ここに「酒文化のメッカ」とも呼べる“生きた資料館”の建立を提案しました。
これは日本各地から若い人を募集して蔵人を育てる場。
それは学校でもあり、 研究所でもあり、 工房でもあり、 蓄積されつづけた精神や技術を磨く場でもあり、 情報の発信基地でもあり、 あるいは試験的に作られた酒の限定販売もできるなど……・の“生きた資料館”としました。
この水のわき出る井戸を中心に庭園を整備する計画があります。
それに合わせて、 この春には日本酒をテーマとしたイベントが開催される予定です。
われわれも積極的に何らかの形で参加させていただきたいと考えています。
木造酒蔵の街並復興を模索しながら、 今後とも活動していきたいと思います。
p4
10団体が惜しくも助成から漏れましたが、 申請された全団体が助成を受けられるよう、 基金規模のさらなる拡大が望まれています。
報告された団体は以下の通り。
・西須磨まちづくり懇談会
復興まちづくりに関わってきた都市計画や商業のコンサルタント、 弁護士などの専門家によるパネルディスカッションが行われ、 専門家の連携のあり方、 これからの復興まちづくり課題などが語られました。
いつものように、 まちづくりニュースを送ってください(2月7日(金)までに事務局に届いた分を掲載します)。
今回をもってこのシリーズの締め括りとしますが、 今後も何らかのかたちで、 復興まちづくりに取り組む地元の生の情報を発信していきたいと考えています。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
共同再建事業を終えて
住市総事業の適用及び補助率の震災特例(2/3→4/5)により、 共同施設整備費、 設計費など合計で事業費の約2割の補助を得ることができ、 事業推進に当たっての大きな力となった。「きんもくせい通り協調住宅」建築概要
1F……・Oさん自宅兼作業場、 店舗、 駐車場
2F……・住宅1戸(1LDK)、 コープラン
3F……・住宅3戸(1LDK2戸+2DK1戸)
※当敷地は角地のため建ぺい率は10%緩和され、 70%となっている。

'96.3時点の“きんもくせい通り”(25号に掲載)
現在の“きんもくせい通り”。
通りに面した敷地はほぼ再建された。
「きんもくせい通り協調住宅」全景
築地からの報告・1
まち計画 山口研究室 山口 憲二
尼崎市築地地区では平成7年8月8日に土地区画整理事業区域等の都市計画決定後、 同年9月14日に住宅地区改良事業の地区指定がされ、 10月18日には築地地区復興委員会が「築地地区まちづくり案」を尼崎市長に提出。
(つづく)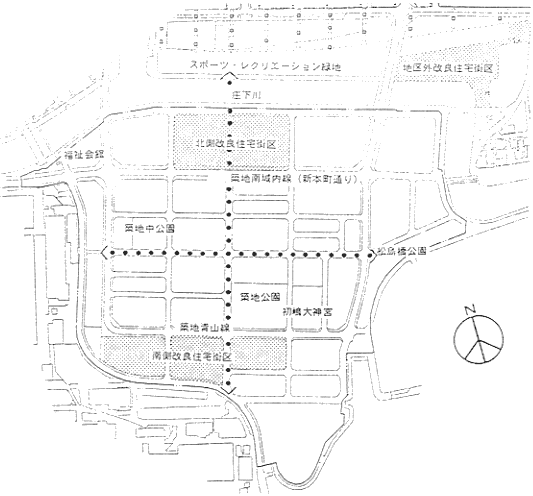
築地地区構想図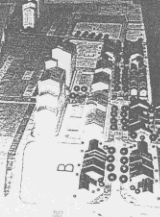
北側改良住宅街区周辺のイメージ模型
「木造酒蔵」なき街のルネッサンス
「灘の酒蔵を復興させる会」 水谷 嘉信
神戸市東部から西宮にかけて広がる「灘五郷」は、 全国の清酒の約3割を出荷する日本一の酒どころです。大桶を利用した写真展
何か地元の人々に生きがいを与えられないか、 あるいは以前の街並みの「記憶」を呼び戻せないかと思い、 秋祭りの時期にイベントとして開催しました。木造酒蔵再建イベントでの写真展
灘の中堅清酒メーカー、 大黒正宗、 灘泉、 滝鯉、 酒豪、 福寿の五社は、 “神戸に地酒あり!”……・をアピールして地酒振興を目指す「神戸地酒金賞会」を震災後に結成しました。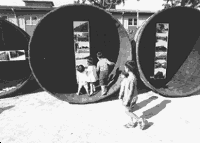
大桶を利用した木造酒蔵の写真パネル展示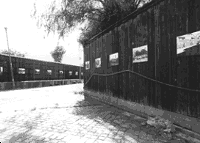
唯一震災を免れた酒蔵の板塀を活用した、 木造酒蔵の写真パネル展示“フォリー”による「酒ラリー」復活の提案
灘三郷では、 例年酒造りの季節には「酒ラリー」という催しが「酒蔵の道」沿いで開かれていましたが、 木造酒蔵が無くなった現在は中止されています。“生きた資料館”の提案
言うまでもなく酒造りは、 震災以前から多くの問題を抱えていました。その他西宮郷、 今津郷、 今後の活動
灘五郷の中でも西宮に位置する西宮郷は、 「宮水」の発祥の地。
阪神・淡路ルネッサンスファンド(HARはる基金)第3回助成決定
昨年12月8日、 第3回目の阪神・淡路ルネッサンスファンド(HAR基金)の公開審査会が、 こうべまちづくり会館で行われ、 右のように14団体、 合計800万円の助成が決定しました。活動テーマ/活動グループ名称 : 助成金額(万円)
また、 1月25日には第3回助成団体への贈呈式と第2回助成団体報告会が、 こうべまちづくり会館でありました。
/野田北部まちづくり協議会:60
/灘中央地区まちづくり協議会:50
/すたあと長田:30
/シンポジウム「都市の記憶」実行委員会:40
/富島を考える会:140
/野田北部を記録する会:50
/神戸復興塾:30
/ドングリネット神戸:50
/西須磨まちづくり懇談会:90
/緑化コミュニティ「四季」:50
/芦屋市民街づくり連絡会:50
/計画工房INACHI:30
/住吉地区復興支援グループ:70
/第2期コレクティブ・ハウジング応援団:60
合計14件 800万円
・住吉地区復興支援グループ
・長田・共同居住支援団
・尼崎で協同居住型住宅を実現させる会
HAR基金第3回公開審査INFORMATION
復興まちづくりセミナー開催される
1月24日、 「まちづくりにおける専門家の役割と可能性」をテーマとして復興まちづくりセミナー(ひょうご都市づくりセンター、 こうべまちづくりセンター主催)が開かれました。第2次・コレクティブハウジング事業推進応援団
―第4回ミーティング―
コレクティブ住宅募集の説明会について、 他
“久二塚6”に建つ受け皿住宅について語ろう会
阪神グリーンネット・1周年記念会
ネットワーク事務局より
『復興市民まちづくり』vol.8発刊へ
まちづくりニュースを事務局まで送ってください
当ネットワーク編集『阪神大震災/復興市民まちづくり』(学芸出版社刊)の8冊目が2月下旬に発行されます。
第19回東部市街地連絡会(1/28 神戸Fビル)
「特優賃」事業、 神戸市「特目賃」「民借賃」事業などに関する事業例の報告を基に、 民営賃貸住宅の復興課題について討議しました。
P.4
Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
 きんもくせい43号へ
きんもくせい43号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ