2.千歳地区復興まちづくり事業に向けて
昨春から千歳地区の復興支援の活動を始めて以来約1年半、 去る10月25日、 「千歳地区まちづくり計画書」を市長に提出したことによって、 当初予定されていた土地区画整理事業の事業化に向けて、 地元の条件がほぼ整いつつある段階に至ったといえる。
この間の千歳地区連合まちづくり協議会の考え方と進め方について紹介しよう。
千歳地区は、 鷹取東地区として土地区画整理事業と、 地区内の千歳小学校に隣接する位置に約1.3haの近隣公園が計画決定された。
市街地の基盤は、 耕地整理等によりほぼ100mの格子状に8m程度の道路が整備されているものの、 それらの街区内は、 ほぼ3m前後の幅の私道と、 それに接して建てられた戸建てや長屋が大半であった。
震災後の2ケ月経った3月には、 連合自治会は、 「地元に仮設住宅を」と「一方的な区画整理でなく、 住民の意見を入れよ」とする第1号「千歳地区ニュース」を発行し、 一方で地区住民のための仮設住宅の建設について、 市の部長と交渉を続けた。
その姿勢が、 その後の復興まちづくり計画を作っていく土台ともなっており、 先日市長に提出した「千歳まちづくの計画書」にも十分現れているので、 以下にそれを紹介する。
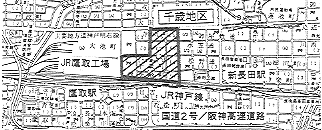
位置図
3.千歳地区連合まちづくり協議会の考え方
千歳地区連合まちづくり協議会は、 発会当初から、 「住まいの再建・確保なくして街の復興はない、 地区の実情に基づく要望が実現できるなら、 負担や傷みが伴う土地区画整理事業に協力することもやぶさかでない」という立場で、 以下のような考え方で復興まちづくりに取り組んできた。
第一に、 震災前に住んでいた約1,000世帯のうち、 借家、 借地世帯が8割近くあり、 その多くが高齢者世帯という実情から、 地区に戻りたいと願う世帯のためには、 低家賃の公営住宅の建設を主とする住宅再建への具体的な見通しを立てることが、 街を復興していく最も重要な問題である。
第二に、 今回の震災とその後の大規模火災の中で、 身近な公共用地や防災機能を有する公園・緑地の不足が痛感されたことである。
しかし、 当初千歳町1丁目に計画決定された千歳公園については、 大きな公園が不要だとは思わないが、 千歳地区のコミュニティが分断されるだけでなく、 将来的に街の活性化の障害となること、 そしてもっと身近な公園や緑地が街の防災にとって不可欠であること、 等々の理由から認めるわけにはいかない。
むしろ、 公園を身近な位置に分散し、 それらを緑道で結ぶことを主とする代案を提示し、 日常的にも身近で高齢者にもやさしく、 コミュニティ形成にも有効であると同時に、 将来的にも若い世帯も定住できるだけの快適な街並みを作っていくことが必要であると、 主張してきた。
第三に、 千歳地区の福祉、 文化の中心となる施設を整備することである。
千歳地区での生活中心にもなっている現在の老人いこいの家の拡充、 そして高齢者の暮らしをより安全にしていくための医療施設を併存するケア付公営住宅を整備することが、 高齢社会の街として復興していく重要な課題となっている。
(次号以降につづく)
p1
神戸・都心地域の最近の動向について
(株)地域問題研究所 山本 俊貞
PART1:都心(三宮地区)復興過程の現状と隘路
解体敷地の半数以上が現在も更地
震災によって、 地区計画が指定された「三宮地区」内の約560棟のビルのうち、 3割にあたる160棟余りが崩壊もしくは解体を余儀なくされるという被害を受けた。そして1年9か月が経過した平成8年10月現在、 これら建物が撤去された敷地の内、 再建済み31棟、 工事中26棟、 計画・設計中約50棟で、 仮設建物・駐車場・資材置場等として暫定的に利用されているものを含めると、 残る50余りの敷地では土地の活用方策が未確定である。
つまり「再建済みもしくは工事中」「計画中」「未計画」の敷地が各々3分の1ずつという状況にある。
三宮地区のこのような再建・復興速度を遅いとみるのか、 早いとみるのかの判断は立場や視点によって異なるであろうが、 いずれにしろ半数以上が現在も更地のままであることは現実である。
道路をはじめとする基盤施設の原状復旧が着実に進むなかで、 建物の再建が進んでいない要因は、 業務中枢機能の流出という神戸の従前からの傾向に加え、 近年の全国的な景気低迷を背景として、 大規模な敷地ではビルを再建しても果してテナントが埋まるのかという不透明感であり、 さらに小規模な敷地では、 もともと借地の上に自社ビルを建設していたケースも多く、 資金繰りとともに権利関係の複雑さが早期再建を困難にしている。
この意味では、 住宅密集市街地と同様の問題を抱えている。
進まない共同化
一方、 行政では三宮地区における都心機能と市街地の復興を目指して、 震災後、 地区計画を指定するとともに、 小規模敷地の共同化を積極的に推奨してきた。三宮センター街の西部周辺や市役所前の一部には100m2に満たない小規模な敷地が集積しており、 土地の高度利用と景観形成など都心の魅力向上が狙われたものである。
しかし、 現在までに三宮地区70haのなかで、 共同化について地権者間での検討が進められているのは10数件と少ない。
この要因としては、 被害の大きかった小規模敷地が必ずしも隣接している訳ではないことに加えて、 次のように整理できる。
1)住宅の場合と同様もしくはそれ以上に、 地権者は権利関係が複雑になることを忌避する。
とりわけ戦後の混乱期に苦労して入手した経験をもつ地主は土地に対する執着が強く、 自分の土地に自分の建物を建てたいとする意向が強い。
さらに、 借地権の問題が複雑に絡む。
2)大規模ビルの場合と同様、 共同化によって生まれる増床部分の処分先が不透明である。
3)共同化によって建築規模が大きくなり、 その結果、 駐車場の附置義務が新たに生じ、 レンタブル面積の大幅増加につながらない。
4)行政による支援策として総合設計制度や優良建築物等整備促進事業が用意されているが、 これらによって得られる増床や補助金の額よりも、 空地の確保による経済的デメリットの方が大きいという認識が強い。
求められる市街地形成の指針
被災地の復興をいうとき、 単に従前への復旧のみで満足されるものでは当然ない。ビルが幾つ再建されたかという数の問題だけでなく、 平時のまちづくりや景観形成と同様、 一定の方向性のもとに各々のビルがどのような役割を担いうるかという認識のもとでの再建がより重要である。
そしてこれを可能とするためには、 各々のまちにみあった市街地形成の指針を検討・調整・合意することの意味は大きい。
都心のなかの1つの地区である旧居留地ではこのための試みがなされているといってよい(PART2参照)。
震災直後、 行政を含むさまざまな分野の人々が、 極度の混乱の中で都心の復興について提案し、 論じてきた。
しかし、 最近ますます広がる被災地と他地域との温度差を背景に、 それらの夢を達成することの困難さを思い知らされる中で、 どのようなまちを形づくるべきかという中長期的な議論が後退しつつあるように感じられる。
都心の早期再建という意味からも、 共通の夢/市街地形成の指針を模索する作業を、 行政も含めて再開すべき時期ではないだろうか。
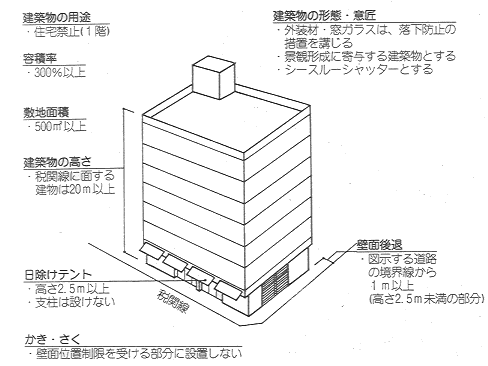
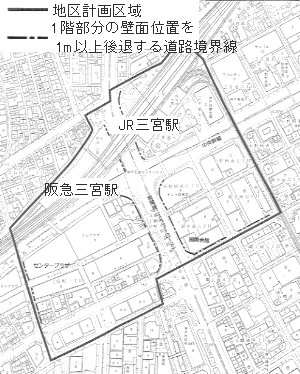
三宮地区地区計画(三宮南地区)の概要
PART2:旧居留地における復興への取り組み
近代神戸発祥の地・旧居留地
旧居留地は、 1868年の兵庫開港に伴い、 イギリス人土木技師の設計のもとに整備された約22haの区域である。当時、 人家の多い既成の兵庫を避け、 農村であった神戸村が選ばれたもので、 近代神戸の成立もこれに端を発している。
歩道や街路樹、 街灯を備えた広幅員の街路、 公園、 下水道などが整い、 街区は平均 1,000m2の敷地に整然と区画割りされていた。
現在でも街路パターンはほとんどそのまま残されており、 敷地割りもあまり変わっておらず、 地番は当時と同じものが使われている。
明治32年に居留地制度が廃止された後も内外の商館が建ち並び、 神戸の都心中枢業務地として発展してきた。
そして、 大正期から昭和初期には石造をはじめとする近代洋風建築物が幾つも建てられ、 第2次世界大戦時の戦災によって多くが破壊されたものの、 震災前までは20棟近くが残されていた。
とりわけ近年では、 この重厚で落ち着いた雰囲気が見直され、 業務ビルの1階や地階にブティックや飲食店が立地し、 新しい形態のショッピングゾーンとしての賑わいもみせていた。
建築解体敷地のうち、 3割が利用計画設定
しかし、 阪神・淡路大震災では、 地区内100棟余りのビルの内、 22棟が解体せざるを得ない状況にまで被害を受けた。被害の大きかったビルの多くは昭和30年代に建設されたものであるが、 この他に、 居留地時代から唯一残されていた旧居留地15番館(明治14年築、 国指定重要文化財)をはじめ、 海岸ビル(大正7年築)、 大興ビル(大正8年築)、 明海ビル(大正10年築)の4棟の近代建築物も含まれている。
その後、 15番館は復元が決定され、 平成10年3月の竣工を目指して工事が進められているし、 海岸ビルは外壁を復元した上で高層ビルに生まれかわろうとしている。
この他にも、 平成8年10月までに7件のビルが着工し、 6件が計画・設計中である。
しかし、 このような再建速度は三宮地区全体の中ではいくぶん早いものの、 仮設建設(3件)や駐車場(1)といった暫定利用を含む7敷地では将来的な利用計画が未定という状況にある。
地元組織による「復興計画」の策定
震災直後、 地区内の道路は波打ち、 随所でビルの解体工事が行われている混乱の中で、 早くまちの落ち着きを取り戻したいとの思いから、 旧居留地で事業を営む法人100余社の集まりである「旧居留地連絡協議会」では、 4月に緊急総会を開き「復興委員会」の設立が提案された。これに先立つ3月末より、 神戸市では当地区の地区計画の素案縦覧がはじめられており、 これへの実質的対応を図るとともに、 都心中枢業務地としての地位を今後とも維持していくためには、 街はどのようにあればよいのかといったことを皆で検討し、 共通目標を持とうとするものであった。
旧居留地連絡協議会は、 戦後まもなく設立された歴史をもち、 異業種ではあっても地区内企業の親睦を図ることを第一の目的に活動が続けられてきた。
そして、 昭和58年、 当地区が神戸市都市景観条例に基づく都市景観形成地域に指定されたのを機に、 まちづくりや景観形成にも取り組んでいた。
プロムナードコンサートなどのイベントの他に、 地区の清掃活動、 プランターボックスの設置・管理などの実践活動、 あるいは、 道路に面して自動販売機を置かないといったような企業間での各種の約束も取り決めていた。
このような素地の上で復興に向けての検討が始められたものであるが、 20数回の協議を重ねた末、 10月に会員間の合意のとれた復興計画書が策定された。
“まちの復興に旧居留地の蓄積を活かす”ことを基本方向とした上で、 4点のまちづくり方針を設定し、 壁面線の統一やパティオ・アトリウム・ポルティコ・パサージュ等、 街区と建築に内包される広場空間の確保など、 目指すまちなみの方向を打ち出している。
「復興ガイドライン」の策定
そして引き続き、 「復興ガイドライン」の策定作業がはじめられた。復興計画がまちの将来方向を設定したのに対して、 これを実現させるために、 ビルの新築や改築時、 あるいは管理上、 各々はどのような点に留意すべきかを整理・提案するものである。
検討作業の中で、 各ビルの個性を封じ込めてしまうことのないように十全の配慮が必要だという議論が幾度となくなされている。
印刷発行は今年度中を目標に現在作業が進められているが、 被災ビルをはじめ多くのビルで設計作業が進行しており、 一刻も早いPRが必要であるとの認識から、 委員会内での合意のとれた内容については、 順次広報されている。
これら計画の会員企業間での合意形成を可能とした要因は、 日頃からのつきあい、 企業コミュニティの存在に加え、 近代建築物もしくはこれらによって形成されていたかつてのまちなみへの思いである。
古くからの神戸の中枢業務地としての地位を存続させ、 近年脚光を浴びていた商業展開の継続・発展を可能とするためには、 旧居留地の伝統的で個性あるアイデンティティを今後とも継承しなければならないということが共感されたといってよい。

震災で全壊した旧居留地15番館('95.1/20撮影)。
現在復元工事中

「神戸旧居留地/復興計画」('95.10)より
復興まちづくりまつり〈第1回世界鷹取祭〉(11/22〜24)の内容決定
「きんもくせい」第36号で紹介しました「第1回世界鷹取祭」の内容が決定しましたので、 お知らせします。
〈A会場〉:日吉町6丁目特設テント
〈B会場〉:海運町2丁目更地
〈C会場〉:野田北部集会所
〈A会場〉
<第2部>分科会
他に、 「魚崎郷再建酒造群」や「鷹取地区周辺ウォールペインティング」など計16件が選ばれました。
ちなみに、 昨年の受賞者は、 オリックスのイチロー選手。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
鷹取祭前夜祭……・11月22日(金)15:00〜17:00
・会場:大国公園
・司会:西条遊児、 岡まりこ
・めでたやもちつき、 ベンポスタこども サーカス、 民族舞踊など
鷹取祭第1日目……・11月23日(土)10:00〜18:00
〈メイン会場〉:大国公園及び周辺
・ベンポスタこどもサーカス、 大道芸、 琵琶法師鎮魂コンサート、
NEWスポーツ、 まちかど伝言板、 屋台出店
・連続シンポジウム
「コレクティブハウジング応援団」13:00〜15:00
「神戸復興塾」15:30〜17:30
「せせらぎの川シンポジウム」18:00〜20:00
・まちかど写真展
「まちつくりゲーム」10:00〜18:00
「各種写真展」同上
「建築祭」10:00〜18:00(1階)
・・地区将来構想模型展、 狭小宅地戸建住宅展、 協調・共同住宅展
「映像祭」同上(2階)
・・青池監督「野田北部・鷹取の人々」第1〜4部上映、 他鷹取祭第2日目……・11月24日(日)10:00〜15:00
〈メイン会場〉
1日目の催し+ドングリ銀行神戸
よろず相談会、 まちかど写真展、 まちかどトーク
〈B会場〉
「公園ワークショップ」10:00〜13:00
「まちつくりゲーム」10:00〜15:00
「各種写真展」同上
〈C会場〉
1日目の催しと同じ復興スタート宣言……・11月24日(日)16:00〜
・大国公園にて
行事(だんじりねり歩き、 だんじり太鼓、 ベンポスタ)
式典(復興宣言、 鏡割り、 未来へのメッセージなど)
〒653 神戸市長田区浪松町2-1-7 TEL.FAX/078-736-2579
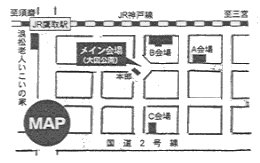
会場見取り図
復興のアイドル“フッコちゃん”INFORMATION
日本都市計画学会防災・復興都市づくりワークショップ
震災に学ぶこれからの都市計画のあり方
(大阪市弁天町オーク2番街7階、 Tel06-577-1430、
JR/地下鉄中央線弁天町下車すぐ
<第1部>復興都市づくりの実態と課題
1)防災計画と復興計画
中林一樹、 吉川仁、 増田昇、 大西一嘉
2)市民参加と計画支援
林泰義、 高見沢実、 小林郁雄
3)計画・事業制度と住宅・市街地復興
北条蓮英、 清水喜代志(大阪市)、 橋本彰 (神戸市)
HAR基金第3回公開審査
(神戸市中央区元町通4丁目、 TEL/078-361-4523)
※HAR基金秋の募金キャンペーン実施中!!
「一人一口1万円を5千人の方にお願いしましょう」

人間のまちづくり映像祭」延藤×青池トーク
11/3〜8 こうべまちづくり会館ネットワーク事務局より
「がれきに花を咲かせましょう」が景観ポイント賞受賞!
「第10・11回神戸景観・ポイント賞」の特別賞に当ネットワークの活動である「がれきに花を咲かせましょう」が受賞しました。![]()
小林郁雄氏、 第6回ロドニー賞受賞!
当ネットワークの世話役である小林郁雄氏は、 震災後のまちづくりに多大な貢献を行ってきたとの理由でロドニー賞を受けました。
P.4
Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
 きんもくせい40号へ
きんもくせい40号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ