
自由討議/1日目:六甲道駅南再開発事務所
そのお礼も兼ねて、 「集中討議」の報告をさせていただきます。

関東では震災関連情報もほとんどなくなり、 次第に震災の記憶が薄れつつあるのが現状です。
個人レベルで何かにかかわろうとしても、 なかなか思うようにいかないのが現実です。
特に被災地から遠く離れた者にとっては、 相当な努力をしない限り時間ばかりがどんどん過ぎていくこの頃です。
「集中討議」は、 そんな中で発案されました。
震災復興について自由に、 かつ集中的に討議できる場、 関東をはじめとする被災地以外の若手研究者 (実行委員会) と地元専門家・市民が自由に討議できる場づくりをしようというのが一番の目的でした。
具体的内容を企画し、 実行委員会を組織化し、 財源を確保し、 さらに専門家に参加を依頼して形が整ってきたのはようやくこの7月に入った頃でした。
最終的な6グループ構成に落ちついたのも、 7月11日のことです。
各セッションでの討議概要・役割分担は一応想定して臨んではみたものの、 実際には前セッションの積み残しや意外な展開などもあって、 セッションが進むにつれて、 セッションの合間に調整したり決定しなければならないことは増大する一方でした。
とくに2日目の討議が終わってから3日目の最終セッション(公開ワークショップ)を迎えるまでの時間は、 相当「充実」したものにならざるをえない、 という状況でした。
この「宣言」は実行委員会から外に向かっての宣言であるとともに、 私たち実行委員自らの規範としての意味をもつものです。
*
その状況については別途、 各グループ・セッションの討議プロセスも含めた「記録」としてとりまとめたいと考えています。
集中討議に加わっていただいた方々はもちろんのこと、 会場となった六甲道駅南再開発事務所、 こうべまちづくり会館には格別の配慮をしていただきました。
神戸芸工大、 神戸大からも学生・院生の協力を得ています。
宿泊所兼作業所となった神戸インスティテュートにも大変お世話になりました。
また、 住宅総合研究財団の助成なくしてこのような場は実現できなかったことを申し添えます。
この場を借りて、 皆様にお礼申し上げます。
実行委員一同、 今後も何らかの形で息長く復興の問題に関わっていきたいと考えています。
県営片山住宅と市営浜添住宅(共に仮称)はもうすぐ建設が始まり、 第1号入居は来春3月の片山住宅である。
ワークショップの枠組みは次のようである。
入居者が決定していない段階で、 しかも仮設住宅の多くの人はできれば地元の公営住宅に入りたいと熱望しているのに、 入居できるのか否かの保証なしでワークショップに参画してもらうのは、 あまりにも酷なんではないかと思った。
《コレクティブハウジングは集まって共に住みあう意味が強いだけに、 入居後の協同居住をうまく稼働させるためには、 入居前の協同居住の学習と協働トレーニングが欠かせない。
加えて、 コレクティブハウジングの本領を発揮させるためには、 核となる共有スペースにおいて住み手の希望、 提案を計画案に反映させる仕組みづくりも欠かせない。
その点において、 ワークショップはコレクティブハウジングを知ってもらい、 共に住みこなすための意識を喚起し、 また安心して住みつづけられるための運営・管理のあり方を住み手自らが考えていくのによい方法である。
》というのは、 私の持論でもある。
しかし、 これはすでに入居者が確定している場合の話である。
ワークショップ方式は大賛成だが、 不特定多数が使用する公共施設等の計画づくりと、 公営住宅といえども特定使用となる住宅での計画、 しかも多くの人ができれば当選して入居したいと思っている被災地での状況とではちがうのではないだろうか……。
しかし一方で、 行政と専門家が独りよがりで計画策定しているのではないだろうか、 コレクティブハウジングのニーズは確かにあるだろうが、 わたしたちの思いが本当に受け入れてもらえるのだろうかという不安もないわけではなかった。
これに対して延藤さんの意見は次のようであった。
また、 今回の計画は、 災害公営住宅の一環として供給されることから、 いくつかの制約は否めない。
ワークショップ実施前に以下の点について、 専門家と行政の意識を共有する必要がある。
・真野地区に建つとはいえ、 原則では入居者は公募形式を取らざるを得ないが、 早期の入居者の選定、 グループ応募の実現は可能かどうか。
》
それでも私はまだつらい気分で、 第1回ワークショップを迎えた。
当日の参加者は、 真野地区の仮設住宅入居者やまちづくり協議会の役員と住民の方々、 それに遠方から自転車に乗って来られた久二塚まちづくり協議会の仮設住宅入居者、 延藤研究室のスタッフ、 まちづくりプランナーや学生、 神戸市職員等々、 総勢70名を越えた。
ワークショップが始まってしばらくした頃、
「わしら入れてくれるんやったら、 なんぼでも意見ゆうけど……」
という声が聞こえた。
ワークショップが終わる頃、
「まぁ、 入れる人は少ないな。
全戸が地元優先入居というわけでもないやろうし。
入れんかっても、 また工場跡地こうてもろて、 次にもこんな住宅建ててもらお」
という声が聞こえた。
私は心から頭を下げた。
ワークショップは延藤研究室の周到な準備に負うところがとてもとても大きかった。
さらに真野地区の長い歴史をもつ住民主体のまちづくりの土壌があってのものである。
この年になってひとり住まいをしていると、 周りの人に心配をかけるので。
」〉
合う集合住宅とする。
建設戸数29戸のうち、 21戸を高齢者世帯に、 8戸を一般世帯とする。
なお、 高齢者住宅は生活援助員の派遣があるシルバーハウジングプロジェクトである。
自然の色。
町屋風の屋根等。
南側廊下と住戸近くのたまり場づくり(路地の再現)。
戸外への広がり、 連続性をもつ住戸プラン(例えば、 住戸内の台所と戸外のたまり場への連続性をもつ型)。
高齢者の生活の安全性への配慮(緊急通報システム、 オール電化システム等)。
住戸と住戸専用面積(1DK・35m2・15戸 2DK・45m2・12戸3DK・55m2・2戸)。
合計面積 206m2)。
屋外(青空テラス=立体路地、 たまり場、 屋上菜園、 屋上広場)
その検討の主な内容は次のようなものである。
これまで製作された第1部〜第4部を1日で観ることができます。
最終日の8日(19時〜)には、 青池監督、 延藤安弘氏(名城大学教授)、 及び海外から来神される映画監督のゲスト(交渉中)を交えたトークも行われます。
なお、 これは“人間復興”をテーマに11月1日から行われる「神戸100年映画祭」の一連のイベントとして行われるものです。
こうべまちづくり会館2階ホール(神戸市中央区元町通4 TEL.078-361-4523)
阪神春日野道駅南すぐ)
編集の都合上11月5日(火)必着分までを掲載します。
早い目に事務局までお送りください。
「集中討議」開催までの経緯
「集中討議」の発案は昨年暮れにさかのぼります。
公開ワークショップ/3日目:こうべまちづくり会館「集中討議」の概要
6グループの構成と「集中討議」の全体の流れは、 右の通りです。「集中討議・神戸宣言」
最終的に実行委員会が「神戸宣言」としてとりまとめ、 最後の公開ワークショップで発表したものの主要部分をここでは紹介します(WWW版では全文を掲載しています)。「集中討議・神戸宣言」全文
まちづくりとすまいづくりの連携を目指した提案「集中討議」を終えて
「できる限り自前でやる」との基本方針で臨んだ「集中討議」でしたが、 多くの面で地元の力を借していただきました。
6グループ構成と「集中討議」の全体の流れ
(★:グループ討議 ☆全体討議)日程 9/11 9/12 9/13 グループ s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 G1マクロ ★自由討議 意識・認識の共有 ☆
情報交換会★
先進的・萌芽的事例の検討★
事例を踏まえて一般システムへ☆
中間報告会★
行動計画★
発表準備☆
公開ワークショップG2連続復興 G3コミュニティ G4計画・事業 G5情報 G6組織
災害公営住宅でコレクティブハウジングの建設が始まる!
ワークショップ方式で決めた真野地区浜添コレクティブハウジングの計画
(被災地にコレクティブハウジングを!/その9)石東・都市環境研究室 石東 直子
災害公営住宅でコレクティブハウジングの事業化が下表の6地区で進められている。ワークショップで煮つめた浜添住宅の計画案
浜添住宅の基本計画の策定は神戸市職員と外部委員とからなる「真野コレクティブハウジング研究会(宮西悠司座長)」(以下「研究会」と記す)で検討を重ねてきたが、 特筆すべきは地元の仮設住宅入居者やまちづくり協議会の役員等の参画によるワークショップで計画案を決定したことにある。
「研究会」で延藤安弘委員(名城大学教授)が計画づくりを建設予定地の周辺住民や仮設住宅の人たちによるワークショップ方式でやろうと提案された時、 私(石東委員)は声には出さなかったがエッー!と思った。
「コレクティブハウジングを疑似体験してみよう!」
……・夢を語り合い、 不安を解消する知恵をみんなで出し合う
「第1回で語り合った夢や提案はどんな形になったかな」……・設計者による2つの計画案を確認し、 よりよいものにしていく
「管理・運営と入居者選定等に向けての今後の流れを考えよう」……・誰が住むのか、 どうやって住むのか
《今回の計画は、 公営住宅という点から現時点での入居者の特定はできないが、 建設予定地周辺の住民等が疑似的に居住者の役を演じてワークショップをやることは、 さまざまな問題のあぶり出しが期待できるとともに、 入居者選定後の協同居住の学習と協働トレーニングをワークショップでやる場合のよい参考になる。
これらについて「研究会」で検討を重ね、 ワークショップを実施することにした。
・共有スペースと占有スペースの役割分担がどこまで自由になるのか(例えば、 共同風呂を作るとしたときに、 住戸はシャワーのみにできるのかどうか)。
・ワークショップをすることによって得られる住み手側の生の声が、 どこまで反映されるのか。
《 》内の文章は延藤さんのワークショッププログラムの枠組みについてのレジュメから引用。
「入れるかどうか分からんのに、 こんなん殺生や……」
団地名 コレクティブ戸数 入居時期 住戸専用面積 コレクティブ共用面積 県営 東部副都心・脇浜(中央区) 44 10年度下期 35〜44m2 362m2 南本町(同上) 27 9年度下期 32〜43m2 182m2 岩屋北町(灘区) 22 9年度下期 35〜44m2 105m2 片山町(長田区) 6 8年度下期 31m2 56m2 大倉山(中央区) 32 9年度下期 34〜37m2 22m2 市営 浜添(長田区) 29 9年度下期 35〜55m2 206m2 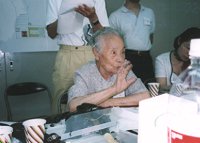
〈第2回ワークショップに参加された94歳のHさん。
「わたしは仮設住宅にはいっていないんやけど、 こんな住宅に入れてほしい。浜添住宅の計画・設計概要
コレクティブ協同部分の内容-屋内(食堂、 厨房、 食品庫、 談話室、 多目的室、 便所、 倉庫。入居時までの検討課題
協同居住を順調に稼働させるための管理・運営システムとそのサポート体制の確立が必要であり、 引き続き「真野コレクティブハウジング研究会(第2部)」と地元でのワークショップによって検討をすすめていく。
(10月10日記)コレクティブハウジング浜添住宅基本計画
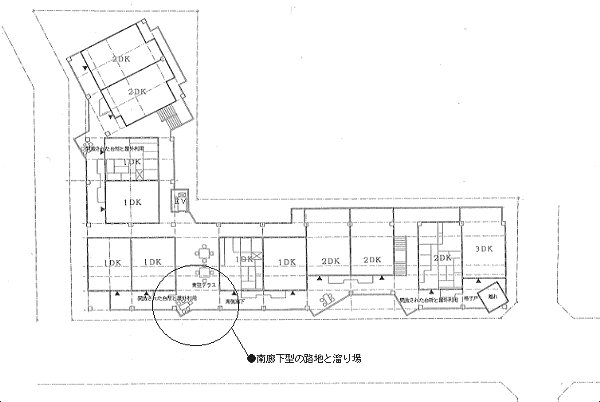
2,3階平面図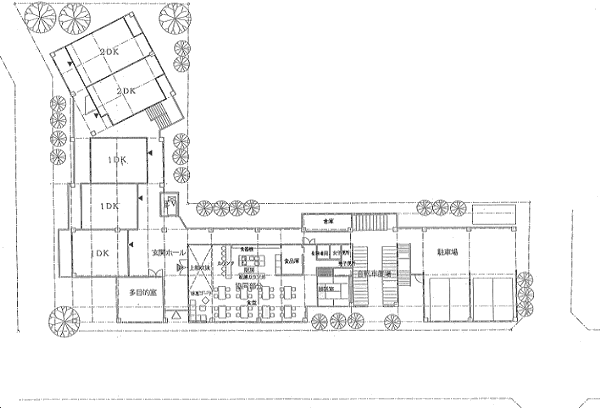
1階平面図
南廊下型の路地とたまり場のイメージ
外観パース
INFORMATION
人よ集え!まちよよみがえれ!「人間のまちづくり映像祭」
震災直後から野田北部・鷹取地区で映像を撮り続けている青池憲司監督の記憶のための連作「野田北部・鷹取の人々」が、 11月3日から8日まで連続5日間にわたって一挙上映されます。
※期間中会場では震災後の野田北部鷹取地区の写真パネルが多数展示されます。現地からの報告とパネルディスカッション
「復興まちづくりの現在」-HAR基金の助成活動から-
〈現地からの報告とパネルディスカッション〉
〈HAR基金からのメッセージ〉
倉本加世子(富島を考える会)
後藤祐介(神戸市東部白地復興支援チーム)
上田耕蔵(長田・協同居住支援団)
岡田兼明(まちづくり市民財団)
ネットワーク事務局より
「復興市民まちづくり」VOL.7発刊へ!
まちづくりニュースを早い目に送ってください。
'96/8〜10に発行されたまちづくりニュース等を収録します。
解体撤去跡地に咲いたコスモス
(神戸市灘区楠丘町3丁目)
P.4
Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
 きんもくせい39号へ
きんもくせい39号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ