
「住吉第一住宅復興・まちづくり協議会」設立総会.
'96.6/22.東灘文化会館
設立総会は、 東灘文化会館において約80名の参加者を集めて開催、 名称・対象エリア・規約・役員の就任等が承認を受け、 今後の活動に向けての組織づくりが行われた。
協議会の目的としては以下の3点が掲げられている。

戦災復興の区画整理が終了していたが、 狭隘・不規則な道路が多くオープンスペースも不足気味でインフラは未整理であり、 また狭小な宅地の割合も高く、 必ずしも良好とは言い難い居住環境であった。
震災の被害は甚大で、 棟数ベースで約46%が滅失し、 戸数ベースではそれが約58%に上る。
死者は40名、 住宅の滅失等の理由により、 従前居住地からの転出を余儀なくされている世帯は約48%に達してる。
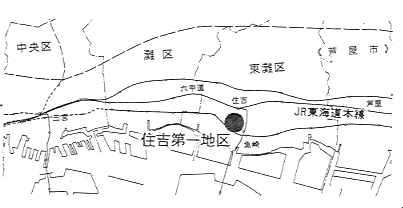
その過程で、 住吉を中心に活動するヴォランティア組織である情報センター、 神戸復興新聞、 林空間研究所と交流するようになり、 平成7年9月に、 これら有志とともに住吉地区復興支援グループを結成し、 様々な支援活動を続けている。
一方、 住吉に9地区あるうちの1つ住之江地区では、 地区長、 副地区長を中心とする有志が、 地元の過疎化や子孫に残せる誇り高い町の衰退を憂えて、 震災直後から、 特に住宅復興を目標に積極的な活動を展開していた。
倒壊建物の解体除去の円滑な推進、 公営住宅建設を要請するための行政との折衝、 地元有力者やこの地域に特徴的である大地主との面談、 仮設住宅入居者への慰問など、 地域復興へ向けた様々な努力が積み重ねられていた。
そして今年の2月頃から、 以上のような状況を踏まえて住吉地区復興支援グループと住之江地区副地区長との間で、 まちづくり協議会設立への合意が得られ、 緊密に連絡を取り合うようになる。
地区協議会役員や震災後この地域の復興に関わってきた有志によって準備会事務局が結成され、 だんじり祭を終えた今年5月13日には住宅促進委員会という名称で準備会が発足、 まちづくり協議会設立へ向けての意思の確認がなされた。
その後、 事務局を中心に、 地区住民全員に対するチラシの配布・郵送、 ポスターの掲示、 各役員を通じての設立総会参加への呼びかけ等、 住民に対する周知活動を行う一方、 今後の組織の運営、 規約や目的を明確にし、 合意を得るための活動が展開された。
そして6月22日、 設立総会開催の日を迎えた。
まず第一に、 住宅の早期復興を目的としている点である。
前述のように住宅の滅失により全世帯の約48%が従前居住地からの移転を余儀なくされており、 種々の理由で希望しても戻ることのできない現状がある。
すなわち、 住民主体のまちづくりを始めようにもその起点がない、 戻って住める場所を確保することから始めなければならない。
これが住宅の早期復興という目的に直接に結び付いている。
次に挙げられるのは、 協議会を「住吉第一」とし、 第二、 第三のまちづくり協議会が立ち上がることを期待している点である。
今回のまちづくり協議会は、 住吉に9つある地区協議会の中の1つを母体に設立されたが、 将来的に複数のまちづくり協議会がまとまりを持ち、 より大きな視点からまちづくりができるように、 他の地区に呼びかけを続けている。
前者はまちづくりの全体構想を、 後者は具体的な事業化をそれぞれ受け持ち、 相互に調整し合うことになっている。
また一方、 まちづくりニュースを発行、 広報活動を継続し、 不在住民の追跡調査や、 意向調査のためのアンケート等も行う予定である。
震災後の阪神・淡路において、 現代都市にまつわる様々な課題が、 時間を一気に圧縮された形で噴出し、 未解決のまま投げ出されている。
住民主体のまちづくりという視点に立ったとき、 そこで何が可能か、 住吉第一住宅復興・まちづくり協議会の設立と今後の活動の継続は、 そのあまりにも大きな課題への、 試みの一つとして位置付けられてゆくだろう。
以上 ('96.9/12記)
p1,4
今リアルに報告するとすれば、 個人、 立場、 協議会、 地区状況によって考え方がいかに多様なものであるかということ、 役員に女性がおられる協議会はまちづくりの実感があるということ、 長田の女性は生活感があって優しいというぐらいか。
そこで、 この「まちづくり報告」はまちづくりの現場における個々個別の話し合いや、 個々の動向の総体をできるだけ鳥瞰的に「後追い的計画論仕立て」として記述することにする。
しかし、 その後今日まで、 社会資本が投資されなかったことから相対的に環境水準は低下し、 インナーシティといわれる都市の衰退化が進行しつつある状況の中、 今回の震よりとりわけ大きな被害を受けることになった。
復興のための土地区画整理事業手法は、 これまで蓄積されてきたコミュニティ・産業・文化(個別性)を含めた地区全体を身体にたとえるならば、 古くなった骨格の補強(新しい骨格の挿入)を図り、 身体自身の回復や新しい成長を図っていくための体質改善システムとして捉えることが大切でないかと考えている(とはいえ大手術であるため相当なカンフル注射等が必要)。
これまでの条里制を踏襲した当地区の骨格を基本にしながら、 骨格の補強を図る手法としての土地区画整理手法の活用という意味から当地区における区画整理手法の展開を「新条里制土地区画整理」と仮称することにする。
長田は高齢者の割合が高く、 零細企業が多い街であるだけに、 もとの街に帰れるか、 もとの生活に戻れるかという個人レベルの「生活の復旧」が最も切実で緊急な問題である。
人々のこれまでのつながりを含め、 これまでの生活をいかにとりもどすかという個人レベルの問題を復興まちづくりは担っている。
●「生活の復旧」に関してまちづくりとしての考慮すべき重要なポイントとしては、 第一に「早期再建」があげられる。
時間の経過によっては、 借地・借家で居住していた人々、 特に地域外待機所で生活している人々の不安を拡大しこれまでと異なる人生の選択に迫られる人々もでてくるだろうし、 地場産業の復興に大きな影響を与える。
特に高齢者の方から「いつ帰れるか」という声を多く耳にしてきた。
協議会の役員さん達が日夜献身的に活動されてきたのも、 「一日も早く」という言葉に集約されている。
●第二に「安い住宅の供給」があげられる。
震災によって、 古い木賃住宅等こそが実は低家賃の住宅を提供する重要な社会資本であったことを思い知らされる結果となった。
公営住宅等の低家賃住宅の供給や、 接道不適格住宅に対する基盤整備と安い住宅供給ができるよう仕組みが求められている。
●第三に「コミュニティ・人間関係の継続」があげられる。
「もとの街に帰りたい」という多くの声はこれまでなじみ親しんだ人々のつながりがいかに大切かを物語っている。
復興まちづくりは単にハードづくりではなく、 震災で離ればなれとなったこれまでのコミュニティ、 人と人のつながりを取り戻すことでもある。
まちづくり協議会はこの時、 コミュニティ組織としての果たす役割も大きい。
当初からの個人の生活復旧についてのストレスに加え、 産業基盤としての地域の発展性の心配からくる事業者のストレスもある。
新しい下町として再興させるには、 誰もが「住みたい」と思う環境水準、 事業者が新しく「都市型産業として再興したい」と思うアメニティ環境等、 まちが新生するにふさわしい長期的展望を踏まえた都市環境基盤の整備も望まれている。
まちづくり協議会は、 この条里制街区コミュニティの1〜2が一つの単位としてそれぞれ単独に順次結成され、 現在21協議会ができている。
一般的には、 地区全体に一つの協議会があり、 その全体のもとに小組織がつくられるいわば「ピラミッド型協議会」が多いが、 新長田駅北地区の場合は、 コミュニティ最小単位(条里制街区=町丁単位)のそれぞれが協議会をつくり、 必要なテーマや足なみに応じて、 いくつかの協議会が連合化するといういわば「リゾーム型協議会」であることが特徴的であるといえる。
●このリゾーム型協議会方式での利点としては、
又、 街区毎の多様な考え方が共生しやすい。
等々。
特に幹線的道路や公園等の根幹的施設の問題、 住工等の住み分け、 産業面の取り組み等に対して。
大掴みにみて21協議会役員のうち中心的活動をされている方が平均5人としても、 当地区には100人以上のリーダー的人材があることになる。
これまで各協議会総会や住宅再建等勉強会などで住民集会が平均5回、 各回50人程度集まっているとするとのべ5,000人にのぼる一般の住民がまちづくりのために集まっていることになる。
これに各協議会役員会での会合を含めると膨大な住民のまちづくりへの参加があり、 これが将来いかされないはずはない。
●一方、 街区を越えるまちづくり課題に対しては、 協議会どうしの協力関係が不可欠であるが、 協議会間の共通テーマ、 調整課題に対する対応を図るため、 まちづくり提案の前後の時期から協議会の様々な街区の連合化が徐々に進行しつつある。
主に都市計画に関わる全国の若手研究者たちが神戸に一同に会し、 被災地で復興まちづくりに取り組む専門家、 住民達も討論に参加しました。
テーマは「連続復興」「コミュニティの再生、 生活と住まいの再建」「計画・事業システム」「情報システム」「まちづくり組織」及び「マクロ(理念、 計画論、 全体の統合)」の6つで、 各グループごとの討論と全体討論が繰り返すかたちで行われ、 最終日にはまとめの報告として公開ワークショップが行われました。
このような取り組みは震災後初めてのもので、 現在の復興まちづくりが抱える困難な状況や震災後の新しい取り組みについての評価・課題等を整理するとともに、 今後の新たな展開に向けての契機となった討議であったように思います。
詳しい内容については、 後日主催者より報告していただく予定。
'96.5〜7月の3ヶ月間に発行されたまちづくりニュースを収録しています。
今回はニュース量はVol.5とほぼ同じですが、 9種類の新しく発行されたニュースを収録しております。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
[特徴]
以上の経過で設立された住吉第一住宅復興・まちづくり協議会には、 2つの大きな特色がある。[活動予定]
この協議会には、 「まちづくり分科会」「すまいづくり分科会」の2つの分科会が設けられている。
新長田駅北地区土地区画整理事業・まちづくり報告(II)
主として五位池線より東側を中心として
(株)久保都市計画事務所 久保 光弘
コー・プランから「きんもくせい」への投稿をかなり前から依頼され、 又幾度となく声をかけていただいていたが、 今回のまちづくりの特質や今現在も動いている状況の中でリアルな報告は一面的になりやすく方法的にかなり難しいと感じそのままになっていた。
II.新条里制土地区画整理
●大正期、 古代条里制を踏襲して行われた長田の大規模な耕地整理は、 いわば当時のニュータウンとして、 産業と生活が一体となったにぎわいのある下町を形成した。
―当地区の区画整理の特徴―II-1 復興土地区画整理に求められている課題
復興まちづくりは地域の人々の生活を短期間で回復させなければならないという切実な「生活の復旧」と、 インナーシティ化が進行する状況の中で将来に向けての「まちの新生」との両面をあわせて取り組むことが求められている。
―「生活の復旧」と「まちの新生」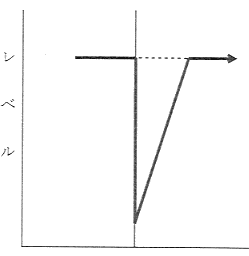
図3 生活の復旧-個人レベルの生活を早期に取り戻す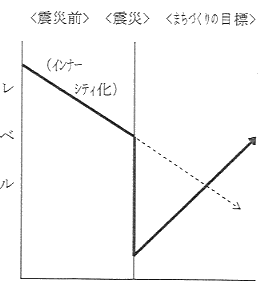
図4まちの新生-産業と生活の新しい展開1) 生活の復旧
●震災は人々の人生の生活設計を大きく狂わせてしまった。2)まちの新生
●ケミカルシューズ関連産業を中核として、 住工商が連環して成り立ってきた当地区においての復興は長期的な視点を踏まえた産業の再構築を図らなければ、 にぎわいのある街を取り戻すことはできない。II-2 まちづくり協議会の形態
●新長田駅北地区においては、 約100m四方の条里制街区が町丁単位であり、 コミュニティ単位となっている。
―リゾーム型協議会
●一方まちづくり推進上の問題点としては、
●しかし現在の人々のまちづくり活動が区画整理事業問題に終始することなく、 老人と子供が遊ぶ、 産業と住宅が共生する、 在日外国人と共生する、 真の新生下町としてまちづくりの方向に向かって長くまちづくりを続けられるならば、 この問題点-この時期の膨大な人々の労力-は当地区の最大の利点となろう。
私が関係している五位池線より東側で住民会合等が200回を越えているので、 新長田駅北地区全体の住民会合等はおそらく400回を越えるものと思われる。
協議会が合同で産業への取り組みを行っていこうとしている。
(注)
('96.9.1記) 〈つづく〉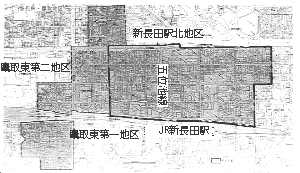
震災復興土地区画整理事業施行区域図-新長田駅北地区、
鷹取東第一・第二地区
INFORMATION
復興に関する“集中討議”行われる
9月11日から13日にかけての3日間、 阪神・淡路大震災復興集中討議実行委員会の主催による集中討議が行われました。
集中討議風景(9/13 こうべまちづくり会館)シンポジウム「緑の復興まちづくり・グリーンサミット」
日時:10月5日(土)13:30〜16:001部-各ネットグループからの報告
ドングリネット神戸(マスダマキコ)
ひょうごグリーンネットワーク(芦谷恒憲)
がんばろう神戸(堀内正美)
コープグリーンネット(丸山禎子)
阪神グリーンネット(林まゆみ)
2部-各代表からの提案
上甫木昭春(人と自然の博物館)
藤原千秋(芦屋市民街づくり連絡会)
吉田信子(神戸 市公園緑化協会)
長谷川弘直(都市環境計画研究所)
辻 信一(環境緑地設計研究所)
3部-全体討議
コーディネーター/中瀬勲(姫路工業大学)
(兵庫県立人と自然の博物館/澤木 TEL/0795-59-2028)
連続映画祭「連帯せよ!復興市民」
(神戸市中央区元町通4丁目 TEL.078-361-4523)ネットワーク事務局より
当ネットワーク編集「復興市民まちづくりVol.6」(学芸出版社刊)が8月30日に発刊されました。
P.4
Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
 きんもくせい36号へ
きんもくせい36号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ