〈特集〉「第1回被災実態学生発表会」
−論文の概要と講評−
7月6日に行われた「第1回被災実態学生発表会」(震災復興・実態調査ネットワーク主催)の概略は、 既に「きんもくせい」31号('96.7/15)でお知らせしましたが、 今回は発表された11組の中から優秀賞の3組の方々の論文/作品の概要、 及び小森星児審査委員長の講評を併せて掲載します。
審査に際し、 内容が都市計画をはじめ建築、 地理、 経済など多岐にわたるため評価が難しいのではないかと懸念したが、 実態調査という点で共通していたため、 専攻の違いはあまり問題にならなかった。
それより報告者の研究歴が学部、 修士、 博士と異なり、 また、 完結した論文かどうかで評価基準の設定が難しい。
前者についてはある程度の相対評価を取り入れることで公平を図ったが、 後者については例えば研究チームの一員として分担箇所を報告した場合、 あるいは博士論文の準備のために序論的な考察を報告した場合はどうしても印象が薄くなることは否定できない。
しかし、 今回の論文発表会の趣旨が大学や専攻の違いを越えた交流機会の拡大と研究成果をまちづくりの共通資産として活用することにあることを考慮して、 たとえ未熟であっても問題意識が明確で、 自らの足で材料を集めた論文を評価したいというのが審査員の共通した考えで、 受賞作はいずれもこの条件を満たしている。
おそらく卒業論文、 修士論文としての評価は今回の審査結果と異なるであろう。
丹念な資料の吟味や精緻な考察は、 わずか10分の口頭発表ではうかがい知ることができない。
その点、 報告者に申し訳ないと思うが、 今後も若者らしい感性と研ぎすまされた知性で被災地の復興に尽力されることを期待したい。
なお、 個々の受賞作については、 賞状授与に際し、 審査委員から審査経過の説明があったので、 以下簡単にそのコメントを紹介する。
調査をまとめた結果について自問自答を始め、 研究の客観的位置づけを考察している。
調査をとおして得たものの中から、 論文にまとめる中で捨てざるを得なかったものに多くの可能性や意味があることを知った。
そこから何を考え、 展開していくかを期待したい。
〈きんもくせい賞:早稲田大学・山本+笠〉
研究室のこれまでの地道な蓄積が個々の成果につながっている。
今後の現地のまちづくりとの連携を期待する。
〈TOMORROW賞:神戸芸工大・枇杷〉
プレゼンテーションが良い。
他都市(東京)からみるとこのような提案が今後の災害対応を考える上で役にたつ。
震災前の状況と震災後の状況を比較し、 未来を考えるとともに、 過去をどう未来に生かすかについても考察をして欲しい。
〈支援ネットワーク賞:神戸大・谷本〉
〈日経大阪BP賞:奈良大・藤田〉
今後の地域への貢献に期待する。
そこでは設備などの空間面はもちろん運営面でも様々な困難が発生しました。
それらの困難を乗り越えるため、 避難所ではみんなが知恵を出し合い、 多くの工夫がなされました。
調査を始めたのは3月下旬、 その後も継続的に小学校やテント村を訪れました。
また大半の施設が避難所としての役割を終えた秋以降も、 様々な施設の管理者に対して追加の聞き取り調査を行いました。
施設の種類によってもともとの条件は異なりますが、 得られた記録や図面からは、 それぞれの長所を活かしながら、 少しでも環境を改善しようという努力の跡がうかがわれます。
これらの経験から、 避難所となった典型的な施設について、 問題点やその克服の可能性を指摘したことが、 本論文の意義だと思われます。
ひとつは、 まちづくりや仮設住宅の環境改善を手伝い、 被災者を支援することです。
そしてもうひとつは、 人災による同じ悲劇を二度と繰り返さないよう、 被災地から多くの教訓を学び取り、 それらを指摘していくことです。
この論文は後者として位置づけられます。
それゆえ調査で被災者に迷惑をかけながら、 結果を直接還元できないという大きなジレンマを抱えることになりました。
また印象に残ったのは、 避難者や運営者の方の気概や苦悩のような人間の感情に根ざした部分です。
論文という客観性を重んじる文では伝えにくいものです。
避難所としての施設の貧しさを、 人のこころの豊かさによって補っていたのが現実でした。
多くの方のお話をうかがうことで、 素晴らしい経験をさせていただきました。
また最大の反省点は、 調査結果をもっと早くまとめて、 この震災での避難所の環境改善に役立てられなかったことです。
最後に私自身の猛省を込めて言っておきたことは、 本来は個人的な避難所調査は混乱期にやるべきではない、 ということです。
私が調査を始めたのは地震から二ヶ月後でしたが、 現場はまだまだ大変な状況でした。
だからその時期の調査については問題もあったと感じています。
誰のための調査なのか、 いつ調査すべきなのか、 共同調査は可能か、 避難者に疎まれてもやるだけの意味があるのか、 災害時の調査公害を防ぐため自らの調査を省みることも今後の大切な課題となります。
〈紅谷さんのURL〉
計画案は、 我々が調査を通して、 また、 実際に神戸に滞在して実感した人々の姿や噴出している問題を「個」の立場から考える、 「属人」というテーマで取り組むこととした。
まず、 個人の権利形態や年代から抱えている問題を抽出し、 それを元に、 それぞれの人の住宅再建を中心とした復興のモデルケースを作成した。
次に、 地域に住み続けることができ、 かつ新しい力を呼び込むことを目的とする共同建替えを「復興新町家」として定式化した。
その新町家は商店・住宅などそれぞれの機能にふさわしい形を持ち、 住環境の良好な街区を構成するものである。
つまり「復興新町家」によって、 様々な年代・職業の人々の復興の手段が建築という形で組み合わさり、 さらに建築が組み合わさることで「まち」になっていく。
この考え方を、 選択の幅を持つ「代替案」を含み、 5年後・10年後を想定した「シナリオ」と併せて提示した。
我々は、 混乱した状況の中でこそ、 解りやすい情報の提示が不可欠であり、 厳しい現実の中でこそ、 将来のイメージを描き続けることが重要だと考える。
今回の発表会を通しても、 各専門分野の成果が、 どのように開示され、 どのように結合し、 どのような形で現実にかなうのかというイメージをもち、 そこから議論を始めることが大切であることを再確認できた。
90Kほどあります。
ここでは、 それと同様に行政側から供給される仮設住居に代わりうる仮設住居システムが提案されている。
このシステムは、 本来建築行為においては脇役であるコンクリート工事用型枠、 リース足場フレーム、 安全シート等の仮設工事用資材を利用して次の点を考慮して計画されたものである。
午前中は「各地区報告」及び塩崎賢明神戸大助教授の中間まとめがあり、 8地区(下記参照)の住民代表から、 行政が進める復興計画に対する住民の活動状況や、 住民独自に進めているまちづくり活動等についての報告がありました。
午後は「区画整理」「再開発」「白地地区・住宅再建」の3つの分科会及び広原盛明京都府立大学学長のまとめと講演が行われました。
なお、 シンポジウムでは、 17地区の復興まちづくりに関する資料集(312頁、 ¥2,500)が配布されました(次回に「復興市民まちづくり連絡会」についての報告をしていただく予定)。
〈各地区報告〉
山手幹線の歩道に咲いていたひまわりの枯れ枝を刈り取っていると、 「夏の間楽しませてくれました。
来年も咲くといいですね。
」といいながら、 沿道の方々がはさみをもって作業に参加してくれる、 といったこともありました。
刈り取ったひまわりからは多くの種がとられ、 来年の春の種蒔きが今から楽しみです。
略儀ですが、 この欄にてお礼申し上げます。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
全体講評
小森星児・審査委員長
最初の試みだけに心配もあったが、 報告者はいずれも限られた時間を上手に使い、 それぞれプレゼンテーションにも工夫のあとが見られ、 長時間にもかかわらず最後まで緊張感が途切れなかったことをまず称賛したい。
第1回被災実態学生発表会風景〈第1回被災実態学生発表会〉
審査結果:
審査委員
委員長:小森星児(神戸商科大学名誉教授)
委員 :大河原徳三(前神戸市中央区長)
齋木崇人(神戸芸術工科大学教授)
高見沢実(横浜国立大学助教授)
山口一史(神戸新聞情報科学研究所顧問)
天川佳美(復興市民まちづくり支援ネットワーク)
p1
受賞作についての審査委員のコメント
優秀賞について
〈ネットワーク大賞:京都大・紅谷〉
学生らしい。
完成度が高い。
実現性に問題はあるが、 被災経験から、 街区内での仮設からの再生をプロセスとして提案していることを評価したい。審査員特別賞について
〈神戸新聞賞:大阪大・岩田〉
自分の足で歩いた学生らしい発見型の論文である。
調査で歩いて聞いたこと、 感じたことを大事にして、 神戸市職員となっても、 地域の人々の状況がわかる役人らしくない役人を続けて欲しい。
グループ調査であるため、 完結した論文としてまとめるには難しい面がでていた。
審査風景〈優秀賞・ネットワーク大賞〉
「阪神・淡路大震災における地域施設の避難所的利用に関する研究」京都大学工学部建築学科 紅谷昇平
論文の概要
ご存じのように、 阪神・淡路大震災では、 多くの住民が長期に渡って非居住用途の地域施設での生活を強いられました。調査を通しての感想
調査中は無我夢中だったのですが、 いま冷静に振り返ると、 学生としてやるべきことが2つ考えられます。今後の課題と反省
調査データをもう少し詳しく分析すること、 それから何らかの形で被災者の方の役に立って、 調査で迷惑をかけた借りを返すことが今後の課題です。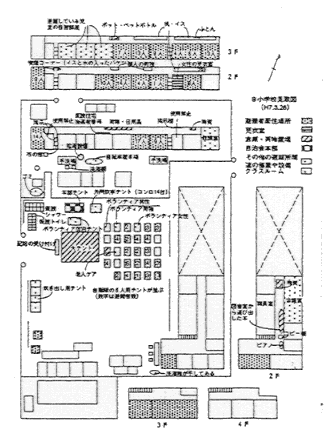
B小学校空間利用状況(H7.3.26)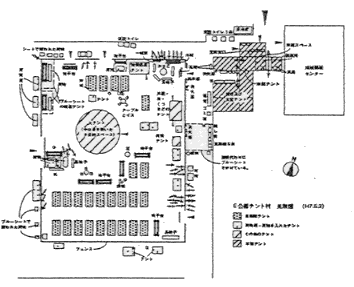
Eテント村の空間利用状況(H7.5.3)
http://fp-mimura4.archi.kyoto-u.ac.jp/persona_intro/beniya2.htm
〈URLは前田追記・96年中は有効でしょう〉
〈優秀賞・きんもくせい賞〉
「復興新町家」によるまちづくりの提案早稲田大学 都市計画佐藤研究室 山本裕道・笠 真希
我々佐藤研究室は、 昨年5月から、 長田区野田北部地区において調査・計画案作成など様々な活動を行ってきたが、 今回は、 その中から研究室の野田北部における活動と作成した計画案を中心に発表した。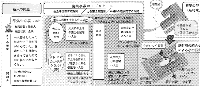
復興事業モデルケースのチャート
大きな画像は上の絵をクリック下さい。〈優秀賞:TOMORROW賞〉
新しい仮設住居システムの提案〜TUT SYSTEM〜−仮設工事資材を利用した仮設住宅−
神戸芸術工科大学環境デザイン学科 枇杷健一
阪神大震災以降、 関西の建築家を中心に様々な仮設住居システムが提案されている。

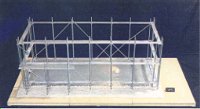
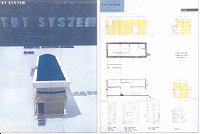
模型及びパネル
INFORMATION
復興市民まちづくり連絡会・シンポジウム開かれる
8月11日、 兵庫県私学会館において、 復興市民まちづくり連絡会主催のシンポジウム“復興まちづくりで今、 何が起こっているのか−区画整理・再開発と住宅再建の展望−”が開かれ、 地元住民、 プランナー、 建築家、 研究者ら約220人が参加しました。
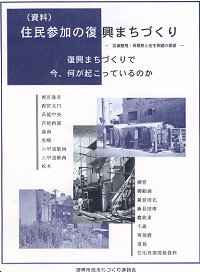
シンポジウム資料/表紙“はるかちゃんひまわり”の刈り取り行われる
8月26日、 地元岡本交友会の方々と阪神グリーンネットのメンバーら約30人でひまわりの刈り取りを行いました。
はるかちゃんひまわりの刈り取り 8/26震災復興・実態調査ネットワーク第4回交流会
「復興まちづくりとGISへの期待」(環境緑地/辻)
(神戸市中央区元町通4丁目 TEL.078-361-4523)
阪神・淡路まちづくり支援機構設立記念レセプション
(神戸市中央区橘通1-4-3 神戸地裁東隣、 TEL.078-341-7061)
第11回・阪神グリーンネット定例会議
ネットワーク事務局より
「きんもくせい」33号に、 切手を所望いたしましたところ、 30人の方々により多くの切手をお送りいただきました。
P.4
Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
 きんもくせい35号へ
きんもくせい35号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ