神戸まちづくり協議会連絡会に期待すること
神戸まちづくり協議会連絡会事務局長、 松本地区まちづくり協議会会長/中島 克元
「まちづくり」は、 平時の場合には、 少なくとも3年から10年位の年月をかけて少しずつ少しずつ進展していくものなのだそうです。「まちづくり」のコンセプトを決定し、 それを実現するためのインフラの整備にはじまり建物の建設計画、 そして街並形成などなど。
私達の「松本地区まちづくり協議会」は、 阪神・淡路大震災によって被災したことから神戸市によって「土地区画整理事業」に指定されたことによって作られました。
そのため「土地区画整理事業」の地域の指定から「まちづくり提案」の提出まで7ヶ月という異例のスピードで進み、 「地区計画」については3週間で決定してしまいました。
全てが異例ななかで進んできたことについて、 慎重論を唱える方からの厳しい指摘もありましたが、 全ては一日もはやい復興への住民の熱い願いがあったために大きなトラブルもなく進んでこれたのでありましょう。
この一連の運動を展開してきたなかで、 現行法の枠組みで行われていく「土地区画整理事業」について正しく勉強すればするほど、 この制度は「面的整備事業」であり、 住民の望んでいる「復興」には、 基本にこそなれ、 この制度一つだけで全てが解決するものではないことを実感しました。
新たな助成事業のお願いをするにしても、 一地域の協議会としては限界がありました。
そこで様々な連絡会に参加し少しでも役にたつことはないものかと、 藁にもすがる気持ちで会合に臨みましたが、 ことごとくがなにかしら特定の目的の有る団体が主催しており、 私達の現状の報告を聞くことはあっても残念ながら余り役にたつものはなかったのでした。
そこに日本建築学会近畿支部環境保全部会からの呼びかけに応じた17の地域の「まちづくり協議会」が発起人になって「神戸まちづくり協議会連絡会」を作ろうということになりました。
私達はここに活路を見い出せそうな感触をもちました。
特定の目的をもった団体によるものにコントロールされることなく、 「まちづくり協議会」のみによる自主的な団体としてスタートしようとし、 去る7月24日33地域の連絡会として発足するに至りました。
「神戸まちづくり協議会連絡会」として発足できましたことにつきましては、 関係者の皆様に心より感謝いたします。
今後の連絡会の活動の大きな柱は、 「まちづくり」に役にたつ情報の交換であると思っています。
そして一日もはやい「復興」のためにともすれば「要求団体」としてしか機能しなかった「まちづくり協議会」から実力をもった「実践部隊」となれるように努力していきたいと思っています。
対立から共生へと運動を転換できなければ「まちづくり」は、 たいへんな重荷となってしまうでしょう。
「まちづくり」を実現していく上で、 各々の立場の住民や、 行政機関の人達は全力を尽くすことは当然のことですが、 人間というのは完全体ではありません。
弱い人ばかりです。
お互いが弱い部分を補い合ってこそ大きな力となることでしょう。
「まちづくり」を進めているリーダーにかかる精神的ストレスは、 計り知れないものがあります。
幹部の人達にしか解らない苦労もあります。
「苦労」して「苦労」してその結果が「徒労」になってしまわぬように、 励まし合っていきたいと思います。
阪神・淡路大震災を体験した私達は、 なにもカップラーメンの作り方だけを覚えたわけではありません。
人と人との間のコミュニケーションの素晴しさ、 助け合うことの素晴しさを学びました。
今後は、 この豊かにでき上がったコミュニケーションを如何にして形にしていくかということであろうと思っています。
「三人寄れば文殊の知恵」というじゃありませんか。
話し合いましょう。
知恵を出しあいましょう。
そして一日もはやい「復興」の為に努力しましょう。

神戸まちづくり協議会連絡会設立総会
('96.7.24神戸アートビレッジセンター)
阪神大震災のもう一つの視点
建築家 武田 則明
1995年1月17日の兵庫県南部地震が起きて私も家は無事であったが、 アトリエが全壊した。ランニング中の計画や現場の図面や資料を救出するのが精一杯であったが、 大勢の人のおかげで約70%の図面、 図書、 資料は救出できたがフロッピーは飛び出してめちゃくちゃに潰れた。
コンピューターやコピー機は持ち出せなかった。
現在でもあると思っていた資料が欠けているのに気付かされる。
地震直後から建物の診断及び補強の相談を受けた。
マンション3、 店舗4、 戸建住宅7棟、 寺2、 教会1、 である。
マンションの場合震災直後から緊急建物判定の段階で、 ある人はレッドカード(危険)を貼るし、 別の人はグリーン(安全)を貼って混乱が起きていた。
当初は建物の内部に入らないで外観だけの判定であるので、 外観上問題が少なく見えても、 内部に入ったり、 詳細にチェックすると危険と判定されることもあった。
何時余震が来るかも知れない状況の中でやむを得ないことであった。
一方建物の構造施工が判っている人の場合は良いがそうでない時はより危険の方に判定する傾向がみられた。
例えば耐震壁が小さなクラックが発生していて、 雑壁が剪断破壊を受けている場合、 又耐震壁のクラックでも地震のための剪断クラックか地震以前から存在したとみられる収縮クラックかの区別がつかない場合は、 もし余震がきて安全と判断したのに壊れると怖いから悪い方へ悪い方へと判定しがちであった。
私は現在寺1、 廟1、 民家1、 のいずれも木造の耐震補強と改修工事を行っている。
西出町の民家の場合は公費解体の一週間前に相談を受けた。
調査すると、 約1/80程度傾いているが明治中期に建ったこの建物は表に格子と通り庭を持つ2階建てのしっかりした建物で、 持ち主もこの住まいに思い入れがあって、 建て起こし、 基礎の補強柱梁等、 材の朽ちた部分の取り替え及び屋根の葺き替え、 壁の塗り替え、 それに加え耐震壁の補強工事を行う。
問題点としては公費による無料解体は都市を片づける為には効果があったが、 十分に使用に耐える建物、 少し手を入れれば良い建物まで、 簡単に壊してしまったことである。
解体費を補修の補助金として出せば済む話である。
例えば述べ100m2の住宅が半壊状態であった場合、 建て起こしをして、 補強するだけならば300万〜500万程度の費用で済むが、 これを解体に5〜60万、 新築に2〜3000万円の費用がかかるとすれば解体新築に2050〜3060万かかるわけであるから、 300〜500万に対し、 解体費に5〜60万補助すれば250〜440万で済むわけである。
設計者も工務店も総工事費300〜500万円と3000万円を比べれば収益上は後者の方が儲かる。
又日本人は一般に古いものより新しいものを嬉しがる。
この結果解体撤去新築へのベクトルが大きく動いた。
又解体中に多くの住宅メーカーのセールスマンが走り回り、 ふと気付くと神戸中が住宅メーカーの展示場と化したように見える。
私は全ての建物を残せと云うのではなく、 都市のストックとなる建物は文化財でなくても全力を投入して改修して復旧すべきだと考えるからである。
一方私は京都で木造の寺を一棟設計していた。
宝地院が被災したので見に行ったところ、 ご本尊の阿弥陀如来は隣の保育園に避難していて、 本堂には崩壊しないようにつっかい棒で押さえてあった。
住職にこれは簡単に直ると断言すると、 住職はそうか、 それならお前にこの建て直しを頼むと云われた。
木造の場合、 屋根が地面に着くくらいになってしまえば、 建て替えなければならないが、 1/10〜1/20ぐらい傾いても日本の大工技術は仕口を直し補強を入れれば直るのである。
この寺の場合、 一部座敷・ホールの増築計画もあり、 土地の有効利用も考えて地下にそれらの増築部分を設けしっかりとした地下を基礎として木造本堂を元の位置に戻した。
今秋改修工事は完了する予定である。
日本には曳家、 起こし家を専業とする技術が残されている。
この技術を利用すれば大部分の建物は安価で直せたと断言できる。
そして、 当地区内のそれぞれの町丁単位で生まれそれぞれ特徴あるまちづくり活動をし、 まちづくり提案等を行ってきている21のまちづくり協議会は、 「新長田駅北地区まちづくり連合協議会」を結成した。
今、 相互に連携、 協力して、 より総合的なまちづくりに取り組もうとしている。
六甲山系の中の独立峯として、 東側からは単峯、 南側からは双峯の美しい姿を見せているこの高取山は古代の神体山、 神祭りの場であった「神奈備山」である。
また長田区の中央を流れる新湊川(もとの名称は苅藻川)は、 その支流の「檜川」の名が「霊力のある川」の意味を示すように、 農作物を豊かに育ててくれる恵みの多い川であった。
そして長田の名は苅藻川(新湊川)に沿って長く拓けた田地の美称といわれている。
このように長田は、 海に面して美しい山=神奈備山である高取山と、 恵み豊かな苅藻川(新湊川)を背景に弥生時代から人々が生活を始めた地域である。
これを条里制地割といい、 耕地は1町角の109m四方の碁盤目状に整理された。
明治18年作成の陸軍測量部地図を見ると、 長田区はこの整然とした条里制地割がよく残っていることが確認できる。
山陽電鉄西代駅の北側に4ha余りの西代公園があるが、 これは条里制耕地の潅漑池としてつくられた「蓮池」(一説には奈良時代の僧、 行基が造ったともいわれている。)
を埋め立てて造られたものである。
新長田駅北地区の中部から西部の区域は、 蓮池小学校区にあり、 この区域のまちづくり協議会の多くの会合は蓮池公会堂で行われているが、 この「蓮池」の名は歴史的な名称なのである。
「蓮池」の名は山陽道(現在の中央幹線)に沿っていることもあって、 苅藻川の名とともに「平家物語」「増鏡」「太平記」などの古典にしばしばでてくる。
長田の人々はそれに呼応して、 大規模な耕地整理に先進的に取り組んでいる。
明治44年頃、 神戸市農会は各地主に耕地整理の必要性をアピールするため、 小学校で講演会を開催。
市が補助金を出し、 地主が組合をつくる形態となっている。
この大正の初めに始められた耕地整理の特徴は、 将来市街地に発展することを予測しての土地整理であり、 農地を整理し、 道路をつくり、 新町名をつけるというものであった。
新長田駅北地区の大道通、 川西通、 細田町、 神楽町は西部耕地整理組合の耕地整理後新しく誕生した町名であり、 また水笠通、 御屋敷通、 松野通、 細田町(7丁目の一部)、 神楽町(6丁目の一部)は、 西代耕地整理組合の耕地整理後新しく誕生した町名であった。
この耕地整理は条里制による約109mメッシュに約8mの区画道路を配置し、 約100m四方の街区を形成するものであり、 この条里制街区が各町丁の単位すなわちコミュニティの単位となった。
この条里制を踏襲した耕地整理は長田の市街地発展の基礎となり、 大正の半ばには神戸市内で最高の人口増加を示した地域となり、 職住が共存した活気に満ちた下町を形成した。
しかし新長田駅周辺でみると、 山陽電鉄西代駅からJR新長田駅さらに五位池線を中心にJR新長田駅の南側一帯等は、 戦災による焼失が比較的少なかったこともあって、 戦災復興土地区画整理事業区域に含まれなかった。
この戦災復興土地区画整理事業に含まれていない区域は、 古い木造家屋が集中していることもあって、 今回地震により広範囲に倒壊、 焼失等による集中的な被害がみられた。
震災後の市街地開発事業として都市計画の対象区域は、 主にこれらの区域となっている。
「道がもえている」とは、 震災の時活動された消防士であり、 まちづくり協議会会長でもある野村さんの言葉である。
条里制に基づいて行われた耕地整理による約100mメッシュの8m道路も、 今回の震災ではいたるところで建物が折り重なって倒れ、 交通を遮断し、 たきぎのように燃えていったということである。
100mメッシュの街区内はほとんど幅員2〜3mの私道で、 その被害はより一層大きなものであった。
長田の先人達がつくった100m四方の条里制街区は、 町丁の単位としてそれぞれのコミュニティの基礎単位となり、 震災時の助け合いの場となり、 それぞれの条里制街区からまちづくり協議会が生まれ、 新長田駅北地区では協議会数は21に及ぶものとなった。
気心の知れた近隣の人々がつくった多数の協議会は、 大勢の住民が身近なまちづくりとして参加する機会をつくった。
条里制都市・長田の文脈を生かした復興まちづくりのツールとして、 土地区画整理事業手法の新しい展開が試みられてる。
ここではこれを「新条里制土地区画整理」と称し、 そのシステムとプロセスを次回紹介したい。
討論会に先立って、 当日午後からは震災後1年半以上が経過した被災地の見学が行われました(六甲道南→新在家→魚崎→住吉)。
ネットワークメンバーの説明で、 共同再建に取り組んでいる現場や、 震災後まちづくり協議会を結成した地区などを視察しました。
討論会では、 安井地区、 魚崎地区、 住吉地区、 深江地区、 新在家地区の震災後の取り組み報告、 及びフリーディスカッションが行われました。
その中では、 白地区域のまちづくり協議会たち上げの困難性-特に既存住民組織との関係の問題-、 コンサルタント派遣の震災後の実績の地域差(神戸市域とそれ以外)、 今後白地区域のまちづくりを推進していくための方策-実態調査の実施、 まちづくりメニューの検討など―といった議論がなされました。
この会議を契機として、 白地区域対策の充実を図っていくことが望まれます。
22種類あり、 内訳は芦屋3(ポピー)、 岡本4(ひまわり)、 楠丘6(コスモス)、 鷹取6(ペチュニア、 ひまわり)、 その他3です。
1枚200円です。
事務局までFAXにてお問い合わせ下さい。
ポストカードの説明(22種の中から5種を紹介)
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
宝地院の場合
宝地院住職中川浩安氏と私とは忘年会やその他パーティーで知り合っていた。
被災した宝地院の内部。
柱が傾いている様子が分かる。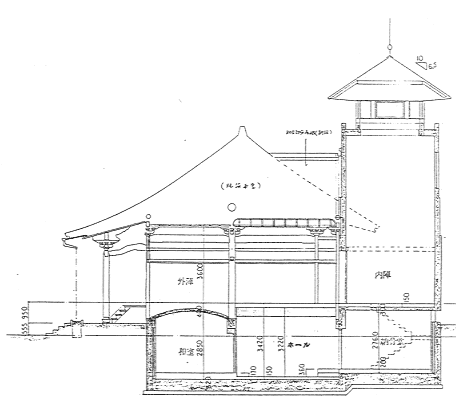
宝地院修復計画図
新長田駅北地区土地区画整理事業
―まちづくり報告(I)―主として五位池線より東側を中心として
(株)久保都市計画事務所 久保 光弘
震災地域最大の土地区画整理事業である新長田駅北地区(42.6ha)は、 平成8年7月9日「事業計画」が決定し、 事業がスタートした。1.条里制都市・長田
1-1 美しく豊かな自然が生んだ長田の里
長田区のどこからも高取山が仰ぎ見られる。1-2 古代条里制地割
古代、 班田収授の基盤として碁盤目状の地割、 いわば耕地整理が行われた。
明治18年の長田1-3 条里制を生かした耕地整理による市街化
土地区画整理法の前身ともいうべき我国の耕地整理法は、 明治42年に施行された。1-4 震災被害の地域
第2次世界大戦後、 戦災復興土地区画整理事業が実施される。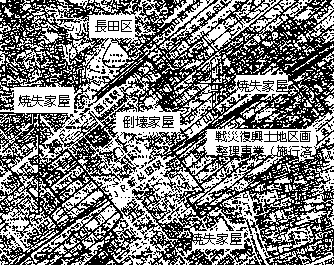
戦災復興土地区画整理事業区域と震災被害状況
(「区画整理9505」日本土地区画整理協会)1-5 震災復興土地区画整理事業へ
長田は、 土地利用や住民の気質等それぞれ個性ある様々な条里制街区コミュニティが多様にパッチワークされた条里制都市である。
('96.8.6 記)
p3
セミナー報告
コメントby前田
INFORMATION
「神戸東部・西宮白地地域対策討論会」開催
8月9日(金)、 都市計画学会防災・復興問題特別委員会第2部会の方々とネットワークメンバー、 及び行政の方々の参加による、 白地区域の復興まちづくりについての討論会が行われました。
新在家地区を見学する都市計画学会
の方々とネットワークメンバー“ガレキに花を”のポストカード(官製はがき)ができました
昨年5月より取り組んできた“ガレキに花を”の活動によって、 各地で見事に花開いた光景をピックアップし、 ポストカードにしました。

芦屋のポピー(96/5)、 岡本のひまわり(96/7)
楠丘のコスモス
(95/7.三角屋根の建物がネットワーク事務局)

鷹取の銀葉ひまわり(95/8)、 須磨の種蒔き風景(96/3)。第10回・阪神グリーンネット
ネットワーク事務局より
第15回・神戸西部市街地連絡会
……・野田北部地区/地区計画、 野田南部地区/復興調査、 湊川地区/ミニ区画整理
第17回・神戸東部市街地連絡会
・場所:神戸Fビル 11F
・内容:六甲道周辺再開発の今と今後の展望
※今後東部市街地連絡会は、 奇数月の第2火曜日に行う予定。
「残暑厳しい日々、 お身体ご自愛下さい」事務局一同
P.4
Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
 きんもくせい34号へ
きんもくせい34号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ