雲仙普賢岳災害その後
関西学院大学総合政策学部教授 片寄俊秀
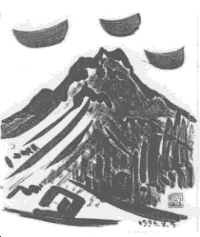
26年間の長崎生活から、 機会があってこの4月に兵庫県に参りました。
前職は長崎総合科学大学建築学科、 新しい職場は昨年新設の関西学院大学総合政策学部(三田市)で都市政策の分野を担当します。
私自身は災害は大嫌いなのですが(もっとも好きな人は少ないでしょうが)、 以前大阪府の千里ニュータウンづくりの現場で働いていたこともあって、 宅造災害など土砂系、 水系の災害には若干の蓄積があり、 長崎で起こった1982年の長崎大水害、 1991年以来の雲仙普賢岳噴火災害の問題、 とくに被災後の都市復興の問題にも取り組んできました。
小生の現在のメインの研究テーマは「観光と地域づくり」と「自然復元型まちづくり」で、 美しい楽しい自然の豊かなまちづくりの追求です。
災害復興の修羅場で夢のような話をするのはかなり勇気のいることですが、 「セキュリティとアメニティの統一的達成」は絶対に必要でありかつ可能であると信じているものです。
雲仙普賢岳災害その後の経過で、 こちらにあまり知られていない情報をいくつか紹介してみたいと思います。
かってイタリアの地震のときに各国から緊急に送られてきた仮設住宅がずらりと並んだとき、 欧米各国からのものと日本からの例のやつとのあまりのレベル差に恥ずかしくて顔を上げれなかった、 との話を聞いたことがあります。
島原では一部に4年近い仮設暮らしが続いたのですが、 阪神地方ではそれ以上という事態も予測されます。
したがって現在の仮設住宅の質の改善が緊急に必要と思われます。
島原市に長崎県が建設した仮設住宅の一部72戸は、 その後の改造によって36戸の公営住宅に生まれ変わって活用されています。
この住宅の特徴は、 (1)規模としては2戸1は変わらないが県の住宅課が主導して市と協力し、 プレハブ業者ではなく仕事の少ない地元業者の救済を兼ねて、 コンクリート布基礎の在来木造住宅方式として発注したこと、 (2)それでいて工期はあまり変わらなかったこと、 (3)土地は10年間の農地借り上げであったことなどです。
仮設住宅からの転出が進む過程で、 県はこの住宅の改造にかかり、 1棟1戸にし、 大屋根を設置することで居住性を良くし、 これを県営住宅(現在は家賃無料)として活用しています。
初動対策への投資を無駄にしないで、 あと5-10年は使える準恒久化した卓抜なアイディアであり、 災害列島のわが国ではこの発想は大いに普及する必要があると思います(図、 写真参照)。
公営住宅は木造平屋で2戸1棟の庭付き2LDKと3LDK、 家賃が13,000-16,000円。
復興用に供給された分譲住宅は土地が100坪で坪6-10万円。
建築費は40-50/坪で、 義捐金と復興基金による概ね1,000万円の支援額は、 住宅再建費用の1/3以上をまかなっています。
大都市の災害復興とはかなり状況が違うわけですが、 人口減とあらゆる産業が災害を機に土建業にシフトしてしまって今後の立ち直りがいよいよ困難になってきている状況の深刻さは、 想像を絶するものがあります。
過密都市の安全確保の困難さと、 過疎地問題の同時的な解決にむけて、 国土の均衡ある使い方についての本当の意味での政策が求められていると思います。
私は現代アートに造詣が深いものではありませんが、 ほぼ同時期にあったヴェネツィア・ビエンナーレにも十分対比でき、 思想的にはそれを上回るものがあり、 連携して世界にアピールすることができればもっとよかったと思いました。
ほとんど廃墟に近い空間が、 彼らの手で一気に光彩を放つさまに、 現代アートには不思議な力があるし、 全体を流れる空気にいつも感じる「現代アートの嘘くささ」がなく、 作家たちもこういう場を得てはじめて燃えるものがあるのではないか、 アートの世界に新しい息吹が生まれたのではないかといったことを感じました。
この間、 人材センターでは、 すまい・まちの復興に取り組む地域の皆様からの要請にお応えし、 建築物の共同・協調化計画、 分譲マンションの再建計画等の策定を支援するための専門家を派遣してきました。
この1年を振り返って、 人材センター発足の経緯や活動状況等について簡単にご報告します。
想像を絶する地震の被害を前にして従来のやり方では十分な対応が困難な場面が随所で見受けられましたが、 とりわけ、 多数の家屋が全半壊し、 すまい・まちの復興が大きな課題となるなか、 問題解決プロセスにおける専門家による助言や指導の果たす役割が常にも増して大きく認識されるようになりました。
つまり、 住宅建設やまちづくりに係わる制度や法律等は複雑な上に非常に専門性、 技術性が高いため、 専門家による支援なしには問題の十分な理解が難しいだけではなく、 建築物共同化・協調化や分譲マンションの再建等の具体的な計画をまとめていく過程のなかでは、 多様な権利者の間の調整を進め、 ルールづくりを行う必要があり、 ここでも専門家が重要な役割を演じることになるからです。
さらに、 被害があまりにも大きかったため、 県・市等の公的な相談窓口だけではマンパワーの面で十分な対応が難しかったことや、 また、 震災直後からコンサルタントや大学の研究者、 弁護士等の専門家がボランティアとして地元の復興支援に取り組んでいる例も多数ありましたが、 これらの専門家に対する資金面での公的な支援の仕組みを考えていく必要もありました。
このような事情を背景として、 専門家による支援制度を整備していこうという動きが震災直後から起こり、 これが人材センターとして具体化されたわけです。
幸い神戸市では震災以前から「まち・すまいづくりコンサルタント派遣制度」「まちづくりアドバイザー派遣制度」を実施していたため、 この制度を基に専門家による支援制度を充実強化することとし、 平成5年11月にまちづくり活動支援の拠点施設として開館されていた「こうべまちづくり会館」の施設と組織を活用して、 平成7年7月7日、 「こうべすまい・まちづくり人材センター」が開設されました。
この結果、 従来、 神戸市で実施していたアドバイザー・コンサルタントの派遣制度は、 「こうべすまい・まちづくり人材センター」に一元化されることになりました。
さらには、 平成7年10月に(財)兵庫県都市整備協会内に「ひょうご都市づくりセンター」が開設され、 「ひょうご都市づくりセンター」を通して阪神・淡路大震災復興基金の資金も活用できるようになり、 専門家派遣に加えて、 地域のまちづくり活動に対する助成事業も行うことになりました。
(1)登録専門家 227社・人
(2)専門家の派遣
主な意見としては、 (1)多様な知識経験を得る上で役立った。
(2)関係者への広報の面で役立った。
(3)中立の立場からの専門的なアドバイスが役立った。
等、 おおむね積極的なコメントをいただいています。
また、 6月17日には、 「ひょうご都市づくりセンター」と共催で「復興まちづくりセミナー」を開催し、 多数の市民、 専門家の皆様に出席をしていただきましたが、 今後もこのような催しを通して多くの方々にこの制度を知っていただくよう努力します。
問題解決プロセスにおける専門家の役割や各種の専門家のチームによるプロセスコンサルテーションの問題等のこれからのまちづくりの場面で役立つ情報を交換できる事例報告会等を開催していきたいと考えています。
さらに、 各種の支援・助成制度等の情報を提供する研修会も開催します。
以上、 簡単に人材センターのご報告をさせていただきましたが、 今後ともご協力をいただきますようよろしくお願いします。
〈お問い合わせ先〉
この野菜畑・花畑は、 かくしゃくとした91歳のおじいさんが専門的な技能を生かしてつくったもので、 それを住民たちで育てています。
先日ははじめて収穫した野菜をみんなで分け合って味わいました。
こういったことを通して仮設住宅の住民コミュニティが徐々に育成され、 「この仮設にずっといたい」といった声まで聞かれるようになっています。
この寿公園仮設住宅は、 ネットワーク事務局の近隣にあり、 今年2月頃から愛知県の育苗業者からいただいた花の苗などを配ってきました。
今後も住民の自主的な環境づくりへの支援を続けていきたいと考えています。
題名は「ひまわりになったはるか」。
震災後1年半を迎えた7月17日、 ひまわりが満開の岡本地区で発表会がありました。
今年3月31日に、 地元の方々と一緒に種をまいた阪神グリーンネットは、 この会でCDの贈呈を受けました。
このCDは、 1,000部作成され、 学校や福祉施設などに配布される予定。
そこで、 神戸市では、 「こうべっこ遊び場マップ」(A1サイズ)を作成し、 現時点で神戸市内で子供たちが遊べる公園を紹介しています。
問い合わせは、 神戸市市民局青少年課 TEL(代)331-8181。
p3
1階には、 震災被害の状況や復興まちづくりの現在など、 阪神大震災に関する豊富な情報をパネルやビデオを通じて紹介しています。
2階には、 相談窓口や被災者復興支援会議の事務局、 約150人ほどの収容できる多目的室(一般利用可)があります。
年末年始を除き年中無休。
開館時間は10〜19時。
8月6日(火)までに事務局に届いたものを対象としますので、 早い目に事務局までお送り下さい。
VOL.6は9月上旬、 大手書店にて発売します。
(2)討論
仮設住宅の改造による準恒久化
被災時に供給されるわが国の仮設住宅の質の悪さは、 国際的にみたとき際だっています。公営住宅の空き家問題
いまの阪神地方の状況では信じがたいことですが、 島原半島の復興公営住宅では96年6月現在で871戸中256戸が空き家となっており、 入居者の共益費アップと地元財政負担が問題となっています。現代アートによる文芸復興の試み
1995年夏に島原市で、 避難地区に指定されて廃屋となっていた6階建てのホテルを使って行われた「復興にKISS」と銘打った現代アート展は、 数十人の力量ある作家が取り組んだ、 なかなかのものでした。
(1996.7/23 記)
準恒久化された仮設住宅(浅野弥三一氏提供)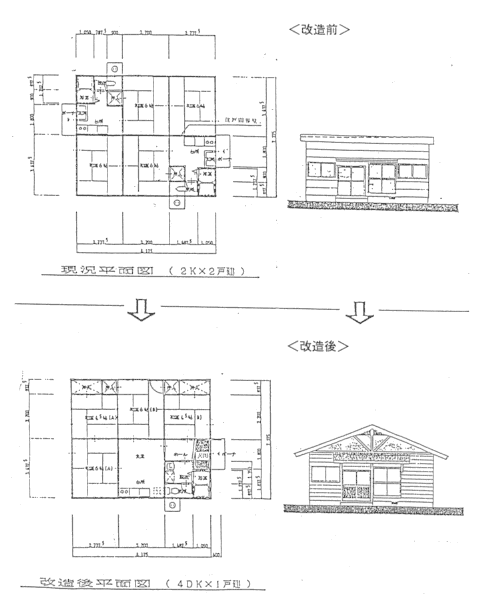
仮設住宅の改造による準恒久住宅化
「島原・深江地区木造住宅改善工事・平面図立面図」
こうべすまい・まちづくり人材センターの1年
こうべまちづくりセンター 明石 照久
平成7年7月7日に(財)神戸市都市整備公社こうべまちづくりセンター内に開設された「こうべすまい・まちづくり人材センター」は、 発足から早くも1年を迎えました。1 こうべすまい・まちづくり人材センター開設の経緯
平成7年1月17日の未明、 兵庫県南部地域を襲った阪神・淡路大震災は地元に未曾有の被害をもたらしました。2 こうべすまい・まちづくり人材センターの実績
専門家の登録件数と派遣実績は次の通りです(平成8年7月8日現在)。
*内訳 コンサルタント:207 弁護士:10
大学教員:7 不動産鑑定士:2 公認会計士:1
アドバイザー派遣・・60件 コンサルタント派遣……・75件 合計135件
建築物共同化、 マンション再建計画等の初動期段階の勉強会の支援
建築物共同化・協調化計画、 マンション再建計画等の基本計画案や基本構想案策定の支援3 専門家を派遣した団体からの評価
平成8年5月に平成7年度中に専門家を派遣した団体(82団体)に対してアンケートを実施しましたが、 61団体から、 回答が寄せられ、 54団体から役に立ったとの回答を得ています。4 今後の取り組み
(1)制度の普及・広報
制度そのものがまだ十分に知られていないように思われますので、 広報紙等による広報に努めていきます。(2)情報交換
現在、 実施しているすまい・まちの復興支援のための専門家派遣については、 質量ともにこれまでのものとは異なっています。
(財)神戸市都市整備公社 こうべまちづくりセンター 電話:361-4523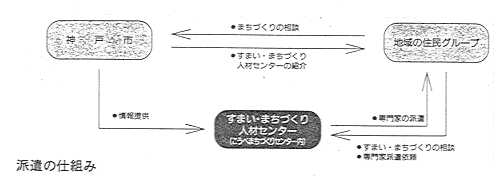
図・派遣の仕組み
INFORMATION
地域型仮設住宅における住民の自主的な環境づくり
神戸市灘区の寿公園仮設住宅(2階建て4棟、 総数28戸)では、 立派な野菜畑・花畑を住民自らがつくり、 自主的に仮設住宅周りの環境づくりを行っています。
仮設住宅の住棟間につくられた野菜・花畑
91歳のおじいさんがつくったカボチャ畑。
アルミサッシの窓枠を半分に切って支柱にした見事な作品!。“はるかちゃんひまわり”のCDできる
“はるかちゃんひまわり”(「きんもくせい」31号参照)が歌になりました。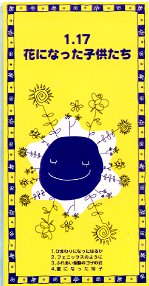
CDの贈呈を受ける阪神グリーンネット
('96.7.17 岡本公会堂にて)
1.17花になった子供たち」CDジャケット「こうべっこ遊び場マップ」できる
被災地では、 多くの公園に仮設住宅が建設されているため、 子供たちの遊ぶ場所が不足しています。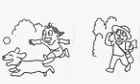
(イラストは井上保子さん)県の「住宅供給プログラム」の学習会
「復興まちづくりで今、 何が起こっているのか」
―区画整理・再開発と住宅再建の展望―
(1)区画整理地区のまちづくり
安藤元夫、 浅野弥三一、 岩藤元郎
(2)再開発地区のまちづくり
児玉善郎、 安田ただし
(3)白地地区と住宅再建
竹山清明、 野崎隆一
TEL.078-272-6872 FAX.078-272-6898震災復興・実態調査ネットワーク/今後の予定について
〈第4回交流会〉:9月7日(土)
〈第5回交流会〉:10月5日(土)
〈第6回交流会〉:11月9日(土)
*場所は、 各回とも、 こうべまちづくりセンター2階ホール(時間は追ってお知らせします)
フェニックスプラザ開設
三宮駅の南側に兵庫県の復興支援館「フェニックスプラザ」が7/20開設しました。
7/20オープンした「フェニックスプラザ」ネットワーク事務局より
「復興市民まちづくり」VOL.6刊行へ
〜まちづくりニュースを今すぐ送って下さい〜
'96.5〜7発行分のまちづくりニュースを掲載します。「神戸東部白地地域対策報告会」
(1)白地区域の取り組み報告
……・住吉地区(重村力)、 魚崎地区(野崎隆一)、 深江地区(後藤祐介)、 安井地区(石東直子)
……・都市計画学会震災復興問題研究会、 行政等の参加による討論
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
P.4
Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
 きんもくせい33号へ
きんもくせい33号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ