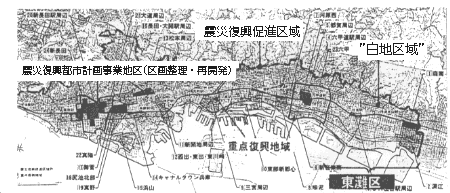
神戸市重点復興地域指定図
(主催:東部白地地域復興支援チーム、 後援:東灘区役所)が開かれました。
区レベルで行われる復興市民まちづくりの取り組みは、 これが初めてです。
参加者は延べ約220人で、 特に午後は主催者側の予想の倍に近い人達が集まり、 活気あふれる催しとなりました。
午前中は、 震災直後から野田北部・鷹取地区で映像をとり続けている青池監督の「野田北部・鷹取の人々」第2部の上映及び監督の語りが行われました。
監督は、 震災後の自身の経験を通して、 まちづくり協議会の結成=コミュニティの自立の必要性について熱っぽく語りました。
午後の前半では、 地元にゆかりのある5人のパネラーによる座談会「東灘らしさを生かしたまちづくり」が行われました。
酒や谷崎潤一郎など東灘の特色ある資産を有効に生かしたまちづくりの必要性、 息の長い住民主体のまちづくりの必要性などについて、 約2時間のディスカッションが行われました。
後半では、 東灘で1つでも多くのまちづくり協議会を立ち上げる目的で、 まちづくり実践講座「まちづくり協議会の設立と運営」が行われました。
神戸方式のまちづくり協議会の特徴についての紹介が行われたのち、 岡本地区、 深江地区、 西宮・安井地区の各まちづくり協議会事務局長が、 具体的な協議会運営の経験や苦労話、 まちづくりにささげる思い、 等々について語りました。
また、 このフォーラムに先だって、 6月5日〜9日の5日間、 コープこうべシーアで「復興まちづくり展示会」が行われました。
震災後、 東灘では関西建築家ボランティア、 住吉復興支援チームなど、 多くの建築家、 プランナーたちが地元支援活動を継続的に展開しており、 市場再建や住宅共同化、 マンション再建、 復旧・復興状況の継続的な調査活動、 神戸市と締結した「まちづくり協定」、 その他さまざまな復興に向けた活動や提案等について、 パネルや模型によりわかりやすく紹介しました。
非常に多くの来訪者の目に触れる催しとなりました。
震災後神戸市内だけでも100近いまちづくり協議会ができましたが、 ほとんどが区画整理、 再開発の都市計画事業地区であり、 “白地区域”では地域ぐるみの復興まちづくりの取り組みは悪戦苦闘を強いられています。
このフォーラムを契機として、 今後地元協議会立ち上げに向けた連続まちづくり講座の開催や、 地元まちづくりを支援する専門家の研修(専門家の絶対数が足りない!)等の取り組みを通して、 “白地地域”の復興まちづくりを発展させていくことが求められています。
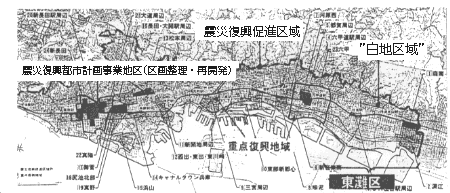


北淡町の場合、 町内6地区のうち、 とりわけ被害が甚大で面的な広がりを示す地区は富島地区(人口2,339人、 世帯数809-平成2年国調)で、 死者25人、 全・半壊家屋が約8割であった。
その後、 地区世帯数の6割程度が家屋を解体・撤去。
現在では富島地区の世帯数全体の約4割程度が、 半壊家屋を起こして修繕したり改築するなどのケースを含め、 震災前からの建物に居住しているといわれる。
北淡町では、 震災半年前の1994年夏頃から〈都市計画区域〉指定(町の大半を未線引による都市計画区域に指定)の必要性が町広報紙等を通じて徐々に住民に流されており、 1995年4月に指定するスケジュールが示されていた。
しかし、 大方の一般住民にとっては〈都市計画区域〉の指定自体は、 実生活に影響がほとんどなく、 とくに緊急に指定する必要性も感じられず、 町が勝手に進め広報も事務的な掲載にとどまり内容の重要度も理解しがたいといった状況であった。
震災は、 こうした行政と一般住民との意識のギャップを一気に吹き出させることになった。
町当局は、 復興予算の獲得を視野に入れ震災後いちはやく都市計画区域指定を2ヶ月繰り上げて2月7日に告示し、 同時に面的に被害のひどかった富島地区の一部(約21ha)に土地区画整理事業導入を決断。
対象地域に入る富島中心部の各町内への説明会を経て、 2月22日土地区画整理事業を実施する〈地域〉と幹線〈道路〉の計画案図を決めて、 都市計画案縦覧(2月28日〜3月13日)を行い、 住民意向調査を進めていった。
3月17日の土地区画整理事業の決定公告までの間に、 復興方針、 区画整理事業のしくみ、 手順や計画案(主として事業実施の範囲と幹線道路の位置)について、 各町内会の小ブロックごとに説明会を開催している。
また、 被災市街地復興特別措置法に基づく被災市街地復興推進地域の指定についても同様な手続きを行っている。
町ではこうした計画の具体的な検討・調整を進め事業を推進していくにあたって、 「地域住民と行政が緊密な連携を図るため」、 富島地区の各種団体役員を中心に指名した委員からなる富島地区震災復興協議会を3月下旬に設置し、 以後基本的には町当局の考え方は復興協議会に示され、 そこでの議論を踏まえて、 内容が煮つめられ町の責任で公表されるというルートが形式的には出来上がっていく。
こうした町当局の対応を見ていくと、 震災前に行政側が描いていたシナリオ(縦貫道路等の建設と開発計画の推進→北淡町の都市化→都市計画区域指定の必然性→中心市街地の土地区画整理事業導入の有利性・必要性)をベースにして、 復興予算の獲得を中央に働きかけやすい条件づくりを一直線に進めていった様相が明らかになろう。
その後、 住民間の大きな争点になる幹線道路の計画(道路幅と位置)は、 いわば土地区画整理事業を絡めて復興予算を獲得するための条件を吟味するなかで行政の論理から素朴に出てきたものであり、 道路位置も公共施設の建物を避けたうえで、 コストと幹線道路基準を勘案して機械的・技術的に描いた結果であるとみることもできよう。
町当局が当初設置しようとした富島地区復興協議会は、 町当局が震災前に描いたシナリオを理解しつつ、 かつ「被災市街地復興推進地域-区画整理事業の導入(事業地域と道路計画)」を前提として、 (復興予算が充分獲得しうる範囲での)スケジュール的制約を受けながら、 事業計画の中身の吟味と大枠の決定を委ねることのできる委員会であったと思われる。
復興協議会のメンバーとしては、 事業計画地域に居住する各種団体の役員、 関連する3つの町内会長、 仮設住宅団地の世話役、 地元町議会議員、 地区外居住の土地権利者を指名し、 専門家のアドバイザーを用意して、 いわば既存の地域住民組織の長や役員を丸抱えし、 その力を結集させて、 住民とのパイプ役、 調整役を委ねるという体制をとったといえよう。
しかしながら、 以上の自由裁量度の形式的な大きさにもかかわらず、 復興協議会には、 当初から実質的にかなり厳しい制約が課せられることになった。
議論すべき内容の専門性の高さ、 解決すべき課題の住民への影響度の大きさ、 住民間の生活条件や意識の違いの大きさ、 行政が結論までに用意しうる時間制約のきつさに加えて、 <区画整理事業導入と道路計画という前提>に関する住民側の疑念や町の掲げる地域の将来イメージと住民各層の抱く地域イメージとの落差が、 深刻な利害対立や利権構造への疑惑を内包しており短期的な解決がきわめて困難であること、 住民構成が都市への通勤者を含み多様化してきたため各種集団や町内会の役員が地域を代表して私権に関わる問題を討議すること自体が困難になってきていることなどが実質的な制約としてあげられる。
これらの制約の中では、 復興協議会の自由裁量度もスケジュールに縛られて、 行政の提示する資料の吟味に終始し、 行政の計画に承認を与えるだけにもなりかねない構造的な難しさを内包していたのである。
復興協議会が会議を重ねていくにつれて徐々にこうした制約があらわになっていき、 それを克服する困難さも明らかになっていった。
復興協議会は、 およそ月に2度のペースで開催され、 当初、 地域の将来像とまちづくりのあり方についての議論を行い、 高齢化、 人口減少をくい止めるまちづくりのための条件を考えていったが、 それを考える前提として、 減歩率や地積の算出方法、 土地の評価額、 残存家屋の移転や再築費用への補償、 小規模宅地の減歩率の扱い等を含め、 区画整理後の具体的なまちのイメージ(街区構成等)を求める声も委員の中には強く、 徐々に残存家屋の移転・再築に対する補償基準のアップや減歩率の引き下げ、 土地の先行買収の可能性の検討といった区画整理事業が住民に受け入れられるための基本条件を示し整備させることに議論の焦点が据えられていった。
こうした復興協議会の活動状況は、 7月初旬までは、 町の震災対策広報である「震災復興ニュース」の中で区画整理事業や手続きの記事内容と一緒に、 部分的に紹介されている。
しかし、 協議会メンバー以外の住民にとっては、 町の区画整理事業決定以降、 5月段階までは住民に対する情報は町の「震災復興ニュース」等の広報に限定されていた。
そこでは、 道路幅と位置を含めた区画整理事業そのものは既決として、 その上での区画整理事業のしくみや技術的問題の解決といった事業推進のための議論しか見えず、 復興協議会の議論内容も不透明で結果として事業促進を支持するものとして映ったため、 家屋が残存している世帯など区画整理事業により甚大な影響を被る住民の危機感と焦りは高まっていった。
こうしたなかで、 昨年5月初旬「富島を愛する会」が結成され、 町当局に対する3項目((1)富島地区だけに区画整理事業を導入した理由、 (2)15mの幹線道路が必要な理由、 (3)住民の意見の反映のさせかた)の申し入れを行った。
これに対する町の回答は、 あらためて区画整理事業導入による住民への影響の大きさを再認識する結果となった。
6月には、 町主催による土地区画整理事業の地区別説明会をはじめ、 有志主催のまちづくり講演会、 「富島を愛する会」の区画整理学習会等があいついで開催され、 それぞれの立場で現状の問題点と対応策を検討し当面の戦術を再構築し、 一般住民への広報活動や会員獲得が積極的に行われた。
それぞれの会合で、 対立があらわになり、 復興への様々な障害への対処の仕方について、 町当局と「富島を愛する会」のギャップが明確になっていった。
ギャップは、 富島地区の将来像、 現状評価、 復興方針すべてに関連し、 震災前に行政側が描いていたシナリオ(縦貫道路等の建設と開発計画の推進→北淡町の都市化→都市計画区域指定の必然性→中心市街地の土地区画整理事業導入の有利性・必要性)そのものに対する疑念とその背後の利権構造への疑惑にまで、 時間がたつにつれて広がっていった。
こうした町当局と「富島を愛する会」とのギャップは、 復興協議会の立場も微妙な性格に変え、 これまでの活動経緯と区画整理事業受け入れ条件についての議論の成果を7月下旬以降「富島地区震災復興協議会だより」として出していく過程で、 住民間での感情の亀裂が顕在化し、 賛成派-反対派の対立という構図が生み出されてくる。
「富島を愛する会」が、 地元の人間関係を駆使して、 対象地区内の482世帯(65%)の署名を集め、 土地区画整理事業を白紙撤回したうえで住民とともに町づくりの話し合いをすべきという申し入れを町長、 町議会に対し展開していったことは、 そのひとつの象徴である。
その後、 復興協議会の活動は、 各住民団体のリーダーの出席が思わしくないため、 結果的には会長を含めた数人の幹事による合議に委ねられ、 実質上の論議は中断され、 町の方針を追認したうえで意見を付す機関としての性格が顕著になっていく。
町は、 独自の責任で各町内会の小ブロックごとの説明会に踏み出すことにより(96年3-4月)、 その説明会での〈感触〉を頼りに、 規定方針に沿った事業計画決定へ進もうとしているのが現状である。
土地の先行買収を既に進めている町としては、 住民による対案・要望が出されない限り突き進まざるをえないし、 最後まで計画に反対するものは少数にとどまり押し切れるという情勢判断をしているということであろう。
しかし、 膠着状態は依然として続いており変化の兆しは見えていない。
現在のところ双方が手探りの状態であり、 その中で信頼関係は狭まって亀裂は深まり、 力での対決の様相すら帯びてきているのである。
被災地と被災地外との「温度差」は、 いつもこれらの壁を崩すうえでの最大の難敵であった。
しかし、 事例にも見られるように、 時間・制度・予算の大きな制約を絶対的な前提条件として設定したうえで、 各地域の復興まちづくりを考えようとしていく限り、 住民が相互に納得し生活再建に結びつくプランの形成は難しい。
また、 基礎自治体が地域住民の亀裂を生み出し、 住民間に鋭い対立が膠着化していくかぎり、 冒頭(「きんもくせい」28号)にも述べた「温度差」を乗り越え被災地の住民と被災地外の住民とがリアリティをもって連携できるロジックと仕掛けを創造する可能性は薄い。
基礎自治体と地域住民との間に、 より創造的な関係が築かれ、 それをバネにして制度そのものや制度の運用のしかたを動かしていく試みが、 いままさに被災地の各地で問われている(おわり)。
今回は、 32団体の申請のなかから下表に示す計16団体に対し、 合計1,100万円の助成が決定しました(1回目は11団体、 計600万円)。
活動テーマ ・ 活動グループ名 ・ (助成金額(万円))
(1)仮設住宅脱出のためのローコストアパートの開発と建設
(2)魚崎郷から御影郷・西郷へと続く「酒蔵のまち」の復興
(3)住民合意、 住民主導と行政支援のまちづくりを目指す
(4)復興コミュニティ・デザイン・プロジェクト
(5)ランドスケープの復興支援-阪神グリーンネット-
(6)復興とまちづくり支援「震災写真記録の現状調査と保全活動」
(7)北淡町富島地区のまちづくりプラン作成活動
(8)震災復興映像記録の作成と上映・普及
(9)神戸市東灘区魚崎・甲南地区の復興まちづくりの支援
(10)元住んでいた住民が一日も早く元の生活を取り戻すため
(11)神戸市東部地区白地地域における復興まちづくり組織のたちあげ
(12)長田地区の下町のよさを生かした街づくりの懇談会
(13)住吉地域における住民主体の復興まちづくり支援活動
(14)長田のよさを生かしたコレクティブ(協同居住)な住まい方の応援
(15)共生の街-神戸アジアタウンの実現-
(16)真野・立江地区共同建替え事例の記録作成と研修活動
合計16件(1,100万円)
今回は、 申請団体のプレゼンテーションも工夫が凝らされ、 これまで行ってきた活動の実績やこれからの活動展望等について活発な発表がなされました。
また、 明治生命の社員の皆様から絶大なるご支援(約430万円)をいただいたことや、 少しずつ基金の輪が広がっていることにより、 第1回の助成より金額、 団体数とも拡大しました。
引き続き、 被災地の「まち・すまい・くらしの再建」を目指すHAR基金の一層の拡大が望まれています。
なお、 6月22日(土)には、 下記のように第2回助成団体の贈呈式と第1回助成の成果報告会が行われました。
<日時>:6月22日(土)13:00〜17:00
なお、 午前中のシドニー大学の発表は、 6月16日より被災地(主に水道筋地区、 鷹取地区)において行ってきている現地調査、 計画設計作業のまとめとして行われるものです。
震災関連では、 阪神グリーンネットも表彰を受けます。
表彰式並びに講演会は以下のとおり。
災害復興まちづくり再考(第2回)
事例:北淡町富島地区の区画整理の経緯と住民の対応
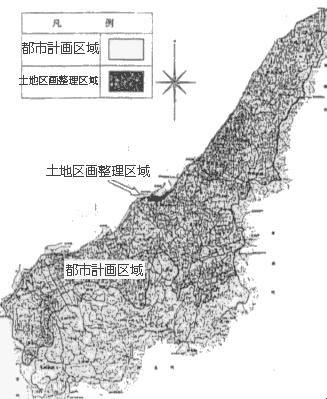
北淡町・都市計画決定図
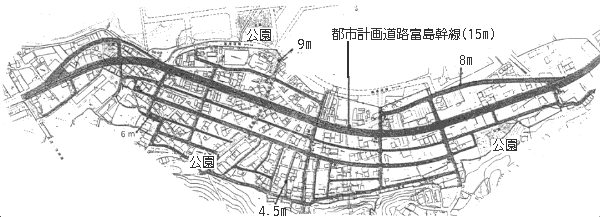
富島地区復興土地区画整理事業・事業計画案
阪神・淡路ルネッサンスファンド(HAR基金)
6月1日、 こうべまちづくり会館において、 阪神・淡路ルネッサンスファンド(HAR基金)の第2回目の公開審査会が行われました(第1回目は昨年11月に実施)。
―第2回助成決定―
坂茂建築設計(150)
灘の酒蔵を復興させる会(30)
西須磨まちづくり懇談会(30)
コミュニティ・デザイン・チーム(30)
ランドスケープ復興支援会議(100)
阪神大震災「震災記録情報センター」(60)
富島を考える会(60)
野田北部を記録する会(100)
関西建築家ボランティア(60)
琵琶町復興住民協議会(30)
神戸市東部白地地域復興支援チーム(100)
長田のよさを生かした街づくり懇談会(30)
住吉地区復興支援グループ(60)
長田・協同居住支援団
ケア付き仮設住宅での実践を踏まえ具体化を図る (140)
尼崎で協同居住型住宅を実現させる会 2団体合同
神戸アジアタウン推進協議会(60)
真野・東尻池町7丁目立江地区共同建替え支援チーム(60)
<場所>:こうべまちづくり会館2階ホール
(神戸市中央区元町通4丁目、 TEL.078-361-4523)
<内容>:・第1回助成団体からの報告
・第2回助成団体からの報告
(上記表の(5)、 (11)、 (14)の団体から発表予定)
・野田北部を記録する会のビデオ上映
・その他


HAR基金第2回公開審査風景(6/7)INFORMATION
第1回被災地実態学生論文発表会について
「きんもくせい」28号でも紹介しましたが、 その後内容の追加・変更がありましたのでお知らせします。
・日時:7月6日(土)10時〜17時
・場所:神戸インスティチュート
(神戸市灘区五毛丸山53-1、 灘丸山公園北側、
阪急六甲駅より市バス2番「五毛」下車 078-881-2277)
・参加費:1,500円(資料代含む)
・お弁当を持参のこと
・論文発表:第1部(AM)シドニー大
第2部(PM)神大、 神戸芸工大、 神戸、 商大、 阪大、
奈良大、 京大、 大市大他
・審査により、 賞状、 副賞を授与
・審査員:小森星児、 齋木崇人、 大河原徳三、 山口一史、 天川佳美
・主催:震災復興・実態調査ネットワーク
(阪大:小浦 06-879-7640、 コー・プラン:小林)
ネットワーク事務局より
「さわやかまちづくり賞」受賞!
復興市民まちづくりネットワークが、 第5回「さわやかまちづくり賞」(まちづくり活動部門)に表彰されます。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
(2)講演「未来につなぐ新しいまちづくり」小森星児(大阪商大教授)
P.4
Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
 きんもくせい30号へ
きんもくせい30号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ