1)「公費除却が過剰に行われた」
倒壊に加えて、 公費除却の進展によって、 特に、 密集地域の狭小敷地戸建て住宅と、 共同住宅が多く滅失した。これは、 アメリカの住宅小切手制のように、 修繕か除却建替えか、 移住かを選ばせる制度であれば、 より多くの修繕が出たものと推察される。
JRの北側から、 阪神電鉄の南側までの最も被災のひどかった100 ha強をとりあげると、 倒壊滅失住戸を戸数ベースで80%を越す街区が数箇所、 60%を越す街区が約20箇所存在する。
現在の状況で見る限りその回復の見通しは、 立っていない。
山手幹線から国道43号までの約130 haのなかで、 約3,600棟の内1300棟が倒壊滅失しているが、 95年12月現在で407棟が再建に着手している。
ただ、 基礎工事で止まっているものも少なくない。
これら407棟の内訳を従前用途から見ると、 長屋建て14棟の内、 長屋建てに戻ったもの1棟、 非木造共同住宅に替わったもの1棟で、 木造賃貸アパート12棟の内、 長屋建てに変わったもの1棟、 非木造共同住宅に変わったものは7棟で、 それぞれ減少していく傾向である。
ただし、 従前用途が戸建てであったものが非木造共同住宅に移りつつあるものが12棟あるが、 これらは長屋建て、 または木造共同住宅の果たしていた低所得層向け住宅ではなさそうである。
到達率は75%であり、 回収は630票である(実質回収率約34%)。
このアンケートでまず驚いたのは、 きわめて広域から郵便が戻ってきたことである。
県外は27%で遠くはブラジルやアメリカ西海岸、 マレーシアからも返送されてきた。
これらの回答者達の現在の住居を見てみると、 公的仮設住宅は20%、 公共代替住宅は6.2%で、 仮設住宅がアンケート公害で回答率が悪いことをさし引いても、 避難者の住居の代表として仮設住宅を考えることは大変危険であることがわかった。
特に、 親戚の家、 友人の家、 関係者の供給等が17.5%もあり、 その他非住居、 間借り等を合わせると20%前後の人々が大変窮屈な思いをしていることを想像させる。
75%の人が住吉地区内に戻りたいとし、 東灘区内で85%を越え、 神戸市内は90%の人々に達する。
では、 人々は何故戻れないのか。
詳しい分析は後に譲るが、 人々が抱えている障害についての自由回答欄からは圧倒的に大きな問題として、 土地、 家屋の権利問題と融資資格の問題が浮かび上がってくる。
既存不適格敷地問題の対策はあっても、 これらの復興阻害要因への緊急対策が必要であろう。
ちなみに12月までに再建を完了した40軒への別のヒアリングでは親戚の家に避難し、 持地に自己資金で再建した例が多い。
公的融資は350万円の緊急融資の使用が目立った程度である。
ここに抜本的対策が望まれている。
本年2月12日、 3月18日に各新聞が報道したように3月17日六甲道駅南地区まちづくり連合協議会は、 地区住民の総意として公園・道路配置計画案を決めました。
今回は、 この案を住民が決定するに至った経過を合意形成の手助けをしてきたコンサルタントの視点から報告します。
詳細な経緯は、 「復興市民まちづくりVol.3、 Vol.4」に4つのまちづくりニュースが掲載されていますので参考にして下さい。
とても、 まちづくりについて住民と行政が話し合う雰囲気ではなかった。
それが、 6月18日3つのまちづくり協議会と連合協議会が発足した時点では半分ぐらいには回復していたと思う。
協議会発足後各ブロック役員会は、 毎週若しくは隔週開催されることになった。
役員約20名、 コンサル4〜5名、 行政3〜4名の会合である。
互いに人間性や誠意が通じる規模である。
役員主導による進行、 それをコンサルがサポート(議案資料提供、 説明、 助言等)し、 行政(施行者)は、 要請のあった時のみ発言するという運営である。
こういう中で、 この事業は住民の意見を十分聞いて進められることが明らかになっていき、 徐々に信頼関係が回復してきた。
これには、 施行者が地区内に事業用仮設住宅を早期(5月、 8月、 10月)に計94戸建設し、 早く当地区に戻ってきたい住民の要請に応えたことも寄与している。
まちづくり協議会で、 公園の大きさ・配置を中心とした5.9haのまちづくり案を議論していこうとするとき、 この案は代替案の1つであると住民(各ブロック役員会には考える会のメンバーがリーダー的役割で数名づつ参加されている)も、 コンサルも考えていた。
この案自体が役員会で俎上に乗ることはなかったが、 街区ごとに小規模な広場を分散配置する案として議論した。
結果的には、 街区内広場を公園と同じ公共施設と見ることは難しく広場部分の土地費は再開発施設建築物の床価額に含まれるという点で、 自己負担額を限りなく小さくしたい住民の総意と異なり、 採択されるに至らなかった。
けだし、 この案は、 都市計画決定案と対比する時、 そのやさしさ、 人間らしさ、 手作りの街らしさ、 暖かさが感じられるものであった。
住民の望む街のイメージとして大切にし、 まちづくり案に反映させたいと思っている。
役員会での主な論点は以下のようなものであった。
そこで、 公園の規模単位で決めるのでなく建物の高さも合わせて街全体としてどの案を選択するかということになり、 次の6つの代替案(模型)をつくることになった。
1案[公園1ha]×[建物低・中・高層混在]の賛成が最も多かったものの、 3案[公園2,500m2]×[建物低・中・高層混在]もかなり接近した票数であった。
役員会では、 この決定を役員会で下すには責任が重すぎるということになり、 昨年11月中旬各ブロックで住民全体集会を開催することになった。
住民集会を開催したが、 各ブロック共20〜25%の出席者しかなく、 出席者だけで決めるのにはことが重大すぎるということになり、 住民全体へこの問題についてのアンケート調査を実施することになり、 12月中旬に回収した。
その結果、 回収率40〜50%で1haの公園が防災上必要ならやむを得ないを含めて56〜85%となり、 深備5と桜備4は本年1月最初の役員会で1ha公園案を役員会の結論とし、 2月11日に全体集会に諮ることとなった。
桜5では、 建設省が1haに対して柔軟に対応することになったらしいという「概ね1ha論」が浮上したことと今後の施設配置に関する議論もあり、 少し遅れて3月17日に全体集会を行うこととなった。
それを受けて、 同日晩、 連合協議会が開かれ、 住民合意によるまちづくり案が決定されたのである。
このビルの区分所有者による管理組合は、 再開発区域に含まれることとなった直後から、 施行者と一体となり一刻も早い復興を目指して活動を開始した。
4月2日には、 コンサルを決定し、 隔週毎に施設計画部会と権利調整部会を開催し、 仮設店舗、 仮設住宅の建設、 建物危険部分の解体と直面する諸課題に対応してきた。
昨年10月中旬には役員会で基本計画案を決定し、 11月26日区分所有者集会に諮り、 役員改案が承認された。
そして本年2月4日施行者の事業計画説明会があり床価額が発表された。
その後2月20日から3月4日まで案の縦覧が行われ、 3月28日事業計画決定となった。
この間、 管理組合の解散と「深田4南まちづくり協議会」の設立が3月24日に行われた。
他の3つのまちづくり協議会が最大課題として取り組んでいた公園の計画区域と直接関連していなかったため、 事業計画決定に至ったのであるが、 この決定は、 当地区再開発住宅の権利床価額の目安を示すものとして、 他の3つの協議会でも大きな関心事として受け止められ、 今後の事業推進を促すものとして意義は大きい。
当面、 住宅権利者、 商業権利者にアンケート調査を行い、 住民意向を把握することになっている。
同時に役員会では、 超高層住宅の視察も行う。
6月末を目途に地区全体計画について連合協議会で一定の結論を出し、 その後、 各ブロック協議会でそれぞれの街区の基本計画を練っていくことになり、 年度末には事業計画決定するのが目標である。
特に地区全体の環境デザインの考え方、 住宅供給の方針、 商業計画の方針等について議論を深めるものである。
基本計画会議のメンバーは、 学識経験者4名、 行政担当者11名、 コンサルタント7名で構成されている。
基本計画会議と環境デザイン部会の座長は安田丑作神戸大学工学部教授、 商業部会の座長は加藤恵正神戸商科大学商経学部教授、 住宅部会は平山洋介神戸大学発達科学部講師、 委員に児玉善郎産業技術短期大学構造学科助教授)の諸先生があたられ、 4月下旬に中間まとめがされることになっている。
が、 この建物は33階建ての超高層であるため工期3年を要し、 入居開始は平成12年予定である。
少し時間がかかり過ぎではないか、 もう少し小規模で工期の短い低・中層住宅を建設し、 一部の方々にでももっと早く再開発住宅に入居してもらう方法がないかを施行者・コンサルで検討をし始めている。
今後も現実的課題を次々に解決していかなければならない。
逐次報告して参ります。
(96年4月17日 記)
p2,3
HAR基金は復興まちづくりに柔軟に対応できる民間非営利(NPO)基金で、 地元組織や専門家の活動の支援のために昨年9月に設立され、 12月に第1回の助成が11団体に行われています(「きんもくせい」20号95.12.8参照)。
また、 第1回と同じく、 助成者の決定は公開審査によって行われます。
コレクティブハウジングが特に被災地高齢者の新たな住宅としてモデル建設される動きが急であり、 それらのソフトな仕組みなしに入れ物となる協同居住型住宅が建設されればどうなるでしょうか。
せめて長田区におけるコレクティブハウジングのケアを考え、 支援する取り組みとして始めたのがこのネットワークです。
福祉ケースワーカー、 看護婦、 医師、 ボランティア・コーディネーターなどの人達と、 住宅・建築・まちづくりプランナーなどの総合的な協同居住支援団です。
建築主は地主3名+持地持家5名で、 事業制度は公団グループ分譲制度と神戸市公社特目賃(特定目的借上公共賃貸住宅制度)。
建設する住宅は5階建て、 住宅18戸(うち賃貸12戸で7戸が従前居住者が入居)、 店舗2戸。
詳しい内容はまた報告してもらいます。
「一般の人々の視点を都市づくり(生活環境づくり)に積極的に反映させるために、 政策の作成過程への市民参加を推進することに賛同し、 行動する人達のための知的交流の場」です。
civilscapeのアドレス:http://www.iipr.org./civilscape
5冊目の「復興市民まちづくり」を5月末に発行します。
今回は96年2月〜4月の復興まちづくりの動きを追います。
5/7(月)必着分までを掲載します。
早く送っていただければ非常に助かります。
よろしくお願いします。
事務局までお問い合わせ下さい。
アドレ
スは、 http://web.kyoto-inet.or.jp/org/gakugei/kobe/index.htmです。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
2)「木造共同住宅の代替物が建たない」
滅失建物は、 棟数としては戸建てが多いが、 木造共同住宅(文化住宅)、 長屋建て住宅が数多く含まれている。3)「仮設住宅と公共代替住宅は4分の1」
筆者らは、 96年1月に住吉地区全域で、 住宅を喪失したと見られる世帯2,468世帯に郵送アンケートを行った(旧住所からの郵送を郵便局に依頼した)。4)「権利問題と融資資格がネックだ」
さらに60%の人々が元の場所に戻りたいと回答している。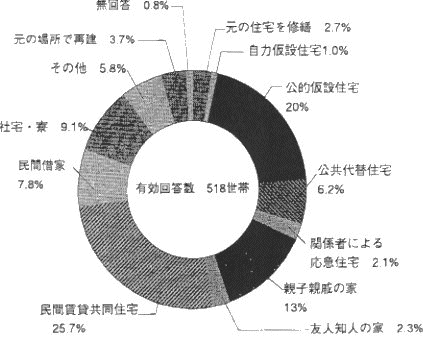
グラフ・住宅滅失世帯の現在の住居
公園・道路配置計画案が決まるまで
六甲道駅南地区第二種市街地再開発事業の報告・第2回
株式会社 環境開発研究所 大阪事務所長 有光 友興
はじめに
昨年7月25日付「きんもくせい」第13号に「4つのまちづくり協議会が発足」と題して第1回の報告をして以来約9ヶ月が経過しました。1.公園・道路配置計画案決定までの経緯
(1)住民と行政との信頼関係の回復
昨年3月17日都市計画決定時点では住民の行政への信頼関係は最悪であった。(2)「考える会案(公園分散配置案)」の果たした役割
まちづくり協議会が発足する前、 神戸大学児玉善郎先生と研究室の学生が支援して住民50人程度による「六甲南地区の新しいまちづくりを考える会」の計画案がまとめられてきた(「きんもくせい」第8号参照)。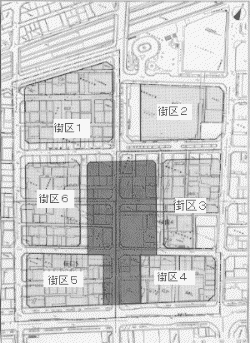
住民が決めた公園・道路配置案(3)公園の大きさについての論点
地域防災拠点整備を事業の目的の1つとしている施行者は、 近隣公園の最小規模の1haを必要としているのに対し、 公園は必要だが、 当該地区の住民を対象とした規模でよいのではないかという住民の意見の中で、 昨年末まで約半年間公園の規模について議論された。
a.市の考えている地域防災の考え方
一方、 超高層住宅は望まない、 低・中層のみの街がよいという意見も度々出ていた。
b.公園の規模と再開発ビルの床価額の関係
c.公園の平常時の使い方
d.公園の地下利用
e.公園の規模と再開発ビルの高さの関係
f.残存マンションの取り扱い
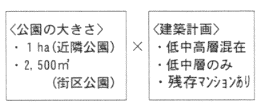
※低層:1〜5F 中層:6〜14F 高層:15F以上
模型「基本計画会議-環境デザイン部会」での検討案(4)住民の合意形成プロセス
上の6つの案について各ブロック役員会で投票が行われた。(5)街区2(旧メイン六甲B・C棟+日本生命)の事業計画決定
この街区は、 昭和48年市街地改造事業により造成されたメイン六甲B・C棟の高層棟が震災により約3度傾き、 今回再び市街地再開発事業により再開発することになった。2.これからの事業展開
(1)現在の協議会活動
公園・道路の配置計画が決まり、 5.9ha全体計画についてまちづくり協議会で議論すべき内容は、 主要施設(公共公益施設、 核となる商業・業務施設等)をどの街区に配置するかということと住宅棟の配置(高さと方位、 賃貸と区分所有等)が主なものとなってきた。(2)「基本計画会議」の設置とまちづくり協議会との関係
基本計画会議は、 地元(まちづくり協議会)が地区全体計画を議論しているなかで、 4つのブロックの計画案が矛盾しないように施行者として全体計画の基本的な考え方を固めておくためのものである。
街区2事業計画決定案おわりに
街区2の事業計画決定がされ、 本年中に管理処分計画が決まれば、 来春には六甲道駅南地区で最初の復興の槌音が聞かれる。
HAR基金の第2回助成事業の募集について
阪神・淡路ルネッサンスファンド(HARはる基金)の第2回助成が以下のように行われます。公開審査会について
HAR基金の応募概要
(神戸市中央区元町通4-2-14 TEL.078-361-4523)
─────────────────────────────
助成金額:1件当たり200万円限度で10件程度
応募方法:助成申請書を応募先へ郵送
応募期間:4月26日(金)〜5月20日(月)
応募先 :〒102 東京都千代田区平河町2-14-3日本青年会議所内
(財)まちづくり市民財団 事務局
TEL03-3234-2607 Fax03-3234-5770
問合せ先:詳しくは、 上記応募先又は当ネットワーク事務局
までお問い合せ下さい。
─────────────────────────────長田コレクティブケアネットワーク発足
「長田・協同居住支援団」(長田コレクティブケアネットワーク:NCCN)が発足しました。次回の会合予定(第4回目)
真野地区で共同建替調印式
真野地区(神戸市長田区)で唯一震災で火災にあったエリアで共同建替えが成立し、 4月21日調印式が行われました。
共同建替えの調印式の様子(4/21)IIPRからのお便り ―ホームページ開設のお知らせ-
アメリカで日本人によって設立された非営利公益法人組織であるIIPR(INSTITUTE OF INTERNATIONAL PLANNING RESEARCH:国際都市研究フォーラム・理事長 ハベレイコ)は、 3/20よりシビルスケープ(CIVILSCAPE)というホームページを開設しています。ネットワーク事務局より
「復興市民まちづくり」Vol.5発刊します
-至急まちづくりニュースを送って下さい-「きんもくせい」(創刊号〜25号)の合本できました
目標の50号までの節目として、 「きんもくせい」の合本をつくりました。
1部500円(送料別)です。「きんもくせい」がインターネットで見れます
学芸出版社のホームページの中に「きんもくせい」のコーナーができました。
復興まちづくりハウスの旗を事務局にたてました(4/14)
Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
P.4
 きんもくせい28号へ
きんもくせい28号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ