
〈お湯を沸かしに食堂へ〉

〈ボランティア・職員たちによる夕食づくりのスタート〉
道路機能や港湾機能の復旧に続いて、 この住環境と文化環境の再構築なくしては、 阪神間の真の復興は実現しない。
神戸地域の産業であるパンやチョコレートや真珠やケミカルシューズは、 神戸ブランドという付加価値で競争力を保持してきた。
それらは二次産業の枠を越えた、 いわば三次産業的な生活関型連産業である。
実際、 阪神地域の居住者は三次産業への就業者が大半を占め、 そうした人々の活動が神戸という都市の総体を形づくってきた。
同様な成熟都市では、 多くの人が三次産業で生計をたてており、 その産業や生活に何がしかの文化力が認められるものである。
これが都市の魅力なのである。
三次産業の雇用が戻り、 それによって生計をたてる人が多数を占める状態に戻ることが最終的な復興であり、 言い替えれば、 都市文化の復興ということである。
もちろん、 都市の魅力が文化力だけでないことも大震災は教えてくれた。
安全であること、 さらには安心してそこに居続けられること、 これも魅力の基本要素である。
災害に遭遇してもその被害が少なくてすみ、 それからの脱出が容易な都市空間や社会システムの必要性も今回の大震災は語りかけた。
魅力を求めれば防災機能の劣る都市空間が出現するといわれる。
人が集まり、 自由な交流の中から刺激的なことが生まれるが、 このための集中やルールの欠如が、 他方で災害の危険性をふやす。
そこで防災を徹底するわけだが、 逆に、 行き過ぎた管理を行えば賑わいやハプニングの機会が減り、 結果として都市の魅力は減る。
安全性を強調するあまり、 広すぎる道ができたり、 堅牢すぎる建物が立ち並びその結果、 都市空間がつまらなくなることがある。
そこには魅力づくりと防災街づくりのジレンマが見え隠れするが、 それをジレンマと捉えずに、 両立させることが成熟した阪神間の復興課題である。
そこで課題を一言で言えば、 「安全な路地づくり」というコンセプトになるのではないか。
また、 防災意識は現実に災害を体験することで社会化され、 強力な危機管理システムが生みだされる。
しかし、 どんな立派なシステムが用意されても、 非常時では、 そのシステムを運営する人間の処理能力が決め手になる。
防災には人の能力も欠かせないから、 そういう人が溢れている都市に戻すことも、 復興にとって大きな課題である。
文化力を維持するために「集中」は必要だが、 環境を維持するために適度な集中でなければならない。
そして防災を考慮すれば余裕のある時空間、 つまり「分散」が求められる。
当分の間、 「文化力の再生」と「環境意識の高い市民づくり」と「余裕のある都市空間」が復興の質を評価する物差しになろう。
その活動の一つとして継続的な現況調査を行っているが、 その経験から指摘できる再生への課題は、 いわゆる白地地区に共通する内容であり、 概略は以下のようなキーワードにまとめられる。
第二に、 まとまりのある小学校区を再生しながら地区の個性を失わずに安全で安心な市街地形成と、 賑いや文化の香りがする市街地形成と、 賑いや文化の香りがする市街地整備を両立させることが挙げられよう。
第三に、 それらを支えるルール造りが求められ、 そのために、 市、 地元団体、 住民、 専門家が協力して上記の点について積極的に取り組むことが挙げられるのである。
(3月26日 記)
p1
こんな住まい方はほんまにええ。
今までは寂しかった。
友達は自分でつくれるけど、 こんな住宅のこんな住まい方は自分でつくられへん。
死ぬ前に幸せつかみたい。
こんな住宅を建ててほしい。
」尼崎市小田南ケア付き仮設住宅に住むMさんはつぶやいた。
彼女の部屋には沢山の友達が訪ねてくる。
私がおじゃました時も友達が帰ったばかり。
6帖程の洋室にトイレと洗面スペース、 押し入れ、 踏み込みスペースで約17m2。
この個室が中廊下をはさんで14室あり、 中央に共用スペースをもつ。
約80m2の共用スペースには、 台所、 食堂兼談話室、 風呂と洗濯スペース、 援助員室がある。
まさにコレクティブハウジングであり、 小田南には2棟(14室型と10室型)がある。
〈尼崎市にはもう1カ所、 三反田ケア付き仮設住宅があり、 市は特別養護老人ホーム「喜楽苑」(小田南)と「園田苑」(三反田)に運営を委託している〉。
芦屋のケア付き仮設住宅も含め3カ所とも建物形式やケアサービスシステムはほぼ同じであるが、 雰囲気は地域性がある。
小田南は下町の長屋住まいのような親しみがあり、 食堂はat homeで、 さすがここは尼崎という気分になる。
96歳のAさんは、 ここは尼崎の競艇に出かけるのに都合がええと言う。
時には尼崎センタープールにとどまらず、 住ノ江ボートまでにも足を伸ばす。
町中の小さな協同住まいは交通の便利もよく住みなれた地域なので、 つらい震災にあったけど元のライフスタイルを取り戻している。
ここには4グループの食事ボランティアの支援があり、 ほぼ毎日、 昼食か夕食がサポートされる。
ボランティアが前もって立てたメニューの食材を買ってきてくれる。入居者は300円程度の実費を払う。
食事づくりには入居者も準備や後片付けに加わり、 全員が集まって食事をし、 時にはそのまま食後の団欒を楽しむ。
夫婦ものは自室で食事をする時もある。
食堂を使う時は、 必要な私物をバスケットに入れて持って来て、 また持ち帰る。
私物を共用スペースに放置しないという協同居住のルールができている。
しかし隣の棟はそうはいっていないとのこと。
1カ所ある共同風呂の入浴順番も、 今では個々人の生活スタイルが把握できたので、 トラブルもなくまあ順調。
2、 3人で連れもって入ることもある。
「今まで旅行に行ったことがない。
いっぺん行ってみたい」という入居者のつぶやきを若い援助員が聞き、 温泉旅行を企画した。
悪戦苦闘の準備があったと聞くが、 1泊2日の高原ロッジに6名が参加した。
冬に入る前に避難訓練も実施した。
火災発生のいろんなケースを想定して、 ケースごとの脱出、 耳の聞こえない人、 目の不自由な人に脱出をどう知らせるのか、 屋外と室内との段差が高いので、 まず布団を放り出してクッションにし、 元気な入居者は相互グループをつくり、 大騒ぎをして行った。
その結果、 防災計画書も作られ、 個人は非常袋の準備、 各部屋には援助員がすぐ使える位置に消火器を置いてもらうことにした。
ここでは、 毎日の食事、 緊急時の避難、 生きがいづくりが大切な課題だという。


〈ボランティア・職員たちによる夕食づくりのスタート〉
この棲み合いを育んできたものは何なんだろう。
震災後4カ月経って共同スペースをもつ仮設住宅が建てられ、 そこに入居しただけというのでは、 こんな住まい方は育たなかっただろう。
ここには協同居住をつくりあげるしっかりした仕掛けがあった。
コーディネーターと生活援助員と看護婦の3職セットである。
小田南の場合は、 コーディネーターにケースワーカーや老人福祉の専門職を経験してこられたベテランの男1名。
看護婦は一般病院での看護婦経験のある女1名。
生活援助員は20〜50歳代の巾広い年齢層で、 夜勤のみのパート(3名)も含めて8名程いる。
これらのスタッフが24時間体制で、 1棟に昼は2〜3名、 夜は1名配置されている。
援助員は入居者の生活をサポートするための、 食事づくりの手助け、 買物や通院の付き添い、 相談や話相手に応じており、 介護福祉士の専門スタッフが多い。
その中には調理や家庭料理のプロもいて、 ずい分恵まれている。
援助員自身の悩みは、 “どこまでサポートすればいいのか”ということだと言う。
例えば、 ある入居者が体調をくずした時、 一時的に手厚いサポートをすると、 回復した後も同じサポートを求めてくる。
サポートしすぎると、 自立した生活ができにくくなるということにもつながる。
若い援助員に対しては入居者の要求も多く、 援助員は悩んでしまう。
看護婦はここでの看護対応だけでなく、 外部からの訪問看護や入居者が通院している医療機関とのつながりも必要となり、 総合的な医療・看護の知識をフル回転しなければならない。
彼女は一時期援助員も兼務していたので、 入居者のニーズもよく分かっているというのが恵まれている。
コーディネーターは援助員、 看護婦と入居者の対応でどんな問題が生じているのかを知り、 うまくいくように異なった立場から話をきき、 調整していく。
入居者同士の協同居住のギクシャクも起きるので、 それが大きくならないうちに事前にキャッチして、 仲もっていくことも大きな任務となる。
ボランティアの調整もする。
入居者にとって全てが結果オーライでいくためには、 この3職のバランスが必要であり、 とくにコーディネーターの任務は大きい。
バラバラで入居してきた人たちの状態を知り、 その個性を尊重しながら協同生活を育んでくるまでには、 多くの試行錯誤があったようで、 入居者の個性、 生活歴、 健康状態、 食事の等を把握するため、 アンケートをしたり個人生活カルテも作られている。
●以上のような話をいっぱいしてくれたのは、 私の娘のような年代の若い援助員であったが、 話を聞くうちに親世代をはるかに越える職業意識と自信と軽やかな行動力をもっているのに感動した。
素敵な人材である。
高齢者・障害者を対象としたケア付き住宅では、 この3職セットが欠かせないが、 元気な自立した人たちのシニア・コレクティブではここまで望むのは現時点では難しいだろう。
コーディネーターだけで十分なのか、 その対応期間はどれくらい必要なのか、 その人材確保は、 入居前に協同居住のトレーニングもいるだろう、 等々‥‥検討しなければならない。
今、 災害復興公営住宅でコレクティブハウジングの供給が始動しょうとしているが、 共同スペースをもった住宅の建設というハード面の供給だけでは協同居住は稼働しない。
的確なソフトシステムを構築し、 その人材確保ができるかどうかが、 新しい住まいコレクティブハウジングの成否を決めるだろう。
生活歴の異なる人たちの協同生活を個性を大切にしながら築き上げていくということは、 わが国ではほとんど未知の分野であるが、 協同居住は同じライフスタイルを指向する人たちと専門的立場からのはまった誘導との合作であり、 ケア付き仮設住宅から学ぶものは多い。
〈続く〉 (3月23日 記)
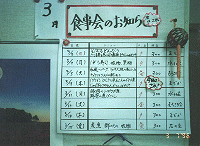

〈空室を利用した団らん室に立派なお雛様が〉
今回より、 こういった「きんもくせい」の配布にご尽力をいただいている都市計画関係の講座のある大学などを拠点としたファックスネットワークの方々や、 「きんもくせいネットワーク」、 その他の方々からのお便りを随時ご紹介します。
○建設省建築研究所 藤田 忍さん
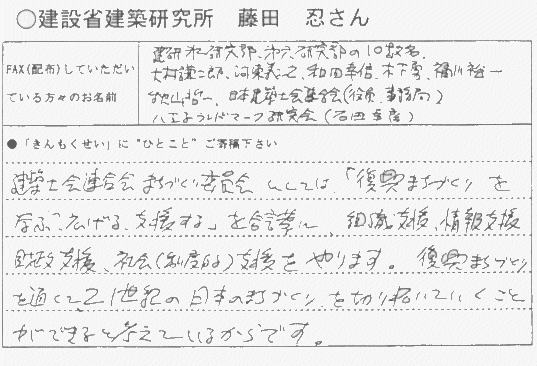
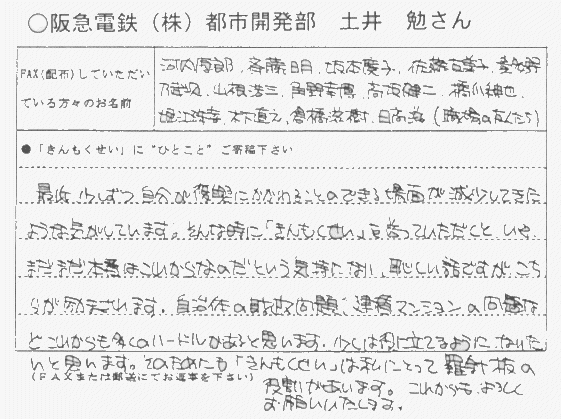
p2,3
参加は自由です。
楽しい企画です。
みなさんの参加をお待ちしています。
3/30 三田での花文字づくり
4/6まで人と自然の博物館横の空き地にて)
お問い合わせは、 人と自然の博物館内 阪神グリーンネットワーク事務局(藤本)まで TEL. 0795-59-2024

4/6、 10amまで見れます〉
これは岡本交友会の呼びかけで、 阪神グリーンネットが協力して行われたもので、 当日はネットワークメンバーや地元の方々約70名が参加し、 岡本1丁目から9丁目まで14ヶ所に蒔きました。
いまからひまわりでまちが彩られるのが楽しみです。
なお、 この種は震災で亡くなった岡本3丁目の小学生が飼っていたインコの餌であったひまわりの種が夏に開花し、 その花から採取したものです。

第1弾は、 「地球を走る会」の日本列島桜駅伝に託して、 緋寒桜10本などが3/31に届きました。
今後、 桜1000本程をはじめ多数提供できるとのお約束をいただきましたので、 各地に1本づつというのではなく、 少しまとまった植樹ができ、 沖縄・奄美の方々が見に来て下さるようなスペースが作れればと考えています。
第2部」監督:青池憲司
まず、 30個のフラワーポットに植えましたが、 それを自分の部屋の鉢持参で植えてもらって持ち帰る人とか、 パンジーはひっぱりだこでした。
一般仮設住宅からは小さな子供と母親、 元気なおばさんの参加もありました。
私としては、 住棟間などにまとめてミニ花壇を作ろうと思っていたのですが、 入居者のすぐそばで各々に咲かせてもらうのも、 皆がやさしい気持ちになれるかなとも思っています。
昨日、 生活援助員さんから今パンジーが満開になっていますと電話をいただきました。
(石東直子)
パンジーが来たよ!〉
P.4
第2回連続映画祭「連帯せよ!復興市民」
第1部:映画
・「人間のまち、 野田北部・鷹取の人々。
第2部:シンポジウム日時:4月11日(木)18:00〜20:30
場 所:こうべまちづくり会館ホール2F(神戸市中央区元町通4丁目)
TEL.078-361-4523
主 催:港まち神戸を愛する会 TEL.078-261-0337
入場料無料(ただし青池監督へのカンパをお願いします)
仮設住宅の環境改善アクション=パンジーの花壇づくり
(コレクティブハウジング事業推進応援団+阪神グリーンネット)
2月24日、 芦屋市ケア付き仮設住宅と隣接の一般仮設住宅で、 入居者と生活援助員の参加のもとに、 コレクティブハウジング事業推進応援団が一緒にパンジー500株を植えました。ケア付き仮設住宅のおばあさんたちは草花の好きな方が多く、 杖をついたり、 連れもって出てこられました。
〈さあー。ネットワーク会議
第4回阪神グリーンネット会議
第13回東部市街地連絡会
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
〈これまで担当されていた児玉善郎さんは産業技術短期大学(尼崎市)へ御転勤になりました〉
 きんもくせい27号へ
きんもくせい27号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ