
コレクティブハウジング事業推進応援団パネル展示
市民とNGO「防災」国際フォーラム.('95.12.9)

「きんもくせい通り」の現在('96.3.9)
昨年2月10日の創刊以来、 ほぼ月2回発行を続け、 1年がたちました。
創刊時に2年間50号までは、 と決意していました。
道なかば前途はるか、 という気分ですが、 もう1年は歯をくいしばってでも続けます。
地域にねざした「市民まちづくり」のきちんとしたニュースを被災地中心から全国のこころある人々に直接伝える、 という当初からの目標はほぼ貫くことができ、 専門家などからもそれなりの評価をしていただいていると自負しています。
●第5号(3/25)の「きんもくせい通り協調住宅」は3軒から2軒の協調化になりましたが、 住市総(優建として)の補助も決まり、 2月18日に安全祈願祭(起工式)を行い10月末に完成の予定です。
●第10号(6/6)の「ガレキに花を咲かせましょう!」は、 芦屋から鷹取まで13カ所にコスモス・ヒマワリの種を5〜6月に蒔き8〜11月に咲きました。
パートIIは11カ所にカスミソウ・ヒナギクを11〜12月に蒔き、 3〜6月に花が咲く予定です。
「ランドスケープ復興支援会議(阪神グリーンネット)」も今年3/1に発足し、 協力して今後も阪神市街地緑花再生プロジェクトを進めていきます。
●第14号(8/17)の「被災地にコレクティブ・ハウジングを!」は第23号まで5回にわたって連載し、 事業推進応援団も3/4に第6回ミーティングで第1期のまとめをしました。
神戸市や兵庫県の公営住宅での実験的な試みが始まりました。
●第16号(9/25)の「阪神・淡路ルネッサンス・ファンド(HAR基金)設立!」は11月より公募を開始し、 11/28公開審査会、 12/12贈呈式で11団体600万円の第1回助成が決まりました。
5月の第2回公募に向けて、 本格的な募金活動がすすめられています。
都市計画事業(黒地)地区や重点復興(灰色)地域でのさまざまなまちづくり活動の状況も、 もちろんお伝えしていくつもりです。
あと1年。
応急仮設住宅が全部なくなるとは、 とても考えられませんが、 それでもあと1年で期限がきます。
「復興市民まちづくり」に期限があるわけではありませんが、 少なくともあと1年50号までよろしくお願いします。


「きんもくせい通り」の現在('96.3.9)
小森星児氏、 中瀬勲氏、 林まゆみ氏が呼びかけ人となって、 ランドスケープ関連の技術者、 研究者等が集まりました。
「きんもくせい」23号で紹介された「あなたの家の垣根からはじめよう-安心な環境づくり」を作成した「ヒューマン&ネイチャー・ネットワーク」、 林氏の復興プランAグループなども含み、 ランドスケープ関連のネットワークを一元化し、 被災地での専門家派遣の要請に応えようとするものです。
当面の活動内容として以下の3つを掲げています。
現在人材のデータ・ベースづくりを行っています。
「ちょっとお金もかかるし、 手間もかかるけどやってみるか」と思って頂ければ成功です。
白地地域を主に対象とします。
詳しくは「きんもくせい」23号の上記マニュアルの記事をご覧下さい。
野菜畑はその成長を楽しめるだけでなく、 何と言ってもできたものを食べることができます。
何かの集まりのきっかけになればと思います。
屋上緑化は来る暑い夏に備えるためで、 現在、 技術開発中です。
そこで、 「花咲かせ隊」「野菜畑耕作隊」と称して大募集したいと思います。
現在、 既に千葉大学をはじめ遠方の大学や人と自然の博物館ボランティアから参加希望を頂いています。
とりあえず、 以下の活動日が決定しています。
〒669-13 三田市弥生が丘6丁目 兵庫県立人と自然の博物館内
もちろん、 (1)に関してもご一報下さい。
愛知県一宮の角田ナーセリーグループから、 大阪植物取引所の緑会の協力でパンジー2万6千鉢が17日の昼頃、 人と自然の博物館に到着しました。
「被災地ではこれだけの量を置くところがない。
」ということで、 趣旨をご理解いただいた北摂整備局のご好意で東側の駐車場跡地に置けることになりました。
この寒さに耐えられるかどうか心配されましたが、 何とか24日の配布までもちました。
当日は多くの方が早朝から集まり、 早くも10時過ぎには予約を含め配布が完了しました。
芦屋、 尼崎、 鷹取(野田北部)、 岡本、 魚崎、 松本、 兵庫駅前の各地では、 地域ぐるみで仮設に配ったり広場に植えようということで、 地域の方々がまとめて苗を取りに来られました。
このネットワークで情報を交換し、 活動しながら方向や次の活動を決めてゆくことになるでしょう。
プランナー同士、 あるいは地元住民との協働作業や議論をまず始めなくては…。
その第一は断水による「被害」である。
断水は消火活動を不能にし、 トイレの使用を不能にし、 発電機などの冷却水切れを起こしてあらゆる人の行動を阻害した。
飲料水はミネラルウォーターや給水車での供給が可能であるがこれら雑用水は使用量が多いだけに対応不可能である。
人々の身近な所に池や川や井戸が姿を消し、 水がなかったのである。
新しい街の計画にあたっては住民に近いところで地下水や河川水の利用を図り、 雨水を貯留して植裁散水や人工的な池や川に利用する。
また排水のリサイクルなども有効である。
このような自己水源確保の手法は近年、 環境共生という言葉で、 どちらかと言えば自然の恩恵を計画的に取り入れる手法として論じられてきたが、 震災によって自然の暴力とも共生するという概念に拡大されたように思える。
自己エネルギーも必要であった。
住民はガス供給の停止によって調理の手段を奪われ、 損壊を免れた発電機も燃料切れで動かなくなった。
停電による暗闇の避難所で不安の日々を過ごした。
避難地には非常用の備蓄倉庫を備え、 非常時に必要な機械器具の他にカセットコンロや小型発電機などのエネルギー源も備蓄する。
燃料補給のために地域にガソリンスタンドが計画されるべきである。
太陽光発電は新しい自己のエネルギー源として有力である。
太陽電池は1KWを発電するのに約10m2の発電ユニットが必要であるので主要な動力源にはならないが、 避難地の夜間照明程度には十分利用することができる。
●図は、 数千戸の集合住宅群からなる新しい地域開発モデルとして、 災害非常時の避難・救助・消火システムを模式的に表現したものである。
これらは非常時だけでなく日常的にも魅力を持って機能することを含めて提案している。
以下、 この図に基づいてその機能を説明する。
●一時避難所として指定されている街区公園には、 災害発生直後に必要な備蓄倉庫や集会所に併設した公衆便所を設ける。
雨水を利用した貯留槽を設け、 日常的には植裁散水や池・噴水・せせらぎに利用する。
●これらの施設は、 異なる事業主体の管理を統括する総合管理事務所が、 街路やライフラインの共用部分とともに維持管理する。
●小中学校は地区防災拠点に指定されており、 本格的な備蓄倉庫の他、 水道管と直結した緊急用飲料水槽、 雨水、 井水、 工水などを利用した消防署管轄の消防用水補給基地、 ガソリンスタンドなどがその周辺に点在している。
●小中学校の屋上には太陽光発電ユニットが設置され、 避難所として利用される講堂、 体育館、 グランドの照明に使われる。
太陽光発電は街区内では、 公衆電話用電源、 池・噴水・せせらぎ循環ポンプ用電源として使われる。
尚、 震災被災地に建設される公的建物に設置される太陽光発電システムには、 通産省の補助金が交付される
以上の内容は、 「まえがき」、 「1.情報通信システムの提案」「2.避難・救助・消火システムの提案」、 「3.街区内「ライフライン敷き」の提案」のうち、 2について掲載している。
その他については、 事務局にお問い合わせ下さい。
p3
昨年7月17日の朝日新聞論壇に「修学旅行は阪神・淡路へ」と書いた記事がきっかけとなりました。
もともと10月に神戸へと決まっていたのが震災でだめになり、 しかも行く先は京都と倉敷に分かれての修学旅行となりました。
その初日と最後の日にオプショナルで神戸を訪ねようという一部の生徒さんたちが長田区の鷹取カトリック教会や更地になった区画整理区域などを見学したり、 北野町の異人館を訪問しました。
帰京されてからのお手紙を転載致します。
実際に自分の目で見て触れて感じた神戸は、 私達に改めていろいろなことを見つめ直すきっかけを与えてくれました。
これからもお体に気をつけて頑張って下さい。
」
テレビや新聞などで震災直後の神戸の様子は知っていたけれど、 実際に自分たちの目で建物が崩れた跡を見てショックを受けましたが、 新しい建物が少しずつ建ち始めたのを見て安心しました。
」
また、 新しく建て直された建物の(壁に書かれた)絵を見て、 現地の人々が、 つらさと戦いながら、 前向きに精一杯生きている様子がうかがえました。
町づくりのお話を聞いて、 みなさんが中心となり、 市民の人々の意見を尊重し、 住みやすい町づくりをしていることがわかり、 大変感心しました。
同じ日本にいながら、 異国の地のように感じられ、 なにもできない自分たちの無力さにいらだちさえ感じられます。
みなさんが神戸の人達のために一生懸命になっている姿を心から尊敬しています。
きっと、 私達の中で被災地に行ったことは、 とてもいい経験として一生残ることと思います。
みなさんの話を聞いて、 私達もぜひ、 神戸のみなさんのために、 ボランティアに参加したいという気持ちになりました。
あまり態度も良くなくてご迷惑をおかけしたかもしれません。
本当にありがとうございました。
機会があったらまた訪れたいと思います。
さようなら。
See you again……・・」
これまで被災地のあちこちで様々な調査主体によって復興まちづくりを支援する復興実態地区調査が行われており、 まちや住まいの再建支援の課題を考える基礎資料だけでなく、 大都市における今後の災害復興計画を検討する上でも貴重な資料になると考えられる。
このネットワークは被災地調査の支援や相互の情報交流をはかろうとする目的で呼びかけた集まりである。
もう一つの狙いは、 調査に参加した学生達のワークにも積極的にスポットを当てて、 学生自身にも復興まちづくりの課題を身をもって感じ、 相互の交流を深めてもらおうということにある。
第1回は、 個別の復興課題や地域の特性に根ざしたまちづくり課題についての議論を深めていきたい。
都市計画研究者だけでなく、 プランナーや学生の皆さんの積極的なご参加をお待ちします。
・第1回「被災地定点調査交流会」
・第2回「被災地フィールドワーク 研修会」
・第3回「被災建物データベース研修会」
Tel.(078)361-4546
・「東灘市民復興まちづくりフォーラムの企画案について」
・3月14日(木)18:30〜20:30
・神戸Fビルディング、 11F
今回は、 まちづくり提案などの住民と専門家との協同作業についても豊富に掲載しています。
継続購読もよろしくお願いします。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
P.4
活動の内容と目的
メンバーは現在37名(増加中)で、 コンサルタント会社、 造園施工会社、 大学等で働く人々で構成されています。(1)専門家派遣
都市計画事業地区を中心に立ち上がったまちづくり協議会等へ、 講師あるいは派遣コンサルタント、 ボランティアとして参加し、 公園や街路に関するコンサルティング等の諸活動を行います。(2)垣根づくりなど緑化推進活動
最初は被災地へ出かけてモデル的な生垣をつくります。(3)野菜畑づくり、 壁面・屋上緑化活動
仮設住宅に出かけて、 野菜畑づくり、 壁面・屋上緑化活動をします。花咲かせ隊、 野菜畑耕作隊、 大募集
上記の(2)(3)は施工技術者等々専門家のアドバイスを受けながら行うのですが、 多くの人手が必要です。
興味のある方は、 やりたいことと連絡先の名前・住所・電話番号・ファックス番号を郵送あるいはファックスで下記へご一報下さい。
パンジー2万6千鉢の配布(盛況裡に終了)
fax 0795-59-2024 阪神グリーンネットワーク事務局:藤本一宮からパンジー2万6千鉢到着
まだまだ寒く雪も降る三田。
一宮の角田ナーセリーなどから贈られた2万6千鉢のパンジー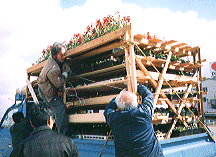
地域に花を配布するためまとめて取りに来られた
野田北部まちづくり協議会のメンバー
豊かな住空間と強靱なライフライン-建築環境・建築設備からの提案(抄)
(株)設備技研 早草 晋
避難・救助・消火システムの提案
災害が発生して、 幸いにも生命が奪われることを免れた人々が最初にしなければならない行動は避難や救助や消火であるが、 今回の震災ではこの面で大きな教訓を残した。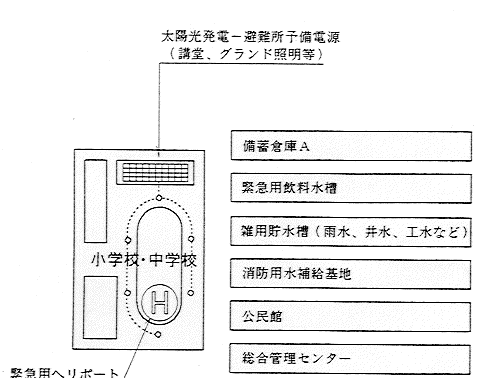
街区防災拠点のイメージ
毛布、 食料、 カセットコンロ、 ボンベ、 小型発動機、 エンジンポンプ(可搬式)、 自転車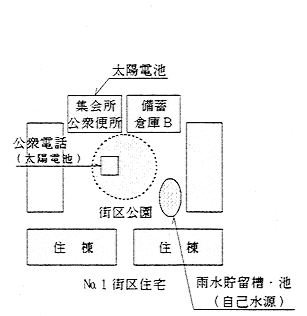
地区防災拠点のイメージ
スコップ、 ジャッキ、 土嚢、 ロープ、 ほうき、 懐中電灯、 自転車
INFORMATION
修学旅行生、 神戸へ
天川 佳美
2月12日と15日に東京都立狛江高校の修学旅行の生徒さん達が被災地神戸を訪れました。東京都立狛江高校の生徒さんから事務局に届いたお便り
これからもがんばってください。
被災地を訪れた修学旅行生たち
(長田区鷹取2/12)「震災復興実態調査ネットワーク」発足
大西一嘉(神戸大学)
震災から1年余り、 復興の動きは地区や個々の敷地ごとに多様で、 抱える課題も異なる。
4月4日(木)13:30-17:00
4月20日(土) 17:00〜20:00
5月25日(土) 13:30〜17:00
参加費:500円
呼びかけ人
齋木(神戸芸工大)、 大西、 平山(神戸大)、 鳴海、 小浦(大阪大)、 小林(コー・プラン)〉ネットワーク事務局より
ネットワーク会議等
○第13回東部市街地連絡会
・「復興市民まちづくり地区別取組み」
灘中央地区-上山卓(コー・プラン)
灘の酒蔵地区-中井清志(関西建築家ボランティア)『復興市民まちづくり』vol.4発行
vol.3よりさらに62頁増加し349頁となりました。
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1029 FAX.078-803-1029
担当:児玉
 きんもくせい26号へ
きんもくせい26号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ