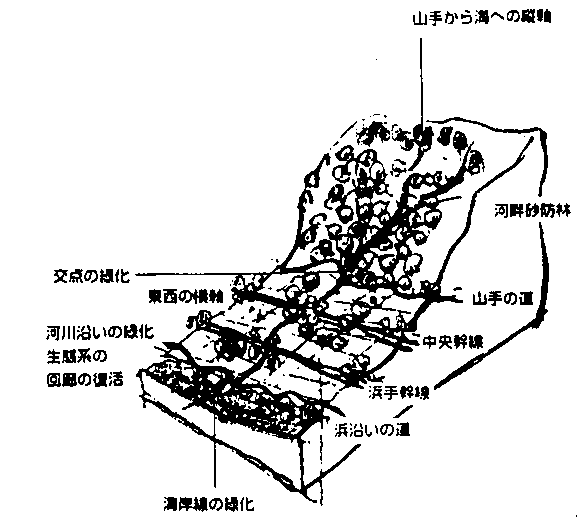
図1「震災復興の環境単位」
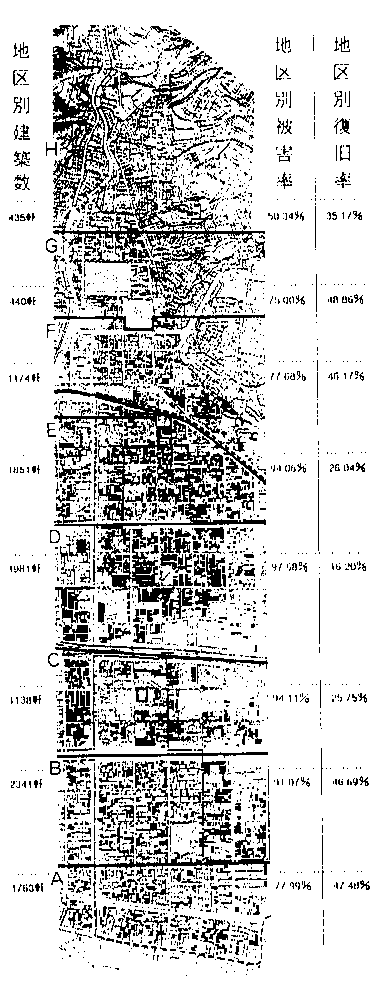
図2「継続調査の対象地域の設定」
復旧、 復興状況は地域によって異なる
その実体はどこまで把握されているか。
この1年を振り返ると多くの人々の支援に支えられつつ、 夢中でその場そのときの必要とされる「こと」を行ってきたと言って良い。
震災発生直後からの被災状況調査は、 都市計画学会、 建築学会を母胎とし、 関西の大学連合とコンサルタント、 全国のボランティアにより実施され、 3月末にはその成果が印刷・出版され、 被災の全体像を把握した。
その資料性について高い評価を得たことも衆知のことである。
その後、 各地域で個別の問題解決を目指して、 地道で苦渋に満ちた復旧・復興が展開されてきたことは、 阪神大震災復興市民まちづくり支援ニュースに記録されている。
それらの活動は、 個別の特性をふまえつつ、 状況に応じた対応が求められ、 モデルのないまちづくりといわれている。
このプロセスの記録は着実に蓄積され、 将来に役立つ財産となるに違いない。
これらの個別の復興まちづくりに加えて、 基礎的な復興の状況把握が現在どの様に集約されているか、 大いに気がかりである、 そこで私たち神戸芸術工科大学で、 震災直後の被災調査から継続してフィールドワークを行っている、 長田区・須磨区の調査事例の報告を行い、 「きんもくせい」の誌上を活用して復興状況の把握とその情報交換の機会を作ることを呼びかけたい。
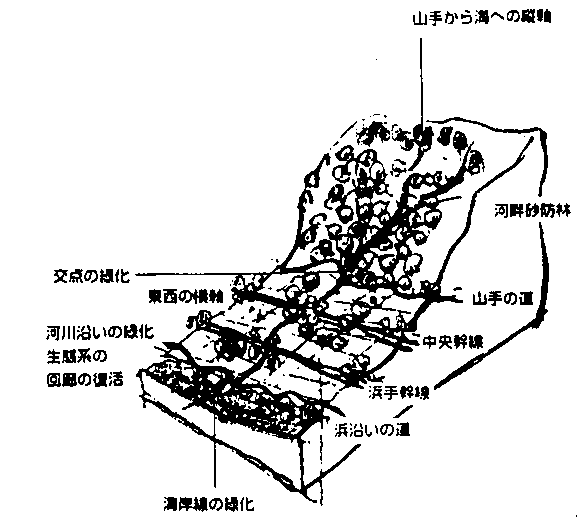
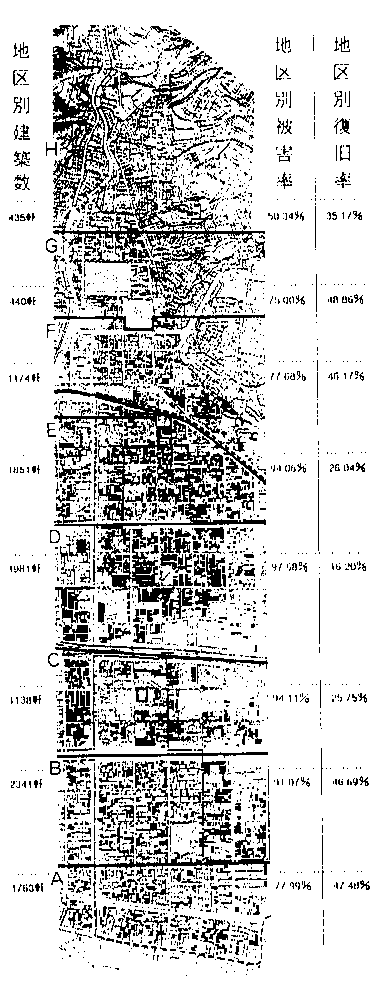
それは、 阪神間の地域コミュニティの基礎は、 場所が持つ自然の骨格により形成されていると仮説するからに他ならない。
この仮説に従って、 継続的な調査地域を長田港から板宿、 妙法寺川の谷間域までの東西幅650m、 南北3300mで設定した。
この地域は震災後行政により指定された、 重点復興地域や区画整理予定地域も含まれ、 自然立地条件と社会条件の交錯する多様な環境単位が確認される地域である。
震災後7カ月後の調査を8月7〜13日に、 10カ月後の調査を11月26日に実施した。
これらは神戸芸術工科大学環境デザイン学科の学生、 犬塚英夫、 懸樋喜康、 瀬崎昌和、 藤澤雅也、 中村美奈子、 沈戴明、 白美愛が行った。
調査は、 建物別にその復旧状況を 1)改築・新築済み・無被害建物(復旧済)、 2)改築・新築中(復旧中途)、 3)応急・臨時建物、 4)駐車場利用敷地、 5)更地(倒壊放置、 解体中、 未整地、 整地済)の5つの分類で調査した。
この調査結果は、 今後の復興計画に活用されることを意図し、 地理情報システム・GIS(神戸大・大西助手らが中心に整理)に重ねて使用できるようにまとめられている。
調査対象地域を海側から山側に向けてA〜Iの地域に仮説分類をおこなった。
この区分された地域別に被災状況と復興状況を被災直後被災建物件数97%〜50%に対して10カ月後の復旧建物件数は16%〜48%でしかない。
これを比較すると状況はAB地域、 CDE地域とFGH地域に大きく分けることができる。
これらをさらに町丁目別にとらえ直すと、 大きな地域差があることがわかる。
たとえば、
可能ならば、 先に述べたように、 刻々と変化する震災復旧状況に対応し、 復興計画策定の基礎的情報を共有化・データベース化するため、 この一年間実施されてきた基礎的な復旧・復興状況の調査報告会を開催すべきであり、 その時がすでに来ているといえよう(1996年1月8日 記)。
p1,4
奈良大学地理学科防災調査団は、 瓦礫撤去の実態と建物建築状況(新築家屋、 仮設的な建物(プレハブ、 コンテナ、 テントなどの種別)を現地調査(構造、 業種別)し、 復興状況を地図化して災害データベースを作成した。
被災地域が再生するプロセスを時系列調査(7月までは1ヶ月単位、 7ヶ月以降は3ヶ月毎)し、 データベース化し、 対策や防災対策への貴重な教訓とすることができるからである。
1回の調査に110人の学生が必要であるが、 現在までに9回の現地調査を実施した(デジタルデータベースの不揃いにより西宮市以東については入力が遅延している)。
この時期は、 ライフラインの復旧にあわせて道路上の瓦礫撤去がみられるのみである。
特に3月下旬から4月にかけては本格的な撤去が開始されはじめ、 4月中旬には2万箇所以上で家屋の解体・撤去が進行した。
また、 仮設のプレハブ住宅やコンテナ小屋、 テントハウスなどが更地に目立ちはじめ、 特に仮設店舗などでの営業が開始され始める。
このころの撤去後の更地での仮設の建物は、 1200以上にのぼっているが、 新築家屋の件数は少なく、 240カ所程度にすぎない。
所有権等で問題の多い物件やマンション等を除き一般的な家屋の撤去総数は、 神戸市と芦屋市において56000件を越える程度まで増加している。
瓦礫撤去後の仮設の建物数も3800軒以上に急増しているが、 この3ヶ月間の新築家屋数は、 4月の10倍程度に増加し、 芦屋市や東灘区等に新築件数が多い。
商店や工場は、 新築家屋よりも仮設店舗や仮設工場が多く、 商店においては、 新築数と仮設店舗数の比率が、 1:6ぐらいに達する。
それに比して個人住宅は、 この時期において新築の方が仮設の建物よりもおおく、 新築住宅は1900軒以上に達し、 瓦礫撤去後の更地に建つ仮設の住宅は1400軒程度である。
4月から7月の30000件以上の増加数に比べると撤去数の増加は極端に少ない。
この期間の特徴は、 撤去後の更地への建物建設数の増加である。
瓦礫撤去後の仮設の建物総数は、 神戸市において4800軒以上に達し、 新築家屋の軒数は5300軒以上に増加している。
この3ヶ月間に仮設の建物は約1000軒程度増加しているのに対し、 新築家屋は、 約2倍の急増であり、 建物総数は、 10000軒以上に達する。
しかし、 この段階でも更地の総数は46000件以上であり、 更地4.6に対し建物建設が1の割合程度にすぎず、 更地の目立つ神戸市の都市景観が特徴である。
交通費の半額補助以外は手弁当で実施され、 データベース作成は、 GIS教育の一環として実施された。
使用したGISソフトは、 京都大学防災研究所で開発されたDiMSIS,アップルカンパニーのRINZO、 パスコ社のARC/INFO、 インフォーマテック社のGDS、 ゼンリンのZmap-coreである。
また、 使用したデジタルベースマップは、 国土地理院発行の数値地図10000、 また、 各地方自治体(神戸市、 芦屋市、 西宮市)でそれぞれ独自に作成された2500分の1のデジタルマップデータ、 建設省建築研究所で作成された2500分の1デジタルマップデータである。
奈良大学地理学科防災調査団が作成した災害データベースは、 広く利用されることが当初の目的であるため、 被災地域の復興の一助として利用されることを望んでいる。
詳しくは、 GIS学会関西支部事務局(奈良大地理学科碓井照子研究室、 FAX&TEL 0742-43-9042)まで連絡ください。
留守がちですのでFAXでお願いします。
適宜、 掲載していく予定です。
第1回目は、 建築家の宮脇檀さんの書かれた記事で、 ネットワークが取り組んでいる「ガレキに花を咲かせましょう」のプロジェクトに関する記事です。
このような熱いメッセージが何より嬉しい支援です。
ありがとうございます。
この機会にご購入下さい。
2年目もできうる限り、 「きんもくい」を通して、 復興市民まちづくりの現状、 課題などを伝えていきたいと考えています。
P.4
調査の方法
調査は震災直後の調査データを基礎とし、 その被災建物がどの様に復旧しているかを建物別に把握していく可視的調査である。
震災復旧・復興調査の継続とデータベース化
今後、 可視的な調査に加えて、 住民や行政の意向、 まちづくりプランナーの動き、 社会条件等を明らかにしていかなければならないが、 これらの調査データを公表し、 他の地域の調査データを共有化することにより、 復興状況のより正確な全体像の把握が可能となると考えている。
GIS(地理情報システム)からみる
奈良大学文学部地理学科助教授、 GIS学会関西支部事務局 碓井照子
―被災地域の復興状況―時系列瓦礫撤去・建物調査からみる復興状況
家屋の解体・撤去は、 被災地域の再生への第一歩でありこの状況を被災地域で広範囲に調査し、 データベース化することにより復旧・復興事業における様々な問題点を整理することができる。震災後1ヶ月目の復旧状況
震災後1ヶ月めの瓦礫撤去は、 大阪市に近接した交通条件のよい市区町ほど早く進行しているが、 神戸市においては中央区の銀行などで独自に撤去が実施される以外、 殆ど撤去作業は進捗していない。
(神戸市、 芦屋市、 西宮市、 宝塚市、 川西市、 尼崎市、 伊丹市)震災後3ヶ月目の復興状況(神戸市と芦屋市)
3月にはいると家屋の解体・撤去が急増してくる。震災後6ヶ月目の復興状況(神戸市と芦屋市)
4月から7月にかけてはもっとも解体・撤去数が多い期間であり、 7月には解体撤去数がピークに達する。震災後9ヶ月目の復興状況(神戸市のみ、 芦屋市入力中)
8月から10月にかけての3ヶ月間で1500件程度の撤去数の増加がある。現地調査とデータベース作成について
現地調査は奈良大学学生のボランティア学術活動として実施され、 1回当たり110人の学生が1-3日かけて現地を歩き回った。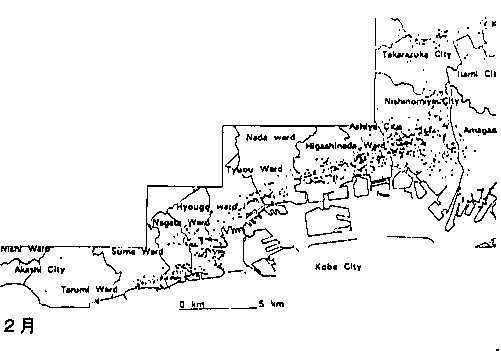
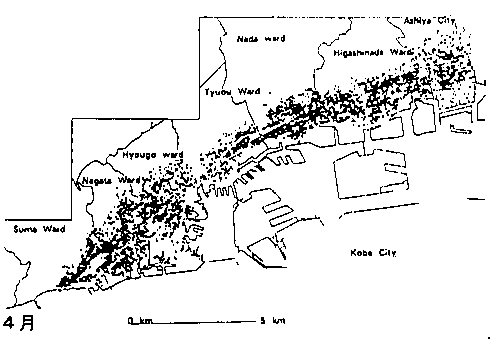
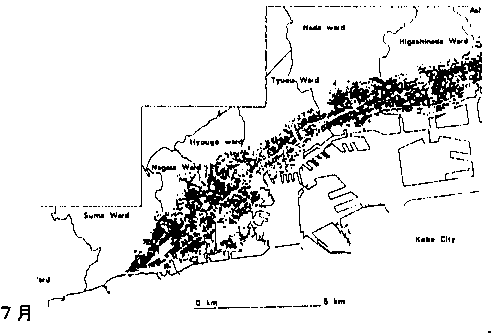
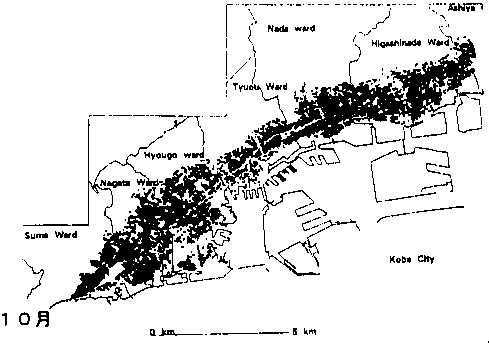
図・瓦礫の撤去状況分布図(奈良大学地理学科防災調査団) INFORMATION
てんさいコーナー/第1回
今回より、 雑誌や新聞等で紹介された復興市民まちづくりに関する記事を転載するコーナーを設けました。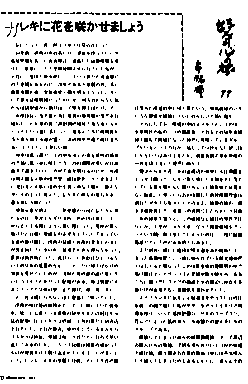
より大きな図(GIF 30K)
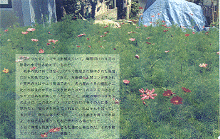
転載内容・東京建築士会「建築東京」1995年9月号より
まちづくり会議(第5回)開催
−阪神・淡路大震災復興のまちづくりから学ぶ−
1月19日(金) 神戸ベイシェラトンバンケットルーム
(神戸市東灘区六甲アイランド、 JR住吉駅→(六甲ライナー)
→アイランドセンター駅)
総合解説(小林郁雄、 15〜)
1月20日(土) アーバングルメRホール他
VTR上映(人間のまち-野田北部の人々、 17〜)
交流会18〜20
1月21日(日) アーバングルメRホール 9〜12
区画整理・再開発/森崎輝行
共同建替・マンション建替/高田昇
都市オープンスペース・防災/佐々木葉二
復興市民まちづくり計画/後藤祐介
第1/森崎+いきいき下町推進協議会
+神戸復興市民まちづくり支援ネットワーク・西部
第2/高田+共同再建支援チーム
第3/佐々木+ASIYA倶楽部
第4/後藤+西宮復興まちづくり支援ネットワーク
全体会、 分科会報告、 討論
Memorial Conference in Kobe 開催

AM−特別講演(兵庫県知事) PM−分科会
AM−分科会 PM−全体パネルディスカッション
第1/地盤の揺れとインフラの被害
第2/都市復興とまちづくり −鳴海邦碩、 阿部泰隆、 岩崎信彦
第3/危機管理
第4/被災者支援
第5/わが家の安全 −藤原悌三、 小林郁雄、 室崎益輝
第6/もしも阪神・淡路大震災が・・
「朝まで長田」開催
震災を語り継ぐ夜−朝まで長田
鎮魂の集い
ネットワーク事務局より
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局 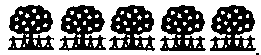
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1029 FAX.078-803-1029
担当:児玉
 きんもくせい23号へ
きんもくせい23号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ