
施設の外観、ストックホルムの旧市街地に立地する
一瞬の偶然で生きながらえた貴重な命なのに、 その後の仮設住宅の生活で孤独に死んでいく一人暮しのお年寄りが後を断たたない。
生きる気力を失って自ら貴重な命を断ち切ってしまう人も出ている。
せっかく生きながらえた人達の命を大切にし、 生きる気力を呼び戻すのが、 無念にも命を奪われて逝った6,00 0名以上もの人達への供養でもある。
〈毎日新聞によると1995年7月15日現在で、 仮設住宅での孤独死は8名、 自殺者は26 名。
自殺者の7割近くが55歳以上の中高年者であるが、 それらの人数はさらに多いという情報もある。
また、 震災による直接被害の死者と関連死の人の合計は6,038名である〉。
被災した下町に住む人達の多くは他所へ移り住んでは生活できない居住地限定階層である。
特に高齢者は長年住み慣れた地域から切り離されては生きていけない。
高齢者が生きる気力を取り戻せるような住宅の供給が必要である。
仮設住宅の建設は入居者と立地場所、 住戸形式のミスマッチという決定的な問題を持ってしまった。
仮設住宅の入居者が恒久住宅としての震災復興公営住宅に移り住む時、 また二度目のミスマッチを犯さないためにも、 仮設住宅供給の問題点をしっかりと把握する必要がある。
既に周知のことであるが、 主たる問題点をあげると、 高齢者は長年住み慣れた地域から切り離されて住めないということ。
住戸の供給とともに日常生活に必要な居住環境条件の供給が求められる要件としてあるということ(例えば、 身近な日常品商店、 医院、 銀行、 郵便局、 交通駅等)。
しかし、 市街地での用地確保の難しさから、 多くの仮設住宅はこれらの点が配慮されず、 遠隔地に大量建設された。
住戸形式の問題では、 今まで下町の長屋やアパートに住んでいた人達は狭小で老朽した住まいであったが、 近隣の人達との触れ合いがあった。
地域で育まれて生活が成り立っていた。
それがバス、 トイレつきの2Kの仮設住宅に移り、 居住水準は上がったようにみえるが、 隣同士の人の触れ合いは失われた。
高齢者、 障害者、 母子家庭等の優先入居を採ったのに、 居住者に対応した最低限のバリアフリーも配慮されていない。
トイレへの段差が30センチもあり、 浴室の手摺りもない。
出入口に軒の庇もない。
恐怖を体験した後では、 ひとりで住むのが不安である。
怖いと訴えている人も少なくない。
今後、 多くの人が仮設住宅から恒久公営住宅に移り住むことになる。
その時また、 同じミスマッチを繰り返さないために、 コレクティブハウスの供給を提案したい。
生きる気力が失せて将来の生活に不安をもつ高齢者等は、 とにかく毎日の人との触れ合いとおしゃべりが必要である。
コレクティブハウスとはコ・ハウジングとも呼ばれる協同居住型集合住宅で、 北欧諸国ではあらゆる世代を対象に、 住宅政策の中に位置づけられて供給されており、 高齢者用のコレクティブハウスもある。
数世帯から20世帯位が集まって、 共に生きる集合住宅での住まい方である。
各々の世帯は居室とトイレ、 浴室(またはシャワー)、 キッチンを持ち、 住宅としての個人の自由とプライバシーの確立はなされているが、 共同の大きな台所、 食堂、 居間、 応接室、 洗濯室、 浴室等々がある。
生活の共同化とそれに必要な機能とスペースの共有化である。
生活の共同化(例えば食事等の家事の分担)の程度は、 居住者同士の取り決めでさまざまなパターンがあるが、 それぞれ独立した住戸で暮らしながら、 コモンルームを核に共同生活が展開されることにより、 安全性、 一緒に住む楽しさ、 心理的な安心感が生まれることのメリットがあげられている。
高齢者等は住み慣れた地域に戻って、 気心知れた人同士が一緒に住めるのが一番いい。
ひとり暮しには8帖程度の居室にトイレ、 浴室(またはシャワー)、 キチネットとたっぷりめの押し入れを、 二人、 三人世帯は2居室を持ち、 後は上述したようなコモンルームがあればいい。
最低限の共同生活のルールを供給主体が示し、 後は居住者相互で助け合いながら生活していくルールを作っていく。
元気な人、 体力的に弱い人、 それぞれ得意の分野を分担して、 生活を営むようなルールが必要である。
見知らぬ人同士が住みはじめても大丈夫。
共同生活スタイルの特定目的の住宅ということで募ればいいだろう。
もちろん高齢者に絞る必要はない。
多世代の家族が集まって住み、 世代間交流があれば、 生活はより楽しい。
神戸市が復興のシンボル事業と位置づけた「神戸市東部新都心」は高齢化社会に配慮したモデル都市として期待されている。
然らばコレクティブハウスの導入は不可欠のはずである。
公的住宅での供給だけでなく、 特定優良賃貸住宅制度の特目住宅での供給も考えられるし、 民間でのシニアコレクティブハウスのグループ建設も可能性はある。
今、 震災を体験して、 共に生きるという気運も高まっている。
下町に人を呼び戻すためには、 まず商店街や市場の復旧が必要であり、 その際にも小規模単位のコレクティブハウスが建設できるような公的助成制度を創設してほしい。
日常生活に必要な施設がセットで供給されれば、 生きる気力は取り戻せる。
実現までにはクリアしなければならない検討項目が幾つもあるが、 仮設住宅での悲劇を繰り返してはならない。
具体的なモデルは、 北欧のコレクティブハウスに止まらず、 お隣の中国で古くから続く伝統的民家、 客家の集住体の住宅(円楼や方形住宅等)、 わが国のグループホームの住宅形式にもそのアイデアとイメージを見ることができる。
〈1995年7月17日記〉


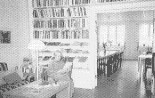
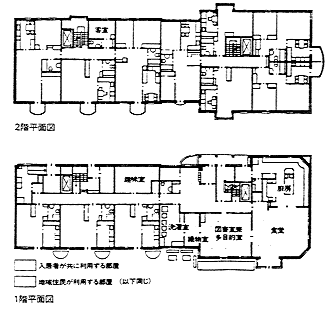
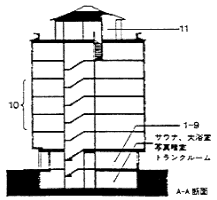
p1,4
水道筋地区においても大きな被害がありましたが、 倒壊した建物の除去も進み、 地域には広い空き地が目立つようになりました。
震災直後に閉まっていたお店も営業を再開し、 活気を取り戻したように思います。
といっても被害を受けた建物での生活を強いられている方も多く、 本来の街の状況からはほど遠いものといえます。
縁があって数年前から、 20年以上子供の頃から親しんできた水道筋で、 地元商店街のリフレッシュを図り、 地域の活性化をめざす勉強会に参加することになり、 街のイメージを高めようとするCI計画など、 地域の方々に便利で親しみやすい商店街の実現を関係者のみなさんとめざしてきました。
婦人会の方々の協力を得て2年前に実施した周辺地域の約1,000人の方々への調査では今後のまちづくりに対して、 積極的なご意見をいただきました。
この結果をふまえて、 具体的な地域の整備目標を定め、 具体的事業への準備をしていた矢先の大震災であったわけです。
しかし、 直後の状況から脱却し、 何とかこの地域を元のいきいきとした街に蘇らせたいという多くの皆さんの呼びかけの中で、 今回、 復興のまちづくりへ向けた協議会が結成されることになりました。
この新しく結成された「灘中央地区まちづくり協議会」は当初のまちづくり計画の対象であった水道筋地区の商店街・市場の皆さんだけでなく、 自治会や婦人会をはじめ、 周辺の住宅地の皆さんからも共に地域の復興を考えていこうという気運が高まり、 一緒に運動を展開していくことになりました。
このまちづくりを進める際の基礎的資料を得るため、 地域の皆さんのご協力を得て、 震災以降の地域の商業施設等の被害や商業活動の状況が調査されました。
また、 震災の後の地域の方々の意識調査も実施されました。
この結果からは、 大きな施設的な被害はあっても将来的にはこの地域の中で今まで以上に地域の復興を図っていこうとする方がほとんどであったということが確認できました。
これからの計画の中ではこのようなまちづくりへの強い意欲をどのように具体化していくかという実際の方法論が課題となります。
地域にはまだまだ生活の再建の見通しさえ立たない不自由な生活を強いられている方々もおられます。
行政による計画だけでなく、 自らの街の復興を自らの創意工夫の中で表現するという夢のあるまちづくりや、 将来、 私たちの子供や孫たちがやはり愛着と誇りをもてる街の実現をめざしたいものです(7/25記)。
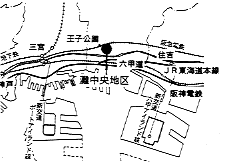
当日は、 一般市民、 行政関係者、 神戸大学学生、 木南会会員など約180名の参加者で、 ほぼ会場が満席となる盛会ぶりだった。
シンポジウムでは、 建築系教室の教授、 助教授ら6名が震災直後から行ってきた被害実態調査や復興まちづくり等の活動を踏まえて、 多様な視点から復興へ向けての提言を行った。
その後、 安田丑作教授の司会で、 会場からの質疑にもとづき、 講演した6名の先生方がパネリストとなり議論が行われた。
耐震基準は今のままでよいのか、 高速道路の復旧をどう考えるか、 復興まちづくりにおける防災性能をどう考えるか等々、 用意された時間内ではおさまりきらないほどの熱心な議論が展開された。
建築系教室及び木南会では、 今回のシンポジウムだけでなく、 震災復興事業として、 震災展示会、 震災記録集の発行などの事業を今後も予定している。
【各先生方の講演テーマ(講演順)】

センターは、 被災地でのすまい・まちづくりに関する諸課題―被災マンションの建替、 狭小・接道不良宅地の集積地での共同・協調建替え、 街区レベルでの協働のまちづくりの推進など―に対応するため、 全国から広く専門家を募り、 住民からの要望に対して無料で(専門家の費用はセンターが負担)専門的アドバイスを行い、 より良いまちの復興のための手助けを行うことを目的としています。
センターには、 開設当初から当ネットワークメンバーがボランティアで住民からの相談等の応対に協力しています。
センターに詰めて改めて感じることは、 1件1件それぞれにおかれている事情が異なり、 同じ種類の相談がないことです。
これは主には、 地域による震災の程度の差、 地域ごとにまちの特性が異なること、 さらには住民の取り組み方の程度が異なること、 などによるものだと考えられます。
住民の方々は震災を機に、 まちづくりについて相当勉強をしています。
時には間違った情報も入っていることもあります。
まちづくりの専門家は適切なアドバイスを行いながら、 多様な被災地の課題に対応して行くことが求められています。
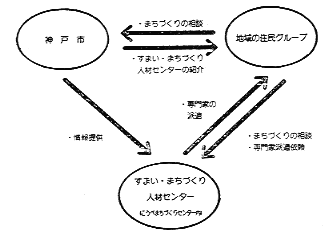
連日の猛暑に水まきできないところは枯れかけており、 雨乞をしたくなっています。
楠丘町では毎日日暮れとともに約1時間水やりをしますが、 ご近所の方々が見かねて一緒に水を撒いてくださったり、 「ありがとう」と声を掛けてくださったりと労ってくださいます。
さて予告いたしました秋蒔きは9月中旬となります。
1)撒きたい場所は、 土地の大きさと種の種類
2)撒きたいひとは労力の提供
の申し出をお受けします。
8月中にネットワーク事務局までご連絡ください。

このあたりは大きな火災にあった地区で、 自力仮設住宅、 店舗が少しずつ建ち始めている。
〒651-22 神戸市西区狩場台1-10-4森栗茂一さんまで。
20日必着。
◎第8回西部市街地連絡会(毎月第3水曜) 9月6日(水)18:30〜 神戸富士バンクビ
ル
◎「復興市民まちづくりvol.2」編集作業進む
「復興市民まちづくりvol.2」を9月上旬に出版する運びとなりました。
前回は18種のニュース(内行政関連5種)を収録しましたが、 今回は31種(同5種)に一気に増加しています。
これは、 主には区画整理区域内でのまちづくり協議会がこの3ヶ月の間に多く発足したことによるものです。
本書は大手書店等で販売しますが、 団体、 グループ等で何十冊かまとめたご予約をされる方は早めに(8月末まで)事務局までご連絡ください。
今後も、 事務局では継続的に各地の復興市民まちづくりの情報入手に努めて行きたいと考えています。
また、 定期的にまちづくりニュース等を事務局までお送りください。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1029 FAX.078-803-1029
担当:児玉
P.4
 きんもくせい15号へ
きんもくせい15号へ