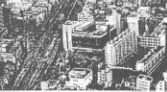
鉄道高架が落下し、 メイン六甲BC棟
が全壊した(2/8)撮影
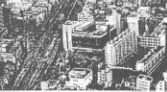
私達コンサルタントが待ちに待った住民との顔合わせも7月1日、 2日に行われた。
これからこの事業は着実に動いていくように思う。
思い起こせば3月5日、 厳冬の日曜日、 高層住宅棟が屈傾したメイン六甲BC棟駐車場で行われた都市計画案の説明会、 ほとんどの人が立ったまま足踏みしながら説明を聞き、 「いきなり再開発区域に決定するとは納得できない。
断固反対する」との声に一斉に拍手が沸き起こった日から4ヶ月あまり経っている。
木造住宅のほとんどが倒壊し、 道路にも崩れ落ちていたガレキも今はほとんどが片づけられ、 更地となり、 ぽつぽつと仮設店舗や、 住宅が建てられている。
この間、 住民も行政も苦しい日々であったが、 何回かの説明会を経て、 住民の気持ちもやっとほぐれてきて今日になったように思う。
この事業は、 これから何年かかるかわからない。
4つの協議会の足踏みが揃うのか、 バラつきが出るのかわからない。
まとめ役のコンサルの任は重い。
ともあれ、 この事業は衆目監視の事業である。
逐次報告していきたい。
役員会においては、 主として(1)まちづくり計画に関する内容、 管理処分(権利変換)計画に関する内容について研究、 協議し、 一定の方向性が出た段階で、 ブロック総会にはかる。
ブロック総会の運営は、 各ブロックの主体性を重んじられることになり、 役員会の開催頻度、 部会方式の賛否等ブロックごとに異なっている。
コンサルタントは、 ブロック協議会、 連合協議会で検討される内容について資料、 材料を提供し、 各協議会の意見集約の手助けをする。
また、 これまで住民の計画案づくりを支援してきた神戸大学の平山、 児玉両先生が各協議会の顧問として位置づけられ、 協議会での意見集約方法等についてアドバイスすることとなった。
協議会役員会で当面研究・協議される2つのテーマの内容は次のとおりである。
まちづくり計画について住民の手によるまちづくりを目指し主要なテーマにつき、 論議・意見集約を図る。
(1)東部副都心としての機能について
(2)1haの防災公園について
(3)残存建物について
(4)建物の高さ・形態・配置(景観)及び用途について
管理処分(権利変換)計画について
住民にとっては極めて現実的な生活再建に関わる内容について、 行政からの説明を補完する意味を含めて、 コンサルが逐一説明を行い、 住民の不安、 疑問に応え、 住民の再開発事業への理解が深まるよう勉強会を行う。
第1回 再開発事業の仕組みと流れ
1つは、 現在の都市計画決定案を住民の意見、 アイデアを込めてどれだけ良い案につくりかえられるかである。
まちづくり協議会が折角できたのになにも変わらなければ何の意味もない。
住民、 コンサル、 行政3者が知恵を絞らねばならない。
もう1つは、 住民の立場の違いによる事業進捗(スピード)に対する考え方の違いである。
倒壊家屋の居住者、 営業者と高齢者は一刻も早い復興を願うであろうし、 現存家屋の居住者と壮年者は、 そんなに焦る必要はないと考えるであろう。
すでに、 ブロックごとの協議会における役員会の開催頻度でも違いが現れてきている。
互いに相手の立場への理解がほしい。
神戸市などと同様西宮市でも2月の初旬、 大学の教員と学生、 建築や都市計画の専門家、 全国からの支援技術者たち約150名を動員して、 災害直後の状況の生々しい市内各地区を分担し一軒一軒調査し、 被災マップにまとめました。
この活動が縁となって、 西宮復興まちづくり支援ネットワークが生まれました。
被災地の状況をつぶさに調べるにつけ、 この街がダメージから立ち直って復興する姿を見届けたい、 その過程で自分にできることがあれば手伝いたい、 という止むに止まれぬ状況がありました。
西宮市を11地区に分け50余名のメンバーを11チームに編成して、 それぞれ分担して作業を進めてきました(「きんもくせい」3号、 6号を参照してください)。
再度の現地調査を含めて被災地の実態をさらに詳細に把握すること、 地区の歴史や自然的条件など地区特性を理解すること、 問題点や復興にあたっての課題を地区別に検討すること、 地区ごとの復興まちづくり構想をたててみること、 などの作業を持ち寄りつつ、 議論を重ねながら段階的に進めてきました。
7月13日予定の集まりが13回目の連絡会議なります。
なかなか本格的な内容になってきました。
西宮ネットワークは混成部隊です。
もともと市に関わりがあった地元に詳しいメンバー、 そうでないメンバー、 専門家、 専門家の卵、 学生などの集まりです。
社会人は自分の仕事を終えてからの参加ということになります。
大阪市大のチームなどは研究生の学生が中心で、 私が出席できないことも多く先輩たちに迷惑をかけながら何とかやってます。
もっと地元に入って復興支援をするべきだ、 行政と連携しなければ意味がない、 プロのビジネスとして成り立つようでなければ、 と言った議論が時には出ます。
いつまで続くのかと自問自答しながらもここまでやってこれたのは、 GU計画研究所の後藤さんと石東研究室の石東さんの2人のリーダーに恵まれたおかげです。
西宮市では、 西宮北口駅北東地区(36ha)、 森具地区(11ha)、 阪神西宮駅南地区(2.4ha)、 JR西宮駅北地区(25ha)の4地区を、 復興の重点面整備事業として進めています。
多くの緊急復旧復興事業を抱える市は、 この4地区の市街地復興を手掛けるだけですでに手一杯の状況です。
その一方で、 残りの95%以上に及ぶ一般の被災市街地が残されます。
一般被災地は民間自力建設による復興に委ねられることになりますが、 一般被災地の復興を将来のまちづくりに向けてどれだけ計画的に促進できるか、 今回の大震災からの復興の成果を大きく左右することは明らかです。
一つ一つの住宅、 一つ一つの街区の再建、 零細敷地の共同化や協調建替、 小規模な区画整理などが積み重ねられて街が復興していくと思います。
復興の足取りのなかなか重い現状ですが、 地元からの要請があれば専門家としてできるだけの技術支援をしたい、 これは西宮ネットワークの大きな願いです。
民間自力による復興まちづくりを支援する、 様々なグループが活動しつつあり、 またこれらの活動を支援するシステムも整備されつつあります。
西宮ネットワークは今後これらの活動との連携を広げつつ、 時には地元自治会等への啓発活動を行い、 具体的支援を拡大して行きたいというのが皆の考えです。
しかしその一方で、 初心に基づいて地区ごとの復興の姿を定期的に調査確認し、 復興まちづくりの行方を見守る仕事を継続したいと願っています(7月8日記)。
きんもくせいの12号でお約束しました西の地域のお便りから始めます。
長田区海運町、 日吉町、 若松町。
ひまわりブレンドは撒いた日にちの差がありますが、 最初の海運町(5/28)ではすっかり大きくなったひまわりが7月19日にはつぼみを4つ見つけました。
種の配合や技術面でもすっかりお世話になった第一園芸の北島さんや児玉さんがこっそり何度も足を運んでくださったのでしょう、 後から撒き足してくださったらしいペチュニアのピンクのかわいい花がひまわりの下で咲き乱れ、 黄色い蝶々がしきりにまわりをふわふわ飛んでいました。
腕塚町は撒いたのが最後だったのと残った家の真ん中にぽつんと空いた広場のためかまだあまり大きくなっていませんが、 やはり撒き足した(これは最初から混ぜていました)ペチュニアの小さな花が咲いています。
大道通の復興まちづくり相談所のまわりはハウスを建てるために焼け跡に土を盛り、 地均しをしたために、 すっかり堅く締まっていた土地でした。
耕すにも骨が折れ、 街区の復興まちづくりの世話役をなさっているお向かいの高山さんと松原さんがとうとう見かねて、 電動ドリルを貸してくださいました。
その甲斐あってかものすごい花ざかり、 お近くの方はお訪ねください。
それぞれの地区の花の成長の様子をお知らせするに際して各地区を訪ねてみますと、 鷹取の焼けてしまった商店をプレファブで再生しようと頑張っておられる人々が笑顔でお水をやってくださっていました。
そして2ケ月程のあいだにあんなに無残だった土地がすっかり蘇っていることに気づきました。
六甲でもたまたま『知人が知らせてくれましたので私の土地に撒いてください、 ただし今他の方に貸していますのでじゃまにならんとこだけ』と最初に(5/26)申し出て来られて方がありました。
そこは話の行き違いでほんの少ししか撒けなかったのですがお隣の方が水をやって下さったり、 毎日声を掛けて下さったりとお世話を惜しまずにして下さったお陰でみごとに成長しました。
まちづくりはあくまでも自分たちの手によるものというのが基本で私たちの活動はそのお手伝いの部分です。
勝手に人の土地に花の種を蒔くなんて叱られないかと心配しましたが、 「咲きましたねありがとう」「きれいですね」「少し分けてもらってもいいですか」というたくさんの声に励まされています。
秋にはもう少し準備を整え、 種を蒔きたい地域を募集し、 その町の人々のご希望も盛り込めるようにして、 春にもっとたくさんの花盛りを迎えたいと思います。
今回は準備不足の性急な取り組みにもかかわらず多くの方々の知恵と力で助けられました。
大阪の第一園芸株式会社をはじめ、 東邦レオ株式会社、 都市環境デザイン会議関西ブロック、 東京の生活文化同人の会から暖かいご支援をいただきました。
お金もないのによくあれだけの量の種を蒔いたもんだと我ながら心細かった当初を思い出していますが、 これらのご支援をもとに基金をお願いし、 もっとたくさんの方々が利用できるものにできればと考えています。
みなさんもいろいろなところへ声を掛けてくださいますようお願いいたします。
(天川 佳美、 7/20記)
つぼみがつき始めた
被災を受けた市街地から遠く離れていて、 交通の便も悪いことから空き家が多かったのですが、 先着順受付に切り換えて、 徐々に居住者が増えてきています。
そんな中で、 以前から鹿の子台に居住していた住民の方々が中心となって「鹿の子台ボランティア連絡会」を結成し、 仮設住宅の住民への支援活動を行っています。
仮設住宅への引っ越しの荷造りや搬入を手伝うボランティア活動や各戸への訪問、 生活に必要な日用品の提供、 時には病院への付添いといったこともやっています。
5月28日には、 ミニコミ紙『バンビーネット』を創刊し、 仮設住民と地域住民の交流を深めていくことを目指しています。
6月25日(日)には、 ボランティア連絡会主催によるバザーが、 仮設住宅敷地内で催されました。
衣料品、 家具、 電気製品等の格安提供や、 炊きだしなどが行われ、 仮設住宅住民と地域住民が入り交じって大いに賑わいました。
当日は、 「まちづくり基金」への協力を呼び掛け、 バザーの収益金と合わせて、 今後の鹿の子台のまちづくりのために使っていこうと考えています。
ボランティア連絡会事務局の西野氏は、 「このまちづくり基金は、 仮設住宅の住民のために何かするというのではなく、 仮設住宅の住民もこの鹿の子台地域の住民の一員であるという認識のもとに、 仮設住民と地域住民が一緒により良い生活やまちづくりのあり方について考えていくきっかけになればと思っている」と語ってくれました(児玉善郎、 7/7記)。
第1回(8・1号)は「復興山分けプラン」として当ネットワークが、 地域の復興を担当するコンサルタントの「シマ分け」と「縄張り」と表現され、 「『談合』の芽」など下司の勘ぐりに基づく下品なルポである。
私が公表している文章や記事を切り張りしてルポができる程度のものに反論する必要もないが、 〈ミニコミにも五分の魂〉。
被災地域の被災市民のまちづくりを支援する当ネットワークを誹謗する目的は何か。
単なる売文か。
(小林 郁雄、 7/25記)
早急にニュースを事務局宛にお送りください。
発行は8月末予定です。
P.4
1.まちづくり協議会設立までの経緯
震災後の住民と行政との主要な関わりの経過は以下の通りである。
2/1―建築基準法84条制限区域指定―市街地再開発事業予定地区となる
2/16―神戸市震災復興緊急整備条例制定―市街地再開発事業検討区域となる
2/21―都市計画決定案―地元6自治会へ説明
2/22―現地相談事務所開設―灘生協の駐車場ビルにて
2/28―都市計画決定案縦覧開始
3/5―都市計画案地元説明会(2回)―メイン六甲BC棟駐車場にて
3/17―都市計画決定
3/22―今後の進め方(協議会4ブロック案)―自治会長他へ説明
4/2―メイン六甲BC棟区分所有者臨時集会―今後の進め方他、 コンサル決定
4/16―メイン六甲BC棟2部会活動開始
4/23―事業の流れ、 コンサル派遣説明会(3回)―メイン六甲BC棟駐車場にて
5/14―損失補償他説明、 まちづくり協議会方式説明(3回)―メイン六甲BC棟駐車場にて
6/5―事業用仮設住宅(36戸)申し込み受付
6/18―まちづくり協議会設立総会(3ブロック)―フォレスタ六甲B1F駐車場にて
7/1―深備5まちづくり協議会・第3回役員会―コンサル顔合わせ
7/2―桜備5まちづくり協議会・第3回役員会―コンサル顔合わせ
7/9―まちづくり連合協議会設立総会―市現地集会所にて
7/9―桜口5まちづくり協議会役員会―コンサル顔合わせ2.協議会の進め方
ブロックごとのまちづくり協議会は、 居住者、 事業者、 権利種別、 現存家屋、 倒壊家屋等、 異なる立場からバランスよく役員を約20名選任する。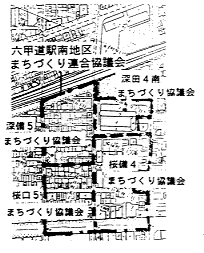
ブロック図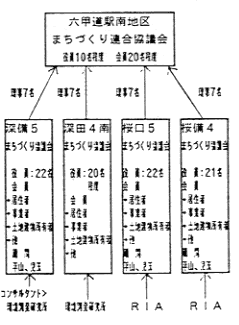
まちづくり協議会組織図
第2回 土地評価の考え方と区分所有法
第3回 建物評価の考え方
第4回 補償・借家権の考え方3.これからの課題
大きく分けて2つある。
(7/20記、 つづく)西宮復興まちづくりネットワークの活動状況
大阪市立大学教授 土井 幸平
建築学会と都市計画学会の有志により企画され合同調査団を組織して行った阪神大震災被害実態緊急調査。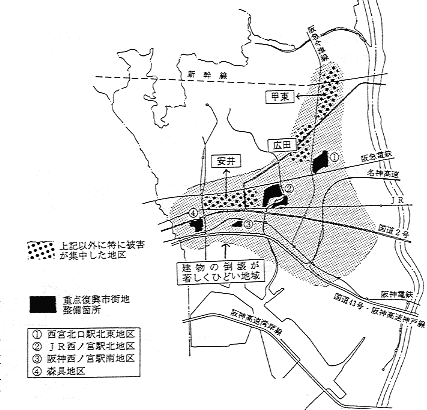
重点復興市街地位置図
ガレキに花を咲かせましょう・その後
5月の終わりごろから始めた、 阪神市街地緑花再生プロジェクト第1段階「ガレキに花を」の“がれきの花畑化”はみごとに花を開きました。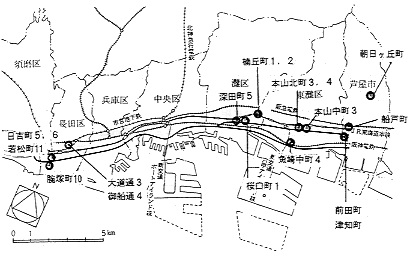
花の種をまいた地区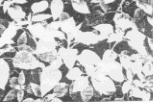
大道通のひまわり。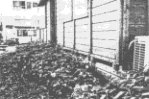
大道通まちづくり相談所周りのペチュニア
仮設住宅と地域住民との交流
神戸市北区鹿の子台には、 3月以降千数百戸もの応急仮設住宅が建設されています。INFORMATION
集英社代表及び鎌田慧氏へ
「Weeklyプレイボーイ」誌で短期連載「神戸・半年目の真実」が始まった。ネットワーク事務局より
◎西部連絡会:8/2(水)18:30〜 三宮 富士バンクビルディング11F
〈コアレポート〉
・新長田駅北、 新開地地区等(広沢) ・浜山地区(細野、 辻)
◎「復興市民まちづくり」vol.2出版へ
5月〜7月末までの各地のまちづくりニュースを収録します。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1029 FAX.078-803-1029
担当:児玉
 きんもくせい14号へ
きんもくせい14号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ