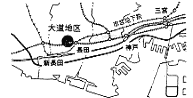
大道地区位置図
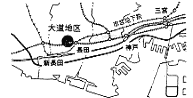
地震によって地区の家屋の23%強が倒壊し、 さらに、 火災により3つの街区が大きな被害を受け、 1街区はほぼ完全に焼失してしまいました。
地区内の旧長田市役所等が現在も避難所となっています。
「大道周辺地区」の大部分が震災復興住宅市街地総合整備事業区域に指定されたのを機に、 3月26日、 神戸市による説明会を開催し、 私たち、 まちづくりコンサルタントの紹介と住民による復興まちづくりの呼びかけを行いました。
翌日からは街区単位の“説明会”“勉強会”を開催し、 引き続き、 共同化による住宅再建の検討など、 住民、 神戸市、 まちづくりコンサルタントが連携して具体的な復興まちづくりを進めています。
街区によってまちづくりの進み方が違っていますが、 先行している街区では、 模型も活用して、 協調や共同化による街区再建の方法について勉強会を重ね、 住民意向の集約と事業化の検討を進めています。
そして、 街区単位の“まちづくり協議会の準備会”が生まれつつあります。
また、 街区別の集会開催と同時に「大道周辺地区復興まちづくり新聞―ひまわり」を発行し、 まちづくりの情報が住民の手に入りやすいようにしています。
また、 5月末から現地に「復興まちづくり相談所」を開設していますが、 相談に訪れるひとが増えてきています。
4m未満の細街路を介して狭小宅地が密集していたまちで、 「元のまちに戻したい」という下町で生まれ育った人達の願望を十分に踏まえた環境再建が必要とされています。
そのためには、 街区ごとの個性、 実状に合わせた復興まちづくりの“処方箋”が必要です。
住戸単体の最低居住水準よりも都市的居住環境に求められる要件を、 じっくり腰を据えて検討していく必要があります。
求められる環境を実現、 担保する条件整備が必要です。
しかし、 被災地住民の避難生活、 仮設居住といった条件のもとで、 まず住宅、 そして、 生活再建の見通しが求められています。
とにかく、 一刻も早く復興まちづくりの具体的な事例ができることを地区の住民も期待しており、 みんなで努力しています。
もう少しすれば具体的なニュースをお知らせできると思います。

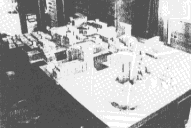
模型をつくって話し合いを進めています
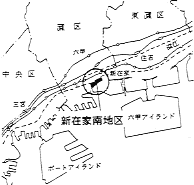
国道43号南側に接する準工業地域で、 環境問題をきっかけに平成3年より神戸市の「まちづくり条例」に基づくまちづくり協議会を組織し、 住民参加のまちづくりに取り組んできた。
今回の大震災では、 39人が死亡、 家屋の約8割が倒壊する大被害を受けた。
本稿では震災後、 筆者が新在家南地区のまちづくり委員会を支援する専門コンサルタントとして、 復興まちづくり、 すまいづくり、 特に接道不良家屋の共同建替え事業等に取組んできた経過を報告する。
なお、 復興への道は長くかかりそうであり、 今後も進ちょくに応じて報告していきたい。
また、 多くの酒造会社に加えて、 神戸製鋼所や小泉製麻等の工場が立地するとともに、 居住ゾーンにおいては、 住工混在や木造住宅過密地区等の住環境の問題をかかえていた。
この敷地は、 面積が740平方メートルで、 接道条件がよく、 神戸市等より優良建築物等整備事業の共同化助成を受ける予定であり、 また、 国道43号沿いで容積率が300%であり、 これらの点で等価交換事業としての経済効率が比較的よい。
即ち、 地主はこの機会に借地権の解消を望んでおり、 借地権者もこの機会に持家になることを希望している。
この敷地は、 面積が680平方メートル、 接道条件がよく、 神戸市から優良建築物等整備事業の助成を受ける予定で、 また、 容積率が300%あり、 等価交換事業として経済効率が比較的よい。
等価交換事業を考えており、 この点でおもて宅地とうら宅地の土地評価が重要なポイントとなっている。
特に、 あじさいシステム事業の中でも長屋等に住んでいた従前居住者のための特定入居制度の設置を望んでいる。
即ち、 共同建替え手法等の説明会にはじまり、 現段階では基本構想の経済条件の概算に基づく個別意向の合意形成がほぼ出来つつある。
1.共同建替え手法等の説明会の開催
即ち、 事業化段階へ進む訳であり、 各種融資制度を活用した資金調達の相談やディベロッパー等の選考に入っていこうとしている。
計画の構成は以下のとおり。
「第4章 市街地復興計画」では、 被災地を都心、 東部、 西部に分け、 それぞれの地域を復興するプロジェクトとして下図に示すものをあげている。
「第5章 シンボルプロジェクト」では、 3つの視点(緊急性が高い、 波及効果が大きい、 神戸復興の象徴となる)から、 右の17が示されている。
今後は、 これらの事業を特別事業・特定事業として国の予算化を図ることをめざしている。
また、 「協働のまちづくり」は本計画の4つの目標の一つの柱となっており、 各地で展開している復興市民まちづくりの多くの積み重ねによって、 復興計画が充実されていくことが期待されている。
もう50〜60cmにのびたコスモスが緑のじゅうたんのようです。
本山中町の商店街跡と六甲道駅南の15種混合はいろんな種類の芽を出しはじめています。
次号は西の地域の便りをお楽しみに。
我が事務局周辺楠丘町のコスモスは本日一輪開花!
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
P.4
復興まちづくり
地区の特性
当地区は、 旧西国街道沿いの古いまちであり、 灘五郷の一つ、 西郷の酒造地区である。地区の位置づけ
当地区は、 復興にあたって、 神戸市震災復興緊急整備条例(H7.2.16施行)に基づき、 東部副都心への住宅の重点供給をめざす六甲地区(約297ha)の一部として、 また、 まちづくり協議会との連携による住宅及び住環境の整備を図る新在家南地区(約 27ha)重点復興地域として、 2重の重点復興地域に位置づけられている。取組み方針
当地区の復興まちづくり方針としては、 「住宅市街地総合整備事業」「密集住宅市街地整備促進事業」等により酒造のまちとしての酒造のみち等の復興、 地区道路の拡幅や倒壊住宅の共同建替え等による住環境の改善及び公的住宅の大量供給が方向づけられるが、 具体的な整備は現在検討中である。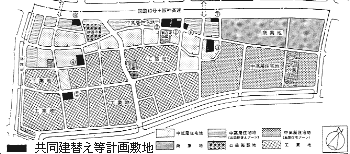
新在家南地区復興まちづくり構想と
共同建替え事業プロット図
(クリックすると大きな図が見られます。53KB)
復興すまいづくり
共同建替え事業の取組み
復興まちづくり計画を検討する一方で、 倒壊した家屋等の建替えについては、 地区内で下図に示すような数箇所で共同建替え計画に取組んでいる。(1)3丁目A:残存家屋2軒も参加
この計画は、 20人の権利者による共同建替え計画で、 残存家屋2軒の協力的参加が得られている点が特筆される。(2)3丁目B:地主1人と借地権者12人の共同建替え
この計画は、 地主1人と借地権者11人による共同事業で、 土地の有効利用と権利関係の整理を目指している。(3)2丁目A:おもて宅地の協力
この計画敷地は、 幅員5.5mの区画道路に面するおもて宅地と幅員2m以下の2項道路にしか接しないうら宅地からなっており、 おもて宅地の協力による共同化計画が進められている。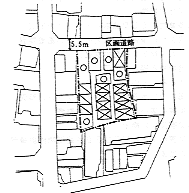
2丁目A区域図(4)4丁目A:借地権者との等価交換とあじさいシステム事業の組合せ
この計画は、 長屋等を所有していた地家主と借地権者との等価交換による共同建替え事業を行うとともに、 地家主は保留床を買い取り、 神戸市のあじさいシステム事業(神戸市特定優良賃貸住宅供給促進制度)との組合せを考えている。共同建替えへの合意形成
当地区においては、 2月当初より、 まちづくり協議会の活動として、 このような家屋の共同化計画の話し合いを敷地単位、 街区単位に進めてきたが、 その経過は以下の手順を辿っている。
↓
2.一部の権利者による共同建替え等の発意
↓
3.基本構想図(タタキ台)の作成
↓
4.全体権利者への周知
↓
5.基本構想の経済条件の概算
↓
6.個別意向の合意形成
↓
基本計画及び事業計画の作成へ次のステップ
次のステップとしては、 個別意向を反映した基本計画及び事業計画の作成に進んでいくが、 事業計画作成にあたっては、 従前資産の評価、 保留床処分価格の設定及び調査設計の精度アップが求められている。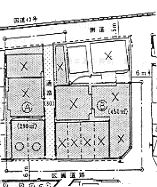
3丁目A街区共同建替え計画図・現況図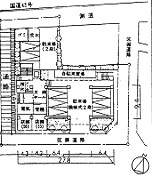
3丁目A街区共同建替え計画図・1階平面図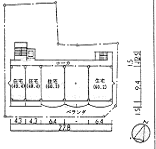
3丁目A街区共同建替え計画図・住宅標準階平面図
3丁目A街区共同建替え計画図・断面計画図
地元での共同建替えの話し合い(7/2)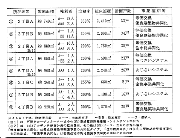
新在家南地区共同建替え等計画一覧
(クリックすると大きな図が見られます。30KB)
神戸市復興計画策定される
6月30日、 神戸市の復興計画が策定された。 第1章 復興の基本的考え方
第1章 復興の基本的考え方
1.復興への基本的課題
2.復興まちづくりの目標
第2章 目標別復興計画
1.“市民のくらし”を復興する
2.“都市の活力”を復興する
3.“神戸の魅力”を復興する
4.“協働のまちづくり”を推進する
第3章 安全都市づくり
1.基本的考え方
2.防災生活圏
3.防災都市基盤
4.防災マネージメント
第4章 市街地復興計画
1.基本的考え方
2.都心地域復興計画
3.東部市街地復興計画
4.西部市街地復興計画
第5章 シンボルプロジェクト
第6章 実現に向けてシンボルプロジェクト
1)市民のすまい再建プラン
2)安全で快適な市街地の形成
3)21世紀に向けた福祉のまちづくり
4)安心ネットワーク
5)東部新都心計画
6)神戸起業ゾーン整備構想
7)中国・アジア交流ゾーン計画
8)21世紀のアジアマザーポートづくり
9)国際性、 近代性などの特色を生かした神戸 文化の振興
10)多重性のある交通ネットワークの形成
11)次世代の情報通信研究のための基盤整備[KIMEC構想の推進]
12)地域防災拠点の形成
13)水とみどりの都市づくり
14)海につながる都心シンボルゾーンの整備
15)災害に強いライフラインの整備
16)災害文化の継承
17)災害科学博物館及び20世紀博物館群構想の推進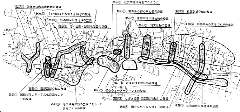
復興プロジェクト位置図
(クリックすると大きな図が見られます。52KB)INFORMATION
花咲かだより その2
 芦屋市の津知町は花まき隊員のアイデアで花畑の真ん中にレンガ囲いの花見スペースがあります。
芦屋市の津知町は花まき隊員のアイデアで花畑の真ん中にレンガ囲いの花見スペースがあります。まちづくりシンポジウム―芦屋の再生に向けて
(主催:AAネットワーク)
―AANの提案と住民との意見交換
7月15日(土)14〜17(定員100名)
芦屋市商工会館/芦屋市公光町4―28
―軽食と音楽による懇親会
7月15日(土)16〜20 同中央地区公光公園
―副知事、 市長を交えてのシンポジウム
7月16日(日)14〜17(定員、 場所はPART1に同じ)
ネットワーク事務局より
○東部市街地連絡会
―新在家地区(後藤)、 六甲駅南地区 (児玉)の報告、 討議
・7月18日(火)18:30〜
・神戸富士バンクビルディング 11F
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1029 FAX.078-803-1029
担当:児玉
 きんもくせい13号へ
きんもくせい13号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ