御菅地区における復興まちづくり初動期の取り組みについて
―事業手法の組み立て上の提案―
(株)アーバンプラニング研究所 北条 蓮英
瓦礫処理の対応などのボランティア活動に関わってこられた森栗大阪外大助教授のご支援や地元関係者の自発的努力により、 地元のまちづくり組織が今立ち上がった。
小学校での避難生活も6ヶ月目に入り、 関係者のいらだちも高じている中での始動に心から敬意を表したい。
私共は、 かつて昭和53年から平成元年にかけて、 神戸市まちづくり条例(昭和56 年)に基づき地元のまちづくり活動の支援に関わり、 ルールづくりとしてはまちづくり協定の締結(平成元年)を、 また、 モノづくりとしては、 地域福祉センターの実現(平成3年)など一定の成果をあげたが、 重要課題と考えていた「長屋等の住宅改善」や「市場・商店街の改善」については手が届かず積み残されたままになっていた。
丸焼けとなった現地にたたずむと、 当時の支援活動の限界を痛感するのを禁じ得ない。
これからの道のりは長く果てしないが、 まちづくりコーディネーターとして復興まちづくりをいかに支援できるのかが問われている。
始まったばかりの、 取り組みの一端を報告したい。
*
御菅地区は、 全面焼失地を中心に土地区画整理事業が都市計画決定(10ha)され、 これを含む隣接地区は重点復興区域(30ha)に指定される。
区画整理事業地区では、 幹線道路(長田線)をはさみ、 2つのブロックでそれぞれまちづくり協議会が設立された。
そのひとつの御菅5、 6丁目地区では、 去る6月18日しとしと雨の中、 100数十名の住民が集まり、 まちづくり協議会が開催された。
地元で自主的に実施したアンケート調査結果によると、 従前地に戻りたい住民が9割にのぼることが報告され、 公営住宅一棟の早期建設の要望書が行政に手渡された。
参加者からは、 「区画整理事業の減歩率をゼロにせよ」「事業区域内での仮設住宅を建設せよ、 自主建設を許容せよ」の強い要求が出された。
私の方からは御菅地区の復興まちづくりの手法の提案を行った。
その概要を以下に記す。
*
1)地元組織による次なる取り組みとして、 地元で共有できるまちの将来像を作成する必要性を述べタタキ台として、
a)復旧ではなく、 復興を視野にいれた定住できるまちづくり
b)生活再建に向けて活気あるまちづくり
c)従来の町の良さを生かしつつ、 不燃化を促進するまちづくり
を示した。

長田区役所内での地区模型の展示(「神戸新聞」6/19より)
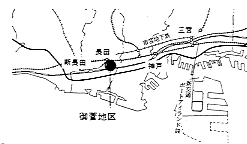
御菅地区位置図
2)こうしたまちの将来像を実現する事業手法として、 すでに土地区画整理事業が都市計画決定されているが、 これに加えて建物整備事業を同時に進めていく必要があること。
土地区画整理事業は、 土地の区画形質の整備、 換地をすすめる手法であって、 建物整備まで関与できない以上、 区画整理は、 まちづくりの手段であって、 目標ではない。
したがって、 建物整備までを視野にいれた事業手法の導入が必要である。
当地区の町割については耕地整理時代の街区(一辺100m)を継承していることから、 街区の単位が約1haと大きい。
地元の減歩ゼロの要求に直接答えるものではないが、 極力まとまって共同化することで減歩緩和に寄与できる可能性があることを提起した。
3)具体的には、 2つのモデル街区(幹線沿道の容積率300%を含む街区と、 容積率200%の一般街区)をとりあげて、 建築計画上の概略検討を行い、 共同化の単位と建物イメージ、 確保できる住宅戸数のシミュレーションを行い、 あわせて、 イメージ模型を示した。
その結果は、
a)幹線道路沿道街区では、 表と裏の容積率の差異(300%と200%)がある区域を一体的な敷地とすることで、 共同建築の有利性が大きく発揮される。
b)しかし、 容積率200%の街区では、 従前居住者の住宅戸数を確保するには容積率100数十%が必要で、 このためには、 街区の1/2の5,000m2以上にまとめる必要がある。
c)町並みからみると、 中層タイプ(5〜6階)では、 容積率100数十%しか確保できず、 200%近くまで活用しようとすると、 高層(12〜3階)タイプになる。
d)共同化の単位が大きくなれば、 土地利用上のメリットとして、 道路面積が節約できる。
私道の集約統合により、 公共用地の効率化、 つまり、 減歩率の緩和に貢献できる可能性がある。
4)住宅戸数を法的制約の中で最有効利用によりできるだけ確保し、 余剰床を生み出し、 これを公的住宅として取得(買取り公営住宅、 借り上げ公営住宅)する事業の組み立てが必要である。
5)先行的に土地の公的取得ができると、 まちづくりに有利に働く。
売却に協力してもらえる地主から土地を取得して、 換地手法により道路、 公園等に充当する。
また、 取得した用地は個別に分散しているのを、 区画整理事業の換地で公的住宅の用地として活用することができる。
6)御菅地区の特性として住宅と工場とが混在した土地利用を成している。
現行用途は準工業地域であるが、 一定の区域を工業地区として集める仕掛けとして、 地区計画制度を適用する必要があるのではないか。
*
今後、 小単位ごとの住民協議によりニーズを把握しながら、 確かな事業化方策を構築していく必要がある。
ただ、 説明の後、 「そんな夢のような話よりも、 早く避難所から元のところに戻りたいのですよ。
」という声はこたえたが、 乗り越えねばならない山であるといえよう(6月21日記)。
p1
災害に強いまちづくりについて思うこと
建設省都市局都市計画課まちづくり事業推進室 伊藤 明子
阪神・淡路大震災後の復興にあたって、 皆様方のご努力に深く敬意を表します。
私ごとで恐縮だが、 中学・高校の3年間神戸市内に住み、 つい1年前まで宝塚市役所に出向し、 現在友人も両親も被災地におり、 今回の震災についてはさまざまな思いを抱いた。
特に、 しばらくの間は、 現場から離れているもどかしさとそれゆえの一種の罪悪感や現場のじゃまをあまりしないようにという思い、 頑張ってほしいという祈りの気分などが交錯した。
現場の個々の事業については、 その時々の判断で今努力されているわけだから、 「べき」論を振りかざすことは控えたい。
本稿では、 現場から少し離れた話になるかもしれないが、 今回の災害を契機として全国的に言われている災害に強いまちづくりについての議論について、 個人的な考えを述べさせていただきたいと思う。
今回の災害は、 従来より言われていることのほかに、 ライフラインや長期の避難生活など災害に強いまちづくりについて新しい課題を提示したが、 議論の内容は、 やはり、 災害があっても大きな被害が起きない強いまちにする、 復興のまちづくりをするというハード面が中心になっている。
勿論、 これが第一であるが、 同時に、 仮に被災した場合に、 復興のまちづくりをうまく行うためにも、 どのようなソフトなしくみを持つかについても目を向ける必要があると思う。
被災したところは、 もともとまちづくりにおいて課題を抱えるところもあった。
私が仕事をさせていただいた宝塚市の場合でも、 もともと再開発の計画があり地元とも話をしていたところが被災した例がある。
事業が行われていればという悔いは残るが、 このような地区においては、 行政も、 地元住民も、 復興に早期始動しやすかったように思う。
逆に、 十分な計画をあらかじめ持っていない場合は、 緊急時において早期の立ち上げをするのはなかなかむずかしい。
まず、 復興にあたっては、 どのようなまちにするかビジョンが重要である。
その地区の課題、 基本的な方向について、 被災前に行政も住民も以前にきちんと議論したことがあれば、 被災によって前提条件が変わるにしろ、 走り出しやすい。
問題点の把握にあたっては、 コミュニティや福祉政策など総合的な視点もあることが望ましい。
できれば地域事情をよくわかるコンサルタントなどまちづくり専門家が地元にかかわっていればなおいい。
まちづくりのビジョンは、 現在都市計画のマスタープランなどが市民参加を得ながらつくられつつある。
しかし、 住民がまちづくりを自分たちの問題として考えられるか、 行政もそれをきちんと受け止められるかというと、 まだまだこれからの感がある。
神戸市では、 条例に基づきアドバイザーの派遣やまちづくり協議会への助成を行ってきており、 今回もこの仕組みが大いに活用されることになっている。
また、 他の市などでもアドバイザー派遣などの予定があると聞いている。
このような仕組みは、 緊急時のみに有効であろうか。
むしろ、 本来は、 日常時から行われてこそ、 より有効ではないかと思う。
非常にむずかしいことではあるが、 日頃から総合的に住民と行政が地域について語り、 問題点を共有化する、 まちづくりの専門家とつきあうということが重要である。
災害があってから始めるのは、 信頼関係の構築などにかかる時間を思うと大変である(今回そのハンデを乗り越えて行われている地区は大変な努力だと思う)。
災害に強いまちづくりという特別なまちづくりがあるのではない。
すべてのまちづくりが災害に強い必要があり、 今後、 さまざまな地区において、 ハード面のみならず、 ソフト面での協働作業としてのまちづくりが展開されるためのしくみがつくられることを大いに望みたい。
なお、 行政では助成する団体への公平性の確保やある程度の成果を求めるところがあり、 一定の限度がある場合もあるので、 初動期においてはより柔軟な対応が可能なまちづくりファンドなどのしくみの構築も求められる。
以上のことは、 「きんもくせい」にかかわられる方々には当たり前のことであり、 何を今さらと言われそうであるが、 こういう準備活動は地道で災害に強いまちづくりという中では、 なかなか取り上げられないので、 むしろ他の地域の方々へという観点から、 あえて述べさせていただいた。
建設省においても、 市民参加のまちづくりに対する支援やそのための情報提供等の場の確保や、 仕組みづくり(例えばまちづくり情報センター)の検討を行う地方公共団体を様々な形で支援している。
今後さらに充実する方向での検討も必要と考えているが、 とりあえず、 現在実施されている内容の一端を紹介することにしたい。
なお、 この事業は、 今回の被災地においても活用されている。
阪神地域の復興と今後のより魅力的なまちづくりに向けてこのような事業が一助になればと願いつつ。
- 街並み・まちづくり総合支援事業
(街並み・まちづくり特定事業調査)
―まちづくりアドバイザーの派遣等市民参加のまちづくり活動への助成、 まちづくり情報センター等市民参加のまちづくりのしくみの検討調査
(街並み・まちづくり支援施設整備事業)
―高度情報センター整備費を活用し、 まちづくり情報センターの整備費に対して補助
- まちなみデザイン推進事業
―地区内権利者等からなる協議会組織による良好なまちなみ形成の推進方策等の検討への助成
(*問い合わせ先/建設省都市局まちづくり事業推進室、 住宅局市街地建築課)
p2
「神戸・復興住宅メッセ」誕生
「神戸・住宅復興メッセ」は、 「神戸市震災復興住宅緊急整備3ヶ年計画」にて市をあげて阪神大震災で失われた住宅ストックの再生に取り組んでいる中で、 主に民間住宅の復興促進の誘導を担う。
建設省・公庫の後援を受け、 神戸市の住宅施策の一環として各種公的住宅団体から紹介を受けた民間住宅建設主体の協力を得て開催する。
具体的には、 住宅メーカー、 コンサルタント、 デベロッパー、 地元工務店、 総合建設会社が参加し、 住宅再建の諸条件を整備し、 戸建のすみやかな復興、 共同化の推進、 狭小宅地の協調建替の公的支援など、 すみやかな住宅復興体制をつくる。
施設内容について
◎テーマ
「耐震、 耐火等の防災すまいづくりと協調建替」
◎活動内容
戸建・連棟型3層テラスハウスに関する建築条件の整理を行い、 住宅建築の総合的な条件整理と建築方針の設定を行う。
住宅を再建しようとする市民は、 耐震・耐火の情報や建設条件・コストを明確に把握し、 具体的な施行会社選択することができる。
また、 等価交換方式による集合住宅の新規建設についての誘導・促進として、 土地活用、 融資条件、 プランニング等のコンサルティング、 及び建設方法について具体的な相談を行う。
特に、 住宅復興が難航し、 純然たる民間ベースでは成立しない狭小敷地地区では、 地元のまちづくり活動を公的に支援しながら協調建替の相談に応じるほか、 街区提案も行う。
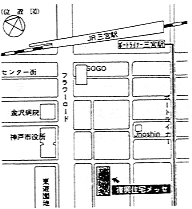
神戸・復興住宅メッセ位置図

6/22オープン時
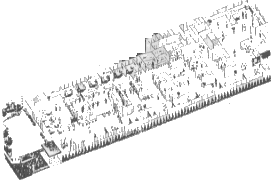
メッセ会場
開催期間/平成7年6月〜10年4月(約3年間)
主 催/神戸市住宅供給公社
後 援/建設省、 住宅金融公庫大阪支店、 神戸市
協 力/(社)プレハブ建築協会、 (社)日本ツーバイフォー建築協会、 (社)日本木造住宅産業協会、 (社)日本高層住宅協会、 (社)不動産協会、 (社)兵庫県建設業協会、 兵庫県木材協同組合連合会、 (社)日本ツーバイフォー建築協会兵庫支部、 神戸市建築協力会
協賛企業/住宅メーカー、 コンサルタント、 デベロッパー、 地元工務店、 総合建設会社等多数(企業名省略)

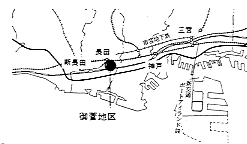
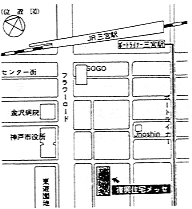

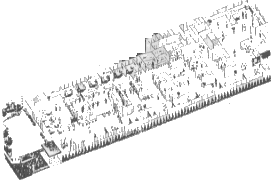

 「きんもくせい」第10号でお知らせいたしました花の芽は、 一雨ごとにすくすく育って大きくなってまいりました。
「きんもくせい」第10号でお知らせいたしました花の芽は、 一雨ごとにすくすく育って大きくなってまいりました。
