
子供達も参加して行われた種まき
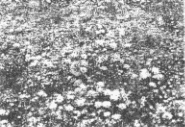
花いっぱいで被災地にうるおいを!
すっかり撤去された夕焼けの跡地にポツンと立たれ、 愛しいわが家を懐かしむような後ろ姿を何人見かけたことでしょう。
すっかり空地になってしまった我が社のまわりも植木や鉢植の花がひとまとめにして残されていたり、 ここで無残にも亡くなられたであろう人を想い供えられた花束が枯れかけているのを見ると、 無念さが胸に迫ります。
『ガレキに花を咲かせましょう』の始まりは、 瓦礫から家々の建設への過程の第一歩として、 夏から秋に向けて荒地を花畑にしよう、 暑くてほこりっぽい日々に備えて
第1段階 「ガレキに花を」 がれきの花畑化
第2段階 「家に苗木を」 敷地周辺の苗木(記念樹)植栽
第3段階 「まちに生垣を」 建物の生垣・庭づくり
第4段階 「都市に広場を」 まちの緑いっぱい花いっぱい
という「阪神市街地緑花再生プロジェクト1」です。
一日目はネットワークの面々が約400m2をプロの指導のもとに耕し、 みんなでまきました。
二日目は地元住民50人の手で区画整理区域を線引きにし、 空から見たらどうなるかと2箇月後に思いを馳せています。
こうして、 一週間西から東へと7ケ所まきました。
芽が出て蕾がつき、 花が咲くのを、 そこに住んでおられた方々が時々訪ねてくださるようになればと願っています。
そしてお家を建てられるようになったら『思いでの木』を植えましょうとお誘いし、 家々のまわりは好きな木々で整え、 表は生垣で、 やがて“緑”がつながり、 並木になってグリーンラインが公園や防災拠点へと人々を導く役目を果たしてくれればと思います。
六日目のきょう、 芽がでたのを見つけました。
今後の生育は「きんもくせい」でお知らせします、 楽しみにしていてください。
“花咲かじいさん”、 “花咲かばあさん”より

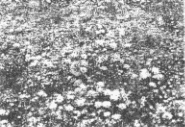
花いっぱいで被災地にうるおいを!
野田北部まちづくり協議会(会長・浅山三郎氏)は、 震災までの2年間に大国公園の整備、 同公園を挟む南北コミュニティ道路整備などを経験してきている。
震災前の地区内世帯数は約1,200世帯(約3,400人)で、 この震災により倒壊・焼失等で現在地区内に居住できていない世帯数は、 約900世帯(5月末現在)にのぼっている。
私は神戸市の依頼にもとづき、 住宅・都市整備公団が窓口となった「新長田駅周辺地区復興計画」の策定チームに1月末より参画する機会があり、 なかでも、 野田北部地区の一部が含まれる鷹取東地区・区画整理事業エリアの素案策定を、 地元出身の建築家で私の20数年来の友人である森崎輝行氏と協働でまとめるという“縁"があった。
森崎氏は、 その後も地元のまちづくりアドバイザーとして、 地元の人々に建築・都市計画的情報をレクチャーしつつ、 地元意向を汲みとり、 改めて、 地元発意の区画整理案等の策定に奮闘している。
私は前述の“縁"の続きで、 氏と併走するかたちで、 復興対策本部主催の復興対策会議に参画している。
同本部は、 地震後3日目には看板があげられ、 復興対策会議は月3〜4回のペースで5月末までに12回開催されている。
また、 個別の議題に関する勉強会・ヒアリング等も間断なく開催されている。
主な内容としては、 震災後の現況模型による状況把握、 計画決定された区画整理事業案の模型による検討(ちなみにこれら模型作成には、 筑波大、 東経大、 早大、 東大の学生ヴォランティアが参画)、 共同再建イメージの検討などが積み重ねられている。
また、 現在区画整理事業に含まれている海運町2、 3丁目(約2.3ha)については、 具体案について大づめの段階にまで成果が実りつつある。
そこでの減歩率の目標は10%未満を目指しており、 案検討と並行して住民から共同再建、 土地売却などの意向をきめ細かく把握するよう努められている。
「市は今後、 地元協議会を進めて、 8月にも事業計画決定したいとしている」状況である。
また、 「街なみ誘導型地区計画」も導入する方向でその検討も進めつつある。
一体的なまちづくりを目指すという考えから、 区画整理事業区域外の野田北部地区住民に対しても、 地区計画等によるまちづくりの重要性を訴えかけている。
また、 野田北部に隣接する地区についても、 同様の主旨より、 状況を見つつ声がかけられている。
以上がおおよその活動状況である。
最後に、 野田北部地区のまとまりの良さ、 復興に向けての復元力の強さについて、 伴走させてもらっている者として感じることを2〜3述べる。
まず、 まちづくりに対する熱心な住民リーダーの存在と、 リーダーを信頼してまちづくり活動を行える若手・中堅メンバーの存在、 さらにそれらの人々の活動を支える集会所の存在、 (今までの蓄積に裏付けられたまちづくりコミュニティの存在)。
復興対策会議等における問題意識、 議題の組み立て方として大上段に構えた都市計画の説明の仕方ではなく、 あくまで“個人の利害、 納得”に訴えかける徹底した姿勢。
さらに、 各方面からのヴォランティアの受け入れ、 行政担当者との接触をはじめとして、 まちづくりに良い意味で生かせるあらゆる契機を取り込み得る姿勢(ポジティブ・シンキング)などをあげることができる。
そして、 大都市非戦災地における曲がりくねった細街路を持つ既成市街地が、 その住環境整備に悪戦苦闘している情況と照らし合わせてみるに、 野田北部地区の震災前道路パターンが、 すでにきれいなグリッド・パターンであったことが(ただし幅員は狭い)、 区画整理の議論を判りやすく、 明快なものにし、 復元力を強めていることを明記せざるを得ない。
このパターンは、 歴史的には、 神戸市ではじめて行われた耕地整理事業に端を発し、 戦災復興土地区画整理事業を経て今日に至っている。
この地区の先輩が遺してくれた「復元力」に見合うような、 いかなる新たな復元力をこの地区は未来に向けて創造することができるか。
先はまだながい。
しかし光は徐々に確かなものとして見えつつある。
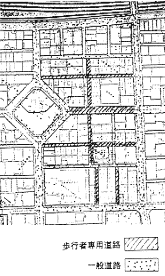
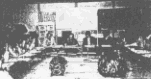
第11回野田北部まちづくり協議会
そして、 平成5年に市に対して「まちづくり提案」を行っている。
この提案は、 (1)街区ごとに将来方向を定め住宅と工場・商業の共存を図る、 (2)快適で円滑な道路環境をつくりだす、 (3)生活に必要な施設を整備する、 (4)福祉や教育問題にみんなで取り組む、 (5)住宅を改善し定住を促す、 の5項目をまちづくりの方針として掲げたものであったが、 道路等の施設整備や住宅更新など、 具体的な計画については、 逐次話し合いを進めるなかで決めていこうとするものであった。
阪神大震災から1ヵ月を経た2月18日、 地区内に残っていた役員が集まり、 かねてから地区の大きな課題となっていた東部(梅ヶ香ブロック)の道路整備について、 地区住民等に対し緊急に提案することとなった(下図参照)。
2月23日梅ヶ香ブロックの住民集会が約60名の参加者を得て開かれたが、 この中で、 道路拡幅はともかく今日寝る場所をどう考えるのか、 新たに住宅を建てる場合道路中心から2m後退していたのでは建たない、 住宅の共同化というが何のことかわからない、 などという意見が続出した。
そこで、 道路拡幅について提案するニュースを全戸配布する一方で、 住宅共同化のスタディ、 4日間にわたる建築個別相談会、 あるいは山口県豊浦町まちづくり建築協議会の支援による住宅等応急修繕の斡旋を実施し、 将来のまちづくりを検討する一方で、 被災地区住民の緊急的要望にも対応する活動を実践してきた。
震災後、 4ヵ月近くの活動の中で常に意見が対立し、 また共通の悩みとなったのは、 まちづくりの視点から地区共有の環境向上を優先させるのか、 あるいは当面の生活基盤の確保や個人の権利を優先させるのか、 といった点である。
これまで、 尻池北部地区の活動においては、 (1)最低限度の生活の確保、 (2)建築基準法を守った建設活動の推進、 (3)道路整備や住宅の共同化等居住環境の向上、 の順でとりあえずの優先順位をつけてきた。
そして、 そろそろを(3)を具体的に促進すべき段階にはいりつつあり、 機運のもりあがりが期待されているブロックにおいて、 住宅共同化のための勉強・検討会をまず有志が集まって聞こうとしている。
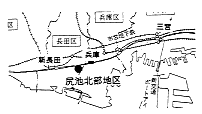
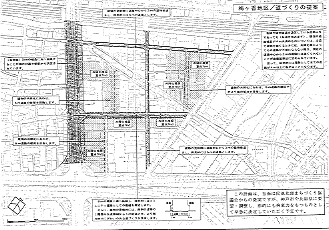
梅ヶ香地区/道作りの提案
(クリックすると大きな画像で見られます。80K)
センターは、 震災復興まちづくりという現場でなければできない分野を研究テーマとしており、 被災地の中にあり、 プランナーや研究者が集まりやすい場所ということで、 当事務局の隣にコンテナハウスを設置して開設することになった。
差し当たり推進する活動は以下の3点である。
情報のギブアンドテイクでセンターの運営を図る方針である。


センター内での会議風景(5/27)
神戸市長田区・真野地区では約30年間の住民主体のまちづくり運動の蓄積が、 今回の震災でいかんなく発揮されている。
本書では、 震災後の住民やこれを支援する東京などの後方部隊の活動が具体的に掲載されており、 こういったとりくみが、 他の多くの被災地で展開していくことが期待されている(自治体研究社発行、 1,400円)。
本書は、 震災後被災地各地で発行されたまちづくりニュース等をそのままのかたちで合本収録したもので、 復興まちづくりの実践や課題、 ノウハウ等を交流することで、 今後の復興まちづくりに役立てることををねらいとしています。
一人でも多くの方に本書を活用していただければと思っています。
また、 今後vol.2を発行する予定ですので、 各地で発行されているまちづくり通信や、 本書についてのご意見等を事務局までお寄せください。
A4・1枚分でなくてもかまいません。
簡単なまちづくりの途中経過等でもいいですから、 どんどん事務局までアクセスしてください。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
P.4
ネットワーク事務局より
『復興市民まちづくりvol.1』発刊
当ネットワーク事務局編集による『復興市民まちづくりvol.1』(学芸出版社、 1,85 4円)が刊行されました。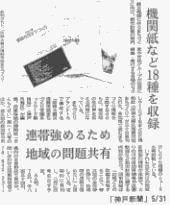
「神戸新聞」5.31より「きんもくせい」への投稿お願いします。
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1029 FAX.078-803-1029
担当:児玉
 きんもくせい11号へ
きんもくせい11号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ