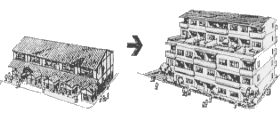
アパート・文化住宅・賃貸マンションの共同再建のイメージ
同潤会は、 その後、 年に千戸のペースで当時としては力強い住宅建設を展開します。
この時日本に最初に集合住宅、 マンションが登場したことになります。
さて、 阪神大震災の後、 「土地区画整理」や「大量住宅建設」といった施策が打ち出されているものの、 まちをどう立て直すのか、 その場合の新しい方法は、 という点では、 70年前のような「発見」はまだ見られません。
大震災から4ヶ月をすぎて不安と困難が交錯するなか、 復興にむけて希望を見出そうとするものの、 市民にとってもっとも切実で身近な生活環境の再建が実際どのようにすすむのかわからないまま、 立ち往生したり、 ひとりで行動するしかないというような場面が被災地の大半のところにみられます。
一方ではいろんな町で市民が復興にたちあがり、 「まちづくり協議会」方式による市民主導の復興へのとりくみが力強く芽をふき始めました。
大きな「都市計画」と同時に大切なのは、 市民がばらばらに建物を再建するのではなく、 そこに住む人が結束して小さな「共同事業」をつみかさね、 まちぐるみ復興していくことではないでしょうか。
私たちは今一番求められている共同再建をすすめるためには、 住民が話し合いの場をもつこと、 専門家が共同でやろうとする人たちに助言し、 事業計画づくりを手伝うことが必要だと考えます。
そこで、 神戸、 大阪、 阪神間でこれまでまちづくり・建築活動にとりくんできた仲間、 コーポラティブ住宅づくりを進めてきた仲間30人ほどが手を組んで、 まちづくりとしての復興を実際に支援できるチームをつくりました。
4月29日には神戸市内で、 地域のまちづくり団体とも連携する「パートナーシップ型共同再建をすすめる集い」を開き、 市民・地域と専門家、 行政がネットワークをつくっていくこと、 地域ごとでとりくまれつつある復興まちづくりの動きが交流し、 連携しあうことが呼びかけられました。
私たちは、 この考え方にもとづいて、 これから行動していこうとしています。
そのために神戸・三宮に事務所を開設しました(神戸市中央区御幸通6-1-20三宮山田東急ビル2階 TEL・FAX.078-261-1770)。
被災地の多くは狭い道路に面して小さな敷地に老朽家屋が密集していたところであり、 1)店舗付住宅数戸程度の共同再建 2)長屋の共同再建 3)アパート・文化住宅、 賃貸マンション等の再建 4)街区単位の共同再建 5)協調建替え など、 きめ細かく、 かつスピーディに進めるのが、 復興のもっとも重要な事業となると考えています。
それを実行するために、 私たちは、 まずわかりやすいパンフレットをつくって、 多くの人に呼びかけること、 常時相談窓口を設けることからスタートさせ、 隣近所で共同再建を考えようという動きがあれば、 出向いて、 進め方の説明をし、 相談にのっています。
また、 実際にするかどうかの目途づけのために、 概略の事業計画をつくり、 助言できる体制をとっています。
どなたでも、 どんな組織でも大いに、 この「チーム」をうまく活用していただければ、 と待っています。
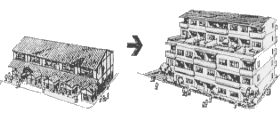
近年では、 ブティックやレストランなどが進出するとともに、 年間150万人を超える観光客が訪れるなど、 かつての住宅地が様々な表情をもつまちに変貌してきている。
神戸市でも、 この地区の歴史的特性を保全・育成するために、 昭和54年、 約32haの区域を「都市景観形成地域」に、 さらにその中で異人館などの伝統的建造物が集中する約9.3haの範囲を「伝統的建造物群保存地区」に指定し、 翌55年には重要伝統的建造物群保存地区として国の選定を受けている。
これは関係する6自治会と2婦人会および商業者組織を構成団体として発足したもので、 同年、 神戸市都市景観条例に基づく景観形成市民団体の第1号として認定され、 以後、 神戸市とも連携を保ちながら悪いところをなくし、 良いところを伸ばすという点からの実践活動を広範に展開してきた。
そして昨年からは、 身近な歴史を掘り起こし、 記録する「まちの記憶を引き継ぐ運動」にも取り組んでいる。
この中で、 伝建による指定建物(異人館28棟、 和風住宅4棟)については、 助成率9割という行政による手厚い支援策が約束された。
しかしこの対象は、 原則として外観に係る部分についてのみであり、 全体で80棟ともいわれる異人館のうち指定外のものや、 指定建物であっても内装、 あるいは公開異人館の展示品等については自力での復元が求められている。
そして、 訪れる観光客が激減したこともあって、 震災前は24棟を数えた公開異人館のなかで、 ゴールデンウィーク中に再開できたものは9館にすぎず、 多くは再開のめどさえたっていない。
このような状況が長引けば、 閉館する民間の公開異人館が続出することが予想され、 やがては当地区を個性づけ、 魅力づけてきた異人館そのものが、 姿を消すという事態も危具される。
これまで、 「まもり、 そだてる会」では、 当地区の落ち着いたまちなみをまもり、 育てるという主旨から、 過度の観光地化に疑問を呈し、 ゴミ、 トイレ、 不法駐車に代表してされるいわゆる観光公害の低減に取り組んできた。
ただ、 営利目的の民間施設であれ、 公開施設として活用されてきたことがこれらの異人館の保存につながってきたという面も見逃せない。
このような状況の中で、 「まもり、 そだてる会」では次のような事業に取り組むことを緊急に決議した。
しかし、 一日も早く実行に移さなければ、 まちが崩壊するという危機意識からの出発である。
皆様方にも、 異人館基金設立のための支援をお願いします。
支援金のお払込みは、 郵便振替で、 01160-1-60707/北野・山本地区をまもり、 そだてる会 までお願いします。
100万ドルと賞せられたその夜景も一時は、 真暗闇となったが、 現在は50万ドルぐらいまで持ちなおしてきたところか。
1月17日約100万軒のお客さまが大地震に伴い停電。
関西電力では、 保安上や公的機関、 病院など社会的影響を考え、 一刻も早く電気を回復しなければとの使命感のもとに、 6日後の1月23日昼ごろ、 復旧することができた。
某電機メーカーのコマーシャルであるが、 ホテルの窓を利用して壁面に照明で「ファイト」という文字が浮かび上がった時、 神戸復活のシンボルを見るようにホッとしたのは私一人であったろうか。
同時に、 町の明かり・希望のひかりを灯す仕事をしてきてつくづく良かったと思うのは、 すべての電力マン共通の思いであった。
関西電力では、 現在主にまちの復興や仮設住宅等への送電作業に携わると同時に、 電力設備も多大の被害を受けており順次本格復旧作業を行っているところである。
復旧にあたっての、 電力設備をはじめとしたライフラインの信頼性については、 次の二面から評価する必要があると考えている。
一つは、 地震の際にライフラインの「機能を維持すること」と、 もう一つは、 地震時にいったん機能を失っても、 「早期に復旧すること」である。
とくに電力設備は、 ライフラインのベースとしての役割から、 幹線である送電設備は耐震性を高め機能を維持すべきであり、 お客様と直結する配電設備は、 早期復旧を優先して考える必要がある。
以上のような考えのもと、 「災害に強いまちづくり」へ向け、 電力設備の整備を図っているところである。
さて、 震災後100日が経ち、 各地域で震災復興のガイドラインがつくられ、 いろんな規模の復興、 街づくり事業が進められようとしている。
関西電力でも、 街づくりへ何かお手伝いできないか、 提案させていただいているところである。
街づくりの視点は、 災害に強い、 豊かな魅力ある住環境の整備、 創出である。
防災性の向上、 高齢化社会到来等を考えれば効率的な電気の高度利用も、 街づくりを達成する一つの方法として考えられるのではないだろうか。
災害に強い安全で安心な街づくり。
そのために施設等を整備していく必要は十分認識されていると思うが、 これが実際に役立てられるのは、 当然ながら災害時のみである。
この非常用の施設が日常にも用いられて初めて、 街づくりのメニューになりうると思う。
そういう意味で、 ビルや地域の空調用蓄熱槽の防火用水への利用や、 家庭の電化等を考えていったらどうだろう。
今後、 個性的で集客性をもった魅力ある街づくりに電気が役立てればと思っている。
今回は、 魚崎出身の住田昌二氏(大阪市大教授)を迎え魚崎復興の提言、 阪大の加藤晃規氏を講師に魚崎地区のまちづくり課題についての学習会等を行った。
参加者からは、 建替時の諸問題(相続問題等)、 住民への活動の広報などの意見が出された。
第3回は6月4日(日)13:00〜同上場所で開催の予定
―阪神高速道路の復旧見合わせなどを提唱した背景や道路交通政策のあり方等について論議する
日時:5月23日(火)17:30〜20:30
p3
震災前は三宮の設計事務所に勤務していたが、 地元の救援、 復旧活動のため約1カ月間休暇をとりボランティアを行っていた。
一応の区切りがついたので職場に戻ったが、 地元復興への思いが熱く、 倒壊した自宅跡地へ事務所を開設することにした。
竹内さんは、 まず地元の組織づくりにとりかかった。
お隣の野田北部地区でアドバイザーをしている森崎さんの協力も得ながら、 地元住民に声をかけ回り、 4月12日「長田区腕塚10丁目まちづくり推進協議会」の設立にこぎつけ、 事務局長を行うことになった。
事務所の建物は、 神戸市が外国からいただいた義援物資であるコンパネを使い、 自ら大工の経験を生かし約3週間で完成した。
また、 この場所は協議会の活動拠点ともなっている。
腕塚町10丁目地区は、 今回の震災で約8割の家屋が全・半壊し、 現在でも震災前の約1/3の人しか住んでいない。
今後の活動は、 散らばっている住民のまちづくり意向の把握、 自宅をも含めた周辺等の共同化事業の推進などである。
当地区は、 重点復興地域に含まれないエリアで(神戸市内の被災地の約80%の面積を占める)、 こういった地域ぐるみの復興まちづくりの活動は、 多くの被災地復興のモデルケースである。
被災地ではまちづくりプランナー、 建築家等の専門家が足りない状況にあり、 一人でも多くの専門家が竹内さんのような活動を展開していくことが早急に求められている。
何分急を要することなので、 事務局が現時点で入手できたものを収録しています。
この資料が今後の復興市民まちづくりに何らかの手助けになればと思っています。
今後Vol.2,3……と出す予定です。
当事務局へのニュースの送信よろしくお願いします。
〈収録ニュース〉
P.4
「北野・山本地区をまもり、 そだてる会」の活動
このような状況のなかで、 昭和56年、 急増する観光客への対策と地区景観の保全・育成を目的に、 「北野・山本地区をまもり、 そだてる会」が結成された。異人館をまもるための震災後の取り組み
阪神大震災では、 旧居留地や酒蔵地区など市内の他の歴史的地区に比較するといくぶん軽微な罹災に留まったものの、 異人館だけをみても数棟が半壊し、 どの館も煙突が落ちたり壁が壊れるなど、 大なり小なり被害を受けている。
―異人館基金の創設―
これらの実現には、 資金集めや組織の再構成・強化など、 解決すべき課題は山積している。
「まちの記憶を引き継ぐ運動」を一層広範に展開し、 その資料の展示・保管施設として活用する。

「風見鶏の館」(旧トーマス邸)明治42年建造、 国指定重要文化財
街づくりにかける電力マンの思い
関西電力(株)神戸支店復興支援センター 澤崎 雄介
久しぶりに神戸の夜景を見た。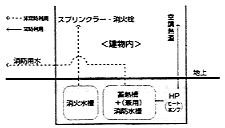
蓄熱槽の消防水槽としての活用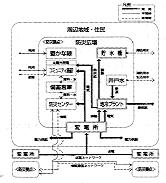
アーバンインフラ機能を保有する防災拠点整備の概念図
(クリックすると大きな図が見られます。32Kバイト)
INFORMATION
第2回魚崎地区シンポジウム開催
連休中の5月3日、 前回と同様魚崎小学校グランドに設置された大テントにおいて、 2回目のシンポジウムが開かれた。
魚崎地区シンポ・5/3ひょうご創生研究会パネルディスカッション・5/23開催
テーマ:まちの復興に生かそう道路づくり
場所:兵庫県私学会館(JR元町駅東口より北へ徒歩2分)TEL.078-331-6623
主催:ひょうご創生研究会、 神戸新聞社
地元の復興に向け建築士奮闘!―長田区/腕塚町10丁目地区
長田区腕塚町10丁目の1級建築士、 竹内市郎さん(38)は、 震災により自宅が倒壊した。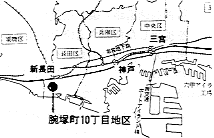
腕塚町10丁目地区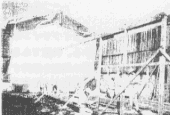
事務所の建設風景.竹内さん自身が大工の経験を生かし組み立てた(4/27)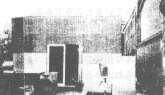
完成した事務所(5/7.内装は未).壁のコンパネは海外からの義援物資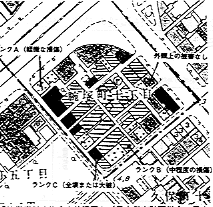
「被災度別建物分布状況図」(日本都市計画学会・日本建築学会)より作成ネットワーク事務局より
「阪神大震災復興市民まちづくりVol.1」が発刊されます(5/30)
「きんもくせい」第7号で少しふれましたが、 各地で発行されている復興まちづくりニュースを、 学芸出版のご厚意により合本出版することになりました。
・「きんもくせい」12 ・「AAN NEWS」08・「味泥復興計画」12 ・「大道周辺地区復興まちづくり新聞」18 ・「Weekly Needs」22 ・「西須磨住民だより」15 ・「六甲道駅南地区まちづくりニュース」(同) ・「新長田駅南地区まちづくりニュース」(同) ・「震災復興土地区画整理事業によるまちづくり」(同) ・「ほくだん地震災害広報」(北淡町)
申込先:学芸出版社 TEL.075-343-0811 FAX.075-343-0810
大都市大手書店にて5/30発売しますネットワーク会議について
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
5月10日(水) 場所:こうべまちづくりセンター
―各地域での取り組み状況と今後の展開に関する情報交流
5月16日(火) 場所:こうべまちづくりセンター
―地元対応型復興まちづくりの取組み動向等
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1029 FAX.078-803-1029
担当:児玉
 きんもくせい10号へ
きんもくせい10号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ