
約80%のケミカルシューズ工場が壊滅した長田区
(2/8撮影)
今回の震災において工場半壊など大きな痛手を負ったあるメーカーの社長は、 自らの復旧体験を振り返りながら今回の震災を契機とした神戸ケミカルシューズ産業全体の変化とその方向についてこのように述べ、 さらに「業界としての速やかな対応と的確な施策提案が必要」と強く指摘されたことは印象的であった。
震災によって、 神戸を代表する都市型地場産業「ケミカルシューズ」は、 長田・須磨地区関連企業約1,600社の内、 全・半壊と焼失を合わせると全体の80%という壊滅的な状況となった。
しかし、 震災後2カ月半が経過した4月初頭において既に約7割が業務を再開したといわれ、 その再興への意欲はきわめて大きく、 動きもはやい。
実際、 神戸市経済局によればケミカルシューズ関連仮設賃貸工場の応募状況は、 3月5日締め切りの第1次募集36戸(中小企業全体で52戸)にたいし、 13.3倍という高倍率となった。
また、 同31日に締め切られた第2次募集では、 ケミカルシューズ関連30戸に限定すれば、 競争率1.1倍という結果であった。
これは、 第1次募集が長田区内に設置された仮設工場であったのにたいし、 第2次がこうした企業集積地域から距離を置いた西区の西神工業団地内であったことも関連していると思われる。
いずれにしても、 金融面、 生産施設・設備など、 再建を模索する事業者に緊急支援することは、 震災後2カ月半を経た現在なお最重要課題であることは強調しておきたい。
こうした「町工場」が厳しい問題に直面しながらも、 意欲的に次々に再建されていく姿は神戸経済の今後を展望するうえで大変勇気づけられるところである。
ところで、 こうした緊急・短期的支援を充実すると同時に、 大都市インナーシティに立地する中小零細企業集積の再生方向ないし中・長期的視点からのビジョンを描いておくことも必要である。
産地として存亡に関わるとも思われる中国など発展途上国製品による追い上げに象徴される経済環境変化は、 震災前以前から顕在化しつつあったここ数週間の円高傾向はこうした問題をより先鋭化させている。
業界や企業に大胆な「変化」が求められており、 冒頭に紹介した企業家の言葉はこの問題への指摘に他ならない。
もちろん、 合成皮革を素材とする安価な女性用サンダルから、 皮革を用いた高級靴へという「革新」への努力がこの業界をこれまで支えてきたことを見逃してはならない。
実際、 神戸ケミカルシューズ産業の将来展望については、 これまでにも幾度か検討が行われてきたところであり震災を契機とする展開についても多方面から議論が行われつつある。
今後、 業界を核としたビジョン作成が待たれるところである(4月5日記)。

激しく被害を受けた。
最近になって解体作業が進みはじめ、 あちこちに“野原”が出現している。
一方では、 復興に向けた明るい足音が聞こえる。
散髪屋、 牛乳屋、 印刷屋などが仮設店舗を建て、 営業を再開した。
ガッツを感じる。
六甲道に電車がきたときは本当に嬉しく思った。
他方では、 深まっていく辛さがみえる。
小学校ではまだまだ多数の家族が避難生活をおくっている。
先日、 その教室を借りて住宅相談会を行った。
「一銭もないし身寄りもない」というお年寄り。
老眼のために私たちが作った資料も読めない。
口頭で避難所脱出の方法をいろいろと説明したが、 うまくいったかどうか自信はない。
ガスがいまだに復旧していない街区もある。
住宅復興に向けてゴソゴソと動きだしたグループがある。
第1は、 “フォーマル・グループ”としての自治会。
12の自治会が集まる連合自治会は復興委員会を結成し、 4月中旬から本格的に始動する。
事務所を設け、 生活相談窓口の常設、 住民所在地の系統的把握などを行う。
高齢の自治会長はほとんどが被災して地区外に出ているので、 地元に残っている若手を中心にした委員人選が進んでいる。
この復興委では、 住宅再建にも取り組んでいく予定。
第2は、 “ボランタリー・グループ”。
地区外からとつぜん現れた“ホット”なおじさんがボランティアを集めて地元復興協力会をつくり、 解体、 補修を自力で手がけている。
メチャクチャやっているようにも見えたが、 実績があがるにつれて、 信用を獲得しはじめている。
また、 自治会とは別に、 自主的に住宅再建の話し合いをはじめたグループがある。
民間施行の再開発を経験したおじさんが中心人物なので、 プロっぽい話しが通じる。
権利者へのアンケート、 街区別話し合い、 勉強会などが活動の中心。
第3に、 筆者らの“プランナー・グループ”は地元と相談しながら、 基礎調査、 復興委への助言、 街区計画と模型作成、 話し合い・勉強会の運営と資料作成、 権利者アンケートの設計・集計などを行っている。
この地区は住市総の重点復興地域に含まれた。
しかし、 区画整理、 再開発のエリアとは異なり、 原則は民間自力復興である。
できることは自分たちでやり、 必要な支援を地区の側から取りにいくようなスタイルが必要になるだろう。
上記の3つのグループがどこまで動けるかが復興のあり方を左右するだろう。
課題は多い。
(1)当地区自治会はしっかりしていたとはいえ、 まちづくりの経験はない。
だから“まちづくり提案”のような計画指針が存在しない。
住民の大半が合意できるような計画をすぐに作れるわけはなく、 勝手に絵を書くのもどうかと思う。
現在は街区単位の復興プランに精力をつぎ込んでいるが、 全体計画があればやり易いのにと感じる。
まちづくりをやってきた地区では、 その成果が今こそモノをいうはずである。
(2)民間自力復興の中心は協調・共同建て替えを基調とした街区再生である。
しかし、 協調建て替えといってもインセンティブは乏しく、 住民に説明するときに骨がおれる。
未接道・狭小宅地が大量にあり、 これはどうしたらよいのか。
インナー長屋制度を使うには地区計画が必要であり、 それをやっているヒマがあるかどうか。
共同建て替えは一般的に難しい。
容積などからみて、 いけそうな場所が数カ所あるが、 実際はややこしいだろう。
優建がもっと使い易くならないか。
権利関係はもともと複雑なうえに罹災都市法の絡みもあってマスマスややこしい。
(3)神戸市が企画している住宅相談・情報センターとしての復興メッセに期待している。
これを区単位、 できれば小学校区単位に設置してくれないだろうか。
何でもすぐに相談できる場所が近くにほしい。
住民がもう少しまとまってきたら、 街区単位に事業コサンルタントを派遣してほしい。
(4)地区の中にいろいろな動きがある。
気になるのは土地の流動化。
震災前の6ガケ価格で土地のタタキ買いがはじまった。
道路沿いはアブナイ筋の人が目を付けている。
沿道を買収できれば未接道のアンコはタタキ買いしてボロ儲けだ。
住民がこれらの動きのスピードについていけるかどうか。
話し合いをするといっても、 住民の7割以上が地区外に散っていて、 集まるだけで苦労しているのが現状である。
ともあれ、 アスベストとNOxだらけの空気を吸いながらではあるが、 住宅復興のための地区住民の努力がはじまったことは確かである。
とても楽観する気分にはなれないが、 悲観もしないように気をつけながら、 できることをガンガンやっていくしかない。
(4月4日 記)

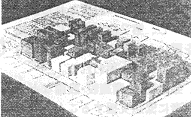
街区ボリュームスタディ模型(敷地単位)
現在は、 新しく長田区社会福祉協議会の中にできた『長田ボランティアセンター』(旧長田ボランティアルーム)の一翼を担う団体として、 避難所へのボランティアの派遣、 ガレキ撤去や引越しの手伝い、 高齢者やハンディキャッパーの病院等への送り迎えなどの活動をおこなうとともに、 ピースボートが毎日発行していた被災者向け情報紙『デイリー・ニーズ』を引き継いで、 週刊の『ウィークリー・ニーズ』(毎週日曜日発行、 4月9日で第5号)を発行しています。
2月17日にピースボート本部へボランティア登録に行ってから、 3月3日に地元住民4人による呼びかけで第1回会合を開いた『これからの長田を考える会』の発足に至る経緯は省きますが、 発足時の趣意は以下のようなものです。
「現在、 被災地では数多くのボランティアによって、 私たちの生活が支えられています。
長田区もその例外ではありません。
そのほとんどは関東などの阪神地域以外から駆けつけてくれているのです。
彼・彼女らは不眠不休でがんばってくれています。
しかし、 そのボランティアたちはまもなくそれぞれの地元へ帰っていきます。
その後は、 被災地の住民である私たち自身の手で、 私たちの生活を支えていかなければなりません。
彼・彼女らが築いたものを、 どう引き継いでいくのか。
今なら、 まだ、 考える時間があります。
彼・彼女らが帰ってからでは間に合いません。
これからの長田をどうするのか。
一緒に考えてみませんか。
長田区のみなさん。
どうか『これからの長田を考える会』に集まってください。
そして、 共に考え、 共に行動しようではありませんか。
」
長田ボランティアルームに集まったボランティアグループの数は20以上になり、 ピースボートだけで述べ600人近くにものぼったが、 今は、 避難所の常駐グループ(約7団体で60人ほど)を除くと、 ほとんどがそれぞれの地元へ帰っていきました。
ところが、 長田区の現状は3月のそれと大して変わっていないのです。
結果的には、 人数が減った分だけ仕事の量は増えていると言えます。
その人手をどこから、 どのように集めて来るかが当面の、 そして長期的にも大きな課題となっています。
「まちづくり」を考えるとき、 「まち」を構成する基本的で、 最も重要な単位である住民が、 いかに活性化していくのが最重要ポイントであることは言うまでもありません。
震災後3カ月が経とうとしていますが、 自立・復興に向けた地元の動きは始まっているとは言え、 まだまだ緩慢なのが現実ではないでしょうか。
震災のショックは想像以上に大きかったということなのでしょう。
『すたあと』の役割は、 「元気の出た」住民がまだ「元気の出ない」住民を少しでも手助けすることによって、 地域全体の活性化を図ることにあると考えています。
ハードがいくら良くても、 そこに住む人間が疲れていては、 何の意味もありません。
「震災に強いまちづくり」は、 「震災に強い建物づくり」ではなく、 「震災に強い社会づくり」でなくてはならないのです。
地元住民、 建築家など、 約250人が参加し、 会場内には、 巨大な1/500地区模型や、 震災後打ち出された各種プロジェクトのパネル・模型展示も行われた。
シンポジウム終了後、 会場では専門家を交え建替の相談会が行われた。
そのために以下のことがらを憲章としてかかげます。
既に4月10日に第1回が「建築・崩壊するものの理由」というテーマで西澤英和氏(京都大)、 中川理氏(京都工芸繊維大)の報告等により行われています。
ネットワーク事務局からも企画員として参加しています。
現時点におけるネットワークとしての参加内容は、 「ラウンドフォーラム」にまちづくりグループの代表としてのパネラーの参加、 「きんもくせい」のパネル展示等です。
また、 神戸市魚崎地区で活動している関西建築家ボランティアからは建築建替相談、 模型展示などを行う予定です。
また、 会場となる兵庫県公館は、 下記に示すような名建築であり、 訪れるだけでも価値があるものです。
戦災により外壁のみを残すだけとなりましたが、 約10年前に改修、 復元が行なわれ、 華麗な姿を今に伝えています。
今回の震災では、 門や塀が破損したものの建物自体は内部の補強等により無傷でした。
現在、 復興に取組んでいる多くの地域ではまちづくりニュースが発行されています。
これらは主に地元向けに発行されていますが、 復興まちづくりにとっては共通課題も多く、 異なる地域がお互いの経験を共有することは重要なことだと考えます。
事務局では、 「きんもくせい」の経験を生かし、 定期的に各地のまちづくりニュースを集約し発信する方法を検討して行きたいと思っています。
そのために、 まずまちづくりニュースを事務局まで送ってくださいますようお願いします(郵送で)。
P.4
魚崎地区まちづくりシンポジウム開かれる
4月9日(日)午後より魚崎地区災害対策本部と関西建築家ボランティア主催による魚崎地区まちづくりシンポジウムが開かれた。魚崎地区まちづくり憲章
1995年4月9日 魚崎地区まちづくり準備協議会
私たち魚崎地区(魚崎小学校区)住民は、 震災後のまちづくりについて地元企業や専門家集団と協働して、 震災前の住環境をとりもどすだけでなく、 地区の歴史と文化を引継ぎながら、 より創造的な復興を行いたいと考えます。
p3
INFORMATION
「関西大震災」緊急連続シンポジウムの開催について
建築フォーラム[AF]主催の連続シンポジウムが開催されます。
〈第2回以降の予定〉
京都市下京区木津屋橋通西洞院東入ル TEL:075―342-2600
「木造建築に未来はあるか」
坂本 功(東京大)
三澤康彦・三澤文子(M’s建築設計事務所)
「都市防災の現実と可能性」
室崎益輝(神戸大)
小林正美(京都大)
「集合住宅の再建をめぐって」
内田雄造(東洋大)
折田泰宏(弁護士・日本マンション学会京都事務局長)
「ホップ!ステップ!元気!ひょうご!県民のつどい」・4/27開催
震災から100日目に当たる4月27日(木)、 兵庫県公館において、 兵庫県民自身の企画によるイベントが開催されます。
兵庫県公館(旧兵庫県庁舎)
設計:山口半六、 明治35年、
煉瓦造(内部をRCで補強)
左下は全壊した栄光教会「ホップ!ステップ!元気!ひょうご!県民のつどい」の概要
兵庫県公館は、 山口半六設計で明治35年建造の神戸を代表する近代建築です。
ネットワーク事務局より
各地の復興まちづくりニュースを 事務局まで送ってください!
2月10日の「きんもくせい」創刊から早や2カ月余りが立ち、 多くの方々のご支援により、 被災地のみならず全国各地にその“香り”がたちこめています。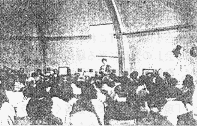
魚崎地区まちづくりシンポジウム(4/9)
防災都市計画研究所の吉川さんを交えた
防災まちづくりワークショップ(西宮4/8)
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1029 FAX.078-803-1029
担当:児玉
 きんもくせい08号へ
きんもくせい08号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ