4/9魚崎地区まちづくりシンポに参加を!
一方、 行政主導の計画にかかっていない当地区のまちづくりをどうするか、 無秩序な再建にならぬよう緩やかなガイドラインを設けるにはどうすればよいか、 建て替え復興の多様なメニューを分かりやすく提示するにはどうすればよいか、 問題が山積している状態である。初期の緊急避難的ボランティア活動が終息に向かったことを念頭に置きつつ、 大阪大学の加藤晃規先生にも参加いただき、 NPO(民間非営利組織)を射程においた体制づくりの検討も開始した。
その方向性の中で我々が今計画しているのは、 4月9日に予定している『魚崎地区まちづくりシンポジウム』の開催である。
4月に入り学校の始業とともに、 外部に避難していた人々が帰還するのを待って、 復興への呼びかけを行いたいと考えている。
シンポジウムは、 既に完成した直径30Mの大テント(カナダ政府提供)を会場にして、 地元住民・建築家・都市プランナー・法律家等の参加によるパネルディスカッション及び現在製作中の500分の1地区模型や各種プロジェクトのパネル展示(常設展示に)を中心に行う予定。
他地区との情報交換も兼ね、 多数の参加を希望している。
(3月27日 記)
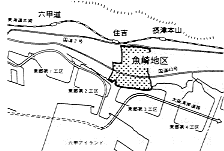
魚崎地区位置図
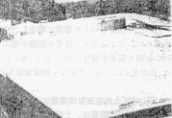
模型写真

模型づくりに励む全国各地の学生ボランティア
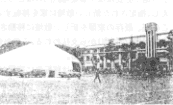
魚崎小学校校庭に建てたれた30mの大テント
(カナダ政府提供)
浜山地区のまちづくり―土地区画整理事業の実際
まちづくり(株)コー・プラン 細野 彰
浜山地区の概況とまちづくりの経緯
浜山地区は兵庫区の臨海部に位置し、 面積約50ha(事業地区約30ha)、 人口約7,500人の住・工・商混在地区であり、 今も下町の良さが残るまとまりのある良好なコミュニティが存在するまちである。
地区全体が戦災を受けなかったため、 道路はほとんどが幅1間半程度の私道であり、 戦前長屋が今なお住宅床の約4割を占め、 近年、 人口の減少と高齢化が進み、 町全体としての活気が薄れるなどいわゆるインナーシティ問題をかえる地区であり、 総合的な整備が必要となっていた。
そこで、 地区のまちづくりを住民が主体となって実現させていくために、 平成元年2月に「まちづくり協議会」が結成され、 平成3年7月にまちの将来像を示す「まちづくり提案」を市長に提出した。
これを受けて市では、 これまで実施されてきた板宿、 上沢、 東灘山手、 河原地区などの既成市街地における土地区画整理事業の実績をふまえ土地区画整理事業を、 さらに狭小な長屋地区であることを考慮して集会所や受皿住宅を整備するコミュニティ住環境整備事業との合併施行による事業を進めることになった。
このようにまちづくり事業に着手し、 土地の先行買収が始められ、 コミュニティ住宅の建設が進んでいるときに今回の阪神大震災が発生した。
しかし、 幸いにして地区の被害は、 長田などにくらべて少なく倒壊家屋もわずかであった。
このお金を元に実際は、 家を新築することになる。
また、 建物移転の際には移転先に家屋が建設されるまでの間、 地区内または近接して建てられる事業用仮設住宅、 店舗が提供さる。
事業費は、 最近の既成市街地では、 1ha当り10億円強かかるといわれている。
浜山地区の場合、 事業費は約300億円で、 平均減歩率は17%であるが、 65 m2未満の土地は減歩率が緩和され、 25m2未満は減歩なしとなっている。
また、 狭小な宅地に建つ長屋の移転を促進するため共同建替のコンサルタント派遣を行い現在5カ所で話を進めている。
事業費は約200億円が予定されており、 30haの区域に区画整理と併せて約500億円の国費、 県費、 市費が投入されることになる。
なお、 正式名称については、 現在検討中である。
1月に発生した阪神大震災で神戸市は未曾有の大打撃を受けました。
旧市街地はことに大きな被害を受け、 多くの建物が倒壊し、 多数の方が避難生活を余儀なくされる結果となりました。
このため、 まちの復旧・復興は焦眉の急務となりましたが、 あまりにも被害が大きく、 職員だけでは十分に対応できないのが実情であり、 多数のボランティアの助力を得る必要が生じました。
まちづくり会館でも2月下旬に東京大学の小出教授からの都市防災・建築系の学生を市の復興事業支援のためのボランティアとして送りたいが、 受け入れは可能かとの打診に応じて関係機関と調整のうえ学生団を受け入れることになりました。
受け入れた学生は、 大学院・学部あわせて延べ63名で、 学校別の内訳は、 東京大学40、 東京理科大7、 横浜国大5、 多摩大3、 東京工大3、 筑波大2、 長岡造形大・早大・獨協大各1となっています。
学生の皆さんには、 大変熱心に都市計画局・住宅局関係の復興作業や、 魚崎地区(1面で紹介)、 真野地区、 浜山地区等、 地域住民自らが復興に取り組んでいる地域での支援活動に取り組んでいただきました。
まちづくりセンターでは、 復興事業を支援するために人材センターを設置することが予定されており、 今回の受け入れで得たノウハウを活用して、 復興事業の支援に向けて人材ネットワークを形成して行きたいと考えています。
今後、 ますますのご支援・ご助力をよろしくお願いします。
当日は、 市役所の職員や地元建築士会のメンバーなど約50名あまりが参加した。
また、 地元のテレビ局(2社)や新聞社なども取材に訪れた。
参加者の中には、 淡路島北淡町の被害実態調査にボランティアとして参加した方々が多いこともあって、 神戸の被害やまちづくりへの関心はきわめて高く、 熱心に報告に聞き入った。
二人の報告の後、 会場からは「歴史的建造物の被害の状況はどうか」「今後、 復興まちづくりに住民の参加を得ていく上での課題は何か」「プレハブではなく、 木造の仮設住宅を供給する仕組みが必要では」「被害を受けた既存不適格の建物の建て替えをどう進めていくのか」などといった活発な質問や意見が出された。
市民まちづくり支援を第一義に考えている当ネットワークとして、 どのような形で協力・とりくみを進めるかについて、 現在協議連絡を重ねています。
3/17以降の当ネットワーク全体としての活動及び今後の予定は以下のとおりです。
これらについての概略と今後の予定は以下のとおりとなっています。
―ランドスケーププランナーの佐々木葉二さんを迎えて
“緑と水のワークショップ”を開催
・街区別共同建替え等課題街区の抽出
・住宅整備の促進手法
4月8日には東京より防災都市計画研究所の吉川仁さんを迎えて防災まちづくりについてのワークショップが開催されます。
また、 4月中をめどに重点地域の抽出及び重点地域の整備手法・整備イメージ案の作成が予定されています。
このエリアは、 重点的に市街地や住宅の整備を進める地域で、 住民 のまちづくり機運の高まりに応じて順次追加指定を行う予定。
重点復興地域内では建築確認申請の30日前に届出が必要で、 この間に市のアドバイスがなされる(詳細は神戸市発行「震災復興まちづくりニュース」第4号・3/21参照)。
P.4
浜山地区土地区画整理事業について
土地区画整理事業は、 土地所有者が道路、 公園などの公共施設に必要な土地を出しあって(これを減歩という)、 土地の配置換え(これを換地という)によって土地を集約し用地を生み出し公共施設を整備する事業である(下図参照)。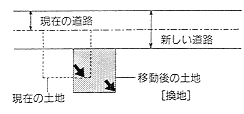
減歩概念図浜山地区コミュニティ住環境整備事業について
土地区画整理事業とあわせて地区の住環境を総合的に改善するため、 まちづくり事業によって住宅に困まる住民が入居できる受皿住宅(コミュニティ住宅)の供給、 集会所、 まちかど広場など生活環境施設の整備を行う事業であり、 現在第1住宅(56戸)が工事中、 第2住宅(85戸)が実施設計を終え、 平成7年度着工の予定である。地元の取り組みについて
まちづくり協議会では震災後、 今までどおり、 まちづくりを積極的に進めることを確認し、 これまでの「協議会ニュース」に加えて、 高松線(幹線道路)沿いの空き地を借りてコンテナハウスを設置し、 地元の住民に情報を伝えるとともに、 神戸市民に対しても区画整理先進地区としての情報発信基地(仮称:浜山まちづくりハウス)を4月上旬をめどに設置する予定である。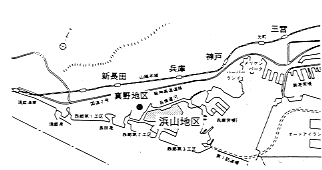
浜山地区位置図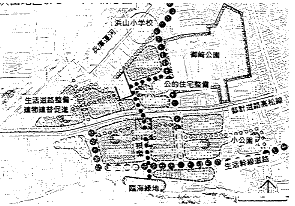
浜山地区まちづくり構想図
まちづくり支援学生ボランティア奮闘
財)神戸市都市整備公社こうべまちづくりセンター 明石 照久
平成7年3月1日から31日まで1カ月間、 東京大学を中心とする阪神大震災復興支援ボランティアをこうべまちづくり会館で受け入れました。こうべまちづくりセンターの概要
1.業務内容:協働によるまちづくりの普及・啓発の推進
1)人材育成(まちづくり大学、 まちづくり学生クラブの創設)
2)人材活用(推進員・専門員制度、 コンサルタント派遣制度の創設)
3)まちづくり情報の収集・提供(図書・ビデオその他資料の収集・提供)
4)広聴・広報と調査研究(まちづくり・コミュニティ相談、 アーバントー
クの発行、 ワークショップ・コンクールの実施、 まちづくりの支援シス
テムの研究)
5)会館の管理・運営
2.まちづくり会館の設立年月日:平成5年11月
3.問い合わせ先:〒650 神戸市中央区元町通4丁目2−14
TEL:078-361-4523 FAX:078-361-4546

「まちづくり学生クラブ本部」玄関

作業中の学生ボランティア(こうべまちづくり会館内)
避難者と同室の学生ボランティアの宿泊所徳島市・都市デザインセミナー『阪神大震災と神戸のまちづくり』開かれる
徳島市役所主催による都市デザインセミナーが3月30日に開かれ、 支援ネットワーク事務局からコー・プランの小林と神戸大の児玉が招かれ、 阪神大震災の被害の実態と復興まちづくりの取り組み状況について、 スライドを交えながら報告を行った。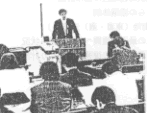
3/31日付徳島新聞記事より
復興市民まちづくり支援ネットワークの活動
神戸復興市民まちづくり支援ネットワークのとりくみ
3/17の都市計画決定に関連して、 住民からの多くの異議申し立て、 審議会からの付帯意見などが続き、 神戸市(区画整理担当)から当ネットワークに対して協力要請がありました。3/20「神戸市東西合同連絡会」
取り組み方策(行政、 市民との連携)、
住宅復興計画の取り組み
―取り組みシステム、 推進策のメニュー、 参加人数:約40名
3/27「新長田周辺地区(土地区画整理事業)コンサルタント協議連絡会」
新長田駅周辺地区の都市計画、
これからの協議体制
今後の取り組み
議事予定:六甲周辺のまちづくり計画、
六甲道駅周辺地区の都市計画、
これからの協議体制
議事予定:各地区の最近の復興への取り組み状況、
灘・東灘市街地の復興まちづくり計画構想について

3/20神戸市東西合同連絡会の会議風景西宮復興まちづくり計画支援ネットワークのとりくみ
西宮のネットワークではこれまでほぼ週1回のペースで計5回の連絡会をもち、 活動しています。
今後の取り組み
これからも、 週1回のペースで連絡会が開催される予定です。
西宮復興まちづくり計画支援ネットワーク事務局
〒662 西宮市中前田町1-25和成ビル2F TEL:0798-26-7717 FAX:0798-26-7367
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1029 FAX.078-803-1029
担当:児玉
 きんもくせい07号へ
きんもくせい07号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ