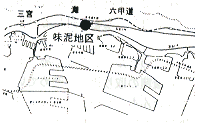
未泥地区位置図
以前からまちづくりを進めてきた灘南部自治会・味泥下町活性化委員会をもとに「味泥復興委員会」が結成され、 まちと住宅の再建に向けての話し合いが始まるとともに、 広報誌「味泥復興計画」第1号が発行された(2/23)。
取り組みの体制は、 復興委員会を中心にして、 具体的な住宅の共同建替や協調建替を進める小単位のグループとして近隣協同事業体が組織される予定である。
それに専門チームとして、 久保都市計画事務所といきいき下町推進協議会が支援していく。
当面、 地区の居住者の被災状況の把握と住宅の建替動向を探るためのアンケート調査と住宅診断・相談会を実施していくが、 この住宅相談にはボランティアの協力を得ている。
ところで、 神戸市の復興計画の枠組みは、 インナーエリアの大半の範囲に及ぶ震災復興促進区域とそのなかの重点復興地域を指定して、 重点復興地域では公的な整備施策によって、 それ以外の促進区域では民間の自助努力で乗り切ろうというものである。
このうち復興促進区域にはインナーエリアの「ふつうの地区」がほとんど含まれるが、 「ふつう」とはいえ、 もともと狭小宅地、 住宅の老朽化、 権利関係の輻輳、 インフラ(区画道路)の未整備、 居住者の高齢化など不利な条件が多くある。
通常ならこの「ふつうの地区」では既存のストックをいかしながらゆるやかに時間をかけてまちづくりが行われることでよかった。
しかし、 震災を経て「ふつうの地区」はふつうでない地区となり、 条件はまったく変わってしまった。
味泥はまさに、 このように位置づけられる地区である。
さて、 この味泥地区で住宅再建のために何が可能かを探ってみると、 具体的な方策がなかなか見いだせない。
復興の主体が民間であるにせよ、 現在のところ支援のメニューは限られたものであり、 とりわけ民間借家居住者を対象とした公的支援策はほとんどない。
そこで、 住宅再建の核となり、 また民間更新活動を計画的に誘導する思い切った公的支援策が望まれる。
第一に小規模持家層に対して、 共同化、 協調化を誘導する強力なインセンティブと即地的・即応的なアドバイスの体制づくりが必要である。
第二に借家居住者に対しては、 借り上げ方式などによって地元居住者が入居できる地区内分散配置型の小規模公営住宅を建設することが有効ではないか。
いずれにせよ味泥の取り組みは被災市街地のほとんどを占める促進区域復興の典型であろうが、 その成否は上のような支援策にかかっている。
(2月25日記)
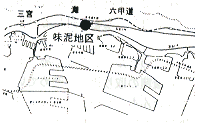
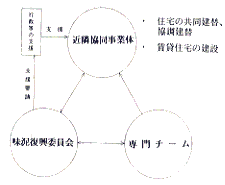
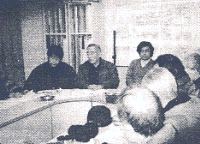
味泥復興委員会の準備状況。
左から3人目が松坂委員長(2/14)
東京から矢野トンプー氏、 林泰義氏、 熊本から延藤安弘氏、 四国から高知のまちづくりを考える会の人達やアメリカのシンシナチ・コミュニティデザインセンターのデュレイドダース氏など10人以上のまちづくりの仲間が集まり、 カードボード(強化ダンボール)を使って避難所になっている空き地や体育館に間仕切りなどをつくり個人の空間を確保することをめざしたプロジェクトが動きだした。
まずは、 真野小学校前の空地にやはりカードボードを使った工房をつくり、 そこで、 間仕切り兼整理棚になる家具づくりを行っている。
避難所の住民や地域の住民にどのようなものができ、 どのように利用できるのかをみてもらい、 希望者に、 加工のノウハウを教えながらつくっている。
大小2戸のコンテナを調達し、 全国各地から大工や設計事務所、 大学の学生などの応援により、 1週間ほどで、 出入り口、 内装、 キッチンセット、 畳などのしつらえを行う。
今回は、 あくまでも実験であり、 今後どのように供給していくかを検討しているところという。
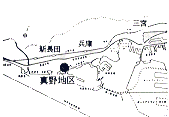
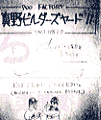
呼び掛けのビラ

ダンボールを使った家具製作にはげむ矢野トンプー氏
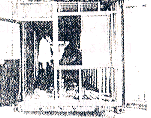
三谷真さんら4人が発起人。
ボランティアの築き上げたものの継承と地元自らの長田再生をどう行っていくかがテーマ
事務局長は東充さん。
84条区域に指定され、 市街地再開発事業の推進のために役員が焼け跡の調査や仮設住宅群をつくるための取り組みをすすめている。
住民側への専門的知識の提供が主な目的。
山崎泰孝さんら約30人の建築家たちが参加。
行政や企業体主導型のまちづくりに疑問を持ち、 防災のみではなく、 自然、 歴史、 アート等の観点から芦屋の再生を図ることがテーマ
代表は木村博昭さんで約60人が活動。
活動範囲は神戸市魚崎地区が中心。
戸建の住宅調査を実施するとともに、 建物の解体・建替相談所を開設し、 project『解援隊』(=住民自らが解体を行う活動)
等を実践している。
また「きんもくせい」の紙面提供を考えていますので、 是非寄稿をお願いいたします。
p2
調査は、 須磨、 長田、 兵庫、 中央、 灘、 東灘の各区からほぼ2ヵ所づつの避難所、 計11ヵ所を選び、 2月上旬にアンケートを配布・回収し、 1,800票あまりの回答を得た。
アンケート結果を分析すると、 いくつかの避難所住民の深刻な状況が伺える。
60歳以上の世帯主が43%を占めていることや単身者が全体の3分の1近くを占めていることから伺える。
また、 全体の4分の3の人は、 地震以後ずっと同じ避難所にいたとこたえており、 親類や知人など他に頼るべきところがなかった状況が伺える。
地域によって多少の差こそあるものの、 全体的にみると、 木造、 老朽化した民営借家に居住していたものが多いことがわかる。
詳しく数字をみると、 民営借家であったものは、 全体の47%と半数近くにもなる。
構造については、 実に7割が木造であったとしている。
さらに、 老朽化の指標として、 築後何年を経過しているかをみると、 全体の約半数が30年以上を経過しており、 20年以上経過したものでは、 実に80%近くになっている。
そして、 今回の震災による住宅の被害状況では、 全壊、 焼失したものが63%にも及んでいる。
当面の居住場所として、 仮設住宅を希望するものがほとんどであるが、 現実問題として、 仮設住宅が全く足りない状況にある。
そこで、 抽選にはずれた場合どうすかるかについて聞いたところ、 全体の80%以上の人がこのまま避難所での生活をつづけるしかないとこたえている。
しかし、 現在困っていることについての問いに対して、 「賃貸住宅家賃の高騰」をあげるものが3割近くもおり、 賃貸住宅探しもそうたやすくない状況が伺える。
ここでは、 そのいくつかを紹介する。
仮設住宅に皆が一日でも早く入れるようにしてほしい願っています(灘区在住)」「無料の老人ホームへ優先的に入れて下さい。
熱く望みます(灘区在住)」「若い世代の人が戻ってこられるように、 公営住宅を充分に(質、 量とも)お願いします(灘区在住)」「安全な町づくり。
近代化を急ぐことをせず、 人間中心主義の行政をしてほしい。
利益優先の行政をしないで(中央区在住)」「老人向けの住宅を希望します。
定期的に保健婦さんや、 ケースワーカーが訪問してくださるような制度を作ってくださればありがたいと思います。
今回の震災で、 隣近所のつきあいや協力がいかに大切かを知りました。
以前の隣組制度が復活したようで、 私は大変助けられました(中央区在住)」「震災がきても建物が壊れないような物件で、 家賃も安く借りれる住まいを望んでいます。
一日も早く元の神戸にかえれるように思っていますが、 仮に仮設に入っても一年後どうなるかが不安です(長田区在住)」「国や自治体が土地や壊れた建物等を買い上げ、 公営の住宅を建設していただいて、 入居可能な家賃で我々に提供して欲しい(長田区在住)」
現状では2万5千戸分の用地がようやく確保でき、 着工しているのは千戸あまりと言われているが、 足りない分については迅速な対応が求められる。
さらに恒久的な住宅対策として、 充分な質を備え、 適切な家賃の賃貸住宅を公的なコントロール(公営、 民間借り上げ、 民間家主支援、 家賃規制、 家賃補助etc.)のもとで大量に供給していくことが最も必要だと考えられる。
避難所生活が長期化し、 今後の生活再建の目処が立たず、 肉体的にも、 精神的にも限界を迎えつつある避難所住民に対し、 できるだけ早く、 住宅対策の方針をうちだすことが望まれる。
文責:児玉善郎 (3月4日記)
p3
森南町・本山中町まちづくり協議会の13人は2月28日、 地区内関係者2,080人の署名を持って神戸市長、 都市計画局長、 都市計画審議会会長に対して陳情に行った。
当日の神戸市の記者会見で「計画については一切変更しないと発言」との記事があった(3/1朝日)。
3月17日までという短期間での都市計画決定という状況下で、 将来を展望した関係者間の良識ある対応が求められている。
そのような状況の中、 何とかもう一度自分たちの家を建て直し、 もとの住みよい町に帰りたいと考えはじめた時、 神戸市より「災害に強いまちづくり」をするため建築制限区域に指定され、 神戸市も私たちのまちづくりを支援してくれ、 神戸市の協力のもとに、 もとの住みよい町に復興できるものと期待しておりました。
そして、 2月22日、 神戸市の相談所が設けられ「森南地区のまちづくり案」が都市計画局の人々によって説明されました。
その内容を要約すると、
・これを土地区画整理事業で施工する。
以上は近く都市計画決定するのでそれ以降の変更は不可能である。
という話でした。
これは住民を集めての説明会としてではなく、 各個人が相談所に足を運んだ人にだけの説明でした。
私たちの住む森南地区は、 戸建の住宅が7〜8割の中にマンションなどの共同住宅がまばらに建つ環境の良い住宅地です。
そこへ駅ができ、 地区内を東西に抜ける道路ができれば、 今でも山手幹線が芦屋で行き止まりとなっていて、 その抜け道として森南地区に流れてくる車で、 日常的に事故が多発している状況であるのに、 この道はまた2号線のバイパスとして通過交通の量が増えるのは目に見えており、 それによる排気ガスや騒音の問題、 また地区内で親しんできた森公園とも分断され、 今までの環境は完全に破壊されてしまいます。
また仮にこの道が芦屋に抜けたとしても、 東は芦屋川、 西は十二間道路にぶつかり、 何ら有効な道とは考えられません。
これは長年にわたり、 山手幹線が芦屋に抜けないがための立案であり、 山手幹線が通れば2号線との間(南北に300mの間)に17mもの幹線道路が必要であるかどうか疑問に思われます。
救援活動のために道路が必要であるなら、 山手幹線を東西で結ぶことこそ優先されるべき時ではないでしょうか。
また、 今回の震災であらゆる道路が車で埋まり、 救援活動の支障になったことも考え合わせると、 道路があれば救援できるという話は成立しないと実証されたばかりです。
それに、 今回は、 たまたま早朝に起きた地震で車の通りも少なかったのですが、 これが2〜3時間後のラッシュ時に起こっていれば、 車の衝突、 そしてじゅずつなぎで炎上していくのは当然考えられる事で、 道路があれば避難できるとはいいがたいと考えます。
また、 防災的に見ても、 延焼・類焼をくい止めるために17m幅員の道が必要なら、 JR軌道がその役目を果たしてくれると充分考えられます。
現在、 避難所生活をしている人々の他に、 家はたて残ったけれど、 水もガスも復旧していない状況で、 その不便ゆえ他府県に避難している人もたくさんあり、 この「森南地区のまちづくり案」があることさえ知らない人々がたくさんいます。
大切な「まちづくり」の話が、 住民不在の中で決定されようとしているのです。
笹山市長は震災前、 神戸市マスタープランに「ぬくもりとやさしさの町」を掲げられていますし、 貝原知事も「まちづくり」は住民の参加と合意に基づきすすめられると発言されました。
ところが「やさしさ」も「参加」も「合意」もないまま「まちづくり」がされようとしているのです。
震災から1ヶ月半がたち、 やっと気持ちも落ち着き、 復興しようと考えはじめたところです。
もう少し待っていただきたい。
地区の人々が「まちづくり」に参加できる状況になるまで、 今少し待っていただきたいと考えます。
そして住民が主体となってつくられる「まちづくり」が神戸市のいわゆる「災害に強い町」としてよみがえられるように神戸市に支援をお願いしたいと考えます。
下記事務局まで今すぐFAXを送ってください。
〈きんもくせい支援ネットワークリスト登録〉
P.4
(1)弱い立場の人が圧倒的に多い
まず第一に、 高齢者を中心とした弱い立場にある人が圧倒的に多いということである。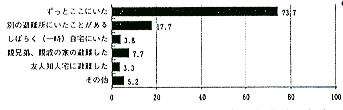
グラフ・地震後の住居(M.A)(2)低質な住宅に居住していた
二つ目の特徴は、 震災以前に住んでいた住宅の質が低かったことである。(3)厳しい、 今後の住宅復興の見通し
三つ目には、 今後の住宅復興の見通しがきわめて厳しいことである。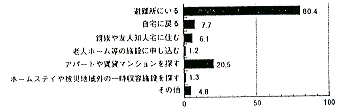
グラフ・抽選がはずれた場合(M.A)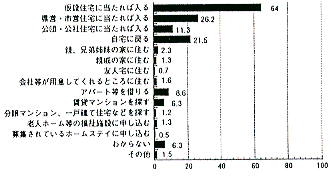
グラフ・移転意向(M.A)(4)避難所住民の切実な声
アンケートの最後に設けた自由記入欄には、 避難所住民の生々しい訴えが数多く記されていた。住宅復興に向けて
以上のアンケート結果を踏まえ、 今後の住宅対策について求められることは、 まず緊急的対策として、 一日でも早く避難所の住民全員が仮設住宅に入れるようにすることである。
神戸市の森南地区・まちづくり案(土地区画整理事業)
森南地区の区画整理案をめぐる問題について
「きんもくせい」第3号(3/3付)で既報の6地区の84条区域(3/17までの建築制限区域)における神戸市のまちづくり案のうち、 森南地区(東灘区)では、 市のまちづくり案に対し、 住民も独自の動きを示している。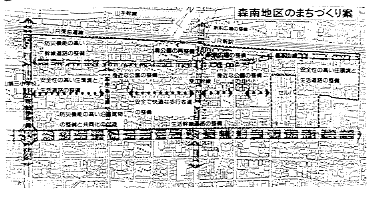
神戸市の森南地区まちづくり案(土地区画整理事業)陳情書(全文)
などの項目については、 住民のみなさんとの話し合いで変更は可能である。復興市民まちづくり支援ネットワークの活動
名乗りをあげてください
あなたが進めている復興まちづくりについて、 あなたがやってみたいと思っている手助けについて、 あなたが何かやらねばと思っている多くの想いについて、 とりあえず名乗りあげてみませんか。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1029 FAX.078-803-1029
担当:児玉
 きんもくせい05号へ
きんもくせい05号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ