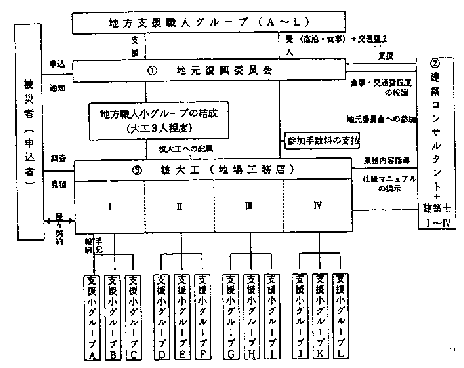
住宅修繕システム図
膨大な倒壊家屋が発生するなか、 大工さんの不足、 法外な修繕費の高騰等の問題が深刻化しており、 これにより、 避難所生活を余儀なくされている人達も少なくない。
森崎氏は、 右図に示すような住宅修繕システムを考案し、 まず3/12〜19に福島県三春町から大工さんを4〜5人呼び実践する。
今のところ8軒の修繕の申し込みがあり(4軒は修繕の必要なし)、 まず2軒から着手を予定している。
これらは下に示すように新聞記事(地方紙等でも同様の内容で掲載)で紹介され、 全国各地から支援の連絡が入っている。
今後の課題としては、 野田北部地区だけでなく被災地全域への展開があげられる。
そのためにはまず、 現在神戸市等の各地で活動しているまちづくり協議会が母体となったとりくみが有効であると考えられ、 建築の専門家や都市計画コンサルタントの参加が不可欠であり、 行政としての支援システムづくりが急がれている(神戸市では現在のところ、 既存のコンサルタント派遣制度で対応するとしている)。
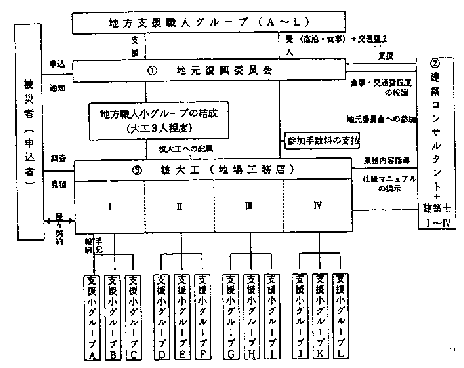
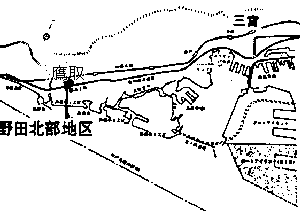
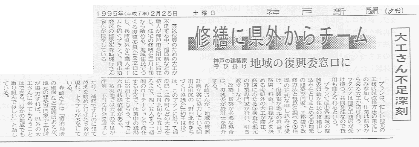
新聞記事のコピー
被災地域での復興計画が始まっている。
「きんもくせい創刊号」にも被災都市でスタートした復興まちづくりの地区名が記されていた。
被災地区の人々にとって一刻も速い復興建設は切望されるところであり、 それに応えて支援コンサルタント等によるプランづくりが急務として夜を徹して進められている。
一方、 従来の都市防災計画の予想をはるかに越えた大地震を経験して、 新たな視点を考慮した都市防災計画の立案も進められている。
いずれもこの機にあって急務のものである。
しかしマスコミ等の情報やプランづくりに参画している知人の話から感じるのは、 余りにもハードな物づくりのプランに偏りすぎているきらいがあるように思われる。
ここに胸痛むひとつのデータがある。
この度の震災で犠牲になった5,300人を越える死亡者の52%が60歳以上の高齢者である。
この数値は激震地区が神戸・芦屋・西宮に至る各市の下町を総なめにしたことから当然の結果の数値として現れたものである。
高齢者は心身状況が弱化しているので多くの死亡者が出たというものではない。
予想を越える大地震だったから不可抗力だったと言えるものではない。
都市の下町には、 今からもう30年以上も前になるわが国の高度経済成長期に建てられた安普請の過小な木造アパートや文化住宅が老朽化したまま多く残っていた。
そこには、 ひとり暮らしのお年寄りや、 老夫婦が住み続けている。
お年寄りたちは階段の上がり降りが堪えるので一階の部屋に住んでいる人が多い。
それらの住宅が全壊し一階に寝ていた人が犠牲になった。
高齢者をはじめとする社会的弱者の安全な暮らしが保証されていなかったのである。
西宮市内の建物被害状況調査で現地に出ると、 住宅地図では木賃アパートや文化住宅として記されているが、 建物全体がぐしゃぐしゃに押し潰されて従前の様子が分からない状態にまで倒壊してしまった住宅が多くあった。
その瓦礫の山のそばにそこで亡くなった人たちへのお花が供えられている場面をしばしば目にした。
涙が噴き出る調査であった。
このような住宅を含め被災した住宅は143,000戸に及び、 避難者は30万人にものぼる(2/16現在)。
まずは住宅再建が緊急課題である。
どこに、 どんな住宅を、 どんな手法で建設して行くのか、 新たな発想が必要であり、 今までのまちづくりとは大きく視点が異なるはずである。
恐怖を体験した人達が長い時間はかかるけど心を癒されて行くような暖かさ、 安心、 やすらぎの仕掛けを内在した復興プランであってほしい。
そのためには急いでハードを重視したプランは描けないはずである。
市民福祉の視点を中心におき、 地元商店街や市場の復興にも小規模単位であってもできるかぎり地域に住んでいた人達の住宅を付設したり、 一気に完成図を目指さないで、 段階的に復興建設していくようなプランも望まれる。
そして今までハードなまちづくりに関与することが少なかった役所の福祉部局や市民生活部局、 お医者さんたちももっとまちづくりに積極的に大きな口出しをしてほしい。
アイデアを提供してほしい。
避難生活の中で芽生えた共に生きる、 共に支えあって生活するというライフスタイルが、 育っていくような仕掛けをもつ生活環境が整備される絶好の機会にしたい。
例えば、 数軒単位の共同建設や、 今行政が建設している応急仮設住宅ではなくて、 3年か5年位住めるような住水準を備えた一時的住宅も建設し、 その後の状況に応じて用途を変えたり、 更に住水準を高めていけるような住宅の建設はできないだろうか。
27m2ワンパターンの応急仮設住宅に入居が決まったお年寄りの中には一人で住むのが不安だと言っていた人もいた。
ひとり暮らしのお年寄りや老夫婦が仲間同士集まって住めるような住宅が市場のそばにでもできないだろうか。
お昼ご飯は市場で働く人達も一緒にできるような食堂があれば楽しいだろう。
弱者に集中して多くの死亡者が出たのは誰の責任だとは今、 言及したくないが、 私たちまちづくりの専門家も含めてそれに対応する側に責任のすべてがかかっていたと思う。
予想を越える大きな天災だったというが、 社会的弱者に対しては人災とも言える側面も大きい
(2月16日記)。
私達は、 避難生活されている人々が今も20万人以上(2/20現在)もおられるので、 なにはともあれ今日のためにしなければならない問題と明日への生活と仕事を建て直すための将来の問題との膨大な課題に同時に取り組まねばならない。
私はこれまで情報システム関係の業務にたずさわってきたことから、 なんらかの情報システムを駆使することでこれらの問題の解決に役立てられないかについて思案して来た。
つまり、 情報システムを活用して今日と明日の問題の解決を円滑にすることができれば、 そのこと自体が来るべき時代の先取りになるとともに神戸の潜在力を引き出し新しい力を創造することになるのではないかと思ったのである。
私は、 この度の震災の被害状況をGISというシステムによってまとめられていることを神戸大学建設学科の研究室へ参加した私の勤務する会社のボランティアや新聞記事から知った。
このGISに被害状況だけでなく、 もっと多方面の情報を地図によって関連づけられれば「都市データベース」ができ、 直面する難問に関係者の叡知を結集できるのではないかと考えたのである。
時間との闘いのなかで錯綜する諸問題に対処するには正しい情報の共有化が原点である。
そのために、 地図上にいろいろな情報をまとめる単位として地区を設定し、 地区ごとに土質、 地盤、 構造物、 建物、 人口、 年齢構成、 企業、 水道・電気・ガスのライフライン、 電話設備、 病院、 消防、 警察、 避難所、 道路などの情報を相互に関連づけてまとめるのである。
例えば、 こんなことも考えられる。
震災によって、 学校などの施設が避難所として大変な役割を果たしている。
地区ごとの避難所を学校にした場合、 ライフラインの幹線をこうした拠点間に付設するとともに、 情報システムのネットワークとパソコンなどの機器も情報化教育の設備としてだけでなく災害時や地域のイベントの情報発信設備として整備していくのである。
これによって、 一朝事があれば教育機器が児童や生徒らも参加できる社会システム機器に転化でき、 必要な情報の発信ができるのである。
先に述べた「都市データベース」の基本的な情報はすでに関係の自治体の各々の組織や関係企業体にある。
問題は同時に重ねてみることができる横糸がないのである。
重ねて関連づけてみることによって多角的に物事が検討できる。
地区ごとに情報をまとめることでプライベートな情報を分離し、 コミュニティ情報に転化し共有化を図ることができれば、 自治体、 企業、 住民が協調して復旧、 復興はもとより、 これからの新しい生活や仕事をも創造していくことができるのではないかと思うのである。
こうしてできた「都市データベース」にマルチメディアの持つ多彩な情報能力と双方向機能を結びつけて展開していけば、 KIMECにも新しい視点を加えていけると思うのだが……。
あらかじめパソコンソフトに入っている白地図に様々な地理的データを入力して都市計画や自然保護にも利用されているようである。
神戸市では2月23日、 「震災復興まちづくりニュース(第3号)」で、 6地区の案が示された。
東西の副都心地区(新長田駅周辺、 六甲道駅周辺)では土地区画整理事業と市街地再開発事業(2種)により、 新たな防災公園の整備、 未整備及び新規の都市計画道路の整備、 高層の再開発ビルによる防災街区の整備を行うとしている。
他の4地区では土地区画整理事業案が示された。
西宮市では、 25日に2地区のうち西宮北口の再開発案が示された。
これらの案の発表を受け、 地元では案の撤回を求める動きもあり(神戸市・森南地区の土地区画整理事業)、 行政、 地元、 コンサルタント等が協調した今後の取組みが求められている。
○連絡事務局
住民団体、 大学関係者、 雑誌、 マスコミ、 一般市民等多岐にわたる方々から、 「まちづくりの情報を得て何か役に立ちたい」、 「例会の資料にしたい」、 「番組でとりあげたい」等、 当活動への関心が寄せられています。
また、 「きんもくせい」はパソコン通信のニフティサーブでも記事の内容を紹介しており、 それを通じても多くの意見が寄せられています。
なお、 これまでに寄せられた様々なご意見やご提案については順次対応をしていきたいと思いますので、 よろしくお願いいたします。
〈きんもくせい支援ネットワークリスト登録〉
○氏名 年令 性別
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
P.4
都市データベースの構築に向けて
三菱重工業株式会社神戸造船所 大橋
震災から1ヶ月経って事態がそれなりに落ち着いてくるにつれて、 現実がボディブローのように重くのしかかってくる。
注)GIS:地理情報システム。
自治体の復興計画案発表-神戸市・西宮市
「きんもくせい」創刊号でも紹介した建基法84条による建築制限区域(2ヶ月間)において、 自治体のまちづくり案が発表された。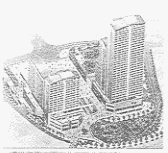
西宮北口駅周辺地区まちづくり案
震災復興で西宮北口駅北側に計画されている高層ビルの予想図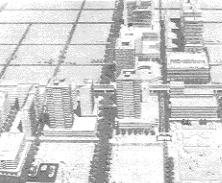
新長田駅周辺地区まちづくり案スケッチ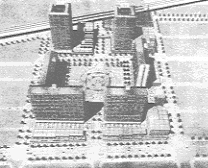
六甲道駅周辺地区まちづくり案スケッチ
復興市民まちづくり支援ネットワークの活動
「西宮市まちづくり復興計画支援ネットワーク」できる
〈目標〉
1.当面の目標
(1)復興計画(西宮市作成)のパイロットプラン(下敷)の役割
(2) 整備課題の抽出及び必要な制度、 手法等の検討
(3)当面の緊急復興相談への対応
2.次の段階の目標
(1)共同化事業等整備課題への取組みへの支援
(2)都市計画マスタープランの「地区別整備計画」への展開
〈西宮市まちづくり復興計画支援ネットワークの体制〉
○まちづくり復興計画支援ネットワーク事務局
・土井(大阪市大) ・後藤(大阪芸大) ・石東(石東研究室)
・萩原(OUR)+数人 ・酒井(大阪市大)
・菅原(大阪市大) ・藤井(奈良女大) ・磯崎(大阪市大)
・大平(大阪芸大) ・小林(コー・プラン)・岩崎(UR)
○地域分担
◇上ヶ原/土井・赤崎(大阪市大) 06-605-2715 F.605-2715
◇段上/寺内(大阪工大)・母倉(リック総研) 06-357-5782 F.357-3361
◇西宮北口/有光・小南(環境開発研究所) 06-252-1370 F.252-6119
◇甲子園口/奥保・亀谷(大阪芸大) 06-531-5480 F.531-3346
◇夙川・甲陽園/朝平・藤田(UR) 06-351-2756 F.358-6081
◇広田/貴志・中川・宇野(RIA) 06-312-9154 F.314-2660
◇香櫨園/馬場(COU)・田村(オオバ) 06-943-9404 F.943-5966
◇阪神西宮/萩原・仲田(OUR) 06-943-8150 F.943-9413
◇浜脇/安原(都住創)・速水(あとりえ玄) 06-354-7468 F.358-8226
◇津門・今津/田端(大阪芸大) 06-323-5913 F.325-4502
石東(石東研究室) 06-871-8555 F.831-2105
◇鳴尾/後藤(大阪芸大)・石井(GU) 0798-26-7717 F.26-7367
(3/7より)
・石東(石東研究室) 06-871-8555 F.831-2105
・猿渡・岩井(西宮市) 0798-35-3526 F.36-6399
注:()は所属、 電話・FAXナンバーは作業場所の連絡先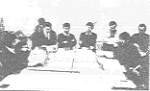
2/15・第1回連絡会議「きんもくせい」への問い合わせ集まる
当「きんもくせい」が2/18日付朝日新聞等で紹介され、 全国から問い合わせや支援の連絡が入っています。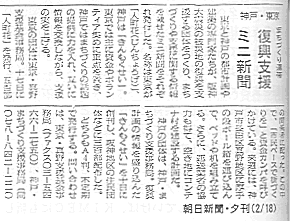
新聞切り抜き
○住所
○電話 FAX
○所属
○何かできそうなこと
下記事務局まで今すぐFAXを送って下さい。
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1029 FAX.078-803-1029
担当:児玉
 きんもくせい04号へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
きんもくせい04号へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ