復興まちづくりに関する情報提供、 投稿のお願い
このニュースは、 復興まちづくりに最前線で関わっておられる皆さんから寄せられる情報をもとに逐次発行していこうと考えています。つきましては、 皆さん大変ご多忙のこととは思いますが、 以下のような情報、 原稿をどんどん編集局宛にFAXでお寄せいただくようお願い致します。
また、 まちづくりの現場や活動の拠点に、 編集局から取材にお伺いすることも考えておりますので、 その節にはご協力のほどお願い致します。
その幅員6mの道を私はひそかに金木犀通と呼んでいた。
1月17日の20秒間に、 金木犀通の家々の大半はガレキと化している。
私達の全壊した事務所も大林組神戸支店のご好意で5日間にわたる慎重な撤去作業により、 ガレキに埋まった資料と事務機材などほぼすべてを発掘してもらった。
おかげで灯油ファンヒータの暖をとることができ、 メモ用紙やワープロを使うことが今はできる。
そして、 東隣りの印刷屋さんの倒れた2階家の撤去もせっかくもってきてもらった巨大なカニのツメ機(CATくん)を使ってはじまり、 西側の断裂した町内会長さんの家と合せて、 3棟の共同建築化を提案している。
北側の屋根瓦がすべて落ちている長屋と、 さらに背割りの北側で、 表通りに面した戸建(大半が傾いている)の街区共同建築を皆さんに呼びかけてみようと、 計画の絵をかきはじめた。
自分たちの街は自分たちで、 より堅固で愛しい金木犀通の街をよみがえらせる。
神戸の復興事業計画の大筋は激災地の区画整理事業、 住宅市街地総合整備事業を基本にした約1,000ha、 15重点地区と、 それも含めた4,000haの震災復興促進地域(東灘区から須磨区までの山麓線以南臨港地以北の市街地全域)という枠組みである。
都市空間の復興事業への対応とそれらへの「まちづくり支援(コンサルタント)ネットワーク」がほぼできた。
後藤、 長嶋、 岩崎、 環研を中心とした東部市街地、 山本、 日建、 竹中、 大林を核とした都心市街地、 山口、 北条、 環再、 OURを中心とした西部市街地、 広く地域をカバーする形での住都公団の参画も含めたプランニング支援ネットワークである(P.4のリスト参照)。
今最も必要で緊急を要する重要事はまず、 「雇用の場である産業経済復興」への総合的な取り組みであり、 そのための〈機能被害〉の実態把握を急がねばならぬ。
次ぎは「人々の生活基盤であるコミュニティ復興」への対策であり、 3番目に「都市空間の復興」である。
まさに21世紀に向けた、 〈理想都市神戸へのスタート〉であるとでも思わねば、 やってられるか。
1995年1月30日
「助けてくれ!!」という絶叫が聞こえてくる。
どうにかしてそこから抜け出してから、 瞬く間に時間がたった。
救出作業を手伝ったり、 たくさんの死体を見たり、 全滅した住宅地と燃えていく商店街の光景に呆然となったり--。
パジャマのままで立ち尽くすおばさんや老人たち。
私が住んでいるエリアは倒壊率が85%だそうだ。
気ばかりあせって、 何から手をつけるべきかなかなか判断できない。
しかし、 まずは本業の能力を生かして貢献すべきであり、 大学の住宅復興調査チームに参加して速攻仕事にとりくむ。
学外からの応援も多い。
みんなで神戸を走り回る。
いろいろと不自由な毎日であるが、 エンジンは全開。
ボルテージが上がりっぱなしなので、 落ち着いて考える余裕がない。
しかし、 住宅復興についての私の意見はとりあえず以下6点。
不正確な情報が飛び交っている。
私たちの調査からは思っているよりヒドイ状況が見えてきそうだ。
2)住宅復興には、 自助、 互助、 公助の3つのすべてが必要。
どれが抜けてもうまくいかない。
3)自助に対する資金・技術・相談・情報支援が必要。
4)互助の新しい仕組みをつくるチャンス。
まちづくり運動をやってきた地域は新しい動きが既に芽生えている。
5)公助は自治体が主体になり、 国はそこに大量の資金を投入し、 制度面で応援すべき。
6)質から量へ?避難所の生活はつらい。
とにかく大量供給という論法もわかる。
調査結果は避難所以外に行き場のない住民が多いことを示している。
数年間はそれなりにキチンと暮らせる場所を迅速に準備し、 それに平行してみんなが協力して住まいと暮らしを復興していく両面作戦が必要だ。
私は灘区に下宿していたが、 この強烈な地震を前に木造の文化住宅はひとたまりもなく、 ゴォーという地鳴りとともに起こった強い揺れで目を覚ました瞬間、 ベッドから振り落とされ建物の下敷きになっていた。
一瞬何が起きたか理解できず、 息苦しさと暗闇の中、 倒壊した建物とベッドとの間にできた、 わずかな隙間でただひたすらもがきながら助けを求め声を上げた。
周囲からは同じように建物の下敷きになった人々の悲鳴や助けを求める叫び声が聞こえた。
もがいているうちに私は幸運にも何とかはい出すことはできたが、 多くの建物が倒れ、 様変わりしている周囲の様子に事の重大さを知った。
すぐ近くで火の手が上がっていたが電話も通じず、 成すすべもなくただ茫然と立ち尽くすしかなかった。
しばらくしてから消防車のサイレンが聞こえてきたが、 倒壊した建物に行く手を阻まれ火災現場に近づくことができず火が燃えるに任せるしかなかったようである。
明るくなり出してから、 あちこちで建物の下敷きになっている人々の救助が近所の人々によって行われ出し、 私も手を貸したが中には既に息を引き取っている人もあり、 自分も紙一重のところで助かったことを知り恐怖にふるえた。
関西には地震はないと信じていた、 私を含め多くの人々の甘さと行政の対応の遅れが今回のような大災害をもたらした一因であったと思うが、 今回の教訓を生かし震災に強い都市・街づくりを目指し、 一日も早い復興を望む。
P2
事務局で判断して、 かなり確度の高い新聞情報を選んでおります。
・今後5年間で恒久的に住める8万戸を建設
P.3
この事実を、 建築学会都市計画部会、 都市計画学会等の関連諸機関では深刻に受け止め、 建物の被災状況について近畿圏の建築系大学が合同で調査を行い、 その実態を把握することになりました。
調査は、 被害の大きかった神戸市、 芦屋市、 西宮市、 宝塚市、 尼崎市、 伊丹市、 及び淡路島、 大阪府下を対象に、 各大学の学生を動員し、 また東京をはじめ遠方からの応援部隊もかけつけるなかで2月1日(〜10日)から行われています。
各調査員は、 住宅地図を片手に、 建物の損傷度を全壊、 半壊、 部分破壊、 被害なしの4段階で評価して記録し、 持ちかえった後2,500分の1の地図に色分けして整理しています。
この調査により、 建物の被災状況の全貌を明らかにするとともに、 今後の復興計画を検討する上での基礎資料として活用されることをねらいとしています。
「きんもくせい」とは密接に関連しあっ
情報提供、 投稿の募集
その他、 どんな情報、 原稿でも結構ですので多数お寄せ下さい。

事務局北側の通称“きんもくせい”通り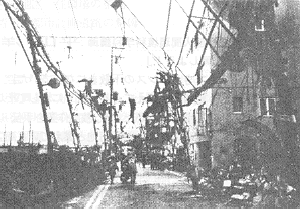
火事で消失した鷹取商店街周辺)
阪神復興に向けて―「きんもくせい」から「じんちょうげ」へ─
まちづくり株式会社コー・プラン 代表 小林 郁雄 「震災2週間の神戸から」
私たちの事務所のあった通りは、 何軒かの家の小さな前庭に金木犀が植えられて、 秋になるといっせいにその金色の小さな花々と匂いにつつまれる。神戸の住まいを復興しよう!
神戸大学発達科学部人間環境科学科講師 平山 洋介
気がついたら倒れてきたタンスの下敷きになっていた。
1)住宅被害の速攻解明。
私たちの経験の共有を無駄にせず、 以前よりもすばらしい住まいと街を作っていきたい。神戸大学工学部大学院環境計画学専攻 今富僚二
1月17日の未明、 淡路島北を震源とした強烈な地震が神戸・阪神間を襲った。
阪神復興に向けたとりくみ―新聞情報より
現在神戸市などからの広報機能がマヒしており、 マスコミ関係の記事はトップニュースでも、 かなり確度の低いものが多く見られます。神戸市
震災復興に向けた基本方針を発表 -「神戸新聞」他2/1-
○2月末をめざし計画と事業手法の都市計画決定を行う
○「震災復興緊急整備条例」の制定・2/15に神戸市議会に提案
-土地区画整理事業、 市街地再開発事業、 地区計画を想定した建築基準法第84条(被災市街地における建築制限)の指定-6地区(→下図参照)、 建築制限の期間は3/17まで
○「震災復興住宅整備緊急3カ年計画」の策定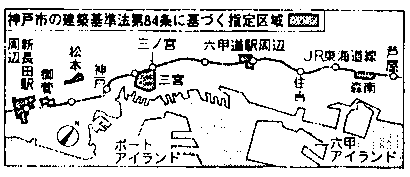
図・神戸市の建築基準法第84条にに基づく指定区域)復興計画検討委員会設置へ -「神戸新聞」2/1(加筆修正)-
○2/7に設置
○3月末までに、 都市防災、 都市計画、 交通、 経済、 心理学、 医療等の様々な視点から復興計画のガイドラインを作成
○テーマ:・災害に強い都市づくり
・都市基盤の総合的整備
・協働によるまちづくりの推進
・安全都市基準の設定
○分科会により作業:
・都市基盤検討分科会(主務:安田丑作)
・市民生活検討分科会(主務:盛岡 通)
・安全都市基準検討分科会(主務:室崎益輝)
○具体的な復興計画づくりはガイドラインを受けて、 「神戸市復興計画審議会」を設置し、 6月に「神戸市復興計画」を策定「震災復興緊急整備条例」の概要が明らかに-「読売新聞」2/5(加筆修正)-
・目的:災害に強い市街地の形成と良好な住宅の供給
・適用区域:東灘区から須磨区に至る4,780ha
-建築確認申請の30日前に建築内容の届出を義務づける
・新たな重点復興地域の指定:先に指定した6地区に加え、 新たに7地区を指定 …合計13地区、 約1,200ha(神戸市街地の5分の1)
-市長が防災に関するアドバイスや共同化の要請など、 地域整備の目標に沿った建築への指導ができる
1)西須磨地区-街路事業
2)大道地区-住宅市街地総合整備事業
3)真野地区-総合住環境整備事業
4)兵庫駅南地区-住宅市街地総合整備事業
5)神戸駅周辺地区-住宅市街地総合整備事業
6)東部新都心地区-土地区画整理事業
7)六甲東地区-住宅地区改良事業西宮市
2地区で建築制限を実施 -「朝日新聞」2/1-
○以下の2地区で土地区画整理事業を実施
・西宮北口地区:約36ha・香櫨園市場周辺地区:約11ha
○2/1に復興本部を設置芦屋市
震災復興基本方針を示す -「朝日新聞」2/9-
○2/8震災復興本部を設置
・都市整備、 公共施設整備、 生活福祉、 資金計画、 企画調整の5部をおき、 6カ月以内に復興基本計画を策定
○4地区の復興事業案を示す
・中央地区、 西部地区:土地区画整理事業→建築制限を実施
・JR芦屋駅南地区:市街地再開発事業・若宮地区:住環境の整備
○未着手の都市計画道路の整備〈宝塚市〉
震災復興基本方針を示す -「朝日新聞」2/9-
○重点復興地域の指定:約32.1ha
・仁川駅周辺地区:市街地再開発事業
・売府神社駅前地区:市街地再開発事業
・花の道周辺地区:市街地再開発事業の検討
・JR中山寺駅前北側地区:地元住民の意見集約により検討
復興まちづくり支援ネットワークの活動
神戸復興に向けたコンサルタントの動き
[東部市街地まちづくりコンサルタント支援ネットワーク]
総括/後藤(GU計画研究所)06-881-3815 F881-3816/030-920-0160
東灘区/長嶋(都市調査計画事務所)078-453-6378 F413-1140
灘 区/細野(コー・プラン)078-842-2311 F842-2203
協力:岩崎(UR神戸)078-821-8761 F821-8764
佐藤(市浦都市開発)06-361-8480 F361-8788
◇深江 ◇岡本 ◇新在家/後藤(GU計画研究所)
◇味泥/久保(久保都市計画事務所)06-364-6584 F364-1254
◇桜口/中川(RIA)06-312-9154 F314-2660
[中央市街地まちづくりコンサルタント支援ネットワーク]
総括/山本(地域問題研究所)0798-64-1106 F64-4889
鎌谷・井口(竹中工務店)06-252-1201 F538-5489
三谷・萩原(大林組)06-946-4430 F946-4767
中川・柏原(安井建築設計事務所)06-943-1371
安田研究会(神戸大)078-803-1008 F803-1052
白国(環境再開発研究所)078-242-3900 F231-1361
◇元町/高田(COM)、 荒巻(OUR)06-243-1002 F243-1006
[西部市街地まちづくりコンサルタント支援ネットワーク]
総括/山口(山口研究室)0727-81-3243 F84-9177
兵庫区/辻(環境緑地設計研究所=ELD)078-392-1701 F392-1576
長田区/岩崎(UR神戸)
須磨区/上山(コー・プラン)078-842-2311 F842-2203
山本(地域問題研究所)
山口(山口研究室)0727-81-3243 F84-9177
協力:北条(アーバンプランニング研究所)
鈴木(OUR)06-243-1002 F243-1006
三好(PPI)06-949-0901 F949-0902
◇新開地/吉田(COM)06-624-2321
◇湊川/齊木(神戸芸工大)078-794-5031 F794-5032
◇浜山/細野(コー・プラン)、 辻(ELD)建築学会、 都市計画学会合同による建物被災状況調査
今回阪神地域を襲った直下型大地震により、 住宅やオフィスビルなど非常に多くの建物が倒壊や焼失するという結果となりました。[建物被災状況調査に参加している大学等]
神戸大学、 大阪大学、 大阪芸術大学、 神戸芸術工科大学、 京都大学、 近畿大学、 大阪市立大学、 京都工芸繊維大学、 コー・プラン、 都市調査計画事務所、 GU計画研究所、 石東研究室、 水谷ゼミナール有志、 全国各地からのボランティア多数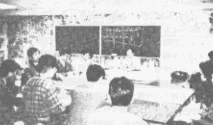
1月30日 西宮市作業室での調査打合せ
※東京の後方支援ネットワークとして、 ニュース「じんちょうげ」が、 バレンタインデ(2/14)を目指して発行が予定されている。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
て発行を予定しているので、 全国ニュースはそちらへも連絡・アクセスされたい(連絡はFAXで! 03-5466-2750)。
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20 まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203 担当:天川、 中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1 神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1029 FAX.078-803-1029 担当:児玉
 きんもくせい2号へ
きんもくせい2号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ