震災復興支援からまちづくり支援へ
-これから本当の市民まちづくりははじまる
まちづくり(株)コー・プラン代表 小林 郁雄
阪神大震災復興市民まちづくり支援ニュース『きんもくせい』は50号をもって、 ひとまず終わりとします。 「50号まで、 もう1年は歯をくいしばってでも続けます」と昨年3月の第25号で書きましたが、 あまりシャカリキになることもなく、 すでに確立したステイタスのおかげか、 多くの筆者から自主的かつ積極的に原稿をお寄せ頂き順調に発行を続け、 半年遅れにはなりましたが終刊号を迎えることになりました。 被災地中心から〈復興市民まちづくり〉に関する最も新鮮な地域にねざした専門情報を、 直接全国に伝えるという『きんもくせい』の使命はとりあえず完うしたと思います。
震災2年半を経て、 被災市街地を満たしているのは復旧復興に対する急速な忘却です。 私たちネットワークの主要課題も〈震災復興〉支援から〈まちづくり〉支援に重点が移っていますが、 いずれにせよ立脚点は〈市民〉にあり、 これから本当の市民まちづくりがはじまると考えています。

地震直後の「きんもくせい通り」。
西側からみる。 (創刊号.'95.2/10)

1年2ヶ月たった「きんもくせい通り」。
東側からみる。 (第25号.'96. 3.11)

現在の「きんもくせい通り」。
西側からみる。 ('97.8/8)

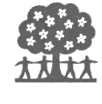
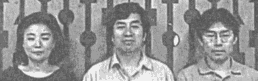
新しいコープラン事務所と編集部顔写真/天川、 小林、 中井
震災後のこれまで2〜3年間を復興復旧段階とすれば、 これからの1〜2年を、 私は『復興リハビリ段階』と考えています。 第2次復興、 復興回復段階といっていいかもしれません。 突然交通事故のような災難に遭遇して足を骨折し、 どうにかギブスがとれた段階が2年半の現在とすれば、 直ちに正常社会復帰は無理で、 しばらくは歩く練習から始めるリハビリテーション期間が必要です。 外見上は旧状に復していても、 硬直した筋肉、 心のキズ、 淋しい〈ふところ〉は見た目わかりません。 つらそうな表情から理解してほしいなア、 といったところでしょうか。
復興リハビリ段階(復興回復期)の課題は次の5つであると考えています。
読者・執筆者の皆様のますますのご支援と、 ネットワークの平常時に向けた変身にご期待ください。 (970820記)
p2
グリーンサミットでも紹介したように、 阪神グリーンネットでは各地からの支援を得て、 草花や樹木の苗を被災地に配布したり、 生け垣づくりなどの実践を通じて被災地にみどりが根付く運動を行ってきました。 どちらかと言えば、 イベント的な活動が主でありましたが、 96年の後半より、 地元からの依頼を受けたみどりのまちづくり活動もできるようになってきました。
阪神グリーンネットもこの地域の区画整理事業に伴って計画される街区公園(500平米程度のものが4箇所)の一つを例にとって、 公園づくりへの住民参加への取り組みのひとつとして、 一日ワークショップを行いました。 天気は快晴、 参加者は約40名ほどで、 最初はワークショップの歌を披露したりしながら和気あいあいとゲーム形式で公園のイメージを出し合い、 その後、 各テーブルに分かれて、 それぞれの意見をまとめた公園の模型を作りました。 思いをこらした公園模型の出来映えはなかなかのもので、 住民が楽しみながら公園づくりを考えた一日となりました。
深江地区の取り組みで、 阪神グリーンネットでは初めて、 遊休地(神戸市の高架事業用地)を利用した広場づくりに取り組みました。 緑化フェアに向けて、 5月末にはこの広場をまちづくり協議会に協賛する形で完成させています。 広場の名前はまちづくり協議会で検討した結果、 「深江駅前花苑」と命名されました。
6月の上旬には、 沖縄各地からのみどりの支援に対する那覇市役所での報告会と、 各地へのお礼の訪問を済ませました。 私達はそこでさらにまた、 グリーンネットの活動が全国的な支援の輪を広げたり、 連携を深めていけるのではないかという希望を抱きました。 イベント的な活動も続けながら、 今後はみどりのまちづくり活動を中心に展開していきたいと考えています。 まちづくり協議会や地元住民から直接の依頼を受けたり、 行政あるいは都市計画等のコンサルタントとの協働の活動も行っていく予定です。
他の分野-それが都市計画であれ、 建築であれ、 またよりソフトな形での復興の要因であれ-との連携なくしては、 みどりのまちづくりもあり得ません。 住民の理解と意欲も必要になります。 各地からの支援も大切です。 さまざまな前進に向けて阪神グリーンネットではこれからも息の長い、 NPO組織としての活動を続けて行くつもりです。
今後とも皆さまの理解と連携を、 是非ともお願い致します。
p3
神戸市営コレクテイブハウジング・真野ふれあい住宅の入居予定者たちによる「入居前協同居住の学習・体験の懇談会」がスタートした。
真野ふれあい住宅の入居予定者(28世帯 43人、 1住戸未定)は次のようである。
高齢者住宅 1DK: 15人 平均年齢 78歳
10時半から、 真野ふれあい住宅協同学習等運営委員会の専門サポーターと学生サポーター(30名弱)で進行の打ち合わせをする。 入居予定者の年齢を見ると、 後期高齢者が圧倒的に多いので、 ワークショップ(以下WSと記す)のプログラムはあるが、 参加者の顔を見て臨機応変に対応しようということを確認した。
WSは1時半の開始だが、 12時半にはもう一人がみえた。 須磨区の仮設住宅からタクシーを利用して来られたとのこと。
1時すぎには数名が到着。 お年寄りの到着は早いわ。
主客続々到着。 介添えボランティアに連れられた人、 歩行車を押しての人、 3〜4人で連れもっての人、 杖をついた人、 おめかししていらした人、 ・・・・
すぐに20名ほどになり、 会場の前方に並べた椅子が埋まっていく。 グループ応募組は固まって座り、 個人応募組は後寄りの離れた席を選ばれる。 真野ふれあい住宅は5グループの応募があり、 4グループ(19世帯)が当選した。 あとの10世帯は個人応募である。
来場者の中に数人の顔見知りがいる。 コレクテイブハウジング事業推進応援団が仮設住宅へ出前説明会に出かけた時会った人、 真野ふれあい住宅の計画づくりWSに参加していた人、 仮設住宅に花の苗を植えに行った時ご一緒した人たちだ。 そのひとりに元気なおばさんがいた。 「えっ!当たったの。 よかったねー。 」と声をかけると、 「そう、 そう、 わたしらみんな当たったんよ。 うれしいわー。 」と、 両手でわたしの手をギュッと握ってきた。 そして、 自分の椅子の半分を開けて「ここ座って」と。
入居予定者は3世帯が欠席で25世帯26名、 それに40名程のサポーター、 神戸市住宅局建設課と管理課の職員、 見学者と報道陣等の総出80名ほどでWSは開会した。 神戸市の若手職員が作成した住宅1階の協同スペースの1/30模型は、 なかなかのものである。 まず、 家主の管理課長のあいさつ。 「全国で初めての試みの公営コレクテイブハウジングは入居者の方々がモデルとなるような新しい住まい方を築いてほしい。 そのために入居前懇談会を、 来年1月入居までに何回か開きたい。 今日のプログラムはサポーターに任せる」ということで、 WS運営委員にバトンが渡された。
続いて、 サポーターの紹介、 コレクテイブハウジングの説明と進み、 コレクテイブハウジングの住まい方イメージを膨らませるためのスライド会に入る。 ここまで運営委員主導で進み、 少し場の雰囲気に馴れたところで、 誕生月順に輪になって座り自己紹介に移る。
輪になって座れるようにサッと椅子を並べかえようとしたが、 ちょっと待って! 立ち上がりが困難で移動がスムーズにいかない人、 誕生月に関係なく知り合い同士座ってしまう人、 トイレにたってなかなか戻って来ない人……。
誕生月と名前の自己紹介は進み、 その座順から5グループに別れて、 テーブルに移動した。 1テーブルは4〜6名の主客とほぼ同数のサポーターが座った。
さぁ、 ここから本番。
真野ふれあい住宅は工場の中にあるので、 緑をいっぱい育てたい。 協同室は図書館み
たいに本があり、 くつろげるものにしたい。 リラックス協同スペースを願う。
共益費のことが一番心配。
入居前に集いをもち、 心がふれあい、 新しい暮らしへの不安を和らげ、 希望を育んでいくことのすばらしさを実感した。 集団の中に40、 50代、 60代前半の若い人が混じると、 その人数の2倍も3倍もの活気が感じられる。 後期高齢者が多いが全体として元気な人が多く、 80歳をこえても気力があり、 新しい生活に夢を抱いておられる。 生活術を身につけた生活達人が揃っており、 園芸、 料理、 大工、 歌、 踊り、 語り部の役者も多く、 楽しい協同生活が展開されそう。
多世代が住み合うこと、 グループ入居制度を採用したこと、 入居前の協同居住の学習・体験等の生活サポート体制をもったこと等々は、 これまでの公営住宅供給システムの大きな変革であり、 神戸市にエールをおくりたい。 コレクテイブハウジング事業推進応援団もここまでくるのに、 いくつもの関を越えたような感がある。 帰り際、 「楽しかった!うれしい!」と、 ひとりのおかあさんが抱きついてこられた。 もっともっとたくさんの人が今日の笑顔をもてるようコレクテイブハウジングを増やしていきたい。 つらい体験をしたんやから、 みんな一緒に幸せになろう。 そのささやかなサポートをわたしたちはします。 (7月8日記)
震災以降の築地のまちづくりの経過を整理すると、 第1段階〈まちづくりという場づくりと大目標設定〉では、 まちづくりの必要性の確認からまちづくり案の検討・作成、 また具体化事業の仕組みの理解をおこない、 第2段階〈まちづくりを実現する事業の枠組み設定〉では、 改良住宅入居条件や減歩率など事業実施条件をめぐっての協議や要望などのやりとりを重ねた。 そして、 現在は、 区画整理事業の仮換地指定を目指して施行者サイドで種々の準備作業が行われている。 この間、 すでに各事業は事業用地の買収、 また改良住宅第1期建設工事というかたちで動き出しており、 区画整理の先行工事部分ではすでに移転補償交渉も進んでいる。
このようにまちづくり事業が具体的に進むにつれ、 いったん組み立てられた事業の枠組みにどう個別権利を納めていくかという事業者サイドの動きを軸とした個別交渉のウェイトが大きくなる。
もとより、 「まちづくり」は、 多様な人の生活の場づくりであり、 地域での生活を媒介にした人と人とのコミュニケーションづくりであり、 その場所づくりである。 そのプロセスの中から、 あたらしい「まち」を生きたものにする力が出てくる。 震災被害からの住まいなど生活の場の再建が「個人個人で出来ないまでの状況になってしまったから皆でやるしかない」を出発点にして、 城下町築地の復興をめざすまちづくりは始まった。 補償金等をめぐる個人個人の交渉事、 これはこれで精一杯やる必要がある。 そういった中で復興委員会としては、 事業の枠組みに納まらないことを集約し、 必要であれば枠組みの修正を提案していかなければならない。 しかし、 これに終始していたのでは、 だれも疲れるだけで面白くない。 疑心暗鬼とギリギリした雰囲気がまちを被い、 広がる事業用地に草が茂る。
お隣りや家族で連れだって来られ、 「あぁ、 そやった、 この橋渡ってこの道通って小学校に通ったんや。 ここに誰々さんが住んだはって…」などと写真の前で昔話しに花が咲き、 「ふーん、 こんな風になるの」と模型の前で感心(?)しあったり、 子供は模型に手を付けてみたくてしようがない様子。 このような場面をこれからも数多くつくり出すことによって、 まちの記憶が伝えられ、 あたらしいまちを生きる力が育っていくことを期待したい。 整理された写真などの資料は、 これからのまちづくりの記憶とあわせて、 新しい地区施設に展示・保存され伝えられていくだろう。
現在は、 事業用地を利用した仮設子供の遊び場と老人のゲートボール場づくり、 新しい地区施設のイメージや交通規制のありかたについて検討を進めている。 また、 来年4月の仮換地指定スケジュールにあわせ、 狭小敷地が多い条件を逆に築地らしい町並みをつくる契機としていくための検討などを持家分科会中心に進めつつあり、 これらの成果は、 いずれまた「まちづくり展」というかたちで、 皆の目に楽しいかたちで公開・報告していくことにしている。
「芦屋シーサイドテニスクラブ」と「港まち神戸を愛する会」この2つの人間関係から人生進路が大きく変わったともいえるけれど、 この度ほど人間関係が財産であると感じたことはなかったように思います。 2年と半年が経ち、 その間にも多くの濃い人間関係がうまれ、 それらが相乗効果的に新たな出会いを引き寄せる状況になっています。 収入は相変わらず安定しませんが、 人間関係(ネットワーク)の財産は確実に増えつつあります。 まだ震災復興ドラマの第1部の前半が終了したところです。 多くの出会いを仕掛けてくれた「きんもくせい」に感謝しつつ、 後半に向かいたいと思います。
ところが、 震災以後、 都市計画のプランナーの情報誌やネットワークに、 こともあろうに医者やボランティア、 おまけに民俗学者までが顔を出した。 個別分断消費社会から、 個を認めた上でのふれあい、 連帯を求める都市人のめばえを予期させる様々なまち協やコレクティブ、 復興塾の活動、 白地での建築家の活動、 公営住宅の入居事前ワークショップ・・・、 ともに悩み考えた。
震災復興が閉塞状況の今日でも、 我々は不思議と挫折感を感じない。 困難な中で、 ともに生きる故郷を作る作業の不思議な充実感、 専門職・職能のやりがい。 インターディシプリンがつながる幸福・・・・。
柳田は昭和初期、 全国の郷土調査の人員を動員して、 海村や山村、 千地区を調査し、 『海村山村生活の研究』を著した。 その調査項目の最後の第百項目には「しあわせの村はありますか」と書かれている。 ところが、 その結果を取りまとめてみると「幸せの村などどこにもないようである。 村には幸福なことより不幸なことの方が多く記憶されていた」となった。 近代初期の村とはそういう崩壊過程にあったのだ。
同様に、 近代の都市にも、 幸福な町などないのかもしれぬ。 どこも、 個人の利害対立ばかりで、 遅々たる歩み、 いらだつことばかり。 しかし、 我々の模索する傷ついた故郷を、 それぞれの職能で関わりつづけたネットワークの3年間は、 闘争過程と困難な状況を持ちつつ、 振り返れば、 不思議な幸福感をもって今日に至っている。 これは近代の終焉だ。
我々は、 故郷の村や家・墓を引きずり、 個別の欲望で成り立つ近代都市とは異なる、 新たな生き方へ「きんもくせい」によって導かれたのではなかろうか。 個人の職能に基づくエゴイスティックな生き甲斐ややり甲斐が、 集団としての地域や都市の心地よさと連動していくような、 ポスト近代の都市人発見の過程である。
月移り星変わり、 百千年の果てまでも、 旅人はこの「きんもくせい」の幹にもたれ、 香りにふれ、 編集者、 中井豊さんの努力をしのぶことであろう。
p7
復興市民まちづくり支援ネットワークの構成員の中で、 私が比較的よくパソコン通信を仕事やホビーで利用していたこともあり、 通信ネットへの掲載担当を申し出た。 当初は、 事務局からフロッピーディスクで届いたテキストファイルを加工していたが、 最近では事務局から直接テキストファイルが電子メールで送られてくるようになった。 各号が7,500〜8,000文字、 ファイル容量にして約20〜25KBである。 単純に計算して創刊号から49号までで、 約38万字、 1200KBほどである。 フロッピーディスク1枚におさまる量である。 これらは、 創刊号から40号まではすでにFCITYのライブラリに登録してあり、 残りの10号分も本号の整理がつき次第登録する予定であるので必要な方はダウンロードして利用してほしい。
なお、 FCITYでの震災復興への取り組みについては、 フォーラムの責任者である太田守幸氏が「都市計画#200、 201合併号、 1996」に報告されているので参照されたい。
こんなつながりで、 被災地と遠隔地の橋渡し的な役割も果たすことができたし、 個人的なネットワークが広がったこともある。 このように、 パソコン通信を通じてより多くの人々に情報を公開、 発信するとともに双方向の情報伝達ができることで、 一つの情報がきっかけとなってよりダイナミックな関係に発展するといったことも経験した。
このほかにも全国で多くの市民まちづくり活動にパソコン通信が利用されていると聞いている。
今後は、 連絡事務、 日常の情報交換、 一定テーマに対する議論など多方面にわたる通信利用が拡大し、 有限の時間をお互いに有効に利用することをめざしたい。 (7月9日記)
あの時の都市計画決定の是非は相変わらず分からないのだが、 一つ確実に分かったことがある。 それは、 まちづくりだ、 参加だと言っても、 そもそも人びとに通じる言葉を都市計画なり、 都市計画サイドからのまちづくりが持っていなかったということだ。 マスコミの一方的な、 センセーショナルな取り上げ方をあげつらうのは簡単だが、 いざと言う時に、 批判するにせよ、 もうすこし適切、 本質的なところからしてくれる人びとを育てなかったのは、 怠慢以外の何者でもない。
インターネットに開いたホームページも、 1年間で2500程のアクセスで、 力不足が身に染みる。 インターネット自体の弱さもあるが、 頑張っている「すたあと長田」には15000近いアクセスがある。 中身もスタイルもちょっとマネができない。 悔しいが、 数はやっぱり彼らに任せておこう。
一方、 プロ指向ながら反響が大きかったのは、 都市環境デザイン会議の震災復興連続セミナーだった。 復興の現場で取り組んでいる人達が率直に語っていたので、 アクセス数は2000近くだが、 熱心な読者の役に立てた。
このような経験を経て思うのは、 専門的ではあっても、 真摯な情報を継続して発信してゆくことの重要さだ。
特に大切なのは、 「争い」をもっとオープンな議論に発展させてゆくことだろう。 あの都市計画決定の性急さについても、 もっとちゃんと説明して欲しい。 それができるのは、 むしろこれからだと思う。
多少はクールになった今、 経験を持ちよって、 支援のあり方、 住民や権力との関係、 ひいては都市計画とはなにかを議論し、 それを少しでも多くの人びとに正しく伝えてゆく努力をしなければならない。 そうしなければ結局、 外から垣間見る大多数の人達にとっては、 訳が分からない世界で終わってしまうのではないか。 『論集きんもくせい』に期待するところでもあり、 また自らの課題でもある。
p8
ジャンヌダルクが高く振りかざす赤い旗のように、 復興をサポートする同志を勇気づけ、 結びつけた。 そして今、 健さんを迎えた風にはためく黄色いハンカチのように、 50号めのニューズレターが結びつけられた。 いく重ものネットワークの輪を組んで。
ジャンヌダルクを担ってきた人、 健さんを迎えた千恵子さん役をつとめた人、 そして、 たくさんたくさんの心やさしい同志と事務局のスタッフに支えられて、 2年半もの間届けられた。 イタリア映画《イル・ポスティーノ》によって配達されたような連帯の便り『きんもくせい』。
小林さん、 天川さん、 中井さんはじめ阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワークの事務局のみなさん、 ありがとうございました。 たくさんの情報を送り届けた被災地サポーターの同志、 新しい舞台での再会を楽しみにしています。
そして、 わたしは“ 被災地にコレクテイブハウジングを! ”の連載11編を含め全部で13編の掲載の場をいただきました。 うれしく思っております。 イル・ポスティーノの「詩は書いた人間のものでなく、 必要としている人間のものだ。 」という台詞に感銘して、 『きんもくせい』を拝読し、 また投稿してきました。 多謝多謝! 再見!再見!
震災による「密集住宅市街地整備促進事業」には2つの面で大きな成果がある。 一つは、 被災地で多くの密集事業への取り組みが起こったことである。 統計と推計の上からは、 通常の年間木賃住宅更新量の10年分の木賃住宅が滅失した。 これは都市整備の面では画期的な事実である反面、 従前居住者に対して失われた住宅をどうするのかの問題が生まれる。
第二は、 非都市部での密集市街地対策の事業が起こっていることである。 密集市街地対策というのは、 大都市、 木賃住宅の密集地というイメージがほとんど固定されている。 しかし、 山間の集落や漁村の密集地にも、 同様の密集市街地問題があるが、 手法の面でも行政の意識からはずされてきた感がある。 それが、 今回の震災で淡路地域の漁村集落での事業展開が図られたことにより、 今後、 非都市部での密集市街地の住環境整備に目が向けられることを期待する。
一方、 密集事業の行き先が見えてこないことも感じている。 密集市街地対策が行政課題であることは確かでも、 どこまでやれば良いのかが定かでない。 民間で作り上げてきた不良住環境ストックに公共がどこまで関われば良いのか、 やり出せばきりがないし、 不公平も生まれてくる。 県行政は、 市町の責務というし、 市町は家主と店子の問題という。 しかし、 何か行政が手を出さねばならない現状にあることは確かである。
そこで、 住民が意気に感じて「何とかしなければ」と思ってもらうための、 市町の働きかけ、 コンサルタントの活躍の場を早くつくり、 震災復興で培われた住民が自分たちの問題として行動するまちづくりの手法を援用して密集市街地対策の自主展開システムを動かしていかなければならない。
震災は、 密集市街地対策に新しい法律を産み、 被災者という名の都市の積年の課題の代表者達に課題解決の糸口を示した。 震災を受けて、 何もかわらなかったなら、 密集市街地対策は永久にできないことを肝に命じて次の展開に向かっていきたい。
これからが、 本格的な取り組みが期待される段階であり、 益々多岐にわたる様々な視点のボランタリーな活動が緩やかなネットワークでつながり、 大きな力となって長期的な市民レベルの復興に寄与していくことが願われるが、 実現は夢のようである。
95年2月以来活動を継続している東京大学生産技術研究所KOBEnetのような広い視野での橋渡し活動は「関西には馴染まない」のであろうか。
大勢の方々にお世話になったが、 震災直後の1月31日からボランタリーに活動を展開してきた「震災記録情報センター(旧称地元NGO文化情報部)」は、 事務局長が東京に戻り、 8月で解散します。
p9
1-2 市場の共同再建の支援活動について
1-3 住宅の共同再建の支援活動について
2-2 西宮市民復興まちづくり支援ネットワークの経過と今後の展望
阪神・淡路大震災の復興すまい・まちづくりは、 一年一年、 その状況課題が移り変わってきており、 私達、 地元まちづくりプランナーにとっては、 今後も5年、 10年、 15年スパンで復興との戦いは続くものと思われます。 「きんもくせい」が50号で一区切りになることはやむを得ないとして、 今後も情報提供・交換誌が必要であり、 「きんもくせい」が何らかのかたちで再生、 引き継がれることを期待しています。
今回の審査会は、 ソフトに重点を置いた団体の応募が増えたことや、 これまで3回助成を受けた団体は今回は申請していないこともあり(HAR基金の助成は復興まちづくりの立ち上がり支援ということで1団体につき3回までとされている)、 復興まちづくりの節目のようなものを感じさせました。 また、 今回は申請者が前回までよりも少な目であったこともあり、 辞退された1団体を除くすべての団体に助成が行われました。
7月19日には、 第3回助成団体の報告会及び第4回助成団体の贈呈式が長田区野田北部地区にある鷹取ペーパードームで行われました。 後半では、 野田北部まちづくり協議会の浅山会長や地元コンサルタントの森崎さんの案内により、 区画整理事業地区及び隣接する町並み誘導型地区計画が決まった現場の見学会も行われました。
2)土地区画整理と整合性を保つ細街路整備推進のため/
3)案内標識等の多言語化に向けての調査と実施/
4)須磨浦通地区まちづくりに向けた共通課題への取り組み/
5)ドングリ銀行神戸震災被災地の緑の復興活動 /
6)神戸市西須磨地区における復興支援活動/
7)住民の自主活動による地域緑化活動/緑花コミュニティ・四季/45
8)専門家・地主・住民の連携によるまちづくりの支援/
9)きんもくせいインターナショナルプロジェクト/
10)情報紙「ウィークリーニーズ」発行/
11)第4回六甲アイランドW・F・O・A・P-のぼり部門/
12)みどりと水のまちづくり阪神グリーンネット/
13)コレクティブハウジング事業推進広報活動/
14)神戸の子供たちに心の復興と紙芝居文化の伝承活動 /
15)コムステイシステムの提案と実践/
16)仮設住宅で星空映画会を/
これは、 同チーム主催の3回目のフォーラムで、 昨年6月に開催した「東灘市民復興まちづくりフォーラム」に続き、 地元まちづくり組織立ち上げをねらいとして行われたものです。
フォーラムでは、 まず小森星児・神戸復興塾長より「3年目の白地地域復興まちづくり」と題する講演があり、 「神戸の復興は10年あと戻りをするのではなくて、 我が国の10年先取りをするまちづくりである」、 「人のつながりを生かした復興まちづくりが大切」、 「神戸らしさを生かした復興の必要性」などについてのお話がありました。
パネルディスカッションでは、 神戸東部地域のまちづくり協議会の方々7名がパネラーとして参加し、 協議会発足の経緯、 自治会との関係など、 協議会運営の経験・苦心等について語っていただきました。
昨年6月のフォーラム以降、 神戸東部地域では2地区でまちづくり協議会が結成されており、 これからも結成される見込みのあるところも見受けられます。
こういったフォーラム等を契機として、 一つでも多くのまちづくり協議会が被災地に結成されるとともに、 まちづくり協議会のさらなる発展がされることが望まれています。
(このフォーラムの詳しい内容は、 「論集きんもくせい」で発表予定。 )
申し込み方法、 購読料等については以下の通りです。
●申し込み方法について
別紙申込用紙に必要事項を記入していただき、 事務局までFAXか郵送してください(申込用紙がない場合は申込用紙をお送りしますので、 住所、 氏名(法人名)、 電話番号、 FAX番号を記入していただき、 事務局までFAXか郵送してください)。
●購読料の振り込みについて
年間購読料は10,000円です。 銀行振込か、 郵便振替にてお願いします。
- 復興にとりくまれているネットワーク、 団体の方々へのお願い -
p11
「きんもくせい」にその時々の活動記録や報告を寄せてくださいましたたくさんの方々、 ありがとうございました。
'97年8月、 50号を発行するにあたり何か思い出のようなことを書こうと思っておりましたら、 偶然にも8月8日に愛知県から35,000株の花の苗を届けていただけることになりました。 '95年6月6日発行の第10号ではじめて「ガレキに花を咲かせましょう」が登場しましてから2年。 思えば被災地を彩るあの活動の最初は、 何にもなくなってしまった我が街の空地からだったのだと、 今となっては少しなつかしい思いさえしています。
愛知県一宮市の花卉業者のネットワークの方々とつながりができるきっかけは、 第10号の「ガレキ花」がもとで大阪の辻本智子さんが孤軍奮闘してくださった結果でした。 1回目は様々な色のサルビアを、 2回目はパンジーをはじめとする春の花花、 3回目は夏すみれや箒ぐさ、 日々草など、 そして今回が4回目。 そのつど30,000から40,000株の苗を提供してくださる花卉生産業者の方々や、 たった一人でその交渉をしてくださる辻本さんの変わらぬご好意は、 並大抵のことではありません。 そしてその花花は地域の人達をつないでくれる役割をしっかりと果たし、 今「茶店きんもくせい」へと姿をかえて歩きだしたところです。
8月9日から12日まで「茶店きんもくせい」のまわりは、 色とりどりの花で埋まりました。 今回は各地域のまちづくり協議会の方々にお願いして配って頂くことになりました。 はるばる旅をしてきた花たちはきっとそれぞれの場所で大きく咲いてくれることでしょう。 全く手探りで出発した「ガレキに花」でしたが、 2年半たって最初のことばどおり、 第1段階から第4段階へと進んできたことを今、 嬉しく思っています。
花に限らずいろいろな活動をみつめてきた「きんもくせい」です。 今までの姿は第50号で一応形を変えて、 まだまだ本当の被災地の姿をできるだけ全国に向けて発信することを続けていければと思っています。 いままでのように月2回ということはできません。 そしてカンパの切手だけでというわけにもいきませんが、 中身はこれまでとかわらぬ姿勢で皆々様の声を届けていきたいと思っています。 どうか、 全国の読者の皆様はもうしばらく神戸を見守ってください。 そして被災地の中で復興の真っ只中の人達はこれまで同様「きんもくせい」を活用して下さいますようお願いいたしまして、 事務局の一員としてお礼とこれからの抱負といたしたいと思います。
ありがとうございました。 そしてこれからもよろしく。
都立大の高見澤先生をはじめ10数名の方々にファックスの一次中継基地として「きんもくせい」を多くの方々に広めていただきました。 IBSの方には建設省の関係者や国会議員へもお送りいただきました。 またインターネット・ニフティへの掲載については、 学芸出版の前田さん、 環境緑地の辻さんにお世話になりました。 その他、 我々の把握できていないところでも、 多くの方々に「きんもくせい」を広めていただいていることと思います。 本当にありがとうございました。
発行し始めた頃は、 日に日にめまぐるしく変化するあわただしい状況のなかで、 高揚した気分を少しは落ち着かせながら、 とにかく我々なりに必要なことを正確に伝えたい、 被災地ではこんなことをやり始めているから多くの人に知ってほしい、 といった気持ちでひたすら「きんもくせい」を発行し続けていました。
その年の夏頃になると、 徐々に復興まちづくりの取り組みが形を見せ始め、 様々な市民レベルのネットワーク活動も盛んになってきました。 伝えるべき情報も増え始めてきました。 そして、 ネットワークメンバーの定期的な報告とともに、 復興まちづくりのなかで出会った多くの仲間たちから原稿が寄せられました。
このような2年半を通して、 “復興市民まちづくり支援ニュース”としての「きんもくせい」の役割が徐々に確立してきたと思います。 (1)地元復興まちづくりの生の正確な情報を我々ネットワークメンバーなど実際に関わっているもの自らが整理し伝え、 そのことを通して広く情報交流を行ってきたこと、 (2)即時的な復興ニュースを事務局として収集・発信しきたこと、 この二つに集約できると思います。
こういった蓄積の元に、 「きんもくせい」は新たな出発をします。 復興まちづくりはこれまでの貴重な経験をふまえ、 様々な困難を抱えながらも前進していくことでしょう。 「きんもくせい」はそういった復興まちづくりを支えるよきパートナーでありたいと考えています。 これまで同様、 あとしばらくのご支援よろしくお願いいたします。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
1:恒久住宅移住にともなうコミュニティ再生
仮設住宅などの仮のすまいから、 公営住宅など本当のすまいへ移ると同時に、 もう一度新たな近隣関係を再生創造していく時期がきている。 そのため、 始めての鉄筋コンクリート共同住宅への入居準備や事前懇親会を用意したり、 市民版引越しプロジェクトなど震災ボランティアと地域コミュニティ組織とのタイアップを進めることが必要である。 2:仮設住宅の統廃止
震災ボランティアの最後で最重要な活動となると予想されるのは、 半数以上が転出した状況になる仮設住宅コミュニティの維持であろう。 97年秋予定の第4次公営住宅等一元募集が過去最大規模でほぼ最終段階となる。 仮設住宅からの転居が98年春にピークを迎え、 その統廃合が震災復興住宅課題の最後で最微妙な段階となる。 3:震災空地への暫定対策
密集地区の接道不良宅地など裏宅地に多くの震災空地が今なおたくさん残っている。 それらは街の再建から取り残された場所ではあるが、 これからの本当の密集市街地改善の貴重な種地でもある。 建て詰まりぺらぺら工業化住宅の群れの中での、 暫定的な広場や花壇利用、 5年後の地区改善(本当の復興)用地確保のために、 復興基金を活用したい。 4:店舗併用住宅などの自主再建支援
西神戸に普通に見られるがらがらの街に、 とりあえずでも人々の生活の息吹を高めるための方策が緊急課題である。 その最も即効的な対策は、 お店を再開しようとしている人達など中間所得層の戸建自主再建への支援である。 それも資金融資や利子補給といった間接的な手段ではなく、 併用住宅などを人口激減地区に直接建設供給する支援の仕組みである。 5:復興再建をめざす地区への包括的地区助成
震災復興に限らず、 住民のための住民による地区整備の最終目標は、 整備内容までも地区の住民主体で決定する仕組みである。 それはまちづくり協議会の最終目標でもある。 復興再建をめざすまちづくり地区にどのような種別の整備かは問わず、 地区再建事業(ハードであれソフトであれ)に包括的に助成する仕組みが切望される。 それは地方主権時代の幕開けにつながる。
ランドスケープ復興支援会議
−阪神グリーンネットのこれから阪神グリーンネット事務局
(神戸芸術工科大学実習指導講師・林環境研究所) 林まゆみグリーンサミット、 その後
きんもくせい第37号では、 96年10月にフェニックスプラザで行われたみどりのまちづくりに従事している様々なグループによるグリーンサミットが報告されました。 阪神グリーンネットではその後もさまざまな活動を通じて復興支援に取り組んできました。 今回では終刊へと向かうきんもくせいの報告で、 阪神グリーンネットのこれまでの活動とこれからの方針に対する理解を得て、 今後の各分野との連携に発展させていきたいと考えています。 第1回世界鷹取祭での一日ワークショップ
96年11月には、 神戸市長田区の鷹取地区で「第一回世界鷹取祭」が開催されました。 これは地元のみならず、 世界に発信できるイベントとして各分野の協力を得た、 復興に向けてのイベントでした。 
第一回世界鷹取祭 公園づくりのワークショップ深江地区での取り組み
神戸市東灘区深江地区では、 神戸市長との間でまちづくり協定が締結されています。 この中で、 みどり関連では生け垣などの奨励が盛り込まれていますが、 より充実したみどりのまちづくりに向けて、 阪神グリーンネットではジーユー計画研究所と連携して深江地区のみどりのまちづくりに取り組んできました。 97年の6月1日にはまちづくり協議会と協力して「深江地区 花とみどりのフェア」を地区内の東灘小学校で開催しました。 1000名以上の住民が参加して、 樹木の苗の提供を受けたり、 地元の緑化材の販売店から格安で草花の苗を購入したりしました。 また同時に開催された緑化相談会にも大勢の住民が訪れています。 
深江駅前花苑淡路島北淡町での取り組み
震源地でもあった淡路島北淡町野島の大石地区の住民からは野島断層下の土地を震災記念公園的な利用にしたい意向が示され、 阪神グリーンネットに協力を求められました。 当地域は高齢化が進み、 村づくりをにらんだみどりの復興を地元住民と一緒に考えていく予定です。 行政からもそれぞれの部署での、 可能なかぎりの協力をしていくという方針が示されています。 阪神グリーンネットの今後
以上に述べたように、 阪神グリーンネットでは設立以来様々な活動を行ってきました。 みどりの効果は震災後、 広く認識されました。 これからのまちづくりの中で、 みどりや水の果たすべき役割は非常に重要です。 うるおいのある、 親しみやすい、 安全な、 そして生き物にやさしいまちづくりの要になるのがみどりの存在です。 しかし、 みどりのまちづくりは、 単独では成立し得ないものです。 住宅の復興やその他の基盤整備、 都市的機能の回復などさまざまな復興と共に考えていかなければいけない問題の一つです。
ふれあいの輪が結びはじめた感動の一日
〜真野ふれあい住宅・入居前の協同居住の学習・体験ワークショップが始まる!〜
7月1日は感動の一日だった。 「やっと、 ここまで来た!」という安堵と、 「はや、 ここまで来たの?」という戸惑いが交差する。
(被災地にコレクテイブハウジングを!/その11) 石東・都市環境研究室 石東 直子
高齢者住宅 2DK: 5世帯 10人 平均年齢 67歳
一般住宅 2DK: 6世帯 9人
一般住宅 3DK: 2世帯 9人
「なんでこの住宅に申し込みはったん?」
「この住宅でどんなことがしたいですか?」
「なにが得意ですか?」
「今、 なにか不安に思ってられますか?」などなど、 おおかた孫や子供世代にあたるサポーターから問いかけられ、 ひとり一人の思いが語られていく。 ふれあいの輪が結ばれはじめる気配を感じる。 茶話会記録から何人かの住人像を写してみよう。

元気に発言する入居予定の豊田さん

5グループに分かれた「茶話会」。
話し合った結果をみんなで壁新聞にした。
築地からの報告・2
まち計画 山口研究室 山口 憲二
計画から事業へ
事業の軌道が決まりその上を震災復興事業予算を推進力として猛スピードで進みはじめるにつれ、 ややもすればまちづくりの総合性が見失われる傾向がある。 〈ギリギリまちづくり〉と〈楽々まちづくり〉
〈ギリギリまちづくり〉と同時に一方で元気の出る〈楽々まちづくり〉を両輪としてやっていこうと、 昨年暮れに町並み施設部会と道路交通部会というテーマ部会の活動を始めた。 町並み施設部会では、 まず、 今年4月に「町並み写真展」を開いた。 地域資料館から借りてきた大正から昭和戦前の写真、 そして、 私が持っていた20年前の地区調査時点での写真と復興委員会が撮影した震災後のつめ痕残る町並み写真などを、 皆で地点別に整理し、 地図に撮影位置を示して対比展示した。 また、 築地周辺のまちの移り変わりがわかる地図や、 築地が生んだ城郭画家・荻原一青の作品のコピー、 町の角角にあったお地蔵さんの写真なども展示した。 会場中央には、 地区全体のまちづくり模型に改良住宅の建築模型を乗せ、 道路交通部会が中心に検討してきた新本町通りのイメージ模型などを置いた。 街路樹はケヤキ。 東西のまちの玄関にあたる部分に、 シンボルツリーとして松(うーん、 松はむずかしいぞ)。 舗装は、 和風を基本にして擬石張りの石畳風。 車止めや街灯のデザインもこれに合わせていくという方向で案をまとめている。 
築地町並み写真展風景('97.4)
築地地区改良住宅街区説明会
「きんもくせい」50号を迎えてのメッセージ
・50号を迎えてのメッセージが8名の方々から寄せられましたので、 ここに紹介いたします。 どうもありがとうございました。 「きんもくせい」最終号をむかえて
少し時期尚早の回想録風に遊空間工房 野崎 隆一
日を追うにつれ仕事はますますジタバタ状態に陥っているにもかかわらず、 「きんもくせい」が最終号を迎えると聞いて、 震災から一月余経ったある土曜日のことが急に脳裏によみがえってきました。 当時は、 普段の日は会社へ行きながら土日は魚崎小学校の避難所へ出かけることの繰り返しだったのですが、 被災したコープランの仮事務所へまだ行ってなかったので、 お昼前にちょっと様子を見にと思ったわけです。 久し振りに会った小林君も天川さんも元気そうで、 むしろ高揚感につつまれているといった様子でした。 魚崎地区での活動を話すと、 地図に活動エリアを書き込んだりしていたように記憶しています。 そのときに、 できあがったばかりの「きんもくせい2号」と1号のコピーを見せてもらいました。 復興市民まちづくり支援ニュースと書いてあり、 これから市民のまちづくりが始まるのかと感動したのを覚えています。 お昼過ぎに東京の林泰義さんから電話が入りJR住吉におり今から行くとのこと。 林さんとは20年振りの再会でしたが、 思い出話をする暇もなくひたすら情報を聞きました。 NPOの法制化についても中央にいる人間として被災地支援のため何とかしたいとも言われていました。 これから震災後2度目の真野行きだとのことで、 現地で行われるコンテナ仮設住宅のデモや、 東京からのボランティアの活動について相変わらずニコニコしながら語っておられました。 そのうち大阪大学の鳴海先生がやってきて、 できあがったばかりの被災地全域の建物被災マップを披露してくれたりもしました。 その場にいたのは3時間ぐらいでしたが、 なんとなく震災復興に対しての心の整理がついたように感じていました。 魚崎小学校の避難所のリーダーがたまたま10年来のテニス仲間であったと言うだけで、 「関西建築家ボランティア」とともに魚崎地区と関わり始めたものの、 この先どこまでどのようにやっていけるのか不安でもあった時期だけに、 今から考えるとあの日が一つのターニングポイントであったのかなと思います。 「きんもくせい」に立つ
大阪外大開発・環境講座助教授 森栗 茂一
昭和初期の産業化の過程で、 柳田国男は経世済民のため、 個人の内省を社会の変化と関わらせて、 世相解説をしようとした。 日本民俗学の創設である。 世相変化のなかで、 日本人とは何か。 日本の庶民の心とは何かと問い続けた。 しかし、 その後の民俗学は残存文化を文化財として採集するだけとなり、 晩年、 柳田は「日本民俗学の頽廃を悲しむ」と遺言して他界した。
まちづくりと通信ネットワーク
(株)環境緑地設計研究所 辻 信一/GHA02037@niftyserve.or.jp
1.NiftyServeへの「きんもくせい」の掲載
復興まちづくりにたずさわるかたわら、 「きんもくせい」を多くの人々に読んでもらうため、 パソコン通信サービスであるNiftyServeのFCITY(都市計画フォーラム)の震災復興特別会議室にテキスト版「きんもくせい」を掲載し続けてきた。 2.ネットワークの拡大
不特定多数が閲覧できるFCITYの会議室に掲載しているため、 被災地から遠く離れ復興まちづくりに興味がありながら情報収集が困難な人々に「きんもくせい」を読んでもらうことができた。 見知らぬ方から直接電子メールで情報提供依頼を受けたり、 個人的に被災地視察のお世話をしてさしあげたこともある。 3.パソコン通信のまちづくりへの利用
パソコン通信を利用した情報発信は、 従来の紙メディアに対し電子メディアを利用しているわけだが、 「属性や空間、 時間の制約から開放されて論議や情報収集ができる」(前出太田氏による)という特性があり、 多くの分野での共同研究から同好会的なサークル活動にまで利用されている。 神戸まちづくり協議会連絡会では、 会員である39団体の内20協議会にパソコンを設置し、 それぞれがホームページを作成するとともに通信連絡にも活用していこうとしている。 また、 神戸復興塾ではNiftyServeのPATIOサービスを利用して非公開の会議室を設け、 情報伝達や意見交換に活用している。 『論集きんもくせい』への期待
(株)学芸出版社 前田裕資
(1)3月17日
毎日のように続いた震災報道の最後の華は、 都市計画決定の無情さへの抗議の嵐だった。 それまで、 「環境デザイン」とか「歴史」「環境」といった視点から本を編集していた僕は、 なんとなく良いことをしていると自負していたのだが、 嫁さんまでもが「何でこんなことをするの。 本を作っているのだから、 分かるでしょ。 説明してよ」と攻めたてる始末である。 (2)真摯で継続的な情報発信を
そのような意味でも、 情報の流通には大きな役割があるはずだ。 そんな思いもあって取り組んだ合本『復興市民まちづくり』も8号にいたっては500部である。 一部には好評で、 確かにあそこから何かを読み取ろうと頑張っている人もいたし、 仕事として解読に取り組んだ人もいた。 しかし、 相当燃えている時でないと、 とても読み解く元気は出ない。
連帯のニューズレター『きんもくせい』ありがとう! 再見!
石東・都市環境研究室 石東 直子
震災の20日すぎから届けられた黄色いレター、 『きんもくせい』。 行政/震災/密集市街地
兵庫県都市住宅部市街地整備課 難波 健
私の体験した震災後の行政活動は、 芦屋の被災地パトロールから始まった、 1月19日のことである。 危険な建物に注意を喚起するアナウンスのコピーを貼ってまわるのが任務だったが、 むしろ人心の安寧のために兵庫県の腕章をつけた建築の相談員が巡回していることに意味があったような気がしている。 次いで、 一時避難所の巡回、 応急仮設住宅建設の進行管理、 そして4月から住環境整備の事業に関わることとなった。 「きんもくせい」最終50号への寄稿文
震災記録情報センター 坂本 勇
震災から2年半の歳月を、 風化・忘却の流れと感じる方も多いであろうが私ども、 「震災記録の収集保存ネットワーク」「歴史的・文化的アイデンティティの復興」「被災された方々の思い出捜し」など精神面や“明日のこと”に重点を置いて関わってきた者には、 むしろ日が経つにつれて気づかされ、 取り組みが始まることも多々あり、 この2年半は混乱した「序幕」のような気持ちであった。
「きんもくせい」に書き残したこと
ジーユー計画研究所 後藤 祐介
「きんもくせい」は、 今回の阪神・淡路大震災の復興まちづくりに関する貴重な情報提供誌の役割を果たしてくれました。 私も「きんもくせい」の紙面を借りて、 私の復興まちづくりへの取り組みの一つである新在家南地区についての実践を12号(H7.7)、 24号(H8.2)、 36号(H8.9)、 48号(H9.6)と定期的に報告してきました。 震災後2年半を経過した今、 「きんもくせい」もとりあえず一段落すると聞き、 残念に思っています。 それは、 新在家南地区の報告について言えば、 60号の時期を目標に成果をまとめ、 また報告させてもらおうと思っていたし、 そのうちに書かせてもらおうと思っていた他の事柄も沢山残っているからです。 ここでは、 その事柄だけでもあげさせてもらいます。 1.新在家南地区以外の復興まち・すまいづくりについての実践報告
1-1 他のまちづくり協議会の支援活動について
(美しいまち岡本協議会、 深江地区まちづくり協議会、 西宮安井まちづくり協議会等)
(湊川中央周辺地区市街地再開発事業、 深江北4地区共同再建事業、 二宮市場共同再建計画等)
(鹿の下地区共同再建、 深江駅周辺地区共同再建、 北口高木土地区画整理地区内共同再建)2.白地地域の復興市民まちづくり支援ネットワーク活動についての実践報告
2-1 神戸市東部市街地復興まちづくり支援ネットワークの経過と今後の展望阪神・淡路ルネッサンスファンド(HAR基金) 第4回助成団体決定
95年11月の第1回以来、 数えて第4回目となる阪神・淡路ルネッサンスファンド(HAR基金)の公開審査会が6月28日に行われ、 17団体に助成が決定しました。 活動のテーマ/活動グループの名称(代表)/助成金額〔万円〕
1)地域型仮設LSA業務のシルバーハウジングと地域コミュニティへの応用/
神戸福祉医療まちづくり研究会(上田耕蔵)/69
野田北部まちづくり協議会(浅山三郎)/48
神戸アジアタウン推進協議会(神田 裕)/34
須磨浦通6丁目自治会専門委員会(野田良平)/42
ドングリネット神戸(マスダマキコ)/74
コミュニティ・デザインチーム(吉田鐵也)/31
まち・コミュニケーション(小野幸一郎)/42
阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク(中井豊)/21
すたあと長田(和田幹司、 他2名)/27
リ・フォープチーム(郭范煌) /27
ランドスケープ復興支援会議(阪神グリーンネット)(近藤公夫)/68
コレクティブハウジング事業推進応援団(石東直子)/88
神戸復興紙芝居プロジェクト(横山忠司)/37
コムステイ実践研究会(森崎輝行)/52
仮設住宅星空映画ネットワーク(伊藤雅春)/30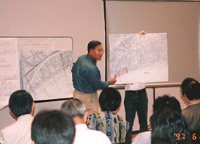
第4回公開審査会(6/28こうべまちづくり会館)
復興が進む野田北部地区の現地見学(7/19)
(和瓦が特徴的な建築中の店舗併用住宅)
神戸東部復興まちづくりフォーラム開催
神戸東部白地復興支援チーム主催によるまちづくりフォーラムが、 7月13日、 再建された神戸酒心館の酒蔵で行われました。 
フォーラム風景(7/19.於:神戸酒心館・神戸市東灘区)「論集きんもくせい」「情報きんもくせい」について
既に49号でお知らせしていますが、 「きんもくせい」は50号でひと区切りとし、 今後は「論集きんもくせい」「情報きんもくせい」として新たな出発をします。
●「論集きんもくせい」について
阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク
復興市民まちづくり支援ネットワーク
●「情報きんもくせい」について
INFORMATION
角田ナーセリーネットワークより4回目の花が届く
被災地に花の苗を定期的に提供していただいている愛知県一宮町の角田ナーセリーネットワークより、 8月9日と11日にトラック3台分、 約30,000鉢の花〜けいとう、 松葉ボタン、 ひまわり、 サルビアなど10数種類〜が届きました。 まちづくり協議会や地域緑化活動団体、 仮設住宅の支援活動をされている団体などに声をかけるとともに、 事務局周辺の近隣の方々にもお配りしました。
編集後記
2年半、 900日あまりを“震災復興に明け暮れて”来られた人々の声を集めた「きんもくせい」。 みなさまのおかげで第50号を迎えました。
〜みなさまどうもありがとうございました〜
事務局前に届いた花の苗(8/9)
Restoration from the Hanshin Earthquake Disaster/SUPPORTER'S NETWORK for community development “Machi-zukuri”
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1017 FAX.078-881-3921
担当:大西 一嘉
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ