1)安心・安全環境の形成
今回の震災において人々は日常的に使われていた公園や学校など、 近隣地区単位の身近な公共施設に避難した。いざという時の安心は、 日常生活のなかで親しまれている環境にある。
安全な環境は、 防災施設の「量」的な整備水準だけで図れるものではなく、 環境と生活の関わり方やコミュニティのあり方など、 都市生活の「質」が反映される。
日常生活のなかで親しまれる安心環境を育てるという考え方で、 地区特性に応じた安全のしくみを選択することが、 安心・安全環境の計画である。
図1は、 安心・安全環境ブロックの考え方の例である。
区画道路に囲まれた街区がひとつの環境単位となり、 街区内の通路や小広場が生活空間のアメニティであり、 また災害時の緊急避難地になる。
このような街区が緑空間によってネットワークされることで、 地区ブロックとしての安心・安全環境になる。
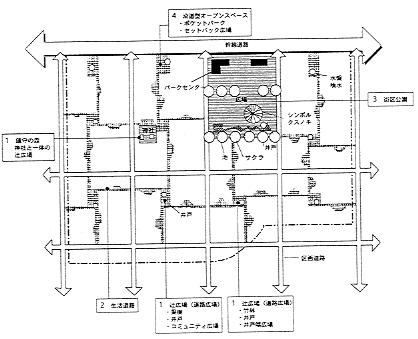
図1・選択できる安進・安全環境をめざして
2)居住環境街区
居住環境街区(図2)は、 安心・安全環境を取り込んだ街区再生のひとつの提案である。多様な住まい方の混在を、 共同空間でつないでいくことにより、 これまでの集まって住む暮らし方を、 安心できる住環境として再生しようという考え方である。
復興土地区画整理事業での復興共同住宅の位置づけや他の住環境整備の事業との合併施行など、 市街地復興は基盤整備だけでは、 生活再建につながらないことが意識されている。
それであれば、 どのような住宅が集まって、 どのような居住環境を形成するかをイメージすることで、 そこから逆に街区設計を検討することが考えられる。
第1段階として街区設計は既存の区画道路パターンを継承し、 その街区内について、 多様な住まい方を住環境として再生する計画とあわせて歩車共存型の道路や小広場を組み込む街区内基盤施設の計画を第2段階で行うことで、 区画整理地区でも居住環境を実現できる。
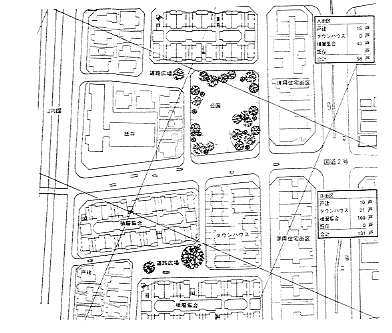
図2・住まい方と連動した居住環境の提案
3)復興カルテとプロセス・プラニング
被災地の状況は様々である。回復の程度も異なる。
地区ごとの状況に応じて、 段階を追って、 適切な対応が必要である。
そのためには、 各段階で「復興地区カルテ」を作成し、 地区の状況を診断しながら、 計画の目標を再確認し、 復興計画を進めていくことが重要である。
現段階では、 事業地区以外の一般市街地での、 接道義務における不適格など既存不適格宅地や狭小宅地での建物再建が課題になっている。
建築確認を受けないで再建が行われている状況も見られる。
密集市街地を再生しないためにも、 一般市街地での、 再建支援を検討する基礎となる「復興地区カルテ」が必要である。
芦屋を事例に再生モデルを検討したが、 そのとき3つの基本方針をたてた。
そのうちのひとつに「住み続けながらのまちの復興」がある。
これだけ大きな被害を受けた神戸・阪神間で、 住宅の復興にはある程度の時間がかかる。
しかし、 仮設住宅をはじめ、 多くの事業・制度における特別措置は2年間というものが多い。
もう少し長いプログラムの中で、 仮設的にも住み続ける方法を考えることが必要ではないだろうか。
様々な被災地の状況と回復の程度の差がだんだん顕在化してきている。
(10/5記)
p1,4
神戸南京町地区のまちづくり活動について
(株)まち空間研究所 白井 治
横浜、 長崎と並ぶ日本の三大中華街の一つで、 神戸の代表的な観光場所になっている南京町地区は、 中国の古正月を祝う春節祭の龍踊りが全国的に有名で、 東西約 160m、 南北約 110mの街区に、 中国料理をはじめ異国情緒豊かな飲食店などが多く集まっている。
昭和60年ごろには区画整理事業により、 中国風の街並みや街路の整備が神戸市の後押しでほぼ出来上がっていたが、 神戸市都市景観条例に基づく南京町沿道景観形成地区の指定(平成2年)を受け、 景観形成市民団体として神戸南京町景観形成協議会(坂東隆会長・138世帯・平成3年7月)が認定された。
地区を一層個性的で魅力的な街にしていくため、 昨年9月から協議会において地区住民や神戸市などの意見を聞きながら、 まちづくり計画を進めてきた。
震災で、 協議会活動は一時中断することとなったが、 4月から検討を再開した。
震災の被害により事業を進めやすくなった面もあるが、 6月2日の総会において総論的には地区内の合意が得られたため、 震災後のまちづくり計画第1号として神戸市への報告と支援要請(7月11日)を行った。
計画の内容は以下の通りである。
まちづくりの目標
1)「グルメ」が基本のまちづくり(中華料理に代表される多彩な異国文化とのふれあい)
2)「本物」志向のまちづくり
(本格的で本物だけが持つ存在感を生かしたまちづくり)
3)「街」ごと楽しめるまちづくり
(街の賑わいや異国情緒等を活かした空間づくり)
まちづくりの基本方針
1)楽しく歩けるグルメのまちづくり2)個性的な美しいまちなみづくり
3)賑わいのある異国情緒を高めるまちづくり
まちづくり計画
具体的には、 ハードな整備計画からソフトな管理計画まで多様な内容で、
1.細街路整備計画
2.8m街路無電柱化計画
3.地区ゲート演出計画
4.夜景演出計画
5.街路広場管理計画
6.街路演出計画
7.サイン案内計画
8.街路等清掃管理計画
9.賑わい演出計画
の9項目で構成している。
今後は、 向こう10年を目標に計画の実現をめざしていくが、 もうその活動にはいっている。
夜景の演出計画については、 春節祭で取りつける仮設の提灯を耐候性のあるものに置き換え常設化する検討に入っている。
8m街路の無電柱化計画については関電のヒヤリングを行い、 実現に向けて様々な課題が出されたが、 そのうちの主要な課題となっている無電柱化に伴う細街路部分の新設電柱(12本)や地上機器の設置場所(11ケ所)の検討を行っている所である。
地上機器については南京町らしい装飾を施した原寸模型を作成し、 実際に現地の設置候補場所に置いてみるなど地先の了解が得られるよう活動している。
細街路整備計画については、 神戸市の震災復旧の道路整備事業にのるよう地元分担費を確保すべく個々の会員の費用負担の検討に入っている。
このように、 南京町地区はバイタリティあふれる元気な市民により、 まちづくり計画の実現に向けて一歩ずつ進行中である。
(10月9日記)
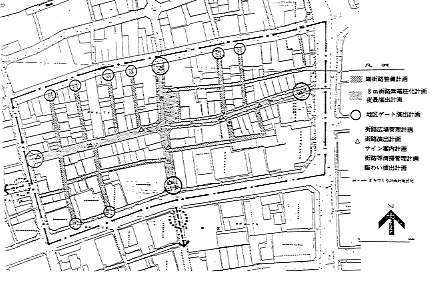
南京町地区まちづくり計画
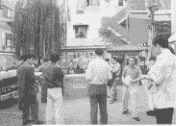
広場での原寸模型を用いた地上機器の説明会

臥龍殿での協議会の検討風景
INFORMATION
第4回・魚崎地区まちづくりシンポジウム開催される―神戸市東灘区
4月9日の第1回以来4回目となる「魚崎地区まちづくりシンポジウム」(主催:関西建築家ボランティア、 魚崎まちづくり支援研究会)が10月10日魚崎地区内の横屋会館で行われ、 地区住民や関係者約130人の参加がありました。
シンポジウムでは、 前半で関ボラがこの間魚崎地区で行って来た活動―住宅の共同再建や市場の再建など―、 神戸市から支援を受け7月より行ってきた調査の概要報告、 今後のまちづくり課題―まちづくり協議会づくり等―、 酒蔵倉地区における一提案、 を行った後、 後半では、 約1時間半、 シンポジウム参加者(主に魚崎地区住民)が発言するという形式で会が進められました。
魚崎地区では、 まだ今後の復興まちづくりを進めていく地域の主体が明確に形成されていません。
また、 魚崎地区には震災前の約半数の人しか住んでおらず、 このシンポジウムへも遠くの仮設住宅から参加されている人もいました。
こういったことから、 このシンポジウムが、 今後の魚崎地区の復興まちづくりの一つの機会になればということから、 住民の方々に語っていただく場を長時間にわたって持つことになりました。
魚崎地区は、 いわゆる“白地地域"で、 自力復興を余儀なくされている地域であり、 重点復興地域(特に事業区域)で行政の支援によりまちづくり協議会が徐々にできている状況に比べ、 立ち遅れはいなめません。
住民、 行政、 専門家が協力しあった復興の取り組みが求められています。
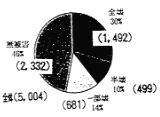
建物被害の状況
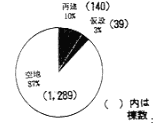
再建の状況

第4回魚崎地区まちづくりシンポ
連続映画祭・第1回「連帯せよ!復興市民」
第1部映画「人間のまち、 野田北部・鷹取の人びと」、 「20年後の東京」
第2部シンポジウム
「震災復興、 市民の連帯をめざして」 場所:神戸朝日ホール
日時:11月4日(土)13:00〜17:00 入場料:1,000円+500円(青池監督カンパ)
主催:港まち神戸を愛する会
今回の震災で大きな被害を受けた野田北部の鷹取地区で地震直後から倒壊した建物と再生へ向かう人々の姿をビデオで撮り続けてこられた青池憲司監督の「映画を見る会」を開催することになりました。
第1作は1月下旬から3月中旬までの焼け落ち、 野ざらしのガレキや倒壊家屋が道路をふさぐ映像が状況説明なしに続きます。
我々にとっては非常につらい光景ですが、 『直後の原風景を語らずして立ち上がろうとする人達の気持ちは伝わらない』との監督の気持ちです。
10月8日に山形で開催された '95国際ドキュメンタリ映画祭でも多くの方々に強い印象を与えたようです。
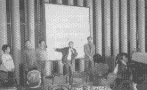
地元の鷹取カトリック教会で行なわれた映画会(10/5)
そしてそれはここに限ったことではではなく、 震災地のどこでも見られた現象だと思う。
震災地の人々を励ましに来たつもりなのに、 励まされているのはわたしの方だった。
そのことに気づいたとき、 この人々の新生の町の復興を撮りたいと思った。
3年後になるか5年後になるか、 この人達がつりあげていく「まだ見ぬ街」をみんなの傍らでわたしも見たいと念じている。
」(青池憲司氏談)
広原盛明氏(京都府立大学学長)の講演及び、 小原嘉文氏(まちづくり市民財団理事長)、 斎藤浩氏(大阪弁護士会)、 鳴海邦碩氏(大阪大学教授)、 安田丑作氏(神戸大学教授)、 垂水英司氏(神戸市住宅局参与)の各パネラーによる討論が行われ、 事業区域以外の住民主体のまちづくりをサポートする専門家の役割の重要性について多角的に語られました。
詳しくは各銀行まで
絵のデザインは和田誠さんです。
価格は1,500円+α(カンパ)。
お問い合わせは事務局まで。
日時:10月28日(土) 14:00〜17:00
これまで東部市街地連絡会(灘区、 東灘区)として、 重点復興地域(灘区が多い)もそれ以外の地域(いわゆる“白地地域”)も同じテーブルで検討してきましたが、 “白地地域”は自力復興にまかされており、 復興がなかなか進まない状況であり、 そのエリアが多い東灘区の復興を別途検討する必要性が出てきました。
第1回会合では、 他地域の復興の取り組みや今後の課題について討論しました。
〈会議メンバー〉
かじわらまち工房、 都市調査計画事務所、 地域問題研究所、 いるか設計集団、 神戸大学工学部重村研究室、 遊空間工房、 大阪大学工学部加藤研究室、 長大、 ジーユー計画研究所、 コー・プラン、 神戸市関係―都市計画局計画課土地利用係、 アーバンデザイン室推進係、 住宅局住環境整備部東部整備課、 東灘区まちづくり推進課
好評により「vol.3」を発刊します。
今回は8〜10月末までの分を掲載します。
概ねのページ数を確定する必要がありますので至急事務局までお送りください(最もきれいな原稿)。
最終は、 11月5日必着分までとします。
■連絡先:阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
P.4
HAR基金発足記念シンポ開催
9月28日、 兵庫県民会館において「阪神・淡路ルネッサンスファンド(HAR基金)」設立のための記念シンポジウムが開催されました。
HAR基金発足記念シンポ(9/28)
普通預金 No.3017262
花咲かだより/2の1
「阪神市街地緑化再生プロジェクト」のTシャツができました。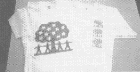
Tシャツ見本
第4回都市環境デザインフォーラム・関西
「まちとアイデンティティ」―震災に見る市民参加の都市環境の連続性―
◎神戸ワークショップ―海上都市のアイデンティティ
日時:10月21日(土),13:20〜17:45
参加費:1,000円(別途シーバス料金800円)
part1 海上都市を感じる
―集合場所:ハーバーランド シーバス乗場(13:20)
part2 海上都市を論じる
―神戸ファッションマート(六甲アイランド内)14:45〜
西宮ワークショップ「阪神間らしさを語る」日本建築学会・阪神地域復興シンポ
「住民参加の復興まちづくり」
―コミュニティ活動が拓く個性ある都市環境、 下町の再生―
会場:こうべまちづくり会館(2階ホール)
神戸市中央区元町通4-2-14 078-361-4523
内容:復興まちづくり活動の報告
―鈴木克彦(京都工繊大)、 各まちづくり協議会代表、 コーディネーター:高田昇(立命大)
費用:無料(但し資料代500円)
主催:日本建築学会近畿支部計画系4部会合同研究会
問合せ:コー・プラン内 上山 078-842-2311長田の良さを生かしたまちづくり懇談会
「住宅問題を考える」
日時:10月19日(木)18:00〜
場所:池田南部公会堂(大道通3丁目、 スバルの中央幹線を挟んで向側)
ネットワーク事務局より
◎東灘区白地対策会議開かれる
10月6日(金)、 東灘区の各地区の担当者や行政からも参加を得て第1回の会合が開かれました。◎復興市民まちづくりvol.3発刊へ!
―復興まちづくり通信を送ってください―○第10回・神戸市東部市街地連絡会
日時:10月17日(火)18:30〜
内容:・六甲地区(佐藤健正)・鷹取東地区(森崎輝行)・各種共同建替事業の補助要
場所:神戸Fビルディング11F
〒657 神戸市灘区楠丘町2-5-20
まちづくり株式会社コー・プラン
TEL.078-842-2311 FAX.078-842-2203
担当:天川・中井
〒657 神戸市灘区六甲台町1
神戸大学工学部建設学科
TEL.078-803-1029 FAX.078-803-1029
担当:児玉
 きんもくせい18号へ
きんもくせい18号へ
このページへのご意見は学芸出版社/前田裕資へ
(c) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク事務局
学芸出版社
詳細目次へ
支援ネットワーク関連ページへ
『震災復興まちづくり』ホームページへ
学芸出版社ホームページへ